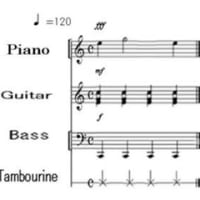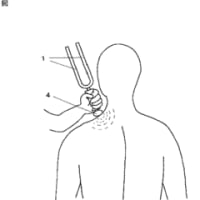今日はいきなり本題。
中国企業と取引する場合の形式的な問題について、前回、「契約当事者の問題」、「口頭での契約成立の問題」、「言語の問題」の3つを書きました。
今日は、残りの2つについて。
4.代表者やその権限の問題
日本では、通常の株式会社や有限会社の場合、会社の代表者は、代表取締役です。代表取締役社長とか、代表取締役会長とか。
会社と契約を結ぶ場合は、このような会社の代表権限がある人との間で結ばないと、通常は、会社に契約の効力を及ぼすことができなくなります。
「代表」という肩書がなくても、○○事業本部長、部長、課長などでも一定の権限が与えられている場合もあります。
事業本部長といった事業部門長であれば、表見支配人という規定(会社法13条)がありますが、部長や課長に至ると、どこまでの権限が与えられているか外からわかりません。
よほど大きな会社の事業部門長でなければ、代表取締役と締結することが安全といえます。
このように、代表権限がある人と契約を締結するというのは、中国の会社との取引でも同じです。
では、中国の会社の代表者は、どういう肩書なのか?
薫事長、総経理といった肩書をよく耳にしますが、それらの肩書≠代表権者とのこと。
代表者は定款で定められるため、薫事長が代表権者である場合、総経理が代表権者である場合、どちらもありですが、実際は、薫事長が代表権者であることが多いそうです。
また、誰が代表権者であるかは、営業許可証(日本の商業登記簿のようなもの?)で確認できるそうです。
5.印鑑の問題
次に、印鑑です。
中国の会社も、契約書には押印します。会社の印鑑としては、公印と契約専用印というものがあり、契約書には契約専用印がよく使用されるとのことです。
ちなみに、中国では、日本の印鑑登録・印鑑証明という制度に当たるものがないそうです。
注意すべきは、署名押印だけのページを作らないこと。
中国政府による契約書の審査が必要とされる場合、政府から修正指導があった部分を後から簡単に差し替えできるよう、便宜のため、署名押印だけのページを作る例もあるそうです。
でも、それをしてしまうと、契約書が勝手に差し替えられてしまうリスクがあるということでした。
便宜のためとはいえ、当然のリスクなので、避けるべきですね。
形式的なところで説明があったのはこんなところです。
で、このセミナーに行った主目的は、紛争解決手法としての「仲裁」に関する話が聞きたかったから。
仲裁についても、いろいろ説明があったので、それはまた改めて、記事にしようと思います。
法律事務所と特許事務所が、AIGIグループとしてタッグを組んでます。
それぞれのページをぜひご覧ください!
★あいぎ法律事務所(名古屋)による知財・企業法務サポート
★あいぎ特許事務所
商標登録に関する情報発信ページ「中小・ベンチャー知財支援サイト」もあります