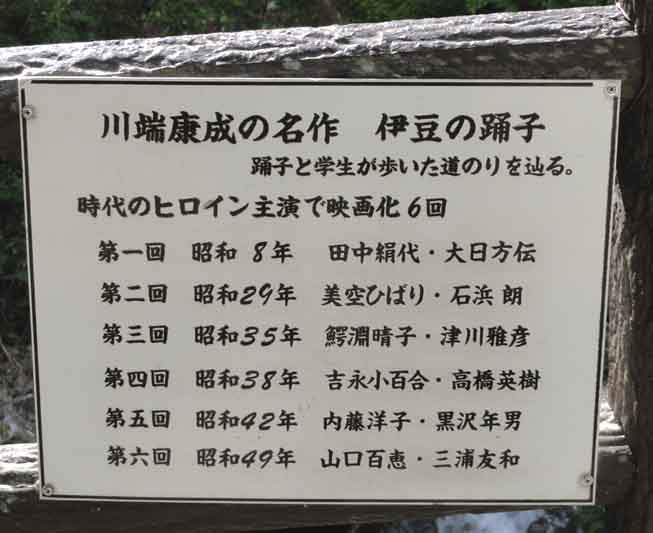22
松江城(まつえじょう)
[ 日本大百科全書(小学館) ].
江戸期の城。島根県松江市殿町(とのまち)にあり、千鳥(ちどり)城ともよばれる。関ヶ原の戦いの軍功により、堀尾吉晴(ほりおよしはる)は、出雲(いずも)、隠岐(おき)24万石の領主として初め富田(とだ)城に入ったが、政治上、軍事上の利点から、国の中央部で、交通の便もよい松江の地を新城地として選んだ。城は宍道(しんじ)湖の水を引いて堀とし、亀田(かめだ)山を利用した平山城(ひらやまじろ)である。1607年(慶長12)着工し、11年にいちおうの完成をみた。亀田山山頂を本丸とし、その南に二の丸、さらに堀を隔てて南に三の丸を設け、ここに居館があった。五層六階の天守閣は現存し、黒の下見板(したみいた)張りで、しかも望楼式の古い様式をとどめている。堀尾氏3代、京極(きょうごく)氏1代を経て、1638年(寛永15)からは松平氏が世襲して幕末に至った。
[ 執筆者:小和田哲男 ]

23

24

25

26