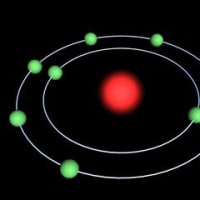昨日書いたように東西本願寺は、看板は昔ながらの浄土真宗ではあるが、その中身は時代とともに聖人の教えと異なっていった。その歪曲、脱線の歴史を何回かに分けて掲載したい。
浄土真宗と名乗らずに、浄土真宗を伝えると、「カルト」呼ばわりされるのなら、浄土真宗と名乗って、浄土真宗ではないことを教える人たちは、何と呼ばれるべきだろう?
あちら側の人たちに聞いてみたいものである。
それはさておき、まずは本題に入ろう。
江戸幕府の宗教政策とは、まずキリスト教の禁制がある。
その目的遂行のため、幕府の打ち出した政策が「本末・寺檀制度」だった。
本末制度とは、仏教の各宗派内で「本山―末寺」の関係を徹底し、末寺は本山の命令に服従すべきとした寺院統制策である。
寺檀制度とは、日本人すべてをいずれかの寺院に所属させ、固定化し、キリスト教徒でないことを寺が保証するかわりに、檀家の人々はその寺院への参詣や、経済的な支援を義務とする、という民衆統制策である。
この幕府の方針は、本山にとっては自らの力の強化となり、また各寺院にとっては、自坊を経済的に支える檀家や門徒が固定化され、生活の基盤が確保できるため、まんまとその政策に乗せられていくのである。
だが、権力者の保護を受けるということは、すなわち権力の統制下に入ることを意味する。
本山は、末寺に絶大な権限を持つかわりに、幕府の命令に従うことになった。
末寺は、檀家や門徒に生活を保障してもらうかわりに、外へ向けての自由な布教はできなくなった。
この、外へ向けて積極果敢に布教することがなくなったという点が重要なのである。
檀家、門徒が所属寺院に固定化されたのは、名目上はキリシタンの禁制であったが、真宗門徒の牙を抜く深謀遠慮でもあったと思われる。事実、真宗界は幕府の介入を受け入れることで、生活の安定を得た代わりに、布教の活力を失ったのである。
実践は宗教の生命といわれる。「十方にひとしくひろむべし」の親鸞聖人の教えに違い、積極的に布教をしなくなれば、浄土真宗は朽ち果てていくのみである。
布教してもしなくても生活は安泰という、いわゆる〃飼い殺し〃の環境に身を置けば、いかに情熱的な僧侶でも、長い時間をかけてゆっくりと生気を失い、四肢が麻痺し、腐敗していくものである。
姦雄信長を相手に、11年間、戦い抜いたような、かつての真宗門徒に漲っていた爆発的な信仰のエネルギー、仏法のためなら命も捨てる真剣さ、教えに純粋でそれ以外の何ものにも迎合しない〃角〃(かど)が、権力者の手によって懐柔され、江戸300年間に、ゆっくり摘み取られていったのである。
当然の結果として、お上に逆らわない、伝える気力もない、大人しい消極的な真宗門徒像が形成されていったのは言うまでもない。
「善などしなくてもよい」「善を勧める必要はない」などという消極的を通り越した、仏教破壊の悪魔の暴言までが、堂々とまかり通るようになっていく素地が、この時代から醸成されていったと考えてよかろう。
近代以降、雨後の竹の子のように急成長していった天理教、創価学会、生長の家などの新興宗教は、教えの是非はともかく、外へ外へと布教してバイタリティがあった。
一方、真宗界は伝統に腰掛け、新たな門徒を獲得する意欲も、新しい人への伝え方、そのノウハウも江戸期にすっかり失ってしまったので、新興宗教の後塵を拝するしかなかった。
おざなりの布教で、地盤沈下のように僧俗の〃体力〃が低下してきたところへ、明治とともに始まった廃仏毀釈運動、さらに海外からドッと流入してきた科学や哲学、あるいはキリスト教、マルクス思想からの真宗教義への痛烈な批判、はたまたカミソリ聖教との異名を持つ『歎異抄』の普及による誤解の蔓延、大乗非仏説論、そして戦時中の国家神道による強烈な思想統制、これら歴史の荒波に翻弄され、真宗は完全に骨抜きにされ、親鸞聖人の教えとは異質なものに変貌していくのである。
それについては、今後も継続して書いていきたい。
浄土真宗と名乗らずに、浄土真宗を伝えると、「カルト」呼ばわりされるのなら、浄土真宗と名乗って、浄土真宗ではないことを教える人たちは、何と呼ばれるべきだろう?
あちら側の人たちに聞いてみたいものである。
それはさておき、まずは本題に入ろう。
江戸幕府の宗教政策とは、まずキリスト教の禁制がある。
その目的遂行のため、幕府の打ち出した政策が「本末・寺檀制度」だった。
本末制度とは、仏教の各宗派内で「本山―末寺」の関係を徹底し、末寺は本山の命令に服従すべきとした寺院統制策である。
寺檀制度とは、日本人すべてをいずれかの寺院に所属させ、固定化し、キリスト教徒でないことを寺が保証するかわりに、檀家の人々はその寺院への参詣や、経済的な支援を義務とする、という民衆統制策である。
この幕府の方針は、本山にとっては自らの力の強化となり、また各寺院にとっては、自坊を経済的に支える檀家や門徒が固定化され、生活の基盤が確保できるため、まんまとその政策に乗せられていくのである。
だが、権力者の保護を受けるということは、すなわち権力の統制下に入ることを意味する。
本山は、末寺に絶大な権限を持つかわりに、幕府の命令に従うことになった。
末寺は、檀家や門徒に生活を保障してもらうかわりに、外へ向けての自由な布教はできなくなった。
この、外へ向けて積極果敢に布教することがなくなったという点が重要なのである。
檀家、門徒が所属寺院に固定化されたのは、名目上はキリシタンの禁制であったが、真宗門徒の牙を抜く深謀遠慮でもあったと思われる。事実、真宗界は幕府の介入を受け入れることで、生活の安定を得た代わりに、布教の活力を失ったのである。
実践は宗教の生命といわれる。「十方にひとしくひろむべし」の親鸞聖人の教えに違い、積極的に布教をしなくなれば、浄土真宗は朽ち果てていくのみである。
布教してもしなくても生活は安泰という、いわゆる〃飼い殺し〃の環境に身を置けば、いかに情熱的な僧侶でも、長い時間をかけてゆっくりと生気を失い、四肢が麻痺し、腐敗していくものである。
姦雄信長を相手に、11年間、戦い抜いたような、かつての真宗門徒に漲っていた爆発的な信仰のエネルギー、仏法のためなら命も捨てる真剣さ、教えに純粋でそれ以外の何ものにも迎合しない〃角〃(かど)が、権力者の手によって懐柔され、江戸300年間に、ゆっくり摘み取られていったのである。
当然の結果として、お上に逆らわない、伝える気力もない、大人しい消極的な真宗門徒像が形成されていったのは言うまでもない。
「善などしなくてもよい」「善を勧める必要はない」などという消極的を通り越した、仏教破壊の悪魔の暴言までが、堂々とまかり通るようになっていく素地が、この時代から醸成されていったと考えてよかろう。
近代以降、雨後の竹の子のように急成長していった天理教、創価学会、生長の家などの新興宗教は、教えの是非はともかく、外へ外へと布教してバイタリティがあった。
一方、真宗界は伝統に腰掛け、新たな門徒を獲得する意欲も、新しい人への伝え方、そのノウハウも江戸期にすっかり失ってしまったので、新興宗教の後塵を拝するしかなかった。
おざなりの布教で、地盤沈下のように僧俗の〃体力〃が低下してきたところへ、明治とともに始まった廃仏毀釈運動、さらに海外からドッと流入してきた科学や哲学、あるいはキリスト教、マルクス思想からの真宗教義への痛烈な批判、はたまたカミソリ聖教との異名を持つ『歎異抄』の普及による誤解の蔓延、大乗非仏説論、そして戦時中の国家神道による強烈な思想統制、これら歴史の荒波に翻弄され、真宗は完全に骨抜きにされ、親鸞聖人の教えとは異質なものに変貌していくのである。
それについては、今後も継続して書いていきたい。