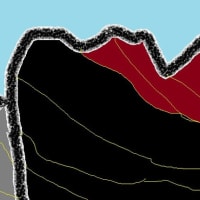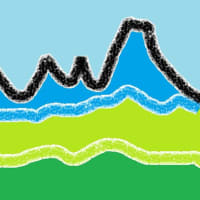しかし人間だから、何か娯楽がないと、田舎へ来て狭い土地では到底暮せるものではない。それで釣に行くとか、文学書を読むとか、または新体詩や俳句を作るとか、何でも高尚な精神的娯楽を求めなくってはいけない……」
だまって聞いてると勝手な熱を吹く。沖へ行って肥料を釣ったり、ゴルキが露西亜の文学者だったり、馴染の芸者が松の木の下に立ったり、古池へ蛙が飛び込んだりするのが精神的娯楽なら、天麩羅を食って団子を呑み込むのも精神的娯楽だ。そんな下さらない娯楽を授けるより赤シャツの洗濯でもするがいい。
おかざき真里氏のえがく、空海と最澄のマンガに、空海が一晩で尚書とかなんとかを記憶しましたという場面があったとおもうが、書経とかってすごいスピードで読める可能性はある。わしはできないが。四書五経だって内容に慣れてくると、上のようなリズムで見えてこないことはない。書経はとくに山を越え谷を越みたいなリズムに乗ってくると立ち止まらなくてもよい気がしてくるのである。
ビギナーズ・クラシックスで「夜の寝覚」がでたのはすごく助かる。学生もこれで入りやすくなる。この物語はごっそりぬけている部分があるからあれなんだが、――ある意味源氏物語を「越」えていこうとしている。作者が誰かはともかく、山を越え谷を越えみたいな体験は文章に影を堕とすんじゃないか。
長野県茅野生まれの国枝史郎は「蔦葛木曽桟」や「神州纐纈城」がすごい作者だが、すごく移動するひとで、長野→東京→大阪→木曽福島→中津川→徳島→知多とあっちこっちに住んでいる。大衆文学に目覚めたのは木曽にいたころらしい。で最後知多に移住して筆が止まった。愛知県は危険(個人のトラウマです)
最近読んだ漫画だと、「セクシーボイスアンドロボ」が、山を越え谷を越えみたいなリズムがあった。しかしこれ、テレビドラマになってたのである。このリズムはテレビではでない。
敗戦後のカストリ雑誌にはときどきすごくおもしろい作品がある。村上昌三の「物を喰べるお尻」とか、お尻に人面瘡(オカメのかたち)が出来てしまっただけの話だ。山あり谷ありなんてもうごめん、みたいな気分にあっている。