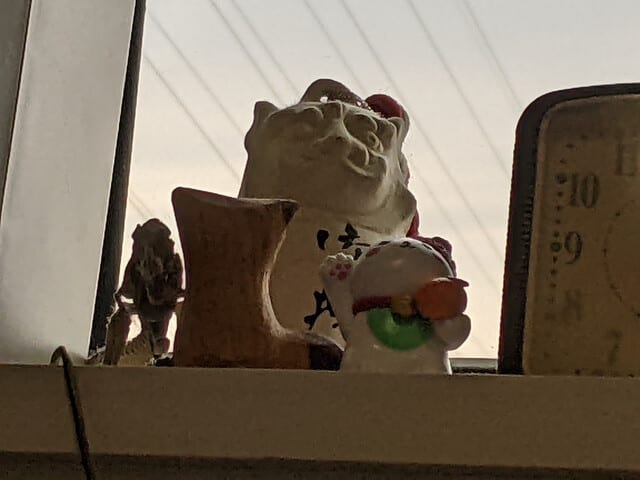ナオミは譲治によってメリイ・ピックフォードそっくりの女に仕立てあげられた時、天才的な娼婦性を発揮する不良少女になるのである。そして晩年の『鍵』になると、「西洋」は軽薄な尖端的風俗をつきぬけて、保守的な大学教授の家庭にまで侵入し、貞淑な教授夫人を「娼婦」に変える。[…]谷崎が『刺青』でいちはやくとらえ、以後晩年まで一貫して追い続けた不安とは自己分裂の不安である。和服を着た「母」、たとえば『瘋癲老人日記』の卯木督助の夢にあらわれる「鼠小紋ニ黒縮緬ノ羽織」をまとい、「素足ニ吾妻下駄」をはいて、「髪銀杏返シ、珊瑚ノ根掛、同ジ珊瑚ノ一ツ玉ヲ挿シ、蝶貝ヲ鏤メタ鼈甲ノ櫛ヲサシ」た「母」は農耕文化の安定したサイクルのなかにいて、心にやすらぎをあたえてくれるが、そこに定住するかぎり「西洋」の約束する官能は永久にわがものにはならない。しかし母性の安息を捨てて「西洋」によって「娼婦」に変身させられた女たちに没頭するとき、そこに待っているのは破滅と死、つまり完全な「自然」の枯死である。この分裂のなかで、谷崎が結局『蓼喰ふ虫』のお久や『細雪』の雪子のような和服の「母」たちよりは、『痴人の愛』のナオミや『鍵』の郁子、あるいは『瘋癲老人日記』の颯子のような洋装の「娼婦」たちを選んだのは、彼が逆に自分の記憶の奥底にひそむ「母」のイメイジの強靭さを信じていられたためかも知れない。[…]昭和三十年代は、まさに日本全国が「近代化」、あるいは「産業化」の波にまきこまれて、ついに近代工業国に変貌をとげた時代である。この全面的な産業化の過程で、一番大きな心理的原動力となったのが、「置き去りにされる」不安だったことはいうまでもない。 エリクソンは、あらゆる女性的な不安のなかでもっとも根源的なものは、この「置き去りにされる」不安だといっている。
――江藤淳「成熟と喪失」
江藤淳の「喪失」は、小島信夫など、空虚そのものをエンジンにしたいような、つまり凧というより、風船みたいな作家たちの作品が根拠になっていた。彼らは江藤淳ほどしょぼくれてはいなかったとおもう。アメリカによる空虚の強制すら喜んでいた節があると思うのである。いまやアメリカが空虚を抱えるこの時代、空虚すぎてブラックホールと化した日本にいまこそはじかれた人々を吸い込むときである。ハーバード大学が留学生を断るなら、日本の地方大学にその留学生、ハーバード大に嫌気が差したインテリたちを吸収すればよいのである。中には、西洋が嫌になった?ハーンやケーベルみたいな人材が混じっているかもしれない。
すなわち、ハーバード大学が香川大に留学すればよいのではないだろうか。而して、どさくさに紛れて我々の研究費も上がるのではないだろうか。
教育は一生懸命やればやるほどうまく行かなくなる逆説がある。おれはいっぱい善い子どもを育てたみたいな、「オレが育てた型教師」が案外棄てたものではないのは、――あまりに馬鹿なので子どもがあまり言うことを聞いていないからである。子どもは鈍感なので、その空虚さえも無視できる。「置き去りにされる不安」はあっても、自分に対して好意的な行為に対しては反応がよくない。日本浪曼派の小説なんかには、自分が空虚故に荒ぶっているので神もあらぶっているみたいな小説がある(先日触れた「白日の書」なんかがそんな感じだった)けど、神はそこまで俺たちに相即的であろうか。神はだいたいに子どもみたいなものではなかろうか。神が中身が空気の人形のように偶像化したときにはそんなキャラクターがせいぜい想像されるわけである。熟慮するんだったら、人間並みだと言うことである。対して、歴史はもっと機械的に残酷である。
例えば、虎ノ門事件で昭和天皇(皇太子)が暗殺されていたらどうなっていたかとも思うが、犯人の難波代助の父親(衆議院議員)が餓死したあと、地盤をついだのが松岡洋右というのがなんというか。ちなみに、難波代助が使った銃は伊藤博文が倫敦で買ってきたものだったらしい。運命は認識され使えるものなら何でも使う、AIみたいな奴なのである。