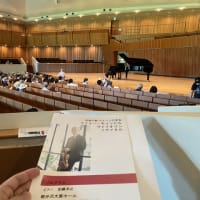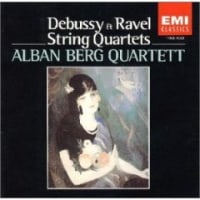人間関係において一番よくないのは直接コミュニケーションをとらずに勝手に悪い感情を増大させること、だと私は今までの経験で感じてきました。自分にある程度の失点がありある人に迷惑をかけたような場合でも、どうしてそのような事態になってしまったかその人に直接話すことができればだいたいの場合わかってもらえるものです。これは狭い研究室のコミュニティーでは結構大事で、特にこういうことはボスがよくわかっていなければいけないことだと思っています。海外にいると外国人同士どういう考えをするかわからないのがある意味当然なので勝手に悪く決めつける前にどうしてこんなことをしているのか、などとダイレクトに聞いてきますからこっちも努力して理解してもらおうとするし、そうすると本当に理解してもらえなくても別にその人との間に悪い感情があるわけではないことは感じてもらえるので変な関係のもつれにつながりません。(これが日本人同士だとうまくいかないから困った物ではあります)
同じ問題が今の将棋界にあるような気がするのです。今将棋界で揉めていること(ここにまとめられています)はネットを活用している将棋ファンなら誰しも気づかされることです。しかし私も以前に書いたようにこれに対して明快な意思表示をしている棋士はいません。きわめて不自然なのはどうやらことが結構大きくなっているし、連盟理事会が強く動いているのは間違いないようですが、将棋連盟のホームページではなんらこれに関する記載がなく、会長の個人的なサイトで彼が非常識な文体で好き勝手なことを書いているに過ぎません。そして彼らが問題にしていて揉め事の発端になったのはmtmt氏の個人的なブログです。それゆえ情報が断片的で連続性にも欠けます。それぞれの感情が先んじた内容であり、いくつかの記事は明らかに勢いで書かれたものと思われます。
問題はファンにとってはこれしか情報源がないということ。一方で沈黙している棋士はおそらくネットを通じてよりは直接事態を知るなり、関係社から伝え聞くなりしていてよりリアルな姿を知っている。またそれぞれの棋士たちはおそらく会長を偉大な棋士として尊敬している。少なくとも彼が棋士としてどんなにすばらしかったかを知っている。このファンと棋士との違いは決定的だと思われるのです。もしかしたら連盟の控え室でブラックジョークを飛ばしている棋士たちにすれば話のネタになるくだらない喧嘩に過ぎないのかもしれない。もしくは世間的にどれくらい問題なのかは中にいるとわからないのかもしれない。だから片上さんがブログで「買ってちょ」なんて言い方をしてしまい、ファンの猛反発を買ったりするのだろう。正直私もそれはやめてくれよと思ったし、片上さんの将棋世界の紹介を読んでものすごく読んでみたくなったが、会長が将棋世界の売り上げにご熱心なのを思い出すと買う気がなくなってしまう。一時期は海外発送の年間購読もしていたくらい自分にとってはかなり読みたい物だが、どうしてももう買う気が起きない。そこに会長得意の言い回して書かれてしまうとかなりの拒絶反応を起こしてしまった。
この温度差、どのように解決していくことができるだろうか?竜王や片上さん遠山さんなどのブログによってかなり棋士の日常が身近になったと思うが、ここではそれ故にファンにとっては歯がゆい思いがするのだ。
同じ問題が今の将棋界にあるような気がするのです。今将棋界で揉めていること(ここにまとめられています)はネットを活用している将棋ファンなら誰しも気づかされることです。しかし私も以前に書いたようにこれに対して明快な意思表示をしている棋士はいません。きわめて不自然なのはどうやらことが結構大きくなっているし、連盟理事会が強く動いているのは間違いないようですが、将棋連盟のホームページではなんらこれに関する記載がなく、会長の個人的なサイトで彼が非常識な文体で好き勝手なことを書いているに過ぎません。そして彼らが問題にしていて揉め事の発端になったのはmtmt氏の個人的なブログです。それゆえ情報が断片的で連続性にも欠けます。それぞれの感情が先んじた内容であり、いくつかの記事は明らかに勢いで書かれたものと思われます。
問題はファンにとってはこれしか情報源がないということ。一方で沈黙している棋士はおそらくネットを通じてよりは直接事態を知るなり、関係社から伝え聞くなりしていてよりリアルな姿を知っている。またそれぞれの棋士たちはおそらく会長を偉大な棋士として尊敬している。少なくとも彼が棋士としてどんなにすばらしかったかを知っている。このファンと棋士との違いは決定的だと思われるのです。もしかしたら連盟の控え室でブラックジョークを飛ばしている棋士たちにすれば話のネタになるくだらない喧嘩に過ぎないのかもしれない。もしくは世間的にどれくらい問題なのかは中にいるとわからないのかもしれない。だから片上さんがブログで「買ってちょ」なんて言い方をしてしまい、ファンの猛反発を買ったりするのだろう。正直私もそれはやめてくれよと思ったし、片上さんの将棋世界の紹介を読んでものすごく読んでみたくなったが、会長が将棋世界の売り上げにご熱心なのを思い出すと買う気がなくなってしまう。一時期は海外発送の年間購読もしていたくらい自分にとってはかなり読みたい物だが、どうしてももう買う気が起きない。そこに会長得意の言い回して書かれてしまうとかなりの拒絶反応を起こしてしまった。
この温度差、どのように解決していくことができるだろうか?竜王や片上さん遠山さんなどのブログによってかなり棋士の日常が身近になったと思うが、ここではそれ故にファンにとっては歯がゆい思いがするのだ。