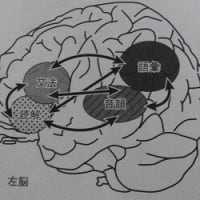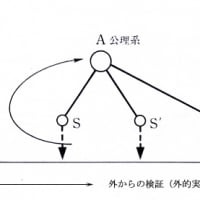図書館から「天声人語」(2020.1~6)を借りてきてパラパラ見ていた。「美濃のマムシの実像」(5.4)を読んでいて、辞書をひくことになった。「それでも長年の梟雄(きょうゆう、ルビ)イメージが払拭されていく手応えがあった」の「梟雄」がわからなかったのである。
手元にある辞書「新明解国語辞典」には次のようにあった。
梟雄 〔「梟」も「雄」も、すぐれる意〕武勇戦略にすぐれた英雄。
違和感があった。これは払拭するイメージではないのではないか。ネットで調べると、「残忍で強く荒々しいこと。また、その人。悪者などの首領にいう。」とある。これなら払拭である。また、梟雄の例として斎藤道三(本木雅弘、「麒麟がくる」では)、松永久秀(吉田鋼太郎、同)などが挙げてあった。
本棚の「広辞苑」には次のようにあった。
残忍でたけだけしい人。
こちらを先に引けば何ごともなかった。
「角川新字源」で「梟」を調べると、1ふくろう、2さらす、3たけだけしい、4すぐれたものとあり、たしかに「すぐれる」の意がある。そして、「梟雄」に「勇猛な英雄」と説明し、「劉備天下梟雄」の例文が載っている。また、「雄」には、1おす、2つよい、3さかんなさま、4ひいでる、5かしらとある。
どうやら「梟雄」は、「梟」「雄」の字義だけではなく、梟(フクロウ)の生態と関係しているようだ。日本と中国では、梟は母親を食べて成長すると考えられていたという。下克上を親殺しと見立てたのが梟雄の由来らしい。「英雄」を「残忍」のイメージが蔽ったのである。
手元にある辞書「新明解国語辞典」には次のようにあった。
梟雄 〔「梟」も「雄」も、すぐれる意〕武勇戦略にすぐれた英雄。
違和感があった。これは払拭するイメージではないのではないか。ネットで調べると、「残忍で強く荒々しいこと。また、その人。悪者などの首領にいう。」とある。これなら払拭である。また、梟雄の例として斎藤道三(本木雅弘、「麒麟がくる」では)、松永久秀(吉田鋼太郎、同)などが挙げてあった。
本棚の「広辞苑」には次のようにあった。
残忍でたけだけしい人。
こちらを先に引けば何ごともなかった。
「角川新字源」で「梟」を調べると、1ふくろう、2さらす、3たけだけしい、4すぐれたものとあり、たしかに「すぐれる」の意がある。そして、「梟雄」に「勇猛な英雄」と説明し、「劉備天下梟雄」の例文が載っている。また、「雄」には、1おす、2つよい、3さかんなさま、4ひいでる、5かしらとある。
どうやら「梟雄」は、「梟」「雄」の字義だけではなく、梟(フクロウ)の生態と関係しているようだ。日本と中国では、梟は母親を食べて成長すると考えられていたという。下克上を親殺しと見立てたのが梟雄の由来らしい。「英雄」を「残忍」のイメージが蔽ったのである。