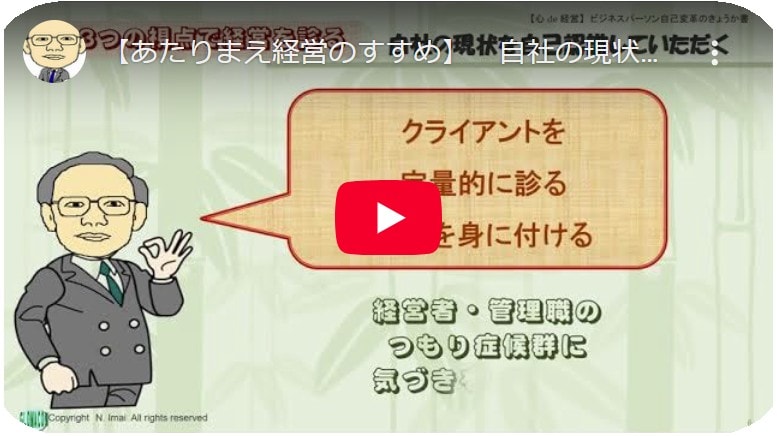■【小説風老いぼれコンサルタントの日記】 4月6日 ◇日本三大名城 ◇ウォーキングまとめ 5-2 記録を付けると辛い運動も頑張れる ◇成功している人の特徴
平素は、私どものブログをご愛読くださりありがとうございます。
この度、下記のように新カテゴリー「【小説風 傘寿】 老いぼれコンサルタントの日記」を連載しています。
日記ですので、原則的には毎日更新、毎日複数本発信すべきなのでしょうが、表題のように「老いぼれ」ですので、気が向いたときに書くことをご容赦ください。

紀貫之の『土佐日記』の冒頭を模して、「をとこもすなる日記といふものを をきなもしてみんとてするなり」と、日々、日暮パソコンにむかひて、つれづれにおもふところを記るさん。
【 注 】
日記の発信は、1日遅れ、すなわち内容は前日のことです。
■【小説風 傘寿の日記】
私自身の前日の出来事を小説日記風に記述しています。
4月6日
早朝ウォーキングのコース沿いに、ウコン種の桜の老木がありました。
「ありました」と過去形なのは、老体ながら、それなりの美しさを保ち、まもなく花を咲かせていたのですが、2024年3月に伐採されてしまいました。
ウコンは、薄緑色の花弁をつける、私が好きな桜なのです。
緑色の花弁といいますと、御衣黄が有名です。
御衣黄は、ウコンより色が濃く、また希少種でもあり、あまり見る機会がありません。
どちらかというと、私は、薄緑のウコンの方がすきです。
八重で、やや遅咲きです。
毎年、この桜を見るのが楽しみだったのです。
どの様な事情があるのかわかりませんが、残念です。
この桜とは別の道にあったかっこいい桜が2023年に切られてしまったのです。
某地銀の寮の門のところに、遠くから見ると扇型をした、「これぞソメイヨシノ」という桜でした。
枝振りが、270度ほど開いた扇に見えました。
その寮が昨年閉鎖され、その時に切られてしまったのでしょう。
桜並木がカミキリムシやカメムシにやられてしまうことはしばしば見聞しますが、街中の桜が人為的に伐採されてしまうのは残念です。
*
週末ですので、気分転換に写真整理をしました。
ようやく水戸偕楽園の写真を動画化することができ、試写会を開きましたが、満足できません。
今回は、ナレーションに加え、テキストテロップを説明的に、ところどころ入れたのは多少プラス効果化が出たと思います。
偕楽園周遊編 https://youtu.be/secPHXtOYBM
偕楽園好文亭と庭園 https://youtu.be/9cETplnsCSI

水戸偕楽園 好文亭
早朝ウォーキングの効果を持続または改善するために、今朝のウォーキングで、自分でどの様にやっているのか反復してみました。
◆5章 ウォーキングと健康体操のまとめ
これまで、ウォーキングや体操について連載してきましたが、最後までお読みくださりありがとうございます。
ここでは、まとめとして、どのようにしたら単調な運動を継続し、効果を上げるのか、ここでも体験を中心にお話します。そのまま鵜呑みにせず、皆様ご自身で体験しながら、修正し、効果を上げてくださるようお願いします。
【 注 】
ここで紹介する情報は、自分で思考したり、入手したりした情報をもとに、ご紹介します。
それが皆様にも良い方法であるとは限りませんので、皆様ご自身のご判断で参考にしてくださるようお願いします。
5-2 記録を付けると辛い運動も頑張れる
NHKのガッテンという長寿番組がありました。そこで、「付けるだけダイエット」という放送がありました。
少しでも痩せたい、ぽっこりお腹を小さくしたい等々、私達は、なぜが体型を気にし過ぎるようです。
さりとて、ダイエットをするほどでもないとか、ダイエットは続かないのよね、とかで、なかなかダイエットを継続できず、リバウンドを起こしたりしてしまいます。
その様な人でも、継続すれば痩せられるというのが「付けるだけダイエット」です。
毎日、決まった時間に体重測定をします。ただし、体重計は100分の一グラムまで測定できる機種が好ましいのです。ダイエットのためですので、そのくらいの投資をした方が、「一万円も投資したのだから」というもったいない意識から継続できるのではないでしょうか。
測定結果をグラフに記入するだけです。
特別になにもしません。ところが、体重が次第に減少して行くのだそうです。
これは、人間が生きていくために、基本的に持っている競争心のようなものが作用し、どこかで、その変化に一喜一憂しているのではないでしょうか。
炭水化物を減らそうとか、間食を辞めようとか、運動をしてみようとかという動きに自然と移行して、その結果、記録を付けるだけでダイエットをすることができるというのではないでしょうか。
NHKのサイトで、記録用のフォーマットファイルをダウンロードできるそうですので、ご興味のある方は試してみてはいかがでしょうか。
さて本論のウォーキングの話にもどりましょう。
上記の例をヒントに、ウォーキングも、毎日の歩数を記録していくと、それが励みとなって継続できるのではないでしょうか。
幸いなことに、スマートフォンは、ウォーキングのときに、あまり邪魔にならない程度の大きさです。スマートフォンの万歩計アプリケーションをダウンロードするだけで、一週間の記録は自動的に保存されています。
できれば、それをExcelなどのアプリを利用して、記入し、グラフ化するようにしたら良いでしょう。ひょっとすると、それが自動的にできるアプリが発売されているかもしれませんね。

■【今日のおすすめ】
【お節介焼き情報】有能なビジネスパーソンといわれる成功している人の特徴
「コンピテンシー」という言葉があります。
成功している人の良いところを「まねぶ」ことにより、自分の実力を上げるときに利用できます。
ここでは、成功しているビジネスパーソンのコンピテンシーのお話を紹介しています。

■【今日は何の日】
当ブログは、既述の通り首題月日の日記で、1日遅れで発信されています。
この欄には、発信日の【今日は何の日】と【きょうの人】などをご紹介します。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/7c95cf6be2a48538c0855431edba1930

■【知り得情報】
政府や自治体も、経営環境に応じて中小企業対策をしています。その情報が中小企業に伝わっていないことが多いです。その弊害除去に、重複することもありますが、お届けしています。
*
◇再掲《公募》「小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>
「小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第17回)」の公募要領(暫定版)が公開されました。公募要領(確定版)については、改めて公知されます。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2025/250304jizoku_01.html
◇《セミナー》マーケティング志向の営業活動の分析と改善(C19)
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知支部ポリテクセンター中部では、自社の商品又はサービスの価値を提供するに当たって、マーケティング志向の営業活動について、分析し、改善策検討方法を習得するセミナーを開催します。
[日 時] 6/12(木)9:30~16:30
[場 所] ポリテクノセンター中部(愛知県小牧市)
[参加費] 3,300円(税込)
詳しくは以下のサイトをご覧下さい
https://www3.jeed.go.jp/aichi/poly/biz/2025opencourse.html#joken2
https://www3.jeed.go.jp/aichi/poly/biz/2025opencourse.html#joken4
出典:e-中小企業庁ネットマガジン

■【経営コンサルタントの独り言】
その日の出来事や自分がしたことをもとに、随筆風に記述してゆきます。経営コンサルティング経験からの見解は、上から目線的に見えるかも知れませんが、反面教師として読んでくださると幸いです。
◆ 日本の3大名城というとあなたはどこを選びますか? 406
4月6日は、「しろの日」だそうです。
姫路市が制定したのですが、「城の日」としないところにおくゆかさを感じます。
白亜の城、白鷺城の白のイメージを出したかった工夫でしょうか。
ところで、日本の三大名城というとあなたはどこを挙げますか?
定説はないようで、良く聞くのが、下記の3城です。
松本城 烏城(からすじょう)
姫路城 白鷺城(はくろじょう・しらさぎじょう)
熊本城 銀杏城(ぎんなんじょう)
熊本大地震で熊本城は大修理中で、修復にはまだ何十年かかかるそうです。早期にできることを願います。
黒を基調とした熊本城と松本城、白を基調とした姫路城と好対照です。
城郭の規模を規準にしますと下記に異論を唱える人は少ないでしょう。
姫路城
名古屋城
大坂城
江戸時代荻生徂徠らによりますと、江戸城を別格として、機能美に優れた点から選んでいます。
名古屋城
大坂城
熊本城
選定の基準により、対象のお城が異なるのは当然ですし、主観的なものもあります。
経営も「ものさし」次第で、エクセレント・カンパニーにもなれば、ブラック・カンパニーにもなります。

■【老いぼれコンサルタントのブログ】
ブログで、このようなことをつぶやきました。タイトルだけのご案内です。詳細はリンク先にありますので、ご笑覧くださると嬉しいです。
明細リストからだけではなく、下記の総合URLからもご覧いただけます。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17
>> もっと見る

■【小説風 傘寿】老いぼれコンサルタントの日記 バックナンバー
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/a8e7a72e1eada198f474d86d7aaf43db
© copyrighit N. Imai All rights reserved

![]()