「ぷらっとウオーク」 情報プラットフォーム、No.255、12(2008)
{久しぶり、仏像との出会い}
近所の香美市立美術館で9月下旬から11月上旬まで開催されていた「古仏との対話-井上芳明と土佐の仏像」を繰返し見に行った。高知県内の仏像25体と井上芳明さん撮影の仏像写真の展覧会である。「土佐魅惑の仏像たち」と題し、青木淳さんの心温まる解説が高知新聞夕刊に連載されていた。大豊町定福寺六地蔵さん達(木彫)がニコニコ顔で横一列の立ち姿で並んでいる。その隣に、湛慶またはその工房作と推定される須崎市上分大日堂大日如来さん(木造・漆箔)が座っている。どの仏さまも私を歓迎してくれているように思えた。若い頃、仏たちに会うためにオートバイで奈良に出かけたことを思い出していた。
東工大のある大岡山から、九品仏駅(9体の阿弥陀如来坐像)、等々力駅(等々力不動尊)、目黒駅や不動前駅(目黒不動尊)は至近距離。これらの仏さまに関心を持ち、久野健著「日本の彫刻」(吉川弘文館(1959))を買ってきた。
仏の名称の由来も、姿や形や振りの持つ意味も知りたくなる。鎌倉を始めとする近郊のお寺回り、仏さま巡りが始まった。また、専門の材料工学の面から仏像の材質と製作法に興味が湧く。結果として、古都奈良への憧れは募るばかり。寺尾勇著の写真集「飛鳥彫刻細見」(奈良美術研究所(1950))を手に入れる。
大和の国で、横の姿の美しい法隆寺百済観音立像(木彫)、微笑みの中宮寺菩薩半跏思惟坐像(木彫)、運慶・快慶の代表作の東大寺南大門仁王立像(木彫)、漆黒の肌の薬師寺薬師如来坐像と日光・月光菩薩立像の三尊像(青銅)に会いたいと思った。
同志は現れず、一人旅のスタートは大晦日。当時は、戸塚に有料高速道(通称、ワンマン道路)はあるが、東海道(国道1号線)には未舗装部分が残っていた。東大寺、興福寺、唐招提寺、薬師寺へ。法隆寺から中宮寺、法輪寺と歩いて回る。戻ると私の単車をライダー達が囲んでいる。府県名なしの数字5桁だけの東京ナンバーが珍しかったのである。
法起寺から西大寺へ。秋篠寺では、今にも歌い出しそうな技芸天立像(乾漆と木造)に会うことが出来た。光明皇后ゆかりの尼寺、法華寺では、端正なお顔の十一面観音菩薩立像(木彫)に出会えた。庫裏で声を掛けて程なく出てきたのは清楚な感じの尼さんである。
拝観の後、掘り炬燵のある部屋に通され、「お正月のお寺参りとは、お若いのにご信心深いことです」と褒められ、お茶お菓子をご馳走になった。真っ黒の煤けた顔、白い埃だらけの服のままである。「拝観料は」「お志で結構です」と言われ戸惑ったことを思い出す。
先の「日本の彫刻」には、高知の6寺19点が記載され、今回はその中の3点を見ることが出来る。運慶の長子湛慶作の雪渓寺毘沙門天立像(木彫、写真展示)と茶目っ気たっぷりな善賦師童子立像(木彫)の2点と安田町北寺薬師如来座像(木彫)である。
そして「土佐の秘仏をめぐる見学会」にも参加できた。青木淳先生を始めとする調査に努力された多くの方々と、そして高知市安楽寺阿弥陀如来坐像(木彫)、高知市円行寺日吉神社薬師堂薬師如来坐像、芸西村瓜生谷観音堂十一面観音立像(木彫)、安芸市妙山寺聖観音立像(木彫)など多くの仏たちに会うことが出来た。
また、鎌倉時代の土佐に、寺院を造営し、これだけの仏像を発注し得る政治力と経済力が存在していたことに驚かされた。幾多の試練の中で地域の人々が仏さまを守り続けた歴史の重みを感じた。ここに地方の時代を生きるヒントが隠れているように思える。また、貴重な文化遺産を県民みんなで守り、後世に伝える必要がある。そのために「地方仏研究会友の会」が発足したことは喜ばしい。
ご感想、ご意見、耳寄りな情報をお聞かせ下さい。
高知県香美郡土佐山田町植718 Tel 0887-52-5154











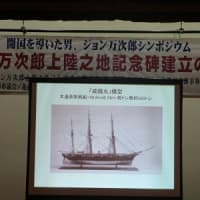







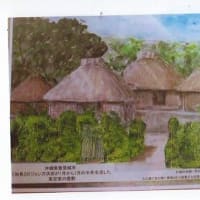
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます