間引き
明治の初期は、日本の国が維新の改革で、三百年も続いた徳川の武家政治も終わり、士農工商の順位も消えて、新しい政治家達によって、ヨーロッパ式の自由の風が吹き始めていたが、田舎の村里では、その新しい風もなかなかに届かず、ほんの一部の偉い商人か、地主、少ない自作農以外の一般庶民は、ほんとに貧しく、その日暮らしで、梅雨で雨の日が続いたりすると、仕事はできず貯えもなく、老人を抱えた子やらいでは、親戚や知人を頼って借り歩き、やっと生き延びていた。
貧しい哀れな時代、ほんとにあった昔の話を少し。
里吉は大工の職人であるが、当時の田舎では新築などはめったに無く、模様替えなどもたまで、本職の大工仕事より手伝い事が主の日雇いで、老母を抱え妻に子供二人の五人家族で、その日暮らしの貧しい家庭であった。
昔の「いろはかるた」に「貧乏人の子だくさん」というのがあったが、貧しい時代は男は仕事一色で、遊びはあっても遊ぶ間もなく、夫婦は喧嘩もするが仲も良く、子供は後へ後へとよく出来る。
里吉の女房の鶴も、子がよう出来る。去年も生むとすぐ死んだが、また腹がふとい。
近所の家主が、ありゃどうもおかしいと思い、臨月の鶴に気を配り度々伺いよった。
ある朝そっと里吉の家に近付くと、とたんに元気な産声が「オギャーオギャー」と、かん高い。
家主は「できた、できた」と喜んだ。その時、子の泣き声がぷっつり消えた。
嫌な予感が家主の頭を走った。こりゃいかんと障子を開けて上がり、奥のふすまを開けて見てびっくり。鶴はできだちの男の赤子の首をねじってすねに敷き、涙をぼろぼろと流しながら、家主を見て、「恥ずかしい、むごいことじゃが、こうせにゃあ、今でさえ食うや食わずでいきよるに、今この子が増えたら、よけかつえるけ。」と。
家主は慌てて、「こりゃ鶴、おんしゃー子供二人じゃ、女子は嫁入りする、男の子は一人で病気にでもかかって死にでもしたら、誰に掛かる。早うすねを放せ、分けて食い合うても育てにゃいかん。」と怒りかかると、鶴は泣く泣くすねを上げて赤子を抱き上げ、首のねじれを直し、背なをさすりながらフーフーと息を吹き掛けた。
すると赤子はやっと息を吹きかえし、「オギャオギャー」と泣き出した。鶴の顔はほぐれて嬉し泣き。家主もほっとくつろぎ、「よかった、よかった、この子はほんとに強い子じゃ。」そして鶴に、「今のような馬鹿なまねは二度とすなよ。この子はええ子になるぞ。」言うて家を出、近所のおなごしを呼んで来て、産湯や後始末を手伝わさした。
その後なぜか鶴に子供は出来なんだ。その時の子供は駒吉と名付けられ、元気ですくすくと育ち、父里吉の跡を継ぎ大工になった。
兄の善太はふとしたことで若死にし、里吉、鶴の老後は駒吉の孝養に掛かることができた。
当時の村落は閉鎖的で、仕事は少なく、労賃も安く、「働けど働けど、我が暮らし楽に成らず」であったので、貧しい家での子育てはほとんど二人で、多くて三人、その後に生まれる子はこっそり産んで、始末して、「月足らずで出来た、ようなかった。」言うて、水子にしてすましていたと。
誠に哀れな悲しい時代の物語。
「愛し子は たれも可愛ゆし 貧ゆえに
殺すと聞かば 仏も泣かむ
念仏の 声にまじりて
花摘み遊ぶ 笑いも聞こゆ」
子育て慶念
「黄金の蔵より子は宝」「貧ほどつらいことはなし」
貧しい哀れな時代、ほんとにあった昔の話を少し。
里吉は大工の職人であるが、当時の田舎では新築などはめったに無く、模様替えなどもたまで、本職の大工仕事より手伝い事が主の日雇いで、老母を抱え妻に子供二人の五人家族で、その日暮らしの貧しい家庭であった。
昔の「いろはかるた」に「貧乏人の子だくさん」というのがあったが、貧しい時代は男は仕事一色で、遊びはあっても遊ぶ間もなく、夫婦は喧嘩もするが仲も良く、子供は後へ後へとよく出来る。
里吉の女房の鶴も、子がよう出来る。去年も生むとすぐ死んだが、また腹がふとい。
近所の家主が、ありゃどうもおかしいと思い、臨月の鶴に気を配り度々伺いよった。
ある朝そっと里吉の家に近付くと、とたんに元気な産声が「オギャーオギャー」と、かん高い。
家主は「できた、できた」と喜んだ。その時、子の泣き声がぷっつり消えた。
嫌な予感が家主の頭を走った。こりゃいかんと障子を開けて上がり、奥のふすまを開けて見てびっくり。鶴はできだちの男の赤子の首をねじってすねに敷き、涙をぼろぼろと流しながら、家主を見て、「恥ずかしい、むごいことじゃが、こうせにゃあ、今でさえ食うや食わずでいきよるに、今この子が増えたら、よけかつえるけ。」と。
家主は慌てて、「こりゃ鶴、おんしゃー子供二人じゃ、女子は嫁入りする、男の子は一人で病気にでもかかって死にでもしたら、誰に掛かる。早うすねを放せ、分けて食い合うても育てにゃいかん。」と怒りかかると、鶴は泣く泣くすねを上げて赤子を抱き上げ、首のねじれを直し、背なをさすりながらフーフーと息を吹き掛けた。
すると赤子はやっと息を吹きかえし、「オギャオギャー」と泣き出した。鶴の顔はほぐれて嬉し泣き。家主もほっとくつろぎ、「よかった、よかった、この子はほんとに強い子じゃ。」そして鶴に、「今のような馬鹿なまねは二度とすなよ。この子はええ子になるぞ。」言うて家を出、近所のおなごしを呼んで来て、産湯や後始末を手伝わさした。
その後なぜか鶴に子供は出来なんだ。その時の子供は駒吉と名付けられ、元気ですくすくと育ち、父里吉の跡を継ぎ大工になった。
兄の善太はふとしたことで若死にし、里吉、鶴の老後は駒吉の孝養に掛かることができた。
当時の村落は閉鎖的で、仕事は少なく、労賃も安く、「働けど働けど、我が暮らし楽に成らず」であったので、貧しい家での子育てはほとんど二人で、多くて三人、その後に生まれる子はこっそり産んで、始末して、「月足らずで出来た、ようなかった。」言うて、水子にしてすましていたと。
誠に哀れな悲しい時代の物語。
「愛し子は たれも可愛ゆし 貧ゆえに
殺すと聞かば 仏も泣かむ
念仏の 声にまじりて
花摘み遊ぶ 笑いも聞こゆ」
子育て慶念
「黄金の蔵より子は宝」「貧ほどつらいことはなし」











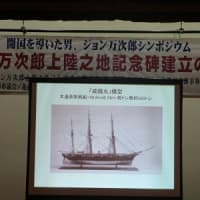







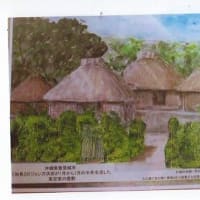
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます