赴任先にたどりついた軍丁は、全員が軍事訓練と防御の任務につくかといえば、そうではない。
明代は、軍隊を基本的には「自給自足」させる方針を貫いた。
特に北辺のモンゴルとの国境に大量の兵士を配備しなければならない情況では、付近の農民の生産力も低く、余剰食糧は多くない。
もし自給しない場合、すべての食糧の費用、またそれを運河で南方から運んでくる輸送費という莫大な費用を負担すれば、国がつぶれかねないからである。
全国の軍戸200万戸から、一戸から一丁(成人男子1人)を出し、戦争がない時も含めて
永久に赴任させ続けるのだから、少なくとも彼らの生きるための食糧が常に必要となる。
常時200万人の軍隊を維持するためには、生きるための最低条件として1人1ヶ月に口糧(食糧)1石を支給すると、
1ヶ月に200万石、1年に2400万石が必要となる。
これは明代の全国の年間総税収とほぼ同じ額である。
屯田という選択しかなかったことが、納得できる。
さて。
赴任した兵士らは、2つのグループに分けられる。
1、「守城旗軍」: 軍人として、日ごろは軍事訓練と防衛を任務とする。
2、「屯田正軍」: 土地を与えられ、農地を耕し、食糧の現物を軍に納める
(「租税」とは呼ばず、「子粒」という)ほか、各種の賦役を負う。
分け方に決まりはなく、恐らく体の壮健なる、はしっこそうな輩は「守城」に優先的に回されたのだろう。
その比率は、例えば京衛軍では、七分が下屯、三分が守城。
遼東では、八分が屯種(屯田を耕す)、二分が守備と巡回。
つまりは2-3割が軍事に従事する以外は、ほとんどすべてが「屯軍」として、
ひたすら百姓仕事に従事しろ、というわけである。
「守城旗軍」には、一応「月糧」が支給される。
「一応」というのは、生活するにはぜんぜん足りないからそういった。
そのために「余丁」がついてきており、生活の糧となる土地も支給される。
それを耕して軍服などを用意したり、家族の生活のために当てたりしなければならない。
妻や両親、兄弟などもついてきていれば、彼らも含めてせっせと働け、というわけである。
逆に上官は、兵士らには「月糧」以外にも収入があることを見越しており、
ちょっとくらいピンはねしても死にはしないとばかりに、何かにつけては横領、差し押さえ、未払いを決め込む。
これが理由で何度も兵士の反乱が起きているのだ。
次に「屯田正軍」には、重いノルマが待っている。
彼らの納めた食糧で、現地の軍糧を賄おうという仕組みなのである。
「屯田正軍」に与えられる土地は、土地の生産性によって、地方によって違うが、南方の水田なら10畝(ムー)、北方は50畝から100畝。
(ムーの広さは、Wikipediaを参考に)
納めるべき「子粒」(穀物の税)は、明初はもっと高かったが、逃亡が相次いだために全国で一律、年間6石、と決められた。
このほかにも馬の飼育、屯草(冬の馬の飼料)、薪の供出、土木工事の使役などさまざまな義務が課せられるのである。
これも本人だけでなく、「余丁」に妻子、家族総出で働くことが期待される。
実際、特に万里の長城を守る北辺の兵士は、生産性の低い土地で、そうでなくてはこなせない。
土地を耕すに際しては、明初の当初は、屯軍一人に対して、農具と牛を1頭支給すると規定されていた。
これも故郷から数千里も離され、地縁のある土地から根っこをごそりと抜き取るように連れて来られたため、
農具、牛を調達してくることができない中では、特に重要となる。
スキやクワといった農具は、金属で鋳造するものなので、一度支給されたら大切に使えば、
何世代も使い続けることもできるだろう。
しかし牛はそういうわけには行かない。
耕牛の不足は、時代が進むにつれてかなり深刻だったようだ。
例えば、我らが舞台・大同/宣府の管轄区では、万全都司(宣府前・左・右の三衛の所属)には
1万頭の牛がいてしかるべきだが、弘治年間の屯牛の数はわずか1128頭。
しかもこれはごく楽観的な数字でしかなく、虚偽の報告を上げて実際はもっと少なかった可能性もある。
ただいくら破廉恥を覚悟しても1000頭程度に報告したということは、現実は推して計るべしである。
では、耕牛の減少は、一体どういう理由が多かったのだろうか。
1、敵の略奪
これまで見てきたとおり、北辺では日常化した異民族の襲撃により、そのたびにあらゆる財産が略奪された。
大同/宣府から甘粛に至るまでの延々と続く万里の長城沿いでは、主にモンゴル勢が、
遼寧では時代が下るほど、女真族の略奪が激しかったのである。
それでも大きな事件の場合は、補充されることもある。
正統14年(1449)の「土木の変」では、数十万人の戦死者を出すという大敗に帰した。
当然のこと、大同/宣府界隈の牛はほぼごっそりとすべて敵に奪い取られていったわけである。
が、この時は後に中央政府が、ほぼ定額どおりに牛を補っているのだ。
2、牛の死亡
むしろこちらがほとんどを占めていたといえる。
あまりの租税の取立ての厳しさに牛を酷使し、過労死させてしまう。
または南方の場合、狭い土地に人々が顔を突き合わせて暮らしているために
牛の飼料となる草、ワラなどを確保することができず、栄養失調で死なせてしまう。
牛だってあぜ道から足を踏み外し、転落死することだってあるだろう。
死なないまでも脚を折り、労働に耐えなくなってしまうこともあるだろう。
あるいは、老死である。
法律では、屯牛は政府から貸し出されるものであり、死なせてしまった場合、
屯軍が弁償しないといけないことになっている。
牛が老死か、病死か、その判断は極めて主観的であり、つまりは予算が厳しくなってきたり、
横領などの腐敗が日常化してくれば、
牛を補充する予算を出すことを上官が渋るようになることは、想像に難くない。
牛が死んでしまう前にオスとメスをかけ合わせれば、子供が生まれるではないか、と思うが、
どうやらあまりそういうシステムが、兵士同士の間で作られていなかったらしい。
遊牧民のように家畜の繁殖のノウハウを持つ民族には簡単にできることでも
例えば、南方からきた一家なら、意外と難しいものなのかもしれない。
各家に1頭しか支給されないということは、単独では実現しない。
よそ者同士の寄せ集まりの衛所の中で、信頼関係がなければできないこの仕事は部外者が想像する以上に難しいことがある。
牛は一回の出産で1頭しか生まない。
長期的な信頼関係をもって1回ずつの出産を持ちまわることも、簡単なように見えて、腰が引けるものである。
耕牛の不足による打撃は、北方のほうが大きい。
南方は温暖な気候で作物がよく育つため、1戸あたりに支給される土地も少ない。
南方は水田が中心。湿った田んぼを牽(ひ)くのは、それほど牛も疲れない。
5-10ムー程度であれば、数軒で1頭の牛を使いまわしても、牛を過労死させるほどではない。
しかし長城付近の農業地帯の最北限では、作物があまり育たないために支給される土地も広大である。
50ムーって、1ムーが99.1736平方メートル、ほぼ100平方メートル弱だとすると、5000平方メートルである。
100ムーなら、1万平方メートル。気の遠くなるような数字だ。
1頭で1万平方メートルも耕させられたら、牛だって過労死するでしょう。
しかも乾燥地帯でがっちがっちに固まった土である。
このため特に遼寧あたりでは本来、牛は1戸に1頭でも足りない、2-3頭が適数だといわれていたらしい。
さもありなん、と納得するが、実際には数頭も支給はなく、1頭しかもらえない。
そのために多くの牛が過労死していったらしい。
これも負のスパイラルの一環である。
牛なしには、畑が耕せない。耕せなければ、作物の収穫が少ない。
そうなると、ノルマの「子粒」が払えない。逃亡するしかなくなる。
・・・・という図式にはまり込んでいくのである。
負のスパイラルは、牛の不足だけではない。
さまざまな要因がいくつにも重なり、軍人の逃亡に歯止めがかからなくなっていく。
その要因をさらに一つ一つ見ていこう。
屯軍に支給される土地は、遠隔地である場合もあった。
特に南方、中原の土地で多く見られた。
つまり、人口の過密なところに軍隊を駐屯させた場合、その周辺の土地はすでに民間人に占拠されており、
政府がそれを屯田のために買い取るのは、莫大な費用になるからできない場合がある。
特に一般に「腹裏」と呼ばれる中国、南方を中心とした国土の中心地では、
民田と屯田が雑居しており、交差しながら複雑に入り組んでいた。
屯田だけを一つの場所にまとめるというわけにいかない。
たとえば、福建訂(さんずいに変える)州衛の左千戸所の屯地は、一部が江西信豊県にあった。
数千里も離れている。
数千里も離れた二つの場所を同時に耕すのは、無理な相談である。
そこで遠隔地の方を人に貸して、小作料を取ることになるが、小作料の取立てだって一苦労である。
前述のとおり、数千里も離れた土地に旅するのは、一財産がぶっ飛ぶ。
しかも遠く離れているから、地元に影響力もコネもない。
そんな情況で小作人が払えない、と居直ってしまった場合、取り立てる手段さえない。
そうなると、遠隔地の土地はしだいに小作人に乗っ取られるか、現地の有力者に乗っ取られるか、という運命しかない。
ところが、納めるべき「子粒」は、減らない。
少ない土地でそのノルマをこなさないといけないのだから、苦しいに決まっている。
このために首が回らなくなることもあったのである。
*****************************************************************
写真:楡林
さて。城壁の陥没部分に突き当たったところで、あきらめて下に降りてきました。
城壁に沿い、少しずつ南に下りていきます。

石畳が続き、風情がありますなあ。

城壁を下から見上げると、こんな感じ。泥の側面がむき出しだっす。
オルドスの砂漠のすぐ南にあるこの地域では、雨があまり降らない、砂漠気候なので、
この状態で明代から500年放置しても崩れることなく、残ってきたのでしょうなあ。

城壁の横にもへばりつくように民家が建てられています。

はるか向こうにお寺が見えます。

通用口発見。城壁にトンネルを開けています。
それにしても奥の深いこと。城壁が如何に分厚いか、よくわかりますな。

城壁と牛ー。

楡林城の東南部分にある「楡林東山関帝廟」。
万暦二十五年(1597)の創建という。

楡林城は、明代のモンゴルとの対峙の際、最も重要な地位にあったにも関わらず、
なんと城内に残る明代の建築群としては、ここが唯一の存在なのだという。
ほかは部分的に残っていても、大きな建築群の塊としては、残っていないということらしい。

手前に見える骨組みは、仮設舞台。
春節期間の出し物のために組まれたらしい。
私たちが訪れたのは、春節のにぎわいも少し納まった頃だったので、静かだった。



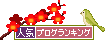

明代は、軍隊を基本的には「自給自足」させる方針を貫いた。
特に北辺のモンゴルとの国境に大量の兵士を配備しなければならない情況では、付近の農民の生産力も低く、余剰食糧は多くない。
もし自給しない場合、すべての食糧の費用、またそれを運河で南方から運んでくる輸送費という莫大な費用を負担すれば、国がつぶれかねないからである。
全国の軍戸200万戸から、一戸から一丁(成人男子1人)を出し、戦争がない時も含めて
永久に赴任させ続けるのだから、少なくとも彼らの生きるための食糧が常に必要となる。
常時200万人の軍隊を維持するためには、生きるための最低条件として1人1ヶ月に口糧(食糧)1石を支給すると、
1ヶ月に200万石、1年に2400万石が必要となる。
これは明代の全国の年間総税収とほぼ同じ額である。
屯田という選択しかなかったことが、納得できる。
さて。
赴任した兵士らは、2つのグループに分けられる。
1、「守城旗軍」: 軍人として、日ごろは軍事訓練と防衛を任務とする。
2、「屯田正軍」: 土地を与えられ、農地を耕し、食糧の現物を軍に納める
(「租税」とは呼ばず、「子粒」という)ほか、各種の賦役を負う。
分け方に決まりはなく、恐らく体の壮健なる、はしっこそうな輩は「守城」に優先的に回されたのだろう。
その比率は、例えば京衛軍では、七分が下屯、三分が守城。
遼東では、八分が屯種(屯田を耕す)、二分が守備と巡回。
つまりは2-3割が軍事に従事する以外は、ほとんどすべてが「屯軍」として、
ひたすら百姓仕事に従事しろ、というわけである。
「守城旗軍」には、一応「月糧」が支給される。
「一応」というのは、生活するにはぜんぜん足りないからそういった。
そのために「余丁」がついてきており、生活の糧となる土地も支給される。
それを耕して軍服などを用意したり、家族の生活のために当てたりしなければならない。
妻や両親、兄弟などもついてきていれば、彼らも含めてせっせと働け、というわけである。
逆に上官は、兵士らには「月糧」以外にも収入があることを見越しており、
ちょっとくらいピンはねしても死にはしないとばかりに、何かにつけては横領、差し押さえ、未払いを決め込む。
これが理由で何度も兵士の反乱が起きているのだ。
次に「屯田正軍」には、重いノルマが待っている。
彼らの納めた食糧で、現地の軍糧を賄おうという仕組みなのである。
「屯田正軍」に与えられる土地は、土地の生産性によって、地方によって違うが、南方の水田なら10畝(ムー)、北方は50畝から100畝。
(ムーの広さは、Wikipediaを参考に)
納めるべき「子粒」(穀物の税)は、明初はもっと高かったが、逃亡が相次いだために全国で一律、年間6石、と決められた。
このほかにも馬の飼育、屯草(冬の馬の飼料)、薪の供出、土木工事の使役などさまざまな義務が課せられるのである。
これも本人だけでなく、「余丁」に妻子、家族総出で働くことが期待される。
実際、特に万里の長城を守る北辺の兵士は、生産性の低い土地で、そうでなくてはこなせない。
土地を耕すに際しては、明初の当初は、屯軍一人に対して、農具と牛を1頭支給すると規定されていた。
これも故郷から数千里も離され、地縁のある土地から根っこをごそりと抜き取るように連れて来られたため、
農具、牛を調達してくることができない中では、特に重要となる。
スキやクワといった農具は、金属で鋳造するものなので、一度支給されたら大切に使えば、
何世代も使い続けることもできるだろう。
しかし牛はそういうわけには行かない。
耕牛の不足は、時代が進むにつれてかなり深刻だったようだ。
例えば、我らが舞台・大同/宣府の管轄区では、万全都司(宣府前・左・右の三衛の所属)には
1万頭の牛がいてしかるべきだが、弘治年間の屯牛の数はわずか1128頭。
しかもこれはごく楽観的な数字でしかなく、虚偽の報告を上げて実際はもっと少なかった可能性もある。
ただいくら破廉恥を覚悟しても1000頭程度に報告したということは、現実は推して計るべしである。
では、耕牛の減少は、一体どういう理由が多かったのだろうか。
1、敵の略奪
これまで見てきたとおり、北辺では日常化した異民族の襲撃により、そのたびにあらゆる財産が略奪された。
大同/宣府から甘粛に至るまでの延々と続く万里の長城沿いでは、主にモンゴル勢が、
遼寧では時代が下るほど、女真族の略奪が激しかったのである。
それでも大きな事件の場合は、補充されることもある。
正統14年(1449)の「土木の変」では、数十万人の戦死者を出すという大敗に帰した。
当然のこと、大同/宣府界隈の牛はほぼごっそりとすべて敵に奪い取られていったわけである。
が、この時は後に中央政府が、ほぼ定額どおりに牛を補っているのだ。
2、牛の死亡
むしろこちらがほとんどを占めていたといえる。
あまりの租税の取立ての厳しさに牛を酷使し、過労死させてしまう。
または南方の場合、狭い土地に人々が顔を突き合わせて暮らしているために
牛の飼料となる草、ワラなどを確保することができず、栄養失調で死なせてしまう。
牛だってあぜ道から足を踏み外し、転落死することだってあるだろう。
死なないまでも脚を折り、労働に耐えなくなってしまうこともあるだろう。
あるいは、老死である。
法律では、屯牛は政府から貸し出されるものであり、死なせてしまった場合、
屯軍が弁償しないといけないことになっている。
牛が老死か、病死か、その判断は極めて主観的であり、つまりは予算が厳しくなってきたり、
横領などの腐敗が日常化してくれば、
牛を補充する予算を出すことを上官が渋るようになることは、想像に難くない。
牛が死んでしまう前にオスとメスをかけ合わせれば、子供が生まれるではないか、と思うが、
どうやらあまりそういうシステムが、兵士同士の間で作られていなかったらしい。
遊牧民のように家畜の繁殖のノウハウを持つ民族には簡単にできることでも
例えば、南方からきた一家なら、意外と難しいものなのかもしれない。
各家に1頭しか支給されないということは、単独では実現しない。
よそ者同士の寄せ集まりの衛所の中で、信頼関係がなければできないこの仕事は部外者が想像する以上に難しいことがある。
牛は一回の出産で1頭しか生まない。
長期的な信頼関係をもって1回ずつの出産を持ちまわることも、簡単なように見えて、腰が引けるものである。
耕牛の不足による打撃は、北方のほうが大きい。
南方は温暖な気候で作物がよく育つため、1戸あたりに支給される土地も少ない。
南方は水田が中心。湿った田んぼを牽(ひ)くのは、それほど牛も疲れない。
5-10ムー程度であれば、数軒で1頭の牛を使いまわしても、牛を過労死させるほどではない。
しかし長城付近の農業地帯の最北限では、作物があまり育たないために支給される土地も広大である。
50ムーって、1ムーが99.1736平方メートル、ほぼ100平方メートル弱だとすると、5000平方メートルである。
100ムーなら、1万平方メートル。気の遠くなるような数字だ。
1頭で1万平方メートルも耕させられたら、牛だって過労死するでしょう。
しかも乾燥地帯でがっちがっちに固まった土である。
このため特に遼寧あたりでは本来、牛は1戸に1頭でも足りない、2-3頭が適数だといわれていたらしい。
さもありなん、と納得するが、実際には数頭も支給はなく、1頭しかもらえない。
そのために多くの牛が過労死していったらしい。
これも負のスパイラルの一環である。
牛なしには、畑が耕せない。耕せなければ、作物の収穫が少ない。
そうなると、ノルマの「子粒」が払えない。逃亡するしかなくなる。
・・・・という図式にはまり込んでいくのである。
負のスパイラルは、牛の不足だけではない。
さまざまな要因がいくつにも重なり、軍人の逃亡に歯止めがかからなくなっていく。
その要因をさらに一つ一つ見ていこう。
屯軍に支給される土地は、遠隔地である場合もあった。
特に南方、中原の土地で多く見られた。
つまり、人口の過密なところに軍隊を駐屯させた場合、その周辺の土地はすでに民間人に占拠されており、
政府がそれを屯田のために買い取るのは、莫大な費用になるからできない場合がある。
特に一般に「腹裏」と呼ばれる中国、南方を中心とした国土の中心地では、
民田と屯田が雑居しており、交差しながら複雑に入り組んでいた。
屯田だけを一つの場所にまとめるというわけにいかない。
たとえば、福建訂(さんずいに変える)州衛の左千戸所の屯地は、一部が江西信豊県にあった。
数千里も離れている。
数千里も離れた二つの場所を同時に耕すのは、無理な相談である。
そこで遠隔地の方を人に貸して、小作料を取ることになるが、小作料の取立てだって一苦労である。
前述のとおり、数千里も離れた土地に旅するのは、一財産がぶっ飛ぶ。
しかも遠く離れているから、地元に影響力もコネもない。
そんな情況で小作人が払えない、と居直ってしまった場合、取り立てる手段さえない。
そうなると、遠隔地の土地はしだいに小作人に乗っ取られるか、現地の有力者に乗っ取られるか、という運命しかない。
ところが、納めるべき「子粒」は、減らない。
少ない土地でそのノルマをこなさないといけないのだから、苦しいに決まっている。
このために首が回らなくなることもあったのである。
*****************************************************************
写真:楡林
さて。城壁の陥没部分に突き当たったところで、あきらめて下に降りてきました。
城壁に沿い、少しずつ南に下りていきます。

石畳が続き、風情がありますなあ。

城壁を下から見上げると、こんな感じ。泥の側面がむき出しだっす。
オルドスの砂漠のすぐ南にあるこの地域では、雨があまり降らない、砂漠気候なので、
この状態で明代から500年放置しても崩れることなく、残ってきたのでしょうなあ。

城壁の横にもへばりつくように民家が建てられています。

はるか向こうにお寺が見えます。

通用口発見。城壁にトンネルを開けています。
それにしても奥の深いこと。城壁が如何に分厚いか、よくわかりますな。

城壁と牛ー。

楡林城の東南部分にある「楡林東山関帝廟」。
万暦二十五年(1597)の創建という。

楡林城は、明代のモンゴルとの対峙の際、最も重要な地位にあったにも関わらず、
なんと城内に残る明代の建築群としては、ここが唯一の存在なのだという。
ほかは部分的に残っていても、大きな建築群の塊としては、残っていないということらしい。

手前に見える骨組みは、仮設舞台。
春節期間の出し物のために組まれたらしい。
私たちが訪れたのは、春節のにぎわいも少し納まった頃だったので、静かだった。





















