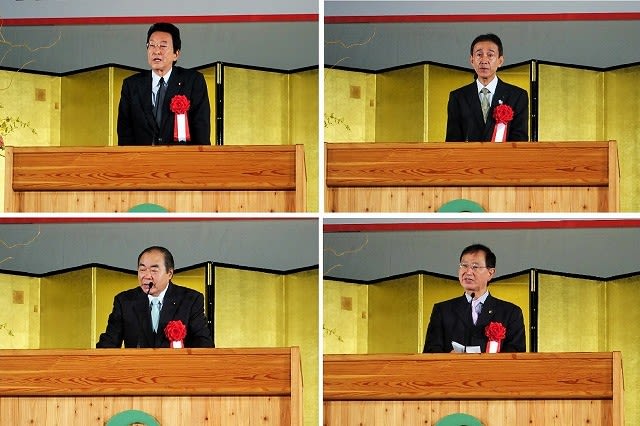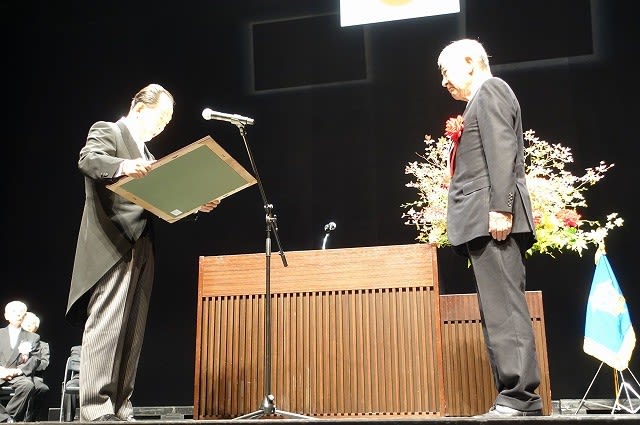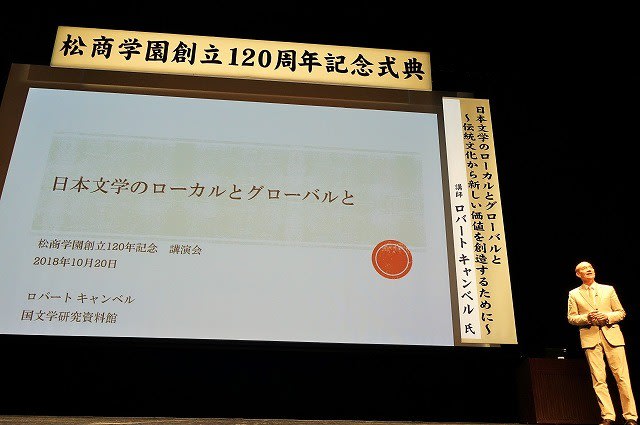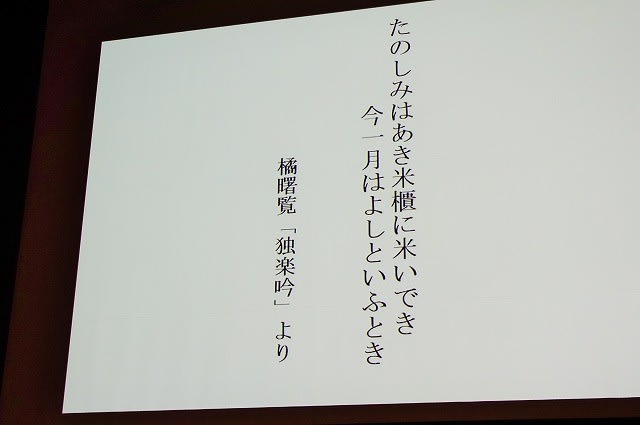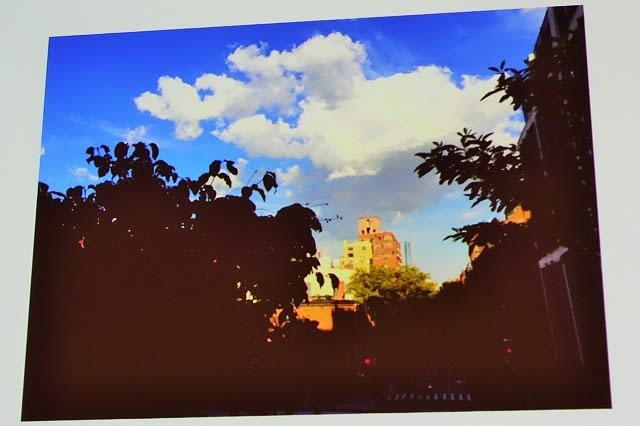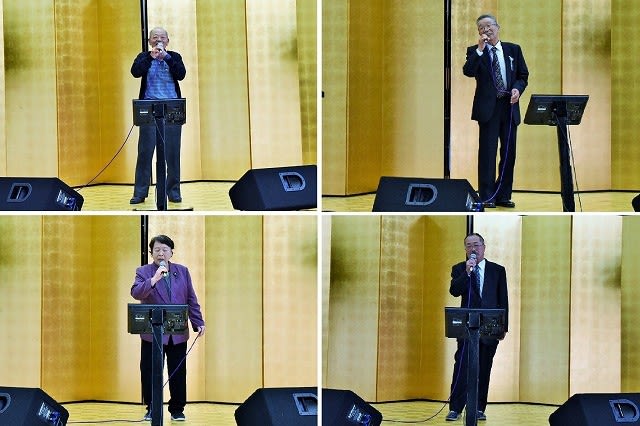22日(月)午後3時から新潟県糸魚川市ホテル國冨アネックスで開催され、(一社)全国治水砂防協会長野県支部の支部長として参加しました。当地区は新潟県・富山県・石川県・福井県と長野県から構成されており、各県の支部長さんか代理の方、参与として各県の砂防課長さんが参加されておりました。
最初に今年度当番県の新潟県出雲崎町長 小林支部長さんの挨拶から始まり、来賓として国土交通省水管理・国土保全局 砂防部 砂防計画課 土砂災害防止技術調整官 林 孝標さんと全国治水砂防協会 理事長 岡本正男さんに、それぞれの立場からご挨拶を頂戴しました。



▽ 自己紹介の後、国土交通省からの提供情報として、「砂防行政に関する最近の話題」と題して、林調整官さんからご講演をいただきました。

平成30年の 3,137件も発生している全国の土砂災害状況、2,000件以上のがけ崩れの発生状況、7月6日の夕方から8日にかけて、11府県で大雨特別警報が発表された平成30年7月豪雨の概要、広島県の平成11年6.29災害、平成26年8.20災害、平成30年7月豪雨災害の雨量・土砂量の比較、TEC-FORCE高度技術指導班による調査、きめ細やかな現地サポート、報道機関にレクチャーなどの活動状況、土砂災害警戒情報の発表状況、土砂災害において避難しなかった主な理由、平素から団地内で避難時の想定をしていたことやコミュニケーションを取っていたなどの避難行動により命を守った事例、ハザードマップの作成等促進の必要性、第1回「実効性のある避難を確保するための土砂災害対策検討委員会」の実施内容、遊砂地等の整備、ライフラインや重要交通網の重点的な保全などの激甚な災害を踏まえた土砂災害対策、土砂災害避難訓練により判明した課題などについて分かりやすく簡潔に説明していただきました。
▽ 次に岡本理事長さんから「風化するのは?」と題して情報提供をしていただきました。

「東日本大震災その後」として、震度5弱を観測した福島県沖地震(H28.11.22 津波高さ4.1m)で41.2%しか避難しなかったことは、被災地でも「心」が風化していて、避難しなかった主な理由は、「大きな津波は来ない」「情報収集を優先」などであり、自己責任の原則を徹底し、地震や津波の危険性を軽視せず、町内で避難を呼びかける体制を整備すべきであるとのことでした。
平成30年7月豪雨で6日の午後10時半ごろで、およそ217万人に避難を呼びかけたが、この時点で実際に避難所に避難していたのは0.3%程度の6,000人余りだったこと、大雨特別警報は、「これまでに経験したことのないような、重大な危機が差し迫った異常な状況にあることを警告している」こと、7月5~8日にかけて指定避難場所への避難は各地区とも3~4%程度であったこと、「自宅は危険性が低い・特に被害が無かった」などが8割以上で、水平避難をしなかった理由などをご説明いただきました。
「行政は知らせる努力・住民は知る努力をしよう」として、市町村長は、災害が発生する恐れがある場合等に住民が適時的確な判断ができるよう、一人ひとりの居住地等にどの災害のリスクがあり、どの様な時に、どの様な避難行動をとるべきかについて、日頃から周知徹底を図る取組を行うことが重要であること、「災害時にトップがなすべきこと」として、日頃から住民と対話し、危機に際して行う意思決定について、あらかじめ伝え、理解を得ておくことや、避難勧告・指示は、真夜中であっても、たとえ空振りになっても、人命第一の観点から躊躇なく行うこと」など、多岐にわたり分かりやすく情報提供していただきました。

各県の提出議題として「住民避難を円滑に進めるための取り組みについて」「土砂災害ハザードマップの周知の徹底について」「避難勧告等の発令に対する避難状況について」「土砂災害警戒情報発表後の避難勧告等発令のタイミングとその伝達方法について」「要配慮者利用施設における避難確保計画策定等に向けた砂防部局の取り組みについて」を各県から議題として提出していただき、他の県が現状の取り組み等について回答していただき、更に全員で協議をしました。


全国治水砂防協会岡本理事長さんから、本年の災害を踏まえた、今後の砂防行政における課題と国(砂防部)、都道府県、協会に臨むことについて、各支部長に意見を求められ、予算が厳しい中、規制を厳しくすること、ハザードマップの周知徹底に努めること、河川の土砂の浚渫をすべきであること、一時避難所を多く設けることなどの発言があり、私からは、11月20日の促進大会で長野県の首長や関係者は砂防事業の重要性を認識されていて、今回も全国の一割近くの皆さんが参集され要望活動をしますので、みんなで力を合わせて砂防関連予算の確保をして、ハード・ソフト一体となって、防災・減災対策を進めましょうなどと発言させていただきました。
今回も各県での避難勧告等の発令による避難の進め方、ハザードマップの周知方法、土砂災害警戒情報の発表による対応など、防災・減災のソフト対策はかなり進んでいると感心させられ、当村での防災・減災対策として参考になる事例があり良い勉強になりました。

▽ 朝の写真は雲根集落上空からの風景です。




その他生坂村では、小学校で認め育む週間、中学校で3年総合テスト・標津町との交流事業打合せ、児童館でおはなしひろばなどが行われました。
最初に今年度当番県の新潟県出雲崎町長 小林支部長さんの挨拶から始まり、来賓として国土交通省水管理・国土保全局 砂防部 砂防計画課 土砂災害防止技術調整官 林 孝標さんと全国治水砂防協会 理事長 岡本正男さんに、それぞれの立場からご挨拶を頂戴しました。



▽ 自己紹介の後、国土交通省からの提供情報として、「砂防行政に関する最近の話題」と題して、林調整官さんからご講演をいただきました。

平成30年の 3,137件も発生している全国の土砂災害状況、2,000件以上のがけ崩れの発生状況、7月6日の夕方から8日にかけて、11府県で大雨特別警報が発表された平成30年7月豪雨の概要、広島県の平成11年6.29災害、平成26年8.20災害、平成30年7月豪雨災害の雨量・土砂量の比較、TEC-FORCE高度技術指導班による調査、きめ細やかな現地サポート、報道機関にレクチャーなどの活動状況、土砂災害警戒情報の発表状況、土砂災害において避難しなかった主な理由、平素から団地内で避難時の想定をしていたことやコミュニケーションを取っていたなどの避難行動により命を守った事例、ハザードマップの作成等促進の必要性、第1回「実効性のある避難を確保するための土砂災害対策検討委員会」の実施内容、遊砂地等の整備、ライフラインや重要交通網の重点的な保全などの激甚な災害を踏まえた土砂災害対策、土砂災害避難訓練により判明した課題などについて分かりやすく簡潔に説明していただきました。
▽ 次に岡本理事長さんから「風化するのは?」と題して情報提供をしていただきました。

「東日本大震災その後」として、震度5弱を観測した福島県沖地震(H28.11.22 津波高さ4.1m)で41.2%しか避難しなかったことは、被災地でも「心」が風化していて、避難しなかった主な理由は、「大きな津波は来ない」「情報収集を優先」などであり、自己責任の原則を徹底し、地震や津波の危険性を軽視せず、町内で避難を呼びかける体制を整備すべきであるとのことでした。
平成30年7月豪雨で6日の午後10時半ごろで、およそ217万人に避難を呼びかけたが、この時点で実際に避難所に避難していたのは0.3%程度の6,000人余りだったこと、大雨特別警報は、「これまでに経験したことのないような、重大な危機が差し迫った異常な状況にあることを警告している」こと、7月5~8日にかけて指定避難場所への避難は各地区とも3~4%程度であったこと、「自宅は危険性が低い・特に被害が無かった」などが8割以上で、水平避難をしなかった理由などをご説明いただきました。
「行政は知らせる努力・住民は知る努力をしよう」として、市町村長は、災害が発生する恐れがある場合等に住民が適時的確な判断ができるよう、一人ひとりの居住地等にどの災害のリスクがあり、どの様な時に、どの様な避難行動をとるべきかについて、日頃から周知徹底を図る取組を行うことが重要であること、「災害時にトップがなすべきこと」として、日頃から住民と対話し、危機に際して行う意思決定について、あらかじめ伝え、理解を得ておくことや、避難勧告・指示は、真夜中であっても、たとえ空振りになっても、人命第一の観点から躊躇なく行うこと」など、多岐にわたり分かりやすく情報提供していただきました。

各県の提出議題として「住民避難を円滑に進めるための取り組みについて」「土砂災害ハザードマップの周知の徹底について」「避難勧告等の発令に対する避難状況について」「土砂災害警戒情報発表後の避難勧告等発令のタイミングとその伝達方法について」「要配慮者利用施設における避難確保計画策定等に向けた砂防部局の取り組みについて」を各県から議題として提出していただき、他の県が現状の取り組み等について回答していただき、更に全員で協議をしました。


全国治水砂防協会岡本理事長さんから、本年の災害を踏まえた、今後の砂防行政における課題と国(砂防部)、都道府県、協会に臨むことについて、各支部長に意見を求められ、予算が厳しい中、規制を厳しくすること、ハザードマップの周知徹底に努めること、河川の土砂の浚渫をすべきであること、一時避難所を多く設けることなどの発言があり、私からは、11月20日の促進大会で長野県の首長や関係者は砂防事業の重要性を認識されていて、今回も全国の一割近くの皆さんが参集され要望活動をしますので、みんなで力を合わせて砂防関連予算の確保をして、ハード・ソフト一体となって、防災・減災対策を進めましょうなどと発言させていただきました。
今回も各県での避難勧告等の発令による避難の進め方、ハザードマップの周知方法、土砂災害警戒情報の発表による対応など、防災・減災のソフト対策はかなり進んでいると感心させられ、当村での防災・減災対策として参考になる事例があり良い勉強になりました。

▽ 朝の写真は雲根集落上空からの風景です。




その他生坂村では、小学校で認め育む週間、中学校で3年総合テスト・標津町との交流事業打合せ、児童館でおはなしひろばなどが行われました。