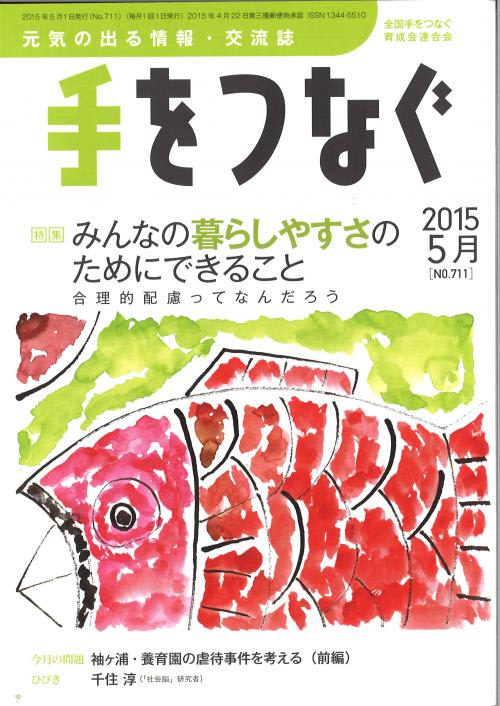元気の出る情報・交流誌「手をつなぐ」が届きました。
(今回の表紙は・・・浦ちゃん・・・?(*^^)v)
今月の特集は
・求められる 家族への支援
家族支援プロジェクトのファシリテーターをやったことのある身としては
とても気になる見出しが満載です。
そして、パラパラとページをめくると私のアンテナに
ピピッ!
と反応する文章のオンパレードです。
子どもの障がい告知を受容することの難しさを
私も何回かこのブログに書いたことがありますが、それも書かれています。
そこには、わが子には障がいがあると認めてからも、揺れる親の心情を
見守る相談員の視点が必要なことも書かれています。
そして、やっぱりありました!
「手をつなぐ」の編集委員でもあり、「家族支援プロジェクト」の開発委員でもあった
西村玲子さんの記事「参加型の研修で(日常)を見直す 家族支援プロジェクトとは?」
7年前(もうそんなに経つのですねぇ)に全日本手をつなぐ育成会が開発したものです。
正式名称は、
「親自身が変わろう!知的障害者親の会によるわが子の権利擁護・地域生活支援プログラム開発」
そしてもう一つ「障害認識プロジェクト」の正式名称は
「障害とは何か~知的障害者親の会による障害認識・啓発プログラム開発」
あれは私がまだ事務局に入ったばかりの頃でした。
ある日、全日本手をつなぐ育成会からファシリテーター養成講座の案内がきました。
養成講座参加には条件が付いていました。
・家族に障害のある人がいること
・年齢が55歳以下であること
・各県1人以上、講座受講に派遣させること
当時の事務局でこの条件に当てはまるのは私(F)しかおりませんでした。
ということで、当時の事務局長から「当てはまるのはFさんしかいないから行ってきてね」と軽く言われました。
当時の私は「えぇ~~~~~~(@_@)私ですかぁ~~~~~」
「あのぉ・・案内には、受講後は地元でワークショップを開いてもらいますとありますが、
これは、私がやらなくちゃならないってことですかぁ????」
というように、かなり後ろ向きの意識でおりました。
で、あくまで業務命令で講座を受講しに東京に出かけたわけですが、
講座の会場についてみたら、全国から集まってきたやる気マンマンの受講生の熱気と
とっても納得できる内容に乗せられてしまい。
「これは絶対に山形でもやらなくちゃ!」と思ってしまった私がおりました。
あ、自分の話が長くなりました・・・・
そしてやはり、家族支援プロジェクトの開発委員長の明星大学教授吉川かおり先生の
「育成会だからこそできる家族支援とは」という記事もあります。
今月の「ひびき」もぜひ読んでほしいです。
「アール・ブリュット」は誰のためか
という見出しです。
実際に知的障がい者の生活支援員として働いてきた人です。
展覧会に出品する際や商品化をすすめる際に主導権を握っているのは
担当スタッフであり、その一挙手一投足で障がいのある人たちの
運命は変わってしまう。
「才能がある」とみなされた障がい者は、まるでベルトコンベアに乗せられるかのように
日々絵を描いたり、粘土をこねる生活を送るようになる。
この部分を読んだ時、ハッとさせられました。
その他の部分にも、う~~~ん、と気づかされるものが多かったです。
そして、先月号からの続き「袖ケ浦養育園の虐待事件を考える」があります。
本当に読めば読むほど、保護者の気持ちとはかけ離れた施設の考え
支援員、管理者、理事長の無責任さに怒りがこみ上げてきます。
本当に何度も何度も書いていますが、このような事件が報道されるたび
怒りと共に虚脱感に襲われてしまいます。
先日も、知的障がい者施設で支援員から虐待をうけているようすが
隠しカメラなのでしょうか動画で撮影されていたものがあり、
ニュースで報道されていました。
本当にもう勘弁してほしいです!!!!
最後の方には、各地の育成会のリーダーの中には、
施設の運営法人で理事等に就いている人もいるでしょうが、
そうした任にある人は、理事会で書面に目を通して終わりではなく、
現場を訪れ、職員や利用者と話してほしい、
おかしいと思うことがあれば質問し、指摘し、是正してください。
との文章もありました。
本当です、どうかよろしくお願いします。
手をつなぐは準備が整い次第発送いたしますのでしばらくお待ちください。
ご訪問ありがとうございます(F)
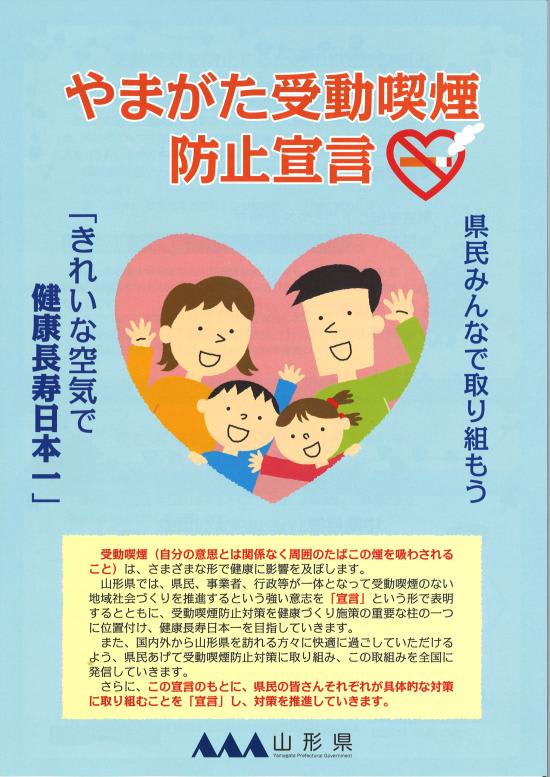
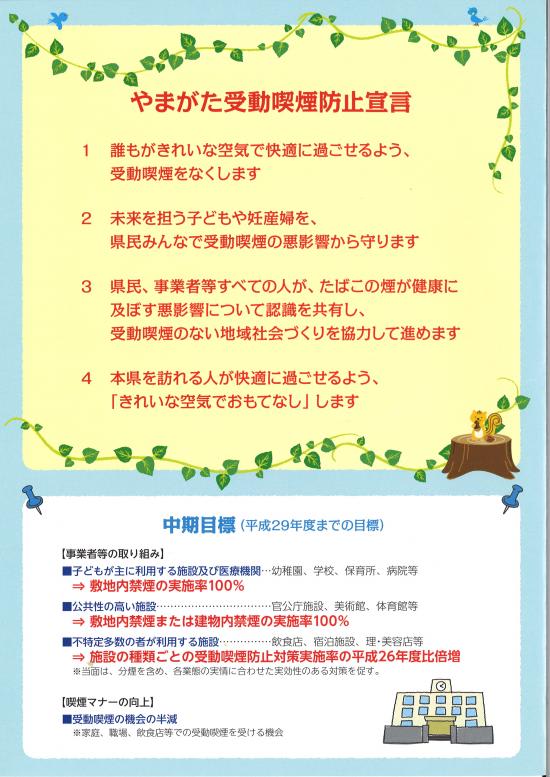


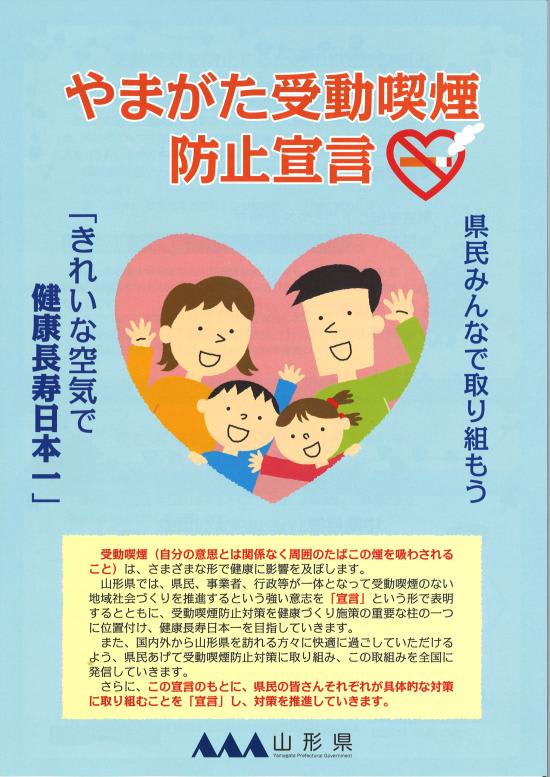
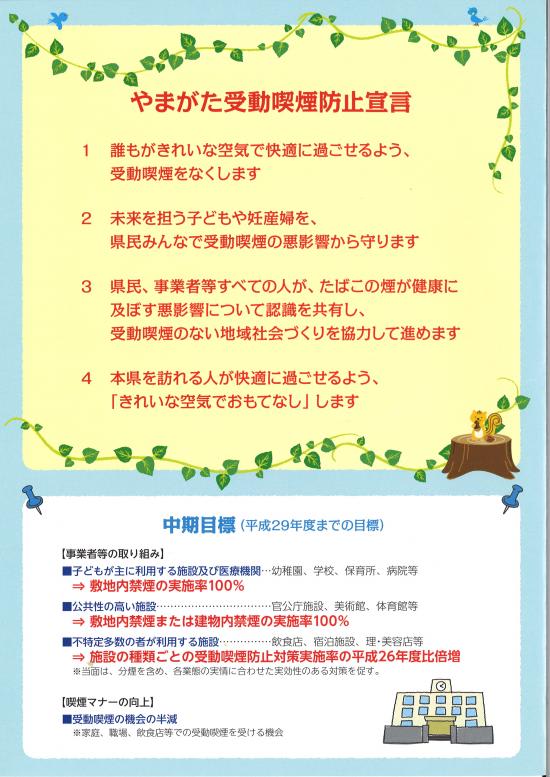













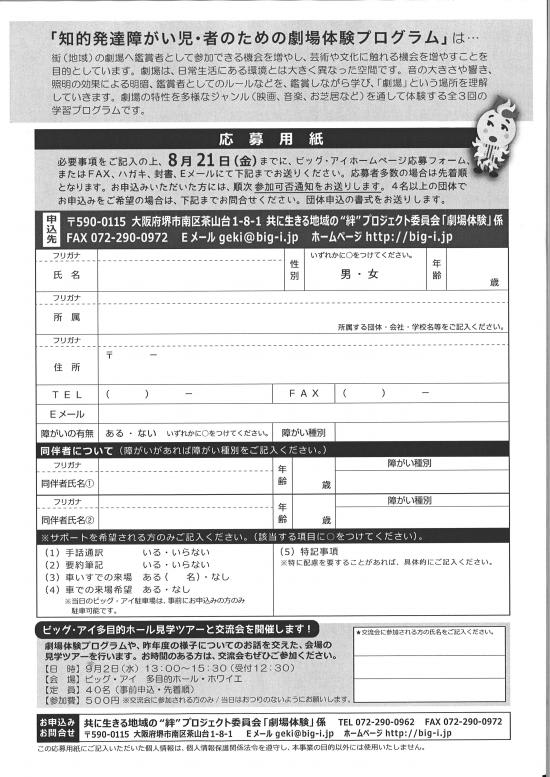
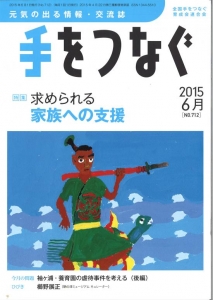

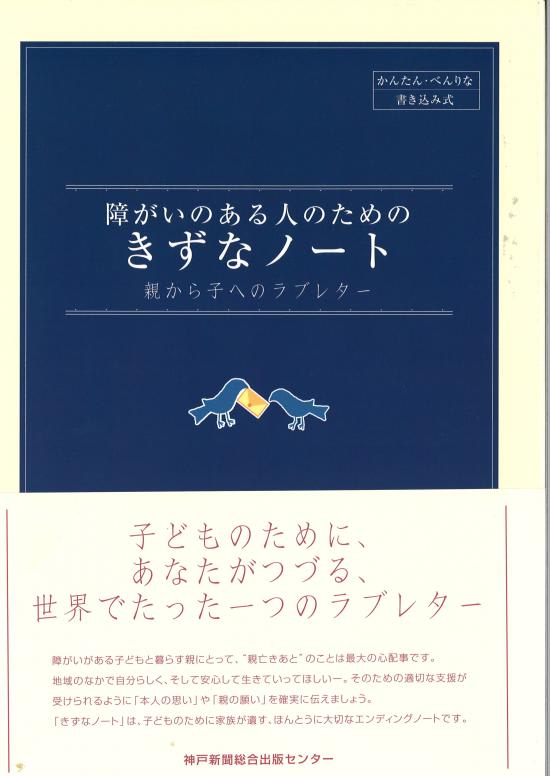

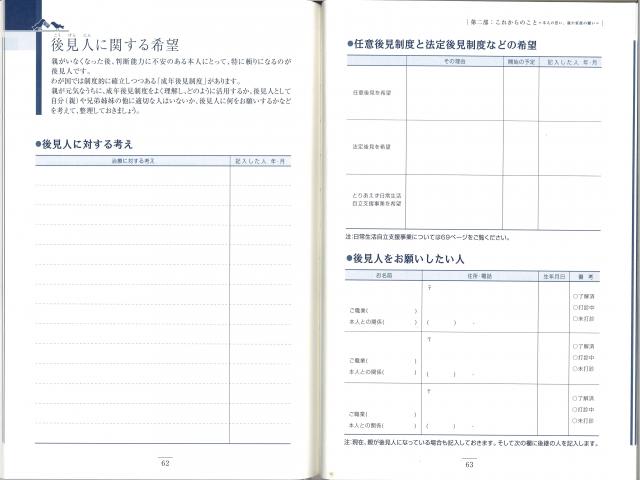

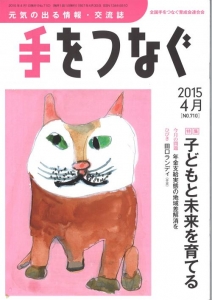




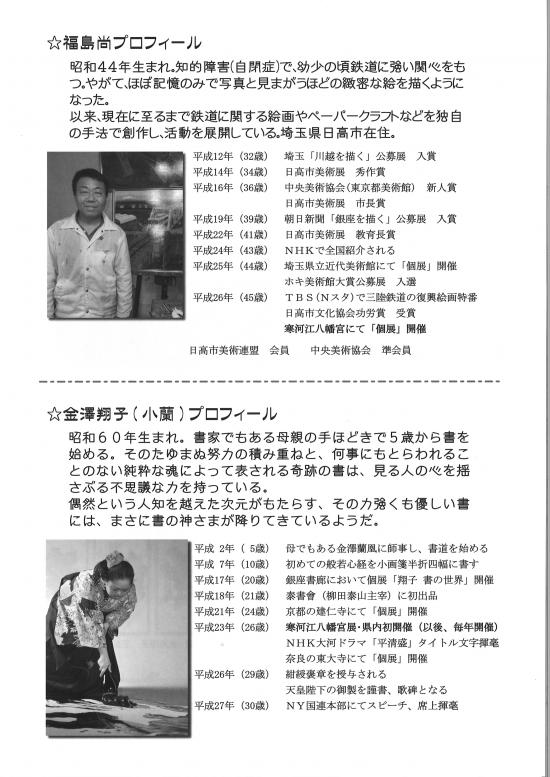
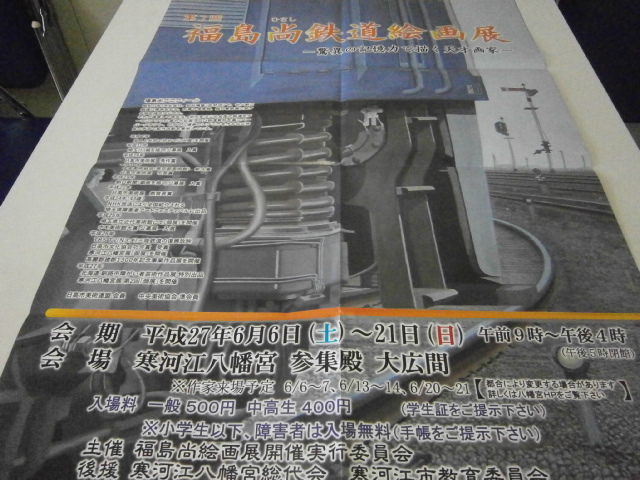
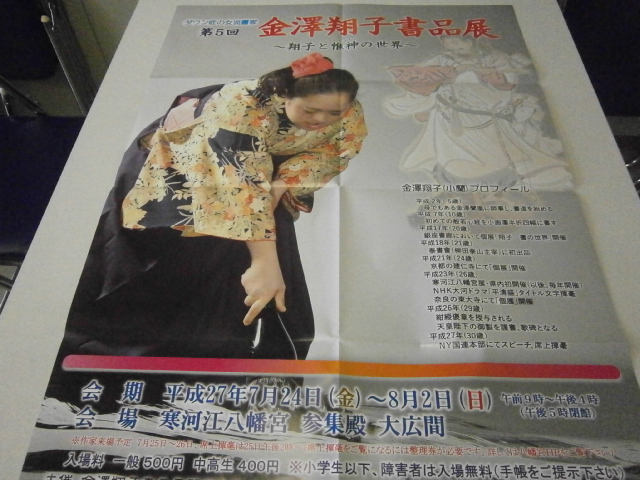
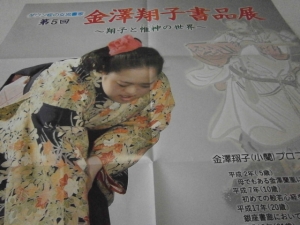
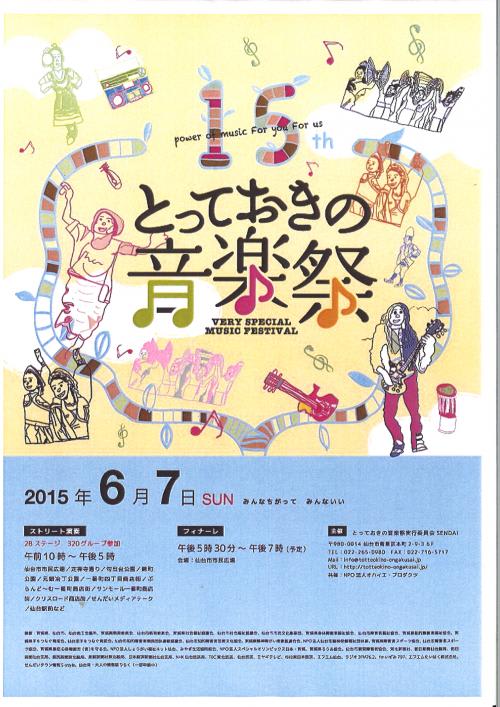


 の時期に入りますが
の時期に入りますが
















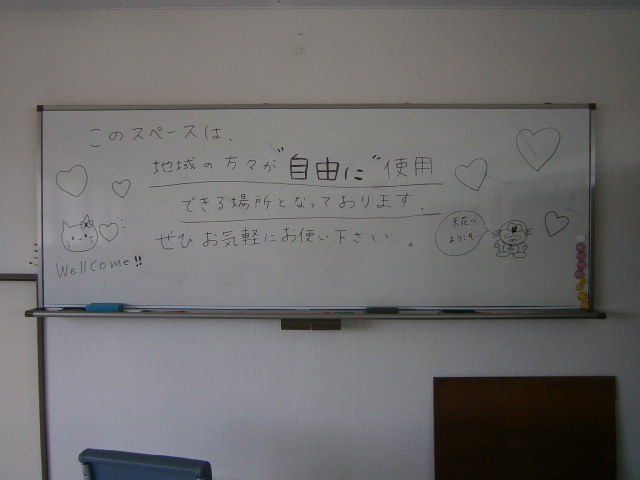








 してしまいます。
してしまいます。
 です)
です)

 見てやってくださいm(__)m
見てやってくださいm(__)m