
ユール=マーシュマロウ
マーシュとマロウの牧場の息子、ユール
シオより年下
双子と同い年くらい、か、下
双子が年下を義兄さん、って呼ぶのも面白いかな?程度の意味合いで下
これを考え出すとまた年表作って辻褄を合わせないといけないので
ほったらかし
(大体シオのSS書いた時点でもうところどころ辻褄合わないところあるだろうなあと思ってかなりめんどくさいことになっている)
(うちのSSは漫画で言うところの絵コンテみたいなかなり雑い殴り書き状態であるのよなあSSの看板外せよなあ、っていう)
(目を通してくださっている方がおられましたら申し訳ない)
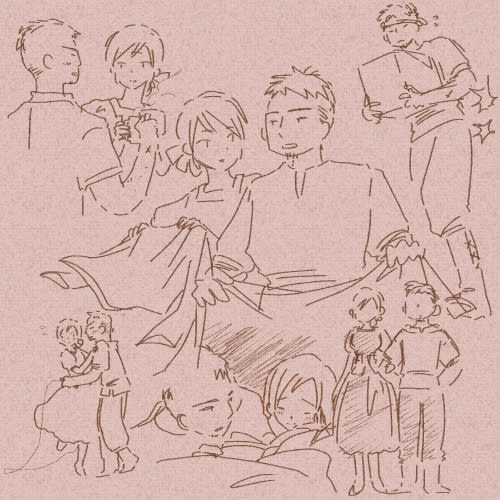
ユールの体格
背の高さの差はないか、シオが少し高いくらいでもいい感じ
中肉中背でありながら牧場仕事で四肢はぶっとい
(とかありえるだろうか?)
こんなイメージだけで彼を今日初めて描きました!
姉妹で夕食の後片付けを分担していたところへ、母と双子が戻ってきた。
「ええ?シオ姉ってば、戻ってたの?」
「なんで家で食事しちゃってんの?!」
炊事場でミオの洗った食器を拭いて仕舞っているシオの姿に双子の声が重なる。
そう言いながらシオの返事は待たずに、ミオへ向き直る。
「あんたさあ、シオ姉が帰ってきたら連れてくるでしょ普通!酒場に!」
「なんのためにあんたを残してったのよ、気が利かないわあ本当に」
「えっ、えっ、えっ」
「あーあ鈍臭さあ!ここまで鈍臭いとは思わなかった」
「あたしたち今まで酒場でシオ姉待ってたんだけど」
二人に詰め寄られて、ようやく自分の役目を理解したらしいミオがごめんなさいを連呼するのは昔から見慣れた光景で。そんな姉妹の様子には無関心らしく、さっさとダイニングの方へ足を向けてソファーに腰を下ろす母もまあ、普段通り。
気が利かない、というより、経験が足りてないんだわ。とシオは思う。なるほど、父とばかり過ごしていたミオには、三人は酒場に行った、と伝えることはできても、そこにシオを連れて合流しようとは思い至らないだろう。
でも。
「良いのよ、あたしが酒場に行く気分じゃなかった、ってだけ」
とのシオの言葉に、双子が面白くなさそうにブスくれながらダイニングのテーブルにつく。
「はーいはい、そうやってシオ姉が庇ってばっかで、どんくさがちっとも治らないじゃないのー」
「庇ってるんじゃないわ。行きたきゃ勝手に行くわよ、ミオを放ってでも」
「シオ姉の気分はどうでも良いのよ、今はミオが鈍臭いことに重きを置くべきよ」
「どうでも良く無いでしょうが。私が行きたくないものをミオがどうしようってのよ」
「そこだよ、シオ姉の甘いところ!これがあたしだったら、そんなに連れて行きたかったらぶん殴ってでも連れていくがいいわ、とか言う癖に!」
「そしてマジでぶん殴ってくるくせに!」
「それはあんたらのわがままがしつこいからでしょうよ!」
他愛無い言い合い、口喧嘩とも言えないただの文句の応酬が始まる。昔からのありきたりな光景。ミオといえば身を縮こまらせて物陰に隠れるか、父がいれば父の背中にひっついているかしているのが当たり前になっていた日常だったけれど。
「皆様!お疲れ様です!!お茶を淹れました!お茶で穏やかに!和みましょう!」
と、ミオがトレイにティーポットと人数分のカップを用意して入り込んできたのには、誰もが我を忘れ、奇妙な静寂がその場を支配した。
それも一瞬。
「なあぁにが、和みましょう、だ!?今あんたの文句を言ってんだわ、こっちは!」
「あんたへの文句のせいで和めて無いんだわ!判れ!」
「は、はいぃっ、すみませんすみません!」
あら意外と。と、シオは妹たちを見る。打たれ強くなっているようなミオも意外だが、それに対する双子もなんだか昔とは違うような。
そこに母の声。
「おや、良い香りだ」
ソファに身を預けて、こちらの騒ぎはどこ吹く風、を決め込んでいた母が少し身を起こしたのをきっかけに、ミオがお茶を注いで回る。
「お、お茶です」
と、真っ先に淹れたハーブティを母の元に届けるだけで、緊張している末の妹。
「見りゃわかる」
とそっけなくあしらわれて、「は、はい」と、すごすご引き下がっている様子には助け舟を出すつもりもない。
皆んなが戻った時に、一息つけるように、と準備をしていたのはミオの気遣いだ。
後片付けをこなしながら、酒の余韻を邪魔しないような茶葉を選んで湯を沸かして蒸して、帰りを待つことができる。決して気が利かないのではない。
「あ、ほんと、これ良い匂い。あんたが買ってきたの?どこの?」
「えと、砂漠の、ご城下の月初の市で、行商に来られてる方が、東から来たって」
「あー、まどろっこしい!砂漠ね、砂漠」
気が合わないんだわ、単純に。
「あ、砂漠、じゃなくて」
「良い、良い。またなんかあったらあんたに買ってきてもらうから」
「あ、はい!喜んで!」
使いっ走りをやらされて喜ぶな。
対等に、とはまだまだいかないのだろうけれど。
昔のような、あからさまな弱者と強者という割合でもなく。
(可笑しい)
と少し笑う。双子は、いつもミオは庇われているというのが不満のようだけれど。もうその不満は形だけのものになっているのかもしれない。
「シオ姉は呑気に笑ってる場合じゃないのよ」
「そうよ、今日だって酒場でシオ姉の結婚相手は誰かって盛り上がってたのに」
「なっ!!?」
盛り上がってた、じゃない。盛り上げた、だ。絶対。その話を持ち込んで酒のアテにされているくらい、わかりきっている。
今までもそう、母が戻っている今なら特に母の取り巻きや、同士が村に集まっている。母世代の女性たちにはシオもよく面倒を見てもらっていただけに頭が上がらなかったりするのだ。
「絶対、行かないわ!」
「でも大体見当はついてる、って言ってたわよ」
「はあ?誰がよ!?」
「ジャヘイラ」
ジャヘイラーーーー!!!
母より3つ上の女性、村の中心部で長老会の筆頭だ。もちろん、シオも幼い頃から可愛がられ、独立するまでは彼女の右腕として信頼もされていたほどの仲では、結婚にもあれこれ口やかましかったのだが。最近ではすっかり興味を失われたものだと思っていたのに。
「牧場屋の倅だってね」
という声に、その場の全員が母を見た。
母はしれっとお茶を啜ってみせる。シオの返答次第では、よからぬ何かが勃発する。そんな空気、母と娘だけが感じる緊張がそこにあって、シオは腹を括った。
「そうですけど?」
それが何かあなたに関係ありますか?という虚勢は、母にはまるで関係がなかった。
あったのは双子の方だ。
「はああ?!牧場、牧、……ユール?!あの?!」
「行商の?うどの大木のユール?!」
ああ、もううるさい。双子のこの反応は大体予想がついていた。姉には、一国の皇女さえもが羨ましがって一月かけて村まで見にくるほどの男(誰だそれは)が婿入りするはずだ、そうでなければ認めん、などと常日頃ほざいているくらいだから。
「うるさい。黙れ。母さんのそれはどこ情報なのよ」
やはりジャヘイラ、その取り巻き当たり、と年配の女性らの抜かりのなさを失念していた自分に苦いものを感じていれば。
「あの人だけど?」
とこともなげに言われて、ぐうの音も出ない。
(父さんんんん…!!)
当然か。
父がそれを秘匿する理由はない。
シオの意思を伝えたことはなかったが父には全てお見通しだというだけ。
「えええー、まじなの。まじで、あれなの。あの、なんの取り柄もない行商しか能のないぬぼーっとした、あいつなの」
「もはや言い表す言葉が、男というだけしかないような、あんな普通な男のどこが良いのよ」
うなだれテーブルに突っ伏している姉にかける言葉がそれか、とシオは双子に向き直る。
「普通のところよ」
どこにでもいるような、ありふれていて、当たり前のもの。そこにあるのが当然の、なんの疑問もない、そんな人が自分を選んでくれるという、それこそがシオにとって何にも変え難い、「特別」。特別の中の、一等級の普通。
「普通なのが良いのよ」
という地を這う声音での答えに、双子はそれでも不服そうで。
仕方ない、シオだって、ついさっきそこに辿り着いたわけで。
「ええー、理解できなーい。誰でも良いんじゃーん、それ」
「ホントだよ、最終的に選んだのがそれって、逃げ打ったのかって言われんじゃん」
わかってもらえるとは思っていないが。
「うるさいな!あんたらのために結婚するんじゃないんだわ!!」
「ううわー、結婚する気だ」
「マジでする気だ、あれと」
する、っつってんだろうが!とシオはキレた。
「言っておきますけど!確かに私は、ミオが一人前になるまでは結婚しないって言ったわよ!けど結婚するからには、私が選んだ世界中でただ一人の男とするわよ!私の意志で!宣誓とか、ケジメとか関係ない、私の!意志で!」
熱が入るあまり、立ち上がって、倒れた椅子の音も聞こえなかった。
部屋にしばしの静寂。
なんだこれ。ああ、なんだか最近よくこんな雰囲気になるな、この家。うん、まああれだけど、原因はミオだったけど。え?いや、あれ、これ、私ミオみたいじゃない??
キレ散らかして我にかえる。末の妹を見るなり。
ミオは、口を半開きに目を潤ませている。何やら感極まって、また何かやらかしそうだ、とこっちが冷静になったのも束の間。
「うん、まあそれが聞けたから、良いわ」
「そうね、シオ姉が自分でそういうの、待ってたんだわ」
と双子に言われて、そっちを振り向く。
「はあ?!」
そこに母の声。
「まったく、世話の焼ける長女だね」
それに追従する双子。なんだか理解が追いついてなくて首振り人形のように全員の顔を見回している末の妹。
「な、んだ、って?」
「シオ姉が腹括ってくれるの待ってたら、老婆になっちまうよ、ってジャヘイラが言うもんでさあ」
「どうすれば腹括ってくれるだろうねえ、って話してたんだけど」
「もう全員で言いくるめるしかないから連れてこいって話になって」
「いやあ、ユールだとは思わなかったからびっくりしたわ」
「びっくりしたけどなんかうまくいったわ」
嵌められた。
酒場での酒のつまみは、シオの意中の相手探しではなく。
結婚宣言への布石だったわけか。
「ジャヘイラたちがそれ一番聞きたかったと思うよ?」
「ホントよ、いっつも村にいない母さんがちゃっかり良いとこどりしてるわ」
まあジャヘイラは母親ヅラしてたから悔しがるだろうよ、と母は鼻で笑う。
「できる女、ってのはこういうことよ」
なんて言う得意満面に鉄球をぶちかましてやりたい。
「母さんをできる女だと思ったことなんかないわ!母さんのは、狡い女っていうのよ!」
「ああ、はいはい。負け犬の吠え面かいてないで、とっとと式の日取りを決めてくれないかね。こっちにも、色々と準備、ってもんがあるんだよ」
憎ったらしいたらありはしない。母には勝てない。喧嘩のやり方、なんてミオにしたり顔で言っておいて、それを一番わかっているのは自分だ。
「だ、誰が式をあげるって言っ」
「うわ、恥知らずにも式を上げないつもりかい?!それがどういう親不孝か、わからない阿呆な娘だとは思わなかったわ」
「お、親不孝って」
「花嫁の父になる名誉も与えられないとか、村中でうしろゆび刺される父親にするつもりなの、あんた」
あんなに育ててもらっといて、というのには、さすがに反論できない。
「父さん、には、ものすごく育ててもらった恩があるわよ、そりゃ」
でもそうなったのはそもそも母さんが。母さん、が、準備?準備って?
「準備って、何よ?」
「はあ?あんた村の結婚式、なんだと思ってんの。その家の権力をこれでもかと村中に知らしめる一大行事だよ。下はもとより上は長老会までももれなく全員一人残らず、平伏させてやるわ!」
「カー!!かっこいい!それでこそ母さん!!全面協力を惜しまないわ!」
「良いねえ!痺れる!!私もなんでもやるわ!母さんについてく!!たのしみぃ!!」
ちょっとやめてよ!!と必死なシオの講義も虚しく、母と双子はそれぞれが考え得る最高権力を見せびらかす算段で盛り上がる。
これが。これが、結婚を延ばしに延ばしたシオへの当てつけだけで行われるというのだから、恐ろしい。
暖かく祝福してくれ、とは言わない。そんな柄じゃない。だが何かが違う。と、震えるシオに、末の妹が近づく。
「お、お姉さん」
そうだ、味方がいた。唯一の味方、といえば頼りないが、シオの考えられる範囲内での常識人が、ここに。
「ミオ、あのねえ」
「私っ、お姉さんの花嫁衣装を作るお手伝いがしたいです!!あっ、多分、お父さんがドレスを作りたい、っていうと思うんですけど!ブーケ、ブーケなら良いですか!?それとも、ベールを作らせてもらっても?!」
だめだ!こいつも味方にならない!!
「お!なかなか根性あンじゃん、見直したよミオ!村の伝説になるくらいの、なっっっっがーいやつ作ってしこたまビビらせてやろうぜ!」
「はいっ頑張ります!」
頑張るな!!
グラグラする頭を抱える。こうなったらもう、おそらく、父も味方にはならないだろう。権力を誇示する結婚式へと、家族総出でまっしぐら、だ。
逃げちゃおうかしら。
それ以前に、結婚相手が逃げちゃわないかしら。と、シオの結婚相手、ユールの顔を思い浮かべる。
いやあの人は、逃げない。それどころか、生真面目に、自分はどの部分を手伝うべきだろうか、と伺いにくるだろう。
ああ。わかっている。腹を括った以上、もうどの方向にも引くことはできないことくらい、わかっていたのだ。
今のシオにはただ、こんな大事になるなんて!!という虚無を抱くのみ。
それを横目に、母が鼻で笑う。
「何しけた面してんだい。最高の親孝行をさせてやろう、ってんだから、もう少し気楽にできないもんかねえ」
勝手を言ってくれる。
そうだ、ここで引いてはならない。母への闘争心だけでシオはここまでやってきたのだ。死ぬまで、母と娘を繋ぐのは闘争心であるのみ!!
「そうね、ありがたいと思うことにするわ。いつ帰るか知れなかったことを思うとね、親孝行させてくれる、っていうんなら、老後の看取りまでしっかり介護させてもらうわ」
娘として精一杯の虚勢。母に弱みは見せない。という一心で口から出た自分の言葉に、シオは胸を突かれる。
そうだ。母も、娘に弱みを見せはしないだろう。老いていく己を、かつて競い合った相手である娘の手に委ねることは屈辱ではないのか。それを良しとせず、村の女は老いてなお戦いの場へ死地を求める。祖母がそうだったように。村の外へ出て。
また父を一人にしてしまう。
そんなシオの胸の内を読んだように、じっと視線を合わせてきた母に言葉を失う。妹たちも、その空気に押し黙った。何度目かの静寂。
それを温度というなら、冷えたそれが嘘のように、ぬくもりに変わる。
母が、見せた微笑は、おそらく母性。
「そうだね、最期の最期まであんたに面倒かけてやるとするかね」
シオだけに感じ取れた母性。永遠のような、一瞬。
「それ、どういう」
どういうつもりで言っているのかわかっているのか、との問いに、いつもの皮肉な笑みが戻ってきていた。
「どうもこうも?言葉通り。あんたの厄介になるってんだわ。もう村で一生を過ごす、って言ってんのに、いつまでも信じない子だね、あんたは」
「だって、母さんなら」
「それがあの人との約束だからさ」
父さん?と、娘たちは、母を見る。
一人、村で妻を待ち、娘を待つ父。家族の、帰る場所を守る唯一の存在。
「好きに生きればいい、だけど死ぬ時は必ずここに帰ってくることが条件だ、ってね」
親の役目も妻の務めも放り出して好き勝手生きることは許しても、一人死にゆくことは許さないというのが父の、ただ一つの願いだったのか。
祖母の最期を看取れなかったことが父を悲しませていたのか。
「村の女は老いを理由に己が弱ることを許せない。母もそうだっただけよ」
「そんなのは、あんまりですよ」
祖母の墓参りで涙を見せた父の背中を覚えている。あれが堪えたのか。娘たちに同じ思いを味わせまいと思ったか。
そこには、娘だからと言っても踏み込めない心情がある。
なぜなら。
「それが、あたしのケジメだね」
だから最期はここで。
最期まで、ここで。
「わかったわ」
その覚悟を受け止める。
「母さんが厄介なのは、もうそれはそれは十分にわかってるのよ。老いては子に従えってね、ケジメだって言うなら、この先存分に思い知ってもらうわ」
「はっ。結婚式ごときでうだうだ逃げ回るようなケツの青い小娘にしちゃ大口叩いたわね。後悔するんじゃないよ」
「こっちのセリフよ」
父に感謝する。
母を繋ぎ止めていてくれたのは、父のそのたった一つの約束。
どうしようもない母親だけど、母親としてはとんでもない生き様だけど、シオにとってはそれで十分。
遠い星のような輝きで魅了しては、流れ星のように消え去ってしまうのでなくて良かった。
文句を言い合える余地を残していてくれて。
「ありがとう」
今、正面きって言える。
母と、妹たちに向き合って。
「最高の結婚式にしてくれる、ってんならせいぜい楽しみにしてるわ。私と私の夫の名を汚したら、赦しはしないわよ」
それに応えるのは、双子の歓声と、末妹の嗚咽。
母の皮肉な笑み。
それらを守ってくれた、父の存在。
丸っと全部、これが私。私を持って、あの人と結婚する。
やだー二年近くかけてやっと完成できたー
四姉妹の祖母
サフランの母であり、オレガノの義母である
郷長の家に生まれ、何不自由ない暮らしで育つ
男尊女卑の社会という環境に加え、郷長という権力を持つ父親は
家族にも郷の人間にもパワハラ気味
生まれながらにその環境に置かれていたヘンルーダもそれを当然と受け入れ
自分より下の者に対しては父親譲りのパワハラ気質に育つ
縁談が決まり、婿養子をあてがわれてからはますますヒートアップ
婿養子は裕福な商家の三男坊
おっとりしたおぼっちゃまだったのがまた災いして、ヘンルーダが夫を虐げる日常
それを止めたのが2歳になる娘、サフランだった
「やめて、父様が死んじゃうよ」
たった2歳の娘が体を張って父親を庇うように覆い被さった光景と
慟哭の叫び声で、初めて自分の異常性に気付かされるヘンルーダ
それでも長年の気質はそうそう改まることもなく、幾度となくそれを繰り返した末に
このままでは家族が壊れると判断したヘンルーダは自ら離縁を申し出る
夫と、その境遇に同情した自分の妹がいつからか恋仲にあることも知って
家を捨てた
自暴自棄のように流離った先にたどり着いた村
たまたま立ち寄った教会で出会ったのは老いた神父
荒んだ様子のヘンルーダを気遣い、気にかけてくれる老神父に日々諭されるうち
なぜか素直にこれまでのことを打ち明けることができた
彼がヘンルーダにとっての救いだったのか
いつしか彼女はその村にとどまり、村の女性たちの一員となっていく
女性優位の社会を築く村で、彼女は第二の人生を始める
村の思想に共感したわけではなかったが、
訳ありの女たちは何も言わずヘンルーダを受け入れた
そしてヘンルーダもまた、老神父から離れがたい思いを抱いていた
父性愛だか異性愛だかは知らないが自分がその感情を自覚することは
置いてきた娘に申し訳が立たないことだと分かっていた
罪と償い、それと同じだけの重さを抱えた思慕は
彼がこの世に別れを告げる時まで頑なに秘められた
それと入れ替わりに現れたのは、娘のサフランだ
老神父がヘンルーダを気遣い、度々にヘンルーダの実家と連絡をとっていたことは
今はもうサフランしか知らない
彼女もまた老神父に敬意を払い、その親切を打ち明けぬまま逝った意志を尊重して
彼の根回しを黙し母親の前に現れた
成長したサフランは時折ヘンルーダに会うために村を訪れていたが
それを重ねるうちに村を訪れる目的は、母親ではなく、
この村の女性たちとの交流へと重きを置いていく
2歳にして勇敢にも怒り狂う母親に立ち向かった幼女は、勇猛な女戦士に成長した
よほどの適正だったのか、あっさりとヘンルーダを凌ぐ戦闘能力で
女戦士ここにあり、と近隣に名を馳せる頃
サフランは村に夫と娘を連れてきた
ヘンルーダにとっては、初孫だ
「親孝行させてくれてありがとう、だわ」
初めての育児に飽いて村を空けるようになった娘に変わって
孫であるシオを可愛がることとなったヘンルーダにサフランは言った
2歳で別れた娘、一度も忘れたことのない面差しを孫に見る
娘の成長を見守ることができなかった代わりに、孫の成長を見守ることができる
そうできる自分が、ここに存在することが尊い
初めて、暴力ではない愛を育てている
(皮肉屋の娘め、ああ本当にこれ以上はない親孝行じゃないか)
償いのために生きるなどとは言わないでください
そんな重いものを背負って、たった一人の人間に何ができるというのでしょう
あなたはまず幸せを知りなさい
その心が多くの幸せを生み、育て、世界を広く豊かにするのが良い
その時に初めて、償い、の意味がわかるはず
まだ村を訪れたての頃、一人、何のために生きていたのかもしれない頃
神の言葉を乞い、教えを必要として毎日のように教会に通ったヘンルーダに
老いた神父はそれを繰り返していた
ただ苦しいだけの人生から、逃れたかったのだとわかる
己の罪を精算して、一刻も早く、楽になりたかった
少なくともそれは、償いなどではなく
ヘンルーダが、その答えにたどり着いた時に真っ先に向かったのは
養老院
子沢山なはずなのに、今は一人ひっそりと養老院で暮らしている元夫の終焉の時
最期に謝る機会をくれてありがとう、と元夫は言った
彼もまた己の罪悪感にもがき足掻いていたのだと知る
一人と一人の人間が互いの罪を抱えて、それに向き合ったのはわずかひと月
許し許されて生涯を終えられるのは幸運
幸運を抱いて、ヘンルーダもまた生涯を閉じる
街道で猛獣に襲われていた人々を助けに入ったところで、馬車の暴走に巻き込まれた
この知らせが、村に届くだろうか
届くのなら、別れの言葉は「幸せだった」と伝わればいい
ありがとう
あなたたちのおかげで、私の人生は充足だった
アルセウス記事から再び不調の波にさらわれて遠くの沖まで流されていましたが
流されるままに漂っていたら思いの外、岸に近い浅瀬にいたんじゃないの?!
ってことで、ずぶ濡れのまま陸に上がってみましたお久しぶり
そしてまた画像のアップロードの練習から始めるのか…
そんなアホな己の不甲斐なさをエネルギーに家族の肖像を殴り書きしていたらば
ミオ以外の五人の髪型が全く思い出せず
己のブログで確認しようにも過去の記事すぎて掘り起こせず
まあそんなこともあるよね!!
って当初の目的の「アップロードをおさらい」完了
どのくらい記事が古いかって、ミオ家族のSS描いてたのがちょうど去年の今頃!
そんな昔の話の続きとかもうどうこねくり回していいかわからん!!
あと一話で完結だったのに(長女が家族に結婚を報告しておしまい)
なんであと一歩のところで力尽きてんのかなあ・・・
と虚無に陥ってしまって読み返す気力もなかったのでそっ閉じ
億万が一にもSS読んでくださっている方がいるとしたら
すみませんちょっと寝かせます
シオが「私結婚するわ」って言って終わるだけなのに
あと何話かかるか(一話じゃないんかい)
予想もつかないので先にミオ視点の4コマに逃げることにしました
久しぶりすぎてそっちもうまいこと描けるのかどうかやや予測不能ですが
生存意思の確認がてら、ぼちぼち行きます
ユールと別れ、上の村への暗い道をカンテラの灯りを頼りに登りながらシオは、一歩進めるごとにこれからの雑事が身近なこととしてこの身に降りかかってくるのを実感していた。
結婚に関わる雑事。
そのどれらも具体的に予定立てていけば、非常に面倒なものだわ、と思う。
実は自分は、結婚ではなくその先にある面倒さから目を逸らしていたのでは無いかと考えてしまうほどだ。
日常の雑事はさほど苦ではないのは、それが当然と身についているからで、元来の自分は実は母と同じ気性で、めんどくさいことから逃げたい人間なのでは無いか。
(あり得なくもないわ)
だってあの母の血を引いているんだもの、と考え、随分おおらかな答えを導き出せるようになったものだ、とここ数日の身の回りに起こったことに一人、苦笑する。
そんなはずはない、私は几帳面な人間だ!と頑なにあった拒否感はもうない。それが母の帰還のためか、ユールとの話し合いからか、結婚への覚悟が決まったことなのかはわからないけれど。
少なくとも日常の家事を煩わしく思わない程度にしつけてくれた父には大変感謝したいところだ。
と、家の中へ戻ってみれば。
「あ!お姉さん、おかえりなさい!」
一人で食卓についていたミオが立ち上がった。
「ミオ?一人なの?」
他のみんなは、と家の中に気配を探るけれど、母と双子の様子はわからない。
食卓には二人分の食事の用意がある。
「あの、お母さんとお姉さんたちは、中央の酒場に行く、って言って」
ついさっき出かけて行きました、と報告する様子には普段と変わったところはない。
そういえば昼過ぎから家を飛び出してから、ミオを一人残していたことに全く気を回していなかった。
「そう、食事を済ませてさっさと飲みに行った、ってことね」
気ままに飛び出したのは自分なのだし、皆もう良い大人だし、シオ一人食卓に揃わなくても特に気にするものでもないだろう。そんなものだ、と思っていると、「いえ」とミオが続ける。
「今日は気分じゃないから外で食べる、って」
「はあ?!」
どうせ母が言ったのだとはわかる。双子もそれに追唱するのもまあわかる。しかし食卓には食事の用意が整っているのだ。
「ミオ、あんたが用意したんでしょ?!」
「あ、はい。そうです」
昼に焼いたパンとスープの他に、キッシュとグラタン、サラダまで揃っている。二人分の食卓には多すぎる。
(ああもう!食べてあげなさいよ、末の娘が考えて作ったんだから!!)
ここにきて再び母親の身勝手さに憤慨する。気分がどうとか言われて拒否られる娘の心情くらい思いやってくれても良いんじゃないの?!たまに戻ってきてこれか。ああいや、たまに戻ってきたのではなかった。確かこれからはずっと家にいるとか、冒険者家業は引退するとか、信憑性はないが、そんなことを言っていたのだった。
だとすればこれからはこれが日常…、と明日から振り回される我が身を思って目を据わらせているシオに、ミオがおずおずと尋ねてくる。
「あ、あの、お姉さんは食べ」
「食べるわよ!」
ついさっきユールと食事を済ませてきていたものの、ここで「食べない」と言えるほど非情にはなれないシオなのだった。
どうして自分が怒鳴られなければならないのか、と不満の一つも返せば良いものを、ミオは「はい!」と跳び上がらんばかりに返事をして、シオと自分の食卓をテキパキと整える。
温められた料理を挟んで、姉と妹が向かい合って少し遅い夕食。
「美味しいわ」
「えっ、ほ、本当ですか?」
「あんたに嘘をついて何になるのよ」
「あっ、すみません!えっと、嬉しくて、つい、えっと、なんか信じられなくて…、あ!この場合はお姉さんが信じられないのではなくてですね!えーと私が現実を受け入れることに対するというかえーとえーと」
などと変にぎこちないのは今までの関係性上仕方がないとは言え。
そんなに怯えなくても良いんじゃないの、と言う代わりに、村の味とは違うけれど、と返して。
「こっちのグラタンも。変わったソースだけど、美味しいわ。随分腕を上げたわね」
先ほどのユールとの食事は味もろくに感じなかったせいか、自然にそんなことが口をついて出ていた。その言葉を信じられないような驚きの表情で固まったように受け止めたミオが、その目にみるみる涙を溜めたかと思うと、大粒の涙をこぼした。
「ちょ、ちょっと、何!?どうしたのいきなり?!」
「あっ、すみません!なんかすごくすごく嬉しくって」
そんなことで?!と動揺するシオを残して、流し台の方へ小走りに逃げたかと思うと、吊るしていた布巾で盛大に鼻をかんでいる。
大量の涙と鼻水を垂らしていた頃のミオのことは嫌と言うほど知っているけれど。
今でも大して変わっていないのか、変わったからシオの言葉一つで泣けるのか。妹の成長を複雑な思いで見守る。
昔からミオは生活に関する仕事は嫌がらずこなしてきた。双子の分まで仕事を押し付けられても黙々と、いやむしろ生き生きと請け負っていた昔の日々。
(そういうところを褒めてあげたことはなかったわ)
祖母がシオにしてくれたように、長所をひたすら褒めて伸ばしてやれば良かったのかもしれない。だがミオの長所は村の女としては致命的だ。女たちとの争いに身を投じる村に生まれた以上、いじめ抜かれる立場にだけは置いてはおけなかったのだ。
そんな複雑な思いを抱えるシオの元に、ミオが、失礼いたしました、なんて冗談なのか本気なのかわからない取り繕い方をして戻ってくる。
「村の女なら料理の腕じゃなくて戦いの腕を褒められて泣いて欲しいものだわ」
軽い激励の意味を込めてそんな言葉を送ってみる。
また盛大にいじけてしまうかと思ったが、予想に反してミオは奮起してみせた。
「それはもちろん!これからますます精進した暁には必ず果たしたいと思います!!」
奮起したのは良いが、さっきからその芝居じみた口調は何とかならないのか。
口調、で何だか思い当たるのは、ミオの仲間の一人。
「あんた、あの男に悪い影響受けすぎじゃないの?」
母親に久しぶりに対面した時の挨拶といい、その後に激情のままに喚き散らした時といい。そこまでは良いものの、我に返って、自分のやらかしに青ざめている様子には多少意見したくもなる。
「え?男?えっと?」
「黒髪の。ヒロとかいう」
「あ、ヒロ君は悪い男ではないですよ?良い人です」
「あんたは悪くないんでしょうけど、あんたが影響されてるのがどうなの、って話よ」
そういえば。
横暴ぶりを見せる母と双子に大して、社会の仕組みとやらを大上段に振り翳していたのだったか。それにも違和感が拭えない。単純に、らしくない、のだ。
「昼にも言ってたけど。社会の成り立ちがどうとか、形成がどうとか」
あれも何なのよ?あいつの詐欺芝居?と続けるシオに、ミオがかしこまる。
「あ、あの、あれはミカさんが」
「ミカさん?」
「はいっ、えっと、ヒロくんとは違う方の、えーと、金の髪で、なんかこうしゃってしたピャってなったキリキリってした感じの」
「ああ、あの金髪」
ミオのこのアホらしい説明にはげんなりもしたが、そうこれがいつものミオで、と考えていると、あのう、と話し出す。
「ミカさんが教養は大事にしろ、っていつも話をしてくれます。いろんなことを。私知らない事がいっぱいで物凄く大変だけどそんな私でも解るように色んな事を教えてくれてて、政治とか経済?とか歴史とか何だかそういう」
ああ。あの男。何やら態度が威圧的だと思ったが、なるほど、上流階級の人間だったか。と思う。教師がついて、上から下の人間を動かすための教育を受けているなら、それは当然に身についているだろう。それをご丁寧に披露してくれているわけか。なんのために?その真意はどこにある?
黒髪と金髪、二人から受ける影響がミオにとって良いものではなかった場合の懸念は姉として当然に抱くものではあったが。
ミオはしょんぼりと肩を落として見せた。
「でも私、村の事さえも知らなくって」
「村?」
「あの、お母さんが。なんのためにこの村が弱者を排除すると思ってるの、って」
徹底的に弱気を挫く。強さこそが正義、圧倒的な力、それ以外に手段は選ばない。そうした気質の村が生まれた理由。
遠い昔。社会的に女の地位が低かった時代。それに不満を抱いた女たちが力を手にすることを選んだ。戦うことを望んだ。強い意志で女社会を築くために各地から賛同者が集まり、戦う女の集団が出来上がった。女の力で生き抜くためにやがて一つところに落ち着き、集落を構えた。それがこの村の始まり。
やがて武勇で名をあげた女たちの元には、助けを必要とする弱い女たちが集まった。当然、女社会を発展させるために、それを迎え入れる意志はあった。だが。
「女たちの駆け込み寺でもあったわけよ。大昔はね。ろくでもない男から逃げてくる女は少なくないわ。でもね、女って生き物はそういうろくでもない男に惹かれるどうしようもない本能ってやつがあるのよ。暴力の支配をありがたがる、働きもしない男に貢ぐことに生きがいを感じる、被害を受ける自分に価値を見出す、そんな厄介な女が一定数いることは確かなの。そういうのは一度逃げてきても、それを忘れられなくてまた戻っていくんだ。それがこっちにどれだけ甚大な被害をもたらそうとね」
そりゃ何度裏切られようとも救ってやりたいと思うさ、同じ女だもの。と、母からそんな話を聞かされたのだという。
「だけど長い間の抗争でそのうち割り切るのさ。女とか男とかじゃない。結局、力があるか、ないかだ、ってね」
だから力のない人間を排除した。広い世界の中で、女が生きる村として対等に渡り合っていくために掲げる大義は、一つ。力なき者は去れ。
(ああ、そうね。昔は祖母がそんな話をしていたわ。村には大婆様たちもたくさんいて、歴史ある武勇を誇っていたのだもの)
だがその生きる大義を生の声として語れるものがいなくなる。伝えていくことはできても、命をもつ言葉として生かすことができなくなる。時と共に風化するのは避けられなくて当然。
「私そんなことも知らないで何だか偉そうなことを言っちゃって」
だからお母さんたちは出てっちゃったんだと思います、と肩を落とすミオに同情する。
「バカね」
とその顔を上げさせる。
「母さんがそんな事で出ていくもんですか。あの人は、茄子が嫌いなのよ」
「へっ?は?え、な、茄子…」
キッシュとグラタンにたっぷりと使われている茄子。
「あああ!私そんなこと知らなくて!いっぱい使っちゃ」
「知らなくて当然。今まで家にいたことなんかなかったんだから。良いのよ、それはこれから知っていけば」
知りたいと思うなら。いくらでも知れることはある。
「それと。あんたはケンカのやり方を知らないから。口喧嘩で負けてんのよ」
「けんか」
「本当にね。料理の腕は一端になっても、こっちはまだまだだって言うのは、そういう所」
茄子はシオの好物で。母親と双子に容赦なく貶されていた姉のために孤軍奮闘で立ち向かって。一人でシオの帰りを待っていたりして。
(そういうのはあんたの良い所なんだけど。残念ながらそれは武器にならないのよ、あの人には)
「負けたら終わり、じゃない。この村の始まりを知ったんでしょ?上等じゃない、それを手に入れて、次にあんたができることは何なの?」
「私、の、できること」
「村にない味を作れるようになったんでしょ。知識だって同じよ。村にない知識で、あんたはまだ戦えるでしょ」
村が弱者を排除する理由。それは、弱者を守る気はないという意思表示。大昔の彼女たちの言葉を借りれば「身を挺して守ってやっても、害こそあれど利点がない」からだ。
「つまり脳みそ筋肉で救済制度を作る能がない、ってことよ」
私がケンカを売るなら、そこを突くわね。と言ってやれば、ミオはポカンと口を開けて呆けている。
「そのアホヅラをやめなさい」
「あ、すみません」
「あんたはお仲間がいて、村の外の社会制度をいくらでも学ぶことができる。母さんはそうそう変わることはないんだから、何度でもケンカを売れば良いのよ。そうやって母さんの話を引き出して、自分のものにすれば良いだけ。小娘が偉そうに、なんて言わせておけば良いのよ。言いたいんだから。自分が小娘じゃなくなったから、やっと堂々と言えるわ、なんて思ってんのよ。言わせてやりなさいよ」
父さんも言ってたでしょ、と昼間の父の言葉を繰り返す。
「みんな意見が違って当たり前、その先をどうするかが家族会議だ、ってね」
「家族…」
「そう、あんたができるのは私たちの誰とも違う意見を言うこと。それを言えるようにちゃんと村の外で学んでくること」
母さんは話を最後まで聞いてくれたんでしょ?と問えば、はい!と力強い声が返ってくる。それで良い。
「うん。それでね。あんたの話をね、何がなんでも全否定!するのが母さんだから」
と念を押しておく。
再びミオが大口を開けて呆けるのに苦笑して。
「そういう人なの。人の話を聞いておいて、そのくせ最後には聞く耳持たない風で、全力でばかにするのが好きなの。そういうケンカの仕方なのよ、母さんは」
だからもっと話をしてやって。
多分、母が気にかけるのはシオではなく、ミオのような娘だろう。シオのように母に憧憬するでもなく、双子のように面白がるのでもなく、生真面目で純粋な小娘。今まで母親と離れていた分のまっさらな時間こそが、ミオのたった一つの武器だ。
女と男の見栄も外聞も役立たず、自然にこぼれた言葉に返るのは平熱。
ユールは淡々と遠い日の話をする。
「俺は初めてシオにあった時のことを今でもよく思い出す」
初めてこの村を紹介されて、行商に訪れたのはちょうど今頃の季節。
まずは下の村での商いを許されて、細々とした日用品を広げていた。村の男たちが賑やかしに集まる中、女の姿もちらほらと散見されるものの売上は芳しくなく。
まあ初めての土地での商いならこんなものか、と午後の昼下がりに手持ち無沙汰になって売上の計上を確認がてら帳簿をつけていて金額が合わないことに気がついた。やや多い。
10名にも満たない客足だったが、一時、やりとりが集中したことがあった。あの時に誰かに釣り銭を渡し損ねている。
そう気がついたユールは思い当たる客数名を探して村を歩き回った。確認の最後の一人は上の村の女性。なれない山道を登っていけば、ちょうどそこで行き合ったのがシオだった。幼い妹が使いやすいような小ぶりの鍋はないか、と言っていたのを覚えている。
釣り銭を渡し間違えた、と言えば、すぐに財布の中身をあらためて、そうみたいね、と古くなって色の悪い銅貨を出した。それで5ゴールド銅貨と50ゴールド銅貨を間違えて渡してしまっていたことが確認できた。上の女性は気性が荒いから気をつけなよ、と下の村を走り回っていた時に散々言われていたことを思い出し、その場で土下座を仕掛けた時。
「私の方も気が付かなかったんだもの、気にしないで」
とシオは言った。
てっきり怒声の一つでも飛んでくるもの、と覚悟していたユールは呆気に取られた。そこに重なるのは労いの言葉。
「かえって手間をかけさせて悪かったわ」
渡し間違えた人間を探し回った事、こんな村の上の方まで来させてしまった事、それを労った上で、手間賃としてそれは取っておいて、なんてことを言う。
そんな昔の話。
それを聞かされて、シオは瞬く。
「それが何か?当たり前のことだと思うけど」
「確かに、シオには当たり前のことかもしれない。でもその当たり前のことが敵わないことだって多い。特に、こんな外回りばかりで商売をしている身の上では」
店舗を構えていない流しの商人たちの世界は、荒れ者も多い。買い付けはもちろん、売りでも荒っぽいやり取りは日常茶飯事だ。だから見た目だけでも肝が据わっているように見える自分がそれを担当しているくらい。
「でも、あなたも頑としてそれを受け取らなかったわ」
手間賃だなんてとんでもない、それは受け取れない、と言うのに重ねて、ご祝儀も兼ねて受け取ってくれると嬉しいんだけど、と言ってもだ。
「そうだった。シオは特に必要でもない小鍋を買ったんだったな」
「必要、っていうか、まあそうね、緊急には必要としていなかったけれど」
初めて村に来てくれたのだから何か買っていくわ、と言った。
「だって、やっぱり次も商売したい、と思ってもらいたいでしょう?その方が村だって助かるんだもの」
「それもシオには当たり前なんだな」
そうよ、と困惑するシオにユールが笑みを見せる。
どうしても受け取れない、と言う態度に、譲ってみせたのはシオだった。わかったわ、と言って互いの手の中にある銅貨を交換して。呆れたような声音だったから、顔を見るのも躊躇われたが、シオはもう一度、手間をかけたわね、と言った。やわらかい声に顔を上げれば、笑ってくれた。
「そういう真っ正直な商売人はいつでも歓迎するわ。村で何かあれば、私の名前を出すといいわ」
と言って名前を教えてくれては。
「私の父が下の村で裁縫職人をしているの。入り用の物ならいくらでもあると思うわ。あなたのことは話しておくから、ぜひ懇意にしてちょうだい」
それは、この村を訪れるからには必ず売上がある、と言うことの確約でもあった。
あれからユールの商売は少しづつ回り始めたのだ。少しづつ、でも確実に。
仕入れも卸も、シオの父オレガノを中心として、村の商売人からさまざまな手解きを受けた。この村との強力な繋がりが近隣への信頼を得てからは、ならず者やヤクザ者を遠ざけていった。
「この辺りでは、私より娘の名の方が力を持っているんですよ」
と彼は言った。自分もそれにあやかっているのだ、と照れくさそうに言うそれは、付き合いを深めていけば自ずと考えさせられることでもあった。
「シオは強い。冒険者としても、村の権力者としても、一目置かれてる。強い人間が多くの人間を従えているのは良くわかる」
だがユールの目から見えるシオの強さは。
「腕っ節なんかじゃない。普通に、当たり前のことができる、その芯があってこその強さだ」
誰もが知る『真っ当』がぶれない人間が力を振るうから、多くの人間が従うのだ。暴力でも金でも闇でもない、ごく当たり前にある普通。誰もが見過ごして気にもかけない、当たり前の日常にある力。
「それが美しいと思った」
これまで自分が生きてきた小さな世界、人間を支配する様々な力があることを知った。暴力であったり、財力であったり、権力であったり。人の集まるところにある「力」の持つ意味はさまざまであり、人や地域によって価値もそれぞれに違う。
だからこそそれらに頼らない、『普通』を維持できる人の営みは尊い、と気付かされて。
そうして当たり前に生きる力が自分にもあることを知った。
「俺が夫婦に成りたいと思ったのは、そんな人だ。」
結婚とは。
その人が不在でもその人を傍らに感じとれることだと思う。遠く離れた場所にいてもすぐそこに感じられる。それが結婚することの意味だと思う。だからこそ、その相手は、シオが良い。
そう口説く男と結婚する。
夫婦となり家族を作る。そこにある多くの制約が、互いを縛る。生き方が違う、自分とは全くの別人とこれからを共に生きていく。気が遠くなるほどの時間は、想像もつかない生き方を己に課すだろう。
「わかったわ」
自分がなぜ彼を選んだのか。
近隣に名を馳せ、世界の果てまでも冒険者として通用するほどの人間を前にして、普通だから良い、と言う男にはお目にかかったことがない。
この男の目に映る自分は、きっとシオ自身も知らない。知らない自分を知っている人間と歩む道行は、険しくとも頼もしい。そうありたい。シオも彼に対して、そうありたいと願う。それを枷と言うか誇りと言うかは、心次第。そうしてユールなら、どのどちらであっても普通に生きる姿として美しい、と言うだろう。
「私もそれを聞かせてくれるあなただから、あなたがいいんだわ」
普通を当たり前のこととしておざなりにしない。日々の他愛無いことや些細なことへの向き合い方が丁寧な人だからこそ。
惹かれたのだとわかった。
そうか、と、いつになく必死にシオを口説いていたユールが、やっと肩の荷が降りた、とでも言うように大きく息を吐き出して姿勢を崩した。そして。
「夫婦になったら、シオはもう少し子供の部分を大事にしたほうが良いと思う」
と、またもや思いもよらないことを言い出す。
「子供の部分?子供、のことじゃなくて?私のこと?」
「そうだ。さっきの、ドラゴンの」
まだそれを言うか。次それを言ったら殴るわよ、と言いかけたシオを慌てて片手で制す。
「いや、咄嗟にそれが出てきたんだろう?シオは子供の童話だ、って言うけど、それを勢いで口にしてしまうのは、子供の頃からの憧れか思い入れがあるからじゃないのか」
どうでも良いことなら、子供時代の童話の一つなんて思い出しもしない。と言われて考えさせられる。
「あなたはどうしても私を子供っぽくしたいのね?」
無邪気に童話を夢見て、今も結婚相手にはドラゴンの牙を渡したいと胸に秘めているような少女趣味があるように見えるとでも?
別におかしなことじゃないと思うが、と言ったユールが恥ずかしそうに顔を背ける。
「俺は今でも縄を扱う時、今なら跳べるんじゃないかとやってみることがある」
縄を。
子供の頃に一度もできなかった縄跳びを、両親に何度も手解きされたそれを、今なら。
「……跳べたの?」
「いや。一度も成功したことはない」
大の大人が。荷造りの拍子にふと思い立って両手に縄を構えて、大真面目にそれを回しては躓く、そんなユールの姿は容易に想像できて。
シオは笑ってしまった。
子供時代の苦さと、それを振り返る切なさが相まって。
愛おしいという感情に包まれる。
「いいわ、今度一緒に跳んであげるわ」
「え、シオが」
「二人なら案外、簡単に跳べるわ」
くすくすと笑いながら、シオのためにそれを告白してくれたユールに応える。
「ドラゴン退治のことも、今夜考えてみるわ」
と約束する。
それは、結婚の約束。
夫婦になるための、シオとユールだけの特別な、でも奇特な。
愛の、交換だった。
「悪かったわ、なんだかよく分からない事で気弱になってる自分が馬鹿らしくって」
思わず笑ってしまった、と目尻の涙を拭いながら謝るシオを見て、呆気に取られていたユールも気負っていた両肩を下げた。そしてこんな事を言う。
「シオでも子供みたいに笑うんだな」
初めて見た、と妙な関心の仕方をされ、子供みたいに、と言われバツが悪くなって前髪を直すフリをして誤魔化す。
「あなたが笑わせるからよ」
「俺のせいか」
「そうよ」
「それで気弱になっていたのが終わったのなら良かった」
役に立てたのなら何より、という響きには微笑む。本当にこの男は。普段は朴訥でありながら、不意にその心の内を広げる。本人も意識しない奥底からの真っ当な生き方は、飾り気のない人柄そのもの。
だから自分はこの人を選ぶ。
そのために。
「結婚について話をしようと思ってきたの。でもそれをどう話したら良いのか分からなくて、ちょっと悩んでいたら、あなたに先を越されたんだわ。あんまり簡単に言うんだもの。じゃあ私は?って思ったら腹が立って、つい、当たり散らしてしまって」
もう一度「悪かったわ」と頭を下げるシオの言葉を静かに受け入れながら、ユールがわずかに首を傾げる。
「何を悩むことが?」
「そうね、それも聞いて欲しいわ。夫婦になる前に、あなたの答えが欲しいのよ」
一人で悩むなんて馬鹿らしい。たった今、シオが成せなかった求婚をあっさりと成せてしまう人間を目の前にして、そう思う。自分のためらいなんて、彼にとっては砂粒ほどの重みもない。それが欲しい、と訴えるシオに向き合って、ユールは口を開いた。
「ええと、それは俺にわかることだろうか」
俺は頭が良くないから、と言う彼には首を振る。
「本当に頭が良くない人間は、村の喜び事を自分のことのように喜んだりしないし、他所の家族の消息を気にかけることもないし、気弱が終わって良かった、とか、悩みはなんだとか、そういう心遣いはしないわよ」
「ええと」
「それができるあなたを、頭が悪い人間だなんて思っていないわ。私はね。……もし他の人間がそれを言ってたとしたら、問答無用で重傷者にして病院から出られなくしてやるわ」
シオなら口だけでなく本当にそれをやってのける事はもうユールも理解している。少し演技がかった口ぶりにも困ったように眉を顰める。
「それは、あまり良くないんじゃないか。その、シオにとっても」
「そう言ってくれるあなただから、そういうあなたの考えが聞きたいのよ」
俺は鈍臭いから、と言うのも、頭が良くないから、と言うのも、自虐でも引け目でもなく。ただありのままの自分を受け入れ、それが自分だからと曝け出しているだけ。もうとっくにシオだって彼の生き様を受け入れているのだ。
「わかった」
「良かったわ。私の分からないことは二つ。いきなりあなたが夫婦になろうと言い出したことよ」
「いきなり、だったか?」
「まあ、この私がちょっと取り乱してしまったくらいにはね」
先ほどのやりとりを思い起こせば、有無もない。
「今までそんな話は一切しなかったでしょう」
「それは……、シオは多分、母親の消息がわかるまではそんな気にはならないだろうと思っていたから。言うつもりもなかった」
それは意外だ。
「私、そんなに母さんのことで必死だったかしら」
自覚はなくても傍目にはそう見えていたのだろうか。村ではそれよりも「妹が一人前になるまでは」の覚悟の方が知れ渡っていたわけだが。
「ああ、いや、俺がそう思っていただけだ」
つまり、とユールが俯いた。
「俺なら多分、お爺かお婆が消息不明になったとして、事件にしろ事故にしろ、それが解決するまではそのことが気がかりで、新しい家族を持とうとか、そういう気にはならないと思って」
「なるほどね。まあ分からないでもないわ」
ユールには帰る場所があって帰りを待つ人がいる。牧場で働く仲間の誰であれ、そのような状況になれば確かにそのことで頭が一杯にはなるだろう。
「それが解決したからもう言っても良いだろう、ってこと?」
だとしたらもうずっと前から、シオと夫婦になることを考えていたことになる。
結婚に現実味を持てなかった自分とは大分心構えが違うな、と思えばやはりもう一つの答えを聞きたくなる。小娘のような甘っちょろい問い。世間知らずのフリをして?あるいは手練手管の冷やかしのように?この歳になってもまだ欲しがるのは満たされていないのか、成熟が足りないのか。
そう迷ったシオにユールは、いや、と強めに否定の音を聞かせた。
そして顔を上げる。
「どうしても今日言いたかったのは、シオの母さんが帰ってきた、って村の人たちが喜んでいるのを見たからだ」
オレガノの嬉しそうな様子、それを取り囲む村の男たちの楽しげな雰囲気、村の女たちが代わる代わる豪快に物を買い占め、ご祝儀だと言って陽気に大枚を放り込んでいく。
「村全部が一人の帰還を喜んでいる中で、俺だけがよそ者だった」
「それは」
仕方がないんじゃないの、と言うシオに、わかってる、とユールは微笑んだ。
「除け者じゃなくて、よそ者、だ。わかってる。むしろ、よそ者の俺にも分け隔てなくそれを与えてくれたのも、すごく感動した。だから余計に考えた。この先もシオとは付き合っていくこともできる、何も変わらないんだろうって思う。今までならそれでいいと思っていたけど」
今までなら。
今までは。
今は。
「同じようにシオが長く村を開けて、何かの功績を持ち帰って、そうして村を上げての祝い事に招かれた俺は、やっぱりよそ者でしかないんだって」
気づいたら。
たまらない寂寥感に襲われた。空洞になった荷箱を抱え上げ、重さのないそれを荷台に積み上げる単純作業。ただただ荷台を埋めていく。今日の箱の中身を一つ一つ思い起こして片付けるだけの自分の目の前に、シオが現れて。
向かい合ったその姿を見てしまったらもう。
「言ってしまっていた」
そんな胸の内を告白されてシオは言葉に詰まった。
「確かに、いきなりだったかもしれない」
迷惑ならすまなかった、と大真面目に謝られては慌てる。
「別に迷惑なんて思ってないけど」
私だってその話のつもりだったんだし、と言うのには、そうだったか、と頷いて。
じゃあ手順か、ドラゴンを倒す話が先だったか、と言われて、もうそれは良いんだってば!と顔を赤くする。
「蒸し返すな、人の醜態を!」
「す、すまない」
「私はただ、結婚の意味がわからなくて」
言い出せなかったのは、動機があまりにも自分勝手にすぎる、との躊躇い。ケジメをつけるため。母の名と、妹の成長の証として宣言するそれにユールを巻き込むことに、大義名分を欲していた。
そんなシオの話を黙って聞いていたユールは、それの何がいけないんだ?と言った。
「俺だって結婚がしたいから夫婦になろうと言ったわけじゃない。シオが良いから結婚しようと思っただけだ」
シオもそうじゃないのか、と問う。結婚が前提じゃない。ユールが良いと思ったから結婚するのだ、と考えて納得する。
「そんなことで良いの」
「俺はむしろ、シオのケジメの付け方に俺を選んだくれたことが嬉しい」
多くの男の中から。これまでに求婚されてきた過去を過去にして、ケジメをつける。過去の男たちがシオのもとを去ったのは結婚がしたかったんだ、と言うユール。シオとは結婚できないから去った。それだけ。
「俺は結婚するならシオが良いと思った。たとえ一緒に暮らすとなっても、俺は行商で家を空ける。シオは冒険家として家を空けるだろう?お互いにそばにいられない事の方が多くても夫婦だってだけで、家の中にもう一人の存在がある。それを安心として暮らしていける。一人じゃない、家の中にいないいつ帰るかもわからないもう一人と一緒に暮らしているんだ。それが結婚することの意味だと思う」
「それだけ?」
「それだけだ」
その相手はシオが良い。シオでなければ、結婚なんて意味がない。
いつになく饒舌にシオを口説く男に、かまととぶるでもなく魔性の女を装うまでもなく、自然に口をついて出た問い。
「なぜ私なの?」
夫婦に。
唐突なその一言には、一瞬理解が追いつかなかった。
異国の言葉か。フーフとかいう珍味だか地方だかの話でもしだしたのかと思ったくらいだ。それにしたって唐突だが。
「はっ?!」
驚いてその場で固まっているシオの反応を見て、いやあの、と口の中でモゴモゴと言葉を濁して、手にしていた皿とフォークを木箱に乗せる。そして、きちんと座り直してもう一度。
「夫婦になろう」
「誰が」
「誰が、って。俺と、シオが」
「俺とシオがなんですって?!」
「だから、夫婦に」
「どうしてそれをあなたが言うのよ!」
「えっ、いけなかったか」
「私が言うはずだったのよ、それを!」
「えっ、なら別にどっちが言っても良」
「良くないわよ!この村では力が証なの!ドラゴンを倒してその牙を根本からぶっこ抜いて生涯の伴侶となる者に受け取らせて婚姻の証とするの!」
「なん、だ、それ」
「童話よ!!!!」
気が動転するあまり子供じみた言いがかりをつけている自覚はある。初めてでもあるまいし、結婚の申し込み如きでこんな醜態を晒すなんて、という屈辱もあったが、それよりも当たり散らされて困惑しているユーズに対しての申し訳なさからの自己嫌悪。それがあっての村に古くからある童話を持ち出しての軌道修正はあまりにも稚拙だ。外れていく話の筋をここから戻すには、と動転に動転を重ねてその場で回転するしかないシオの内心には気づくはずもなく。
大真面目にユーズは言った。
「俺はドラゴンを倒す前に死んでしまう」
だからそれだと夫婦になれない。と言う彼の主張に、今一度キレる。
「ドラゴンを倒すのは私よ!あなたは受け取る方!」
この村では女が主体なのだ、との激昂だったが「なんだそうか」となぜか安心してしまうユーズ。そしてトドメには。
「そのドラゴンの牙は、ミルク缶幾つ分だろうか」
という一撃を繰り出して完全にシオの空回りを止めた。
「知らないわよ!!ミルク缶がどれほどの重さかなんて!」
いや3つ分くらいまでなら持てると思う。掲げろ、と言われればちょっときついかもしれない、などとのたまうのには、開いた口が塞がらない。怒りを通り越して呆れるしかない言動も、彼にとっては大真面目なのだとわかった。
どういうことなの。今あなたは私に理不尽に当たり散らされてるのよ。それに対して思うところがそれなの。少しは気分を害しなさいよ、そっちが怒ってくれないと謝れないじゃないの。
という現実的な思考と。
絵本のようにドラゴンを倒し牙を抜いたとして安全な場所からノコノコ出てきた彼が血みどろの牙を掲げて婚姻を承諾する場面を重ね合わせて。
ミルク缶3つの方が重い。これは大した牙じゃないな。なんて言われた日には。
「あははは!」
思わず笑ってしまうかもしれないな、と考えたと同時に笑い声を上げていた。
なんなの!この男と添い遂げるの?相手はドラゴンの牙がどんなものかも知らない。私はミルク缶を運んだこともない。こんなにも生きてきた道は違うっていうのに?
突然笑い出したシオに、今度はユールの方が呆気に取られる番だった。
ああそうか。生きてきた道が違っても、これから生きていく道が同じになるのか、と思った。自分は、生きていく道を選ぶのではなく、生きていく人を選ぶのだ。
馬車留の柵にもたれ掛かりながら、山の端に今にも沈みそうな夕日を眺めていたシオは、遠い日の幼い恋愛をなんとなく思い出していたが。
「待たせた」
と背後から声をかけられて、その人物を振り返った。
先ほどまでの記憶の中の行商人とは違い、愛想もなければ社交辞令もない、遊びも興も無縁の、無口で堅実な商売をするためだけに生きているような男だ。だから「急がせたのなら悪かったわ」とシオが応えれば、「いつも通りだ」とだけ返して、柵の中に戻っていく。
シオより頭一つ大きい背丈に荷を扱う仕事で鍛えられた肉体は、何も知らない人間が見れば、それなりの武闘家かと見紛うだろうが、この村の人間は知っている。滅多にお目にかかれないほどの、運動神経の悪さを。
現に今も、自分の体の大きさをうまく把握していないかのように、柵に思いっきり腰をぶつけてよろめいていた。おそらくシオだけが知っている、彼の服の下の身体のあちこちにある不用意な青あざやら引っ掻き傷。古いのも新しいのも。それを指先で撫ぜれば、
「俺はどんくさいから」
とだけ、彼は言った。
初めは仲間内や競合相手からのいじめにでも合っているのかと思っていたが、親しくなるにつけ、本当にただ鈍臭いんだな、と嫌でも気づく。
「だから、親と別れて、遠い親戚が経営する牧場に預けられた」
そこで朝から晩まで働くうちに体だけはどんどん育った。親元にいた時とは違って、食べたいだけ食べて良いと言われ、そうしていたらこうなった、というのにも納得だ。
特に意識して体を鍛えたわけでもなく、大食らいとそれを上回る仕事量で作られた筋肉は、それ以外の目的にはうまく働かないらしい。
牧場で働く以上、それで特に問題もなかった。時折、老爺が気を利かせて牛乳の配達に外に連れ出してくれる様な生活。それが少年期から青年期に入って、体が大きく、見た目がいかつくなった頃から、変化が訪れる。
牛乳配達のついでに行商に出るようになった老爺について時折港町にも出入りをしたが、見た目で判断されたか、昔に比べて難癖や言いがかりをつける客が減った。老爺が街の若者と揉めているところに顔を出せば、途端に連中は引いていく。それを理解して、自分が主な行商担当になった。「こんな木偶の棒でも役に立つものだ」なんて自虐にも聞こえるそれを、大真面目に語ったりする。そんな人間だ。
親とはどうしているのか?と尋ねるシオに、数年に一度くらいは会う、と答える様子には、特に何のこだわりもないように見える。
「親は旅芸人の一座で、世界中どこへでも行くから」
なるほど、彼の身体能力の低さでは子供からの芸も身に付かず、お荷物になっていたのだと容易に想像できる。そこからの苦渋の口減らしで、老夫婦の経営する牧場へ預けられた、と。それで一座が近くに来たときは顔を見せる、と言うのだから関係は悪くないのだろう。
いかつい(だけ)の外見を活かして、近隣の村々に牛乳を配達する行商の担当になった。空になった馬車で港町へ向かい、代わりに他の土地の荷を仕入れ、牧場に戻る道すがらにそれを売り売り歩く。その巡回場所の一つにシオの下の村があったというだけ。たったそれだけの縁で、シオはこの男との結婚を考えている。
ユーズ=マーシュマロウ、シオより3つ下の働き盛り。
マーシュとマロウの牧場では行商担当。シオの父、オレガノは特に上客だろう。オレガノの仕事上、彼にあれこれと都合してもらっている代わりに、自分が仕立てた服を他所へ卸すのを任せていたりもする仲だ。
(そんな人をどう紹介するっていうのよ)
なんて頭を悩ましていたからか、先に行った背を追って柵の中へついていったシオは、ユーズが木箱を置いて、座れと示すのにも素直に従っていた。
馬車の傍らに木箱を3つ置いて、そこの一つにランタンと食事の用意。
それに気づいた時には、残る一つの木箱に腰を下ろしてよろめきかけたユーズが体制を立て直していた。
「私、別に食事を頼んだわけではないんだけど」
慌てるシオにも、ユーズは無頓着だ。
わかってる、と言い、麻袋からシャンパンの瓶を一つ取り出してシオに差し出す。
「今日は差し入れをたくさんもらってしまった」
傷んでしまうと申し訳ないから、シオも食べてくれ、と言う。
受け取ったシャンパンの瓶はシオの好みの銘柄。程よく冷えているのを見れば、今し方向こうの通りで買ってきたのかもしれない。
彼にこうも気を遣われているのは珍しいことだったが、特にそれを問題視する余裕はシオにはなかった。仕方がない。何せ、ここ数日は珍しいことばかりに追われて、シオ自身、どこから手をつけていいか途方に暮れていたのだから。これもそのうちの一つ。たった一つ。
「じゃ、ありがたくいただくわ」
うん、と言ったユーズは村の人間からの差し入れだといった夕食にもう手をつけている。
「今日は村に泊まるのね?」
と確認すれば「さっき宿を取った」と言う。今夜は村に滞在して、明日の朝早く帰ると言うので、(それなら良いか)とシオも手前の皿を取った。
馬車の影で、木箱に座って、村人の差し入れてくれた夕飯を囲んで、何の色気もない逢い引きか。傍目には商談でもしているように見えるだろうか、と思って、そっと笑う。
昔から男たちにちやほやされるのが常だった。なんとかしてシオの気を引こうと、男たちの貢物も接待も、過剰になっていった。それがこの村では当たり前のことなのだと受け止めていたけれど、いつしか自分は膿んでいたのかもしれない。人生の華美な装飾に飽きて、それらをもたらす男たちに冷めた。連日連夜の豪勢な食事の後、何気なく蒸しただけの芋を口にして、美味しさに感動する。どうやら自分はそんな人間だったらしい。素朴で質素で堅実な生活で十分。
(ええ、どうせ地味で面白味もない人間でしょうよ)
ここにはいない母と妹二人に向けてのぼやきは癖か、慣れか。
そんなシオに、ユーズは肉の塊を差し出す。それを片手の皿で受ける。こんな場所でなければ、確かに手慣れた夫婦のような感覚。何も気負わない、心地の良い関係。
それを、自分は守りたいのか。誰にも明かさず、守っていたかったのか。今まで、彼に結婚を切り出そうとも思わなかった。ずっとこの関係が続くと思っていたわけでもない。ただ考えようとしなかったそれなのに、今夜、この場所でそれを暴こうというのか。彼の返事を聞くことよりも、自分の本心が固まることの方が未知の領域になるなんて。
よく知った村の味も(今はわからないな)と郷土料理のミートパイを口に運んで黙り込んでいると、ユーズの方が口を開いた。
「今日は差し入れもそうだけど、品の売れ行きも凄かった」
らしくもなく、自分から話題を振ってくる。よほどシオが沈黙しているのに耐えられなかったか。そう思えば、シオはずいぶん長いこと黙り込んでいたらしい。
「あ、ああ、そうね。店じまい、って言ってたものね。完売したの」
いつもなら二、三日滞在することもあったのに。それも出来ず、夕方前には片付けに入っていた様子を思い出す。
「ああ、一つ残らず。それもご祝儀価格で」
「ご祝儀価格?」
「そう言ってた。上の村の女の人たちが。珍しく押しかけてきて。…サフランさんが戻ってきたんだ、って言って」
うっ、と危うく喉にパイを詰まらせるところだった。シャンパンの瓶に口をつけるシオを待って、母さんなんだろう?と言うユーズ。
「そうよ。七年ぶりよ。出て行ってから、7年も居場所を隠して」
「無事だったんだな、良かった」
物静かな口ぶり。シオが時々母親の消息を探して遠出することも知っているユーズ。自分も港町に出入りする関係上、何か情報があれば気づけるから、と母親の詳細を尋ねるユーズには、「まあ便りがないのは元気な証、って昔から言うでしょ」と当たり障りのない言葉を返すこともあったけれど。
彼なりに気遣ってくれていたのには感じ入る。
「オレガノさんも、嬉しそうだった」
「あ、ああ、うん、まあ父さんは、ね」
あの人は感情を隠しもしないだろう。
おかげで下の村の人間もいつもよりざわついてて浮き足立っている。何か変化があればそうやってすぐ広まるのが下の村の特性だけれど。
「けど、それよりも女の人たちが。すごくて」
と今もそれが冷めていないかのように興奮しているのはユーズの方だった。
普段にないお祭り騒ぎに巻き込まれて、物静かな木偶の棒も流石に調子を狂わされているのか。
確かに、シオより上の年代の女性たちが主に、シオの母を取り囲んで姦しいことこの上なかったここ数日だが。
「自分達に嬉しいことがあって、それで普段より良い値で、しかもありったけを買ってくれる、って。なんて」
自分達だけでこの喜びを味わっているんじゃ勿体無い。もっともっと周囲を巻き込んで、お祝い事はより多くの人数で分け合わなくては、喜び事の意味がない。
そんなのが上の村の女性たちの。
「素敵な気質だ」
どれだけ嬉しいかこっちにも伝わってくる。と、普段はまるで感情がないのかと心配するほどに表情も変えないユーズが、そっと微笑んでみせた。
(まあ、珍しいものを見たわ)
とシオが見惚れてしまうのにも気づかないように。
ユーズは少し黙り込んだ。
何かを口にしようとして、気がついたように皿とフォークを持った手を太股に落として、シオを見て言った。
「夫婦になろう、俺たち」
天使御一行様
|
愁(ウレイ) |
天界から落っこちた、元ウォルロ村の守護天使。 |
魔法使い |
|
緋色(ヒイロ) |
身一つで放浪する、善人の皮を2枚かぶった金の亡者。 |
武闘家 |
 |
三日月 |
金持ちの道楽で、優雅に各地を放浪するおぼっちゃま。 |
戦士 |
|
美桜(ミオウ) |
冒険者とは最も遠い生態でありながら、無謀に放浪。 |
僧侶 |




















