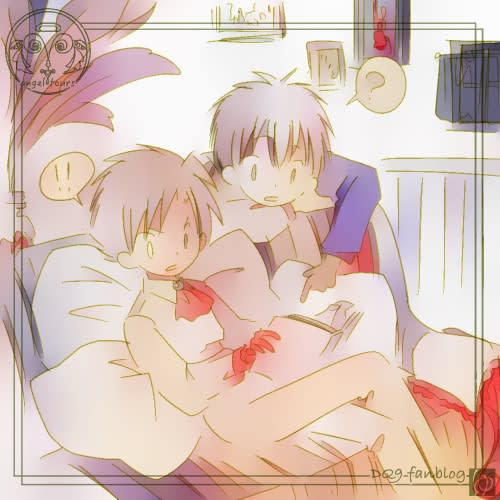大体ミカは機嫌が悪いと一人になりたがる。機嫌が悪いのを悟られたくないのと周囲に当たってしまうのを避けているのではないかな、とヒロは推測している。なので気の済むまで一人にしてやると、自分から「構え」と出てくる。普段ならそれで問題ないのだが、今はちょっと違う。
と本を閉じ、寄りかかっていたソファーから身を起こしたミカが、手段について説明してくれるのをヒロはただ素直に受け止める。
「俺の子供は必然的に御貴族様、ってこと?」
「え?どうして、って?俺が阿呆だから?」
ミカがそれを読みながら、「なんでこいつは唐突に裏切ったんだ」とか「こいつとこいつのつながりはどっからきたんだ」とか主役から端役に至るまで登場人物の行動に事細かく突っ込んでくる事に、それは多分こう、これは伏線がここ、とヒロなりに文章で描かれていない心理描写や人間関係の背景を解説してやっていたのはつい先ほどまでの事。
それはやっぱりー、と言いかけ、ミカは先生との関係に戸惑いを感じているのでは無いか、と思い直した。
それで良いと思う。
失敗を許容してくれる人がいるからこそ、人として望まれる方向に成長する事ができると心得なさい、というのがミカのお爺さんからの伝言だと言う。
「そうですか。それは大変よろしい」
と、先生の声がして、ミカと同時に扉の方を振り返る。
授業の時の様に生真面目な先生の隣には、執事のライダスさんがにこやかに立っている。
「お茶の準備を致しましたよ。一息つかれては如何ですか」
自習も大変お疲れでしょうし、と先生が言うのには「ああ、えっと」と返答に困っているミカを制する様に、立ち上がる。
「先生のお誘いとあらば喜んで!いついかなる時と場所でも馳せ参じます!」
先生にはありったけの感謝を示せ。
やはり過剰であったように、苦笑するライダスと、鼻白む先生。
「…それは興味深いですね。参考までに。いついかなる時と場所とは?」
「そりゃあもう!ドラゴンとの戦闘中でも完璧な正装に早変わりしてキラーパンサーを駆ってひとっ飛びで」
「…ルーラの方が早いと思うぞ」
「今声をかけたのがその時でなくて良かったですよ」
そう言って先生が姿を消す。
だから、ええーなんでー、と先生の背を追いかけて、ミカ振り返って手招く。
「お庭へ参りましょう」
明るい日差しに中庭の緑は鮮やかに、色とりどりの花が柔らかく包み込む東屋。
外は気持ちのいい風が吹いていた。
主人が、外遊を終わらせて国に戻る。
それに従って、従者も任務を切り上げ国に戻る。自然な流れだ。
だがミカヅキはまだサリスを従者だと認めてはおらず、サリスもまだミカヅキを「我が君」と呼ぶ許しを得てはいない。
その許しを得る為に、今回サリスはミカヅキの外遊に強引に同行したのだ。
だから外遊がどういうものであるかは、サリスにとってあまり意味はなかった。ただミカヅキに従者を連れる意味を理解してもらうための第一陣であったので、
(これはこれでまあ、良しとするか)
と、内心では軽く考えていたと言っても良い。
実際、従者を伴って行動することに対して、ミカヅキの拒絶反応はサリスが考えていたより酷くはなかった。
酷かったのは、城にいる時のような完全無欠の貴公子が下品な不良少年に成り代わってしまうミカヅキの在りようだ。
教師がこぞって絶賛するミカヅキの完璧な所作は優雅な服とともに脱ぎ捨ててしまったのか、はたまた、目の前の彼は見た目が同じだけの別人で実は城には本物の彼がいるのではないかと疑ったほどだ。
だがその不良少年が今までの旅装を脱ぎ捨て、後継者としての服装へ身なりを整えただけで、周囲が感嘆するほどの品位を見せつけ馬車に乗り込んでくるのを目にして今、頭痛に目眩さえも覚えるサリスである。
(この人の言動の切り替えはどうなってるんだ)
「なんだ、具合でも悪いのか」
「…いえ、別に」
なんでもありません、とサリスが返事をすれば、向かいに座ったミカヅキはそれを確かめるようにサリスを見て、一人納得して窓の外に合図を送る。
冒険者である旅の仲間を残して、レネーゼ領へと馬車が走り出す。
「まずレネーゼ家、なんですか?」
サリスとしては、旅の行程を終了させてミカヅキと別れ、オットリーの家へ報告をしてから、日を改めて対外交の部署とレネーゼ侯爵家にご機嫌うかがいに参上するつもりだったのだが。
ミカヅキは、家に戻るからお前も来い、と言った。
「対外交に出向く必要はないだろう。上からの指示だった訳でなく、単に書記官の一人がその場の提案をしただけだ」
「それはまあ、そうなんですが」
対外交でアルコーネ公爵が顔を見せた以上、そういうわけにも行かないのでは、と思ったがミカヅキはそれを意に介していないようだ。
「あの方は大体いつもあんな感じだ。用もないのに出てくる」
公爵に対してこの言い様!!と、咄嗟に反応を返せないでいると、ミカヅキの話は先に進んでしまう。
「俺がオットリー家に顔を出した方がいいなら、この後に同行するが」
と言われて、内容が内容だけにこっちには即座に反応できた。
「とんでもない!!ミカヅキ様に足を運んでいだだこうとか、そこまで思い上がっていませんよ!!」
そうか?とミカヅキは不思議そうだが、サリスにとっては一大事である。
なんの成果もなく経過報告だけを手にして家に戻るというのに、その主人候補を連れてきたとなれば、いくら末孫に甘いと言われるオットリー侯爵でも良い顔はするまい。
「オットリーのご子息を連れ回した事に、一言断りがあった方が良いかと思ったんだが」
「いや、それは」
と言いかけ、ミカヅキの不思議そうな態度を理解した。
「俺は家を出る身、ですからね。オットリーの名を持って出るか、他家に入って名を貰うかは今の時点で決まってませんから。それほどの扱いではないんですよ」
そうだ。直系の子息とはいえ、ミカヅキと違い正当後継者ほどの格はない。次の後継が父、その後が兄。兄には今年、息子が生まれている。サリスとしては、後継者の予備としての役割はすでに無いと言ってもいい。
そう言った事情を、ミカヅキは実感できていないのだろうと思う。
そういうものか、と相槌を打つ様子も特にその辺りに興味があるようでもなかったので、話題を戻すことにする。
「それより、レネーゼ家へはどのように」
どのように話が進んでいるのか、と問いかければ、ミカヅキもあっさりその話題に移った。
「侯爵にはお時間を頂く様、先に言付けてある。お前を侯爵家のお抱えにするつもりがある事は話しておかないと駄目だろう」
だからお前も同席しろ、と何でもない事の様に言われては一瞬、理解が追いつかなかった。
レネーゼ侯爵家のお抱え、それはレネーゼ直系ではない者を専属で家に迎え入れることを言う。
「えっ?お抱え、俺を?!俺が?レネーゼの専属に??」
「レネーゼの、って言うか、俺の従者として、な」
「いやっ、それはそうでしょうけど!?」
サリスとしてもレネーゼのどことも知れぬところで一家臣として雇われるつもりはない。ミカヅキの側仕えがいいと言うのは大前提だが。
「どこでそう言う話になったんです?!」
「どこで、って…、最初から、そのつもりで旅に着いて来たんじゃないのか、お前」
それはそうだが。
それをミカヅキが認めてくれているとは思わなかった。従者志願を拒否するミカヅキを、どう説得するかというのが徹頭徹尾、サリスの課題だったはずなのだ。
いつ、どの時点で、ミカヅキの拒否網が撤廃されたのか、全くわからなかった。
「そんな素振り、微塵もなかったじゃないですか」
「俺はそのつもりだったが」
「はあ?!俺のせいですか?!」
サリスの、身を乗りださんばかりの驚愕の勢いには、ミカヅキもやや気圧された様に座席に身を寄せる。
「わかった、順を追って話す」
その一言で冷静になれた。
よく考えれば、このまま喚いていて「じゃあ取り消す」などと言われようものなら、もう二度と機会に恵まれない事は確実だ。
「お、お願いします」
揺れる馬車の座席に深く腰を落ち着ける。それを待って、ミカヅキはサリスに向き合った。
▪️ ▪️ ▪️
「まず今回の旅に同行を許したのは、お前に従者の真似事をさせる為じゃない」
と、ミカヅキは話し出す。
「俺が一個人として旅に出る時には従者が必要ない、と言うことを解らせる為だ」
「…それは」
それは、酷い裏切りだと思った。
少なくともサリスは、ミカヅキに従者の必要性を解くために同行する事を伝えてあるのだ。
それを了承したのはミカヅキで、この時点でサリスとミカヅキとの旅の目的は同じでなければならない。今回の事だけでなく、そうでなければ信頼関係など築けはしないはずだ。
それを非難するべきか否か、迷ったサリスをどう捉えたのか、ミカヅキは言葉を続ける。
言葉で説明するより見せた方が早いと思っての事だ、と言われてサリスは押し黙る。
確かに、出発前までミカヅキとサリスの主張は平行線だった。そして、実際、旅の間中ミカヅキはサリスの手を借りることなく、自分の身の回りの事は自分で完結させ、それに不便を見せる事はなかった。
それはミカヅキの普段通りであり、普段から行動を共にすると言う冒険者らから「あまり手を出しすぎると鬱陶しがられるよ」と忠告されたので、サリスも様子見として手を出さずに見守るに留めたわけだが。
「それは良く解りましたよ」
と、かろうじて感情を抑え込みそう答える。
答えたサリスに、ミカヅキは。
「それを理解できる人間なら、お前は俺の味方になると思った」
そんな言葉を使った。
「味方?」
従者ではなく、味方、と言う真意。
「俺が従者もつけずに行動することに周囲の目がどうあるかは解っている。レネーゼの家でもそれは同じだ。昔から変わってはいない。許されているんじゃない、ただ敬遠されているだけだ」
その告白には、少なからず驚きがあった。
貴族界の通例はともかく、レネーゼ侯爵は幼い後継者に甘い、それを許している家臣たちもまた言うにあらず、というのが周囲の見方だと思っていた。少なくとも、サリスたち若い世代やミカヅキの同年代は、それが大方だ。
「それがまかり通らない時期に来ているのも、解っている。おそらく、家か、俺か、今までの均衡をどちらから崩しにかかるのか、と」
互いの手を警戒している所だろうと読んでいる、と言ったミカヅキがサリスを示す。
「そこにお前が来たわけだ」
思わぬ所から現れた伏兵、それをどちらの陣営に引き込むか。
「おっ、俺が均衡を崩す存在になる、って事ですか?!」
思わず腰を浮かせたサリスに、ミカヅキは怪訝そうに眉をひそめる。
「まさか。お前がそんな大それた存在だとは思っていない」
「…そ、うですか」
それでも味方が欲しかったのだ。
侯爵家という組織の中で、ミカヅキが欲しいと思ったもの。
「この先、身軽に外に出る旅に大仰に従者を引き連れて何かを成せるかと言われれば、滑稽な話だ。それをいちいち俺が拒否するのと、実際旅に同行したお前が口添えするのとでは、上からの見方もまるで違うだろう」
猶予は二年余り。正式に正当後継者の儀式に望めば、自由はない。ミカヅキがそう覚悟している事にも驚いたが。
周囲を敵だと認識している。思ったより厳しい環境に置かれているのか、今まで一人の自由を貫いてきたミカヅキが欲しいと思ったもの。
(それを従者というんですよ、…ミカヅキ様)
他人を拒んできたが故に置かれた状況で、自らそれに気づいたというのなら。
必要だと思った時点で、サリスをレネーゼ家に置くことを決めていたのか。
その時なんですか、と問えばミカヅキは、いや、と考える風を見せる。
「従者を育てるようにと言われて考えた事だが」
旅のきっかけとなった対外交で、思わせぶりに登場して見せたアルコーネ公爵の言葉をサリスも思い返す。
格下のサリスの目の前で「子供の遊びだ」なんだと手厳しい事を言われている様子には、居たたまれなさを感じて特にミカヅキを庇ってやる事もできなかったが。
あの一件で。
「俺に従者は必要ない。それは解りきっている。後継の儀を迎えれば、レネーゼ系列の家からこれでもかというほど優秀な従者を過剰に押し付けてくるわけだしな」
それを捌くだけで手がいっぱいだ、というのはミカヅキなりの冗談なのか。本心か。特にサリスの反応を見るでもなく、必要なのは、と視線は窓の外に流れた。
「俺が侯爵家に入った後、あいつらの動向を偏向なく俺に知らせてくれる従者が必要だと思った」
今はいい。
だが後継者として公務に縛られ、今のように自由に城と城の外との行き来ができない将来が来た時。
「あいつらを理解して、時には手を貸したり、必要な要請に応じたり、そういった俺の意思が歪められずに橋渡しができる人間は必要だ」
それに気づいた。
レネーゼ家にその人間を用意することはできない。冒険者としての彼らを、ミカヅキが扱うのと同じように親身に扱う人間はいないだろう。ミカヅキが自ら育てる意味があるとすれば、ここだ。
「それにはお前が適任かと考えた」
窓の外から視線を戻したミカヅキが、サリスに向ける期待。
「前回の夜会で見た限り、お前は交遊の幅が広いようだ。加えて、臨機応変に対応することもできる。その場を統率する意思も、積極性も申し分ない。だから、あいつらに引き合わせた」
「なっ」
ミカヅキはサリスを受け入れている。もうとっくに受け入れているのだ、と言ったのは、ミカヅキの旅の仲間だ。
サリスをよろしく頼む、と仲間に託した。
他の人には考えられないよ、と言ったのは彼女の方。この先、きっとミカちゃんは自分の家の人を連れてくる事に慎重になるよ、と。
よほど見込まれているのだ、とサリスを煽て、ミカヅキの気に入りだと有頂天にさせておいてからの、彼らの企ては何だ。自分は、そちらの方に気を回しすぎて、余りにも彼らの言葉を軽んじてしまったのか。
(いいや、彼らの存在は障害そのものであるはずだ。一国の、爵位を頂く正当後継者にとって)
この数日だけでも、ミカヅキに対する彼らの態度には嫌悪感を拭えなかった。高位にある存在を、誰よりも解っているのは自分たちだ、と主張するようなそれも、ただミカヅキを貶めるだけの悪手にしかなり得なかった。もちろん裏返せば、すべてサリス自身に降りかかってくる自尊心への、障害だ。
障害でなければ、なんだというのか。
「なぜそれを初めに話してくれなかったんですか!」
ああ、サリスをそこまで見込んでくれていたのなら。
旅を初める前に。
お前にこの役目を任せたいのだ、とただそれだけを話してくれてさえいれば。
「話していれば、何か変わったか?」
「もっと、ちゃんと、ご期待に添うことができましたよ!」
激しい後悔に苛まれて思わず口にした言葉に、違う、と冷静な自分の声がする。それを主人に求めるのは違う。解っていながら、感情では割り切れない苦さ。
「違うな」
と、頭の中の声が現実に音になり、サリスはその音が労りを含んでいる事に気づく。
失態を犯した事に俯いていた顔を上げれば、その場の空気は柔らかい。
「俺がはじめに意図を伝えていた事で、結果が変わったというなら、それは俺の期待した結果にはならない」
お前にこの役目は向いていない、と告げられるそれさえも断罪ではなかった。ミカヅキが打ち明けた事実は自分にとって厳しいものであったが、当のミカヅキはそれをまるで問題視していないのだと解った。それどころか。
「向いていない、と言われて何故落胆するのかが解らないんだが」
と言われて困惑する。
「え?ええ、と、それはやはり、主人の期待に応えれられないのいうのは従者としてあるまじき事で」
将来主人を頂く諸侯の子息たちが繰り返し繰り返し教育される事。
それは、主人となるミカヅキには施されるはずのない教育。だからか。
「主人の期待に応えるためだけに向いてない仕事を強要される方が悲惨だと思うが」
どうか?と問われて、そんな考えはなかったな、と呆気にとられた。
そんな甘い考えで主従関係が成り立つか?向いている仕事だけを任されているのは自分的には楽だろうが、それでいいか?と、初めての思考にただ唖然とするばかりのサリスに。
「それに、俺はお前に対する期待が失せたとは言ってないからな」
向いてない、と言ったんだ、と主張するミカヅキが、誤算があったとすれば俺の方だ、と続けた。
「お前の存在を余りにも軽く見過ぎていたのだと思う」と言い、自分の感覚が鈍ってしまっているのだと解るなと告白するそれ。
「お前の処遇がどうあろうとも、やはりオットリー家の子息で、その身分というものに生かされている以上は、例えあいつらであっても粗雑に接していい人間ではない。それは上には勿論、下の人間に対しても侮蔑になる」
何よりあいつらがお前を軽く扱う事に不快感がある、と言い切ったミカヅキは、生まれながらの爵位の後継者だった。
城から出て自由を求め、上下のない庶民の子等と馴れ合い、それを快くは思っていない上の方々からは「とっとと呼び戻せ!」と、道を見誤っているかのような扱いを受けているミカヅキは。その本分を見失ってはいない。
(俺たちが引き戻す必要もない)
まさかミカヅキがそこまで踏み込んで自分の事を考えてくれるとは思わなかった。
ただただ自分は旅に同行し、ミカヅキの気に入られるために下に媚びて無難にやり過ごせばいい事だろうと高を括っていたと言うのに。
「お前も不快な思いをしただろうが」
と切り出されて、慌てて居住まいを正す。主人格に頭を下げさせるわけにはいかない。
「いえ!あの、俺の方こそ、そこまで考えが至らず」
「そうだな、考えなしに強引に着いてくるって言ったのお前の方だからな。俺からあいつらの態度に関しては謝らねえけどな」
そこは手厳しい。いや全くミカヅキの言う通りそこはサリスの自業自得なのだが。
厳しさと優しさの根底が同じだ。それは純粋に、ミカヅキという人柄を信じられると思ったと同時に。
「お前が軽く扱われているのが不快だ、と思うのと、お前が俺に言う事も同じなのだと気づくことができた」
「あ」
「ならばやはりこれは、自分たち以外に見せるべき部分ではないのだろう」
冒険者として、後継者が外へ出て行く事。それに対する貴族界の総意も、実感として掴んだという。
(そこを解ってもらえたか!)
そこを簡単に乗り越えられるものなら、この先、ミカヅキの抱える難題はきっと話して聞かせれば解ってもらえるだろう。
結果的に、そして総合的に、この旅は有意義なものであったと伝えて、サリスを否定しない。その姿勢を見せるミカヅキは主人として十分な素質を備えていると希望が見えた。
「だから、ここの部分は保留だ」
将来的に、ミカヅキと冒険者の彼らの橋渡しをする役目を負う者。
そこにいるべき人間の選出は今はまだ置いておく、というミカヅキにサリスは同調してみせる。上からの指示は「引き離せ」という方向ではあるものの、ミカヅキのこの様子であれば強攻策に出るよりは、ミカヅキが自ら距離を置く流れを期待した方が良い。ミカヅキは本分を見失ってはいない。
そう確信して、サリスは希望を見る。
▪️ ▪️ ▪️
「そういうわけで、宙に浮いたお前の処遇を考えてみた」
「あ、はい!」
お前は期待した役目には向いていない、と良い、向いていない役目を任せる気は無いというミカヅキの主義。
従者ではなく、味方が欲しいと言ったミカヅキの趣意。
「職ならどこへでも行ける。オットリーの名があればどこでも高待遇で迎えてくれるだろう。最悪オットリー家の世話にもなれる立場で、あえて今まで交遊のなかった俺の下に就きたいと志願するのはどういうことか」
「あー…」
「懇意にしているスワロウ家でなく、あえてレネーゼ家だ。だとすれば、レネーゼの名が欲しいのだと思う。名が欲しい場合は大概政が関わってくるものだが、そんな野心家には見えないしな。むしろ、気の良い仲間と争うことなく平穏に過ごしていたい人物だと見た」
サリスの処遇、を考える前に、サリスの志願の動機を考えたらしい。
当たらずとも遠からずで苦笑いしかできない。
「そ、そうですね、ええ、その通りで」
「なら、根回しだな。俺なら正当後継者の中でも年少で、手懐けやすい。今まで供の一人もいない、従者という空きもある。上からの後押しも楽にいただけるだろうしな」
そこに潜り込んでおいてスワロウ家あたりから繋がりを作っておけと命令されたか、とサリスの動機を不安材料としていいものかどうかを確かめている。
その不穏さには、全力否定だ。
「まさか!違いますよ!命令なんかじゃなく!俺個人で動いてるんですよ!」
ていうか俺個人しか動いてないんですよ、と考えて情けなくなる。
交友関係の幅は広くとも、貴族界の将来に確たる展望を抱いて上昇志向を持つ者がいない。陰謀だろうと策略だとろうと、何かしらあった方がまだましだったかもしれない、と憂えるほど呑気だ。実際、そんな陰が生まれればそれはそれでサリスを煩わせただろうが。
「いないんですよねー…」
と苦笑さえも生まれない返答に、ミカヅキの呆れたような声。
「道楽者の、起爆剤にでもなるつもりか。もの好きだな」
「ええ?なんでそれを分かっちゃうんです!?」
他人に興味がなさそうなのに、意外とサリスの事を見られているようで焦る。
それにミカヅキは、薄く笑った。
「なんだ読み通りか。人のことを単純だという割にお前も、単純だったな」
それは、従者志願にレネーゼを訪れたサリスがとった挑発。
ミカヅキに相手をされそうもないので、まずは自分に興味を持たせるためにと考えたシナリオの一手。その挑発を根に持ってのことか。
(意外と執念深かったり?)
と、この時のサリスはまだミカヅキという人物を把握しきれていなかったが。
彼の専属従者となった後のサリスなら、執念深いのではなく、子供っぽいのだと判断しただろう。時折見せる不完全なそれは、実際の年齢よりも幼く、拙い。
それはミカヅキが今まで同年代の子供たちとほとんど交流をしてこなかったことの現れか。子供らしい振る舞いをどこかに押し込め、大人たちばかりに混じって後継者として生きてきただけの彼が、時折渇望するもの。
それがあの冒険者らからのみ与えられる現状だとすれば、「彼らとの交流を継続させるべき」と判断した老侯爵の意思を汲み取って、彼らの存在を許すことも出来るのだが。
それはまだ後の話。今のサリスでは、ミカヅキを理解しようと努めるのに精一杯。
「いやでもその、レネーゼの名前の皮を被ろうとか、そういう不遜な動機ではなくて」
「別に不遜でも不敬でも不届きでも、俺は一向に構わないんだけどな」
「ええ?」
「むしろ、レネーゼの名前を利用してやる、くらいの意気込みでいてくれた方がいい」
俺は味方が欲しい、と再度繰り返される。
「従者は要らない、味方が欲しい。そのためにお前を利用する気満々だ。聖人君子並みに清い動機でそばに居られると却って扱いにくいだろ」
それに。
「山ほど従者を押し付けられるんだぞ。それも各家から。思惑も目的も派閥闘争も渦巻いてる所に、お前一人が安穏と過ごせると思うなよ?他の家を出し抜いて、俺の第一側近にのし上がる、と周囲に宣言するくらいでないと従者として迎え入れる気は無いからな」
(ひええええっ)
「いや、それは、待ってください!第一側近とか、いきなり最高峰すぎますよ!せめて、側仕えの一人として」
「その程度の覚悟で腹を搔っ捌く気だったのか、お前」
返す言葉に詰まる。
「俺の従者を志願するというなら、第一側近だ。他の地位は認めない」
数多の家から送り込まれるであろう従者候補を軒並み抜いて、後継者に並び立つ地位まで来いと言う。
それがレネーゼに名を連ねないサリスを迎え入れる条件。
「そこまでしないと、レネーゼはオットリーの名を持つお前を認めないだろうしな」
腹を捌いてみせる方が楽か?と揶揄されても、おいそれと答えることができない。
膝に置いた自分の両の手が力任せに握られているのは、そうでもしないと膝が震えてしまいそうだったからだ。
(大変なことを言ってしまった)
ミカヅキに対面した時に、作戦とはいえ挑発した言葉が今更サリスの命を狙う。
後継者としての立場を軽んじるな、とミカヅキに向けた言葉は、今まさにサリスに返ってその身を突き刺すも同然の刃。
引くか、受け入れるか、二つに一つだ。
従者としてその覚悟を疑われる事あらば、腹を掻っ捌き、絶対服従の証を立てよ。
幼少からサリスを可愛がってくれた爺やが、事あるごとに聞かせてはサリスを面白がらせていた言葉だ。それは知らず知らずのうちに、自分の血となり肉となっている。
嫌でも身に染み付いたそれを思えば、まさか腹を搔っ捌く方が楽だと思う日が来るとは思わなかった。
これが後継者か。
家を継ぐということの重みは、サリスには一生縁のないものだ。だからこそ、家を継がなくてはならない親友の愚痴にも付き合えた。互いに立場が違う者同士、相手に同情していながら、その内実を真剣に考えたことなどなかったのかもしれない。
(自分の甘さは十分、解っていたつもりだった、けど)
レネーゼ領へ向かう馬車は走り続けている。侯爵位へサリスの処遇を決めたことを伝えに行くための馬車だ。
だからこそ、サリスの答え一つで、ミカヅキは馬車を止めるだろう。
それなのに、目の前にいる彼は答えを急かしてはこない。急かさない理由があるとすれば。
ミカはもうとっくにサリス様を受け入れているんだよ。
そう言った彼らの顔がちらつく。格下の彼らに面と向かえば素直に受け入れられなかった言葉。
つい先ほどに、彼らの言を聞き入れなかったことで味わった後悔は苦かったはずだ。それをまたここで繰り返して良いのか。
誇りよりも大事なものがあると思ったのは、わずかな希望だった。
「わかりました」
サリスは顔を上げる。
主人となる人に、真っ向から自分をさらけ出す。
「ミカヅキ様の第一側近を志願させていただきます」
「うん」
それだけ。
たったそれだけの反応。それこそが、自分は受け入れられていることの証であるというのに。
「それだけですか?!」
サリスは思わず身を乗り出す。
「なんかもっとこうないんですか?すっごい手に汗握りましたよ俺!!」
思っていた以上に重圧を感じていたのか、あまりにもあっけなく終わったばかりに身も心も浮つく。
自分は、ミカヅキの従者となる。
「なんか、ってなんだよ?」
「いやそれは俺も解らないですけど!俺なんかが第一側近に名乗り上げるって、相当おこがましいですからね?!」
「そのための二年だろ」
ミカヅキの真意は窺い知れない。ただ淡々と、サリスの宣言を聞く前と変わらず、言葉をつなぐ。
「二年で、お前を第一側近に押し上げるために俺も準備は整えるつもりだ」
「準備、って」
主人が従者の地位向上に手を貸すという。これは、はたから見ればどうだ?遊びか?
身を乗り出していた体勢が、がく、と背もたれに崩れた。
「例えば、レネーゼの外との交遊」
「外」
「お前言っただろ、夜会で。多くの家と交流しろ、って。あれを盛大に仕掛ける。今までレネーゼのどの家も口出しできなかった部分だ。お前が多くを働きかけて成果が上がったとなれば、多少は褒賞の嵩上げになるだろ」
名門地位上下いかんに関わらずありとあらゆる家と交流してやろうじゃないか、とミカヅキは笑う。
「そこは協力してやるから地ならしをしておけ。末端まで取りこぼすことなく、円滑に交遊できるように根回しに勤しめよ」
そこに期待しているからな、と念を押されて思い至る。
「レネーゼの名を」
「存分に使え。お前が志願した動機とやらに利用されてやる」
将来。
必ず訪れる、ミカヅキ世代が政の中心となる将来に、仲間たちが誰も落ちこぼれることなく関われるようにという願い。
親友である彼が、同等の爵位を頂くミカヅキに、見劣りすることなく引けをとる事なく対等に渡り合えるようにという願い。
サリスの子供じみた願いには耳を貸さず、それでも「利用されてやる」などという愛敬を見せることのできるミカヅキには敬服するしかない。
「そういう意味ではお前は城勤め向きだな。俺が育てるにしては完成度が高すぎる。むしろ、俺の方がお前から教わる部分の方が多いんだろうと思う」
「いや、まさかそんな」
「俺に謙遜は無意味だぞ。自分の価値を高めるためには、俺さえも利用しろ。そうでもしないとレネーゼに居場所は確保できないと思え」
「居場所」
「俺が外に出ている間にも仕事を任せろと言ったよな」
お望み通り任せてやる、という事だ。上にも下にも、ミカヅキが後継者として円滑に交流できるだけの地盤を築く。
旅の間の不在を埋めるだけの働きを期待されている。
それはいつかの夜会でも話題に上がったミカヅキの展望だ。
「あの時、はっきり俺に指令をくれませんでしたよね」
皆に事前に言い聞かせるようには言われたが、その後に人脈を作るための指示はなかった。サリスを使う気は無かった、という事から考えても、ミカヅキの気が変わった事は何か意味があるのか。
「あの時は、お前を孤立させるだけだと思ったからな」
「あ、ああ」
そうだ。ミカヅキはこう見えて、思ったより情が深いのだった。
他人と付き合わない、他人に心を開かない。それが、サリスを含め周囲が思い描いていた人物像。
空気を読まず、他者の立場を慮る事なく自由に発言しては、その場を急冷凍の惨状に落としれる悪の申し子。と言ったのは誰だったか。
ミカヅキと行動を共にしてサリスもその異名に納得せざるを得なかったこの数日。
「お前が孤立したら、俺は誰を頼れば良いんだよ?」
「……」
もっと頼れと言ったの、お前だぞ。と大真面目に言われて、情が深いという決めつけは早計か、とサリスが返答に困って見せれば。
微妙は雰囲気を感じたか、少し何かを考えるように視線を傾げたミカヅキが、お爺様が、と小さく呟いた。
レネーゼ侯爵が、ではなく。
お爺様が、というのを初めて聞いた気がする。そしてそれは、思った以上にミカヅキの感情を露わにしていた。
「人を束ねるという事は頼りない糸を束ねる事と同じだ、と」
サリスもその繊細さに触れて、ただそっと息を潜めた。
ミカヅキが現レネーゼ侯爵に、常々言い聞かせられているという言葉。
それが、レネーゼ領へ向けて走る馬車の中で語られる。
(糸を、束ねる)
細く繊細な糸を、一本一本、自分の意に美しく添わせ整えるように束ねていく。
細さも強度も色も全く異なるそれらを、集め、束ねる。意のままに。
意のままに束ねようと、どれほどの努力と研鑽があっての事でも、初めには頼りなく、中ほどでは緩みと張りが妄りに繰り返され、後ほどにはもう解けないほどの束になる。
それがレネーゼの在りようだ、とミカヅキは言う。
子供の頃に。何度もなんども、想像の中で糸を束ねては解き、束ねては解き、それを自分の責務だと思い描いてきたのだろう。
(この人は真面目すぎる)
あまりにも真面目すぎるのだと解った。
夜会の席でミカヅキに伴われて上の方々への挨拶回りでも、特にミカヅキの親戚筋からは「真面目すぎるので多少は羽目をはずす方がいい」「もっと遊びを教えてやってくれ」などとからかわれている姿は見ていたが。
(あれは冗談でなく、あの方達の本音だったのかもしれないな)
真面目過ぎて、老侯爵からの「子供に解りやすいように」と加減をした例え話にさえも、一糸乱れぬ統率を思い描き一人疲弊していたのだとすれば、従者を持つ事を忌避するようになるのも理解できる。
それに何を言ってやれば良いのか。サリスの逡巡は轍に押し込められるかの様だ。
何万という家臣を束ね、 束ねたものが太くなればなるほど中の様子は伺い知れず、繊細さも美しさも、ありのままの形を保つことさえもなく、ただただ一つの束となって、主の手に握られる。
握られたその重みを、誰に言われることもなく知る。
レネーゼの名の下に、家臣は束となり、領土を、領民をつなぎとめる命綱となるのだ。
「俺の、その最初の一本がお前だ」
その言葉が、胸を貫く。
覚悟を受け取った、と言ったミカヅキの、サリスへの答えがそれだった。
ミカヅキの意に添い、多くの糸をその手に委ねるための始まりの一糸。
「必ず」
震えたのは、声か。心か。
「必ず、ご期待に応えてみせます、我が君」
「うん」
反してなんの感情も見せず、ただ頷いたミカヅキの抱える重圧は計り知れない。
それでも自分は、その将来を共に担うことに恐れを抱いてはいない。
多くの命綱を握る主としては繊細すぎる彼が、慎重に慎重を重ねギリギリまで時をかけて吟味した一糸。
糸の先は、固く結ばれている。
そのはずだ。
スワルツ・サリス・オットリー。
オットリー侯爵の祖父を持ち、次期後継者である父とその長子である兄に、「お前は侯爵家の一員としての覇気が足りない」と、常日頃から責めたてられながらも、一切口答えせず、道も踏み外さず、心優しく育った21歳の好青年である。
…と、自分では思っているがしかし「好青年」は果たして相手に好印象をもたらす特徴になり得るであろうか、というのが最近の不安材料だ。
特に今日は。
今日だけは好印象を爆上げで臨みたい会見である。
レネーゼ侯爵家の来客室で一人、会見の相手の到着を待ちながら深呼吸を一つ。
それに驚いたわけもないだろうが、窓の外で鳥が飛び立つ気配がした。
そちらに目をやり、所在なげなソファーから立ち上がったサリスは窓辺へ歩み寄って、そこからの景色に想いを寄せる。
明るく手入れの行き届いた庭は偶然にも、あの日、レネーゼの後継者によって夜会の開かれた場所だった。
前回の月見の夜会。
レネーゼ侯爵家の正統後継者ミカヅキが、サリスらの若い世代に向けて自身を公開した庭。
それまで頑なに人との交流を拒み、孤高の存在として貴族界にあった彼の内面を、その場にいたどれほどの人間が理解し得ただろうか。
(恐らくは誰も)
誰もが戸惑い、遠巻きに様子を伺う中で、サリスの目に映った人物像はそれまでの印象よりもなお一層、寂寥感に包まれていた。
(知り得ない)
その寂しさは時間が経つにすれ、度々、サリスの胸を締め付けるようになり。
(だから)
こうして、今、レネーゼ侯爵家のこの場所へとサリスを引き寄せた。
サリスがこの場で待つのは、レネーゼの正統後継者ミカヅキその人であり、彼の了承の一言である。
(その一言を頂くまで、この場を離れない)
不動の意志で相対するのは、大いなる権力の奔流。どれほど乱されようとも決して引いてはならない。
その為になら、「好青年」などと言う曖昧な印象はかなぐりすてろ。
スワルツ・サリス・オットリー、生まれて初めての奮戦に挑む。
◾️ ◾️ ◾️
侯爵家月見の夜会。
諸侯らが集い、権力の渦巻く宴が華々しく開かれているその一角で、次期当主が若い世代を集めての会を催すことは誰もが黙認していた。
事前にその情報を細部まで収集しておきながら、我々の知り得ぬところ、と嘯く。
そんな状況下にあって、その会を準備万端に整えておくように、と次期当主本人から事前に指示されたのはサリス一人。
そこに至るまでの過程は、単純な偶然の仕合わせでしかないと理解している。
特にサリスの何かが彼に選ばれたわけではなく、他に誰かが居合わせれば恐らくはその誰かがこの役目を負わされていた事くらいは、簡単に想像できる。
貧乏くじを引いたな、という思いを抱えながらも指示された通りに下準備を済ませたサリスは、約束の時間まで間があるのでその辺りをふらついていた。
いつものように遊び仲間と一緒にいるのが気詰まりだった、というのもある。
侯爵家の次期当主、ミカヅキは若い世代の誰とも交流しない事で知られた人物だ。あからさまに爪弾きにされているわけではないが、彼が輪に入るだけで場が不興になるのは、サリスたちより下の世代では誰もが知る所である。
そんなミカヅキと交流を持つべく奔走している(と言うか正確には奔走させられている、のだが)サリスの評価は、仲間内だけでなく周囲にもダダ下がりである。
余計なことをしてくれる、と言う暗黙の冷ややかさに耐えられなくて場を離れたのだが。
宴の庭で、当のミカヅキに出くわしてしまった。
(俺、この夜会ではこの人になんか妙な縁があるな)
と運命を呪ってはいても顔には出さない。
「やー、やあ!もう皆集めて、準備万端だよ」
昨夜からミカヅキ本人が望んだように、なるべく対等に、ざっくばらんに、気安く、親しげに、なるように声をかけてみたが。
ちらりとサリスを見てミカヅキは言った。
「ずいぶん早いだろ」
その態度からは、待ちきれずに早々に会にやってきた、というわけではなさそうだ。
もっと言えば、今朝のミカヅキに感じた、…根回しを頼むと持ちかけてきた時のような、少しはサリスに打ち解けてくれたと思える様子さえもない。
それはもう、余計なことをしてくれる、という仲間内の冷ややかさよりもさらに温度が低く、「そうしろって言ったの貴方ですよね?!」と言いたくなる素っ気なさだ。
「ああ、そうだな、ずいぶん、かな」
とサリスが言葉を探っていると、周囲に目をやったミカヅキが今度はちゃんと向き合うように立つ。
「先に上の方々に挨拶を済ませてくる」
「挨拶?」
「明日まで滞在の方に終宴までの心尽くしとこの度の御礼の挨拶な」
そんな事までやってるのか、この人!と、サリスは驚く。
いや、確かにミカヅキの立場でいえば正統後継者であるのだから、自分たちの父世代と同様の役目をこなしているだけの事なのだが。
サリスより5つは下のミカヅキがそれをやっているというのが衝撃的すぎた。
「ああ、じゃあ俺も行きますよ!」
「はあ?お前が?なぜ?」
「え?なぜって、ほら、…この宴、ミカヅキ殿が若い者たちを集めてるのは上の方々もすでに知ってますからね。唐突になんだ、何があった?って変な勘ぐりを持たれる前に、あ、いや別に勘ぐられてるわけじゃないですよ?!そうじゃないんですけど、なんかそういうの、まず、俺が一緒に行動している方が、なんだ和気藹々騒ぐ仲間ができたんだな、って見方もしてもらえると思うんですよね」
サリスの長々とした説得に口を挟む事なく、大人しく最後まで聞いていたミカヅキが、そうか?と小さく呟くように聞いてくるのに、そうですよ!と畳み掛ける。
それに、そうか、と答えるのは、サリスの提案を受け入れた様子。
この時はサリスにさえも、なぜここまで強引にミカヅキについて行こうとしていたのか、考えることもできなかったが。
ミカヅキの上の方々への挨拶回りに同行して、サリスは自分の行動を理解できた。
それは、貴族社会で叩き込まれた生存本能そのもの。
ミカヅキを一人にしてはならないという、無意識の行動だった。
まだ少年の域を出ていない、未成年であるミカヅキは上の世代に非常に受けがいいのは良くわかった。
年寄りの長話にも丁寧に対応し、大仰な説教や小言にも鬱陶しがる素ぶりをわずかも見せず、謙虚に慎ましい礼を返す。ミカヅキの内心を伺うことはできないがそれでも、自分や仲間たちの態度を思い返せば、ここまで徹底した礼節で上の方々と接することはできないな、と、サリスは感心を通り越して恐れさえも感じていたのだが。
何件めかの挨拶の時に、和やかに談笑を続けながらもミカヅキが二杯目のグラスを勧められているのを見て、思わず身を乗り出していた。
「ハノンヴェール様、その杯は私が頂戴します」
ミカヅキの手に渡されるはずのグラスを横から押し戴く。その場の全員が、突然割り込んできたサリスの存在に驚いたように、わずかな間があった。…ミカヅキも、同様に。
だがサリスはそれらが場を固める前に、ハノンヴェールの統治を称え繁栄を祝う言葉を述べて、その杯を飲み干して見せた。
正直、口当たりよりもはるかに強い酒だ。
成人していないミカヅキには、早すぎる。
驚いたようなミカヅキの瞳は、すぐにサリスを案じるような影を落としていた。それに笑みを返す。
何も心配する事はない、と笑みだけで返しておいてすぐにハノンヴェールの席に向き直った。
「ああ、これはハノンヴェール様が御気に入られるだけはある、特別な逸品ですね」
この宴のためにレネーゼ公爵家が用意したものではなく、彼が自ら持ち込んだものだろう、という意味合い。そういえば、ハノンヴェールがわずかに身を乗り出した。解るか、と言った彼の興味は、ミカヅキではなく初めてサリスに注がれる。
「それはもう。この宴で口にしたどの銘柄よりも明快な口当たりで、なるほど美酒とはこういうことかと」
適当に調子を合わせればハノンヴェールも、取り巻きも、面白そうにサリスの話を引き出そうとする。
サリスはほどほどに相槌を打ちながら、興が削がれないギリギリのところでグラスを返し、ミカヅキを庇う。
「けれどミカヅキ様がこの美酒の違いをわかるには、いま少し、早いですね」
今後の牽制も込めて。
引き際を見極めて。
「ミカヅキ様はようやく宴を楽しむことを覚えたところです。ハノンヴェール様のお相手になるまでは、今少し。まずは若輩者の私たちの座にお招きしたいと思っている次第で」
この後、若者たちが集う意味合いをも抜かりなく披露しておく。
それは貴族社会全体が願ってもないことだ。自ら孤立するミカヅキを、どうあってでも手中に取り込め、というのはどの諸侯の子息たちにも下された厳命だったのだから。
「おいおい大事な正統後継者に悪い遊びを教えてくれるなよ」
と、ハノンヴェールが口にした酒の席での揶揄も鷹揚さを気取っていながら、その芯にあるものは決して公にはできないミカヅキの処遇。
それを明言する。
「もちろん、ご心配なく」
決して悪いようには致しません、とその場を離れる時にはもう、サリスにも分かっていた。
貴族社会で数多の子息が、主人を守れと教育を受ける。それは逃れられない宿命のようなもの。望むと望まざるとにかかわらず、サリスの中にもその血が流れている。
供も付けず宴の輪の中に挑みゆくミカヅキを、このまま一人行かせてはならない、と無意識にこみ上げた衝動も、今なら解る。
「お前、大丈夫なのか」
あれからさらに二件の挨拶をこなし、ハノンヴェールの席と同じようにミカヅキに代わってグラスを重ねた。
宴の中心から離れ、人の輪から遠ざかって、その事を持ち出したミカヅキに、サリスは平然と頷いた。
「ええ、俺、酒は割と強いんですよ」
煌びやかな灯りを背に、ミカヅキと連れ立って人気のない庭園の端まで歩を進めて、ここらでいいか、とサリスはミカヅキを誘うように立ち止まった。
「座りますか?」
と、バラ園のベンチを指せば、いいや、とミカヅキが返す。
館からの宴の灯りだけを頼りに、ここまでミカヅキを連れ出したのは、何よりもミカヅキの身を案じたからである。
「ミカヅキ様こそ、だいぶ酔いが回ってるでしょう」
少し冷ました方がいい、と言えば、ようやくミカヅキはベンチに腰を下ろした。
随分と気を這っているのだと思う。まるでそうとは気取らせない、完璧な振る舞いの美しさではあるが、それも宴の光から離れればわずかに気を緩めることができるのではないかと思ってのことだった。
他人の目があれば決してわずかの弱音も吐くことのない幼い後継者、その姿を今回初めて直近に見て、こみ上げたのは庇護欲。
「ミカヅキ様…、貴方いつもああやって杯を受けてるんですか?」
「そうだが」
「断らずに?」
「断れないだろ」
うわ、マジか。と思う。
そう、ミカヅキは今まで側近を持たなかった。今の形だけとはいえ自分が初めての供だ。夜会で見るミカヅキはいつも格上で遠い存在だと思っていたから気づかなかったが、会の度に、お目通りがあるたびに進められるままに杯を重ねていたのか。
「早死にしますよ」
思わず本音が漏れたサリスに、ミカヅキが顔を上げる。
「俺だってお前にグラスを取られたときは生きた心地がしなかったぞ」
ああ、そうか。と思う。あの時、ミカヅキが驚いていたのを思い出す。上の方の不興を買う、それに対応できるかどうかとっさに身構えていたのか。
「…あれくらい、夜会では当たり前にありますよ」
「えっ、そうか?」
「そうですって。ミカヅキ様は側近も連れずに席に出るから知らないんですよ。そんな一諸侯に会うたびにガンガン酒飲まされてるなんて、向こうだって思ってませんよ!思ってないからいい加減に勧めてくるんです、適当に断って適当に受けてりゃいーんですよ、ああいうのは!」
そうして。
自然に、ミカヅキの側に膝を折っていた。
「断るときは俺が受けますから」
そのためにいるんですよ、と言えば、ミカヅキは黙って視線をそらせた。
そうだ。従者はその為にいる。貴方を守る為に、要るのだ。
ミカヅキが他人を受け入れることが出来ない弱さを抱えていようとも、拒めるものではない。
この先に進むのなら、なおのこと。
庭に灯る儚い灯篭の光に、その頼りない姿を見る。初めてミカヅキを、頼りのないただ一人の少年なのだと知った。
「…もっと俺を頼ってくれて良いですから」
思わずそう口にしていたことに、サリス自身が驚いた。
誰かの従者になるだろうこと。それ以外の道はないと、なぜか盲目的に思い込まされていたことも、小さく、ウン、という声が聞こえてたまらなくなる。
(俺は、生涯、この人を主と頂く)
その確信。
「さあ、この後の挨拶は俺にすべて任せてください。供を連れた夜会でのふるまいは俺の方が詳しいですよ」
◾️ ◾️ ◾️
その後、ミカヅキの望むままに挨拶回りを済ませた。
気分が高揚していささか調子に乗りすぎたか、挨拶に予想していた時間を大幅に超えてしまったが、ミカヅキは許してくれた。
「今日は普通に眠れそうだ」
そう言ったミカヅキの横顔は、特にサリスに打ち解けているわけでも、心を委ねてくれているわけでもなかったが、それでも良かった。
自分は役に立てた。
そして、従者を連れることは役に立つ、とミカヅキが認識してくれたことが重要だ。
後は、その従者に誰が選ばれるか、と言う事だけ。
(そのためにも、この夜会は正念場だぞ)
そう、サリスは一人覚悟して、若者たちだけを集めた夜会に挑んだ。
この際自分が選ばれなくても良い。従者としてでなくても良い、この夜会で誰かがミカヅキの気に入られれば、これまで一切の交流がなかったミカヅキの周囲が変わる。
周囲が変われば、ミカヅキもより従者を求めやすくなるだろう。
決して悪い様にはいたしません、と上の方々に大見得を切った様に、それは上手く行くものだと軽く考えていたサリスだが。
その夜、期待していた結果は得られなかった。
「みんなが思ってるほど付き合いにくい人じゃないんだって」
と数人をけしかけても、すぐに会話は途切れ輪が崩れてしまう。
ミカヅキは誰のどんな言葉も真正面から受け止める(それこそ年寄りの愚痴にさえも汚れない笑顔で対応できるほどだから問題ない)が、ミカヅキに対する人間の方に耐性がない。
話しかけては会話に詰まり無理だと分かればあっさり遠巻きにする、それが人を変え、なんども繰り返されるのを見ていて、サリスは問題はミカヅキの方にだけあるのではない、と気づいてしまった。
(俺たちは、気に入った人間としか付き合って来なかった)
仲のいい集団として、学生時代から今まで連んできた仲間たちは気のおけない奴らだが、その実、今が楽しければ良いと言うお気楽さが蔓延している。
煩わしいことを嫌い、上からの強制に不満を抱き、支配から逃げる様に楽な事ばかりを選んできた様に思う。
だからミカヅキとうまくいかない。
気が合わない人間と、いかにうまくやっていくか。
(それに向き合う覚悟が足りていない)
今日の挨拶回りでのミカヅキを見たからこそ言える。
自分たちにあれは無理だ。
まだ現実から目を背けていられる立場だから。
嫌でも向き合うしかないミカヅキとの絶対的差がそこにある。
(だからって)
その差を埋めようとすればするほど、サリスは空回りを演じてしまうのだ。
(どうすれば)
貴族社会における自分の展望を周知徹底しておいてくれ、と事前にミカヅキに言われた通り、この場に集まる人間には話した。
それだけで今までの溝が埋まるはずもなく、交流を持とうとする意思を見せる者とミカヅキとの間に立って互いの意思疎通がうまく行く様に頑張って場を盛り上げようとすればするほど、仲間との温度差が開いていく。
それを気にかけてくれたのはミカヅキただ一人。
「お前、別に俺といなくても良いんだぞ。変に仲間から浮いてるだろ、あっちいけ鬱陶しい」
口は悪いが、その意図は解る。
下準備をしろとは言ったが、会まで付き合わなくても良い、というそれ。
サリスの仲間内での立場まで、分かってくれている。今サリスがミカヅキと懇意にする事で、サリスが周囲から反発を受けることまで案じてくれているのだ。
それは、今までに従者を持たなかったミカヅキの弱みでしかない事ではあっても。
この人は分かってくれているじゃないか、という思い。それは仲間に対する恨みではない。
自分を含めての失意だ。
(俺たちは甘かった)
貴族社会で生き抜くために、ミカヅキはありとあらゆるものを総てかっさらっていく。
後に残された自分たちはどうなるか、それを誰も分かっていなかった。
いや、分かっていた者たちは先に手を打っていたのだろう。ミカヅキにかっさらわれる前に、自分たちの立ち位置を確保する。家の跡を継ぐために、あるいは主を頂くために、国に仕えるために、もっと言えば貴族社会から決別し自力で生き残るために。
(このまま取り残されて良いのか)
それを思い知らされた夜会だった。
夜の庭で、示されたただ一つの道。
それをいくら説いても、仲間には解ってもらえない日々の焦燥にサリスは覚悟を決めたのだ。
どこまでも一人、後継者という道を一人行くしかない彼の、最初の供になる。
選ばれなくても良い、などという甘えた考えは捨てた。
選ばせるのだ、自分を。
父親世代と肩を並べるために先へ先へと突き進むしかないミカヅキを引き止める。引き止めることができるのは、今は自分しかいない。
そして今が楽しければ良いという仲間たちもいずれ気づくだろう。
進むことも戻ることも、今まで自分たちが逃げていたことに向き合わなければ果たせない時がくる。
そうなった時に、ミカヅキとの橋渡しができる様に、今はミカヅキの側に身を置く。
(そう言われたのが俺だっただけだ)
あの日。
この庭で。
レネーゼ侯爵家の次期当主に、下準備をしておいてくれ、と言い渡されたこと。
あれはきっとこの為だった。
夜会で動き出した運命は、今大きく未来を見据えるための道につながっている。
ミカヅキがレネーゼ侯爵と呼ばれる日のために、今、下準備を始める。
彼を孤独のままにはさせない。
それがサリスの役目。
貴族の子息に生まれたその時から言い渡されてきた事。
主に仕え、主を守り、主のために生きよ。
そこから背けていた目を、現実に戻す。
あの夜の庭は、まぶたの裏。
木漏れ日が音を立てる風にきらめいて、その眩しさにサリスは窓の外から室内へと向きを変える。
重厚な扉がノックされ、待ち人が到着したことを告げる侍女の声。
衣服を整え、深呼吸をひとつ。
扉を開けて会見の間へと案内されるサリスの視線の先に。
主となる人がいる。
プー太郎が就職する覚悟を決める話だわ
その日、レアは偶然にも、王城でレネーゼ侯の子息ミカヅキの姿を見つけた。
偶然にも、というのは、レア自身、滅多にないことだが侯爵家の使いで単身王城を訪れていたという事と。
これまた滅多にない事に、世界の国々へと出かけて家を留守にしているはずのミカヅキが王城に立ち寄っていたという事の重なりによる。
(お声をおかけして良いものかしら)
王城という公式の場で、自分の立場とミカヅキの置かれている立場とを考える。
平民という身でありながら侯爵家の侍女という地位へと上り詰めてきたが、未だに公式の場での振る舞いには助言を必要とする事もしばしば。
特にこの場合、何か無作法があったとして上の方からお叱りを受けるのはミカヅキの方なのだ。
立派な成人であるレアのしくじりで未成年のミカヅキが叱責を負う。長くこの社会に身をおいていても、なんとも受け入れがたい慣例だ。
(侯爵家の方から正式に呼び出しは行っている事でしょうし、今私が関わらなくともミカヅキ様は家に戻られる…)
しかしとっくに呼び出しの連絡が行っていながら未だミカヅキがそれに応じていないことを考えると、単に連絡の手違いか、ミカヅキ自身の意思で応じない態度なのかは確認しておく必要があるかもしれない。
そう考えていた為にミカヅキから目を離せないでいると、ミカヅキに近づいていく人影に気付いた。
(あら、あれは)
ご友人だわ、とその微笑ましい光景に頬が緩んだ。
同じ年頃の少年と気兼ねなく雑談しているような姿は、自分が育った町で見慣れた少年たちと何も変わりはしない。
それを。
「ミカヅキ様が普通の少年であってはならぬ事です!」と、教育係であった当時の侍女頭に厳しく窘められた昔の事を同時に胸に思い描いてしまう。
それは許されない。決して許される世界に生きているのではない、と、教育係であった彼女にあれほど厳しく怒りを露わにされたのは、レアが侍女としての位について初めての事だった。
その剣幕には、そばにいた者たちに「レアが失踪してしまうのではないかと気が気では無かった」と後に打ち明けられた程だ。
(確かに震え上がった事は事実だけど)
今思い出しても、肝が冷えるのも事実だけど。
レアが侯爵家の侍女になったのは、侯爵家の為でも家の為でもない。自分の為だ。大切な人を守りたいと思い、その為の力を欲したが故なのだ。
(それを投げ出して失踪したりはしないわ)
と、幾度も言い聞かせてきた言葉を今また胸に落とし込んだ時。
レアの視界の中で、ミカヅキが振り返った。
隣にいる友人に何やら指図され、それを確認するかのような動作でこちらを向く。
とっさの事で、つい動揺し、それと分からないほどの軽い会釈を返したがミカヅキはすぐに視線を隣にいる友人に戻した。
(あら)
少し距離があるために気づかれなかったか、或いは、やはり公の場では良しとされない為になかった事にされたか、と考えていると、ミカヅキが友人と別れ、こちらへと向かって来るのが分かった。
侯爵家にいる時には考えられないほど簡素な服を着てはいるものの、その堂々たる姿は町にいる少年たちと比べられるものではない。
周囲の視線を集めながらその中心であることに僅かの疑問も持たせない存在でなければならない。
どんなに簡素な見かけでも優雅さをわずかでも損なってはいない一挙一動は、侯爵家の正当後継者として育てられた高き使命。それ以外の世界など存在しうるはずもない。そんな空気に威圧されるように、レアも知らず緊張を強いられ背筋を伸ばしていたが。
「お久しぶりです、夫人」
と、側まで来たミカヅキは単純明快な挨拶をした。
あまりにも率直なそれに拍子抜けして、レアも最低限のお辞儀をすることすら失念してしまったほど。
「ええ、月見の宴以来ですわね」
お元気そうで良かったわ、なんて口走りながら内心で焦る。
(ああビックリした、長々と登城の儀なんたらの口上でも述べられるのかと思ったわ)
前触れもなくそんな事になっていたら。
ただでさえ公式の場に馴染めない自分では、危うく失態に失態を重ねて王城中に広まってしまうだろう。
いや、王城の一広間で知人が顔をあわせるだけで、そんな格式張った口上を述べ合うことなど今の時代にはあり得ないとわかっている。
(だけど、そう思わせるほどの)
格式高い儀式での振る舞いであるかのようなミカヅキの雰囲気に飲まれたのだと思う。
いや、違う。これはミカヅキのせいではなく、普通の少年であってはならない、と言われたあの日のトラウマ。
この子供を、普通の少年と同じに見てはならない、と言う強迫観念が故の。
その動揺を、何気なくミカヅキの近況を尋ねたりしてやり過ごしているレアに気づくはずもなく。
それで、とミカヅキの口調がレアの言葉を押しとどめる。
「私を訪ねてこちらまでお越しいただいたのでしょうか」
「ええ、それが」
と事情を話し出そうとするレアを、ミカヅキが再び押しとどめる。今度は、言葉ではなく仕草で。
どうぞ、と無言で差し出された手はまだ少年のそれだが、多くの社交場で手慣れた感はあった。貴婦人を優雅に連れまわす、紳士としてのそれ。
ともすれば、自分の方がエスコートに慣れていないくらいだ、とレアは焦ってその手を取る。
「あ、ええと」
そんな大事ではないないのだが、と説明する前に、「この場を離れます」と短く告げてレアの足元を気にしてくれる。艶やかに磨かれた廊下や、洒落た作りのタイル張りの段差に気を配り、ドレスの裾捌きまで注意して、すぐそこの花園のベンチまで誘導された。
(まーすごいわーこんな事さらっとやっちゃうんだわー子供なのに紳士だわー上流階級のご子息ってみんなこうなのかしらー)
などと舞い上がっていたので、ミカヅキの意図を知れたのはベンチに腰を下ろした時。
「ここなら人の目もありますので」
と、レアの隣に座ったミカヅキの言葉に我に返り、そういえば、と今までいた場所を振り返る。
そろそろ帰ろうとしていたところでミカヅキを目にし、立ち止まった場所。
城内をめぐる入り組んだ通路が放射状にこの広間に集まってくる。豪勢な飾り付け柱や美術品がそこここに並べられ、それがあらゆる方向から視界の邪魔をする。多くを行き交う人々の視界には入りづらく、逆に忍んでいるようにも見えようものなら、有らぬ誤解を受けるだろう。ミカヅキはそれを危惧したのか。
円形の広間であるここは中央の花壇を囲うようにベンチが置かれ、視界は自然と広がり、何処からでも人の視線は自由に見渡されており、かつ人の導線の邪魔にもならない。
(そういう事なんだわ)
と辺りに目を配り、何気なく、ミカヅキといたあの町の少年を探していた。
その姿はもう何処にもなく、どうかされましたか、と隣から声がかかって、慌ててミカヅキに向き直る。
「あ、申し訳ございませんでした。まだ王城にはなれなくて」
ミカヅキの母親ほどの年齢でこれは恥ずかしい事だろう。
「だめね、配慮が足りなくて」
情けなく独り言のように口をついて出た言葉には、いえ、と短い返事ですますミカヅキ。
彼にとって、それ以上もそれ以下もないのがわかる。
(こんなところは、ミソカに似ているわ)
ミカヅキの母である女主人。彼女に長く使えていると、時折二人は重なって見える。
そう思えるのでミカヅキに苦手意識はない。むしろ今のように自分を異性として扱ってくれる分、ミカヅキの方が懇切丁寧なくらいだ。
そんな風に、今のミカヅキと同じ年だった頃の彼女の態度を思い返して比べてみては、微笑ましくなった。
「今日王城に来たのはミカヅキ様とは関係がないのですけれど」
と簡単に今日の用事を説明して、姿を見かけて声をかけようかと迷った原因を話しておく。
「お館様がミカヅキ様に言い渡すことがある、と仰っていたので」
おそらくその侯爵家からの知らせは行っているはずだが、とミカヅキを窺えば、まだ手元にはきていません、と言う。
「しばらく国を離れていました」
「あら、そうでしたの」
ならミカヅキがまだ知らなくても仕方がない。
「緊急ではない様でしたから、きっとミカヅキ様の事情を優先されたのでしょうね」
恐らくそのように指示が出ている。
ミカヅキが戻ったらことが進むよう手筈が整っているはずだ。
「それなのに私ったら」
「いいえ、夫人にお声がけいただけなかったら気づかぬまま国外へ出ているところでした」
「あら、間をおかずまた?それでは」
「いえ、知った以上は私の方で優先度合いを確認して対処します」
声をかけてもらって良かった、というミカヅキが微笑んでみせた気がした。
幼い頃から表情を変えることのない子供だった。感情をあらわにしない、それはそういう教育を受けているものだから、と分かってはいても親子間であってさえ淡々と接する上流階級のそれには未だ馴染めるものではない。
だが今のミカヅキからは、確実に親しみを込められた気がして。
「そう言っていただけて良かったわ、ミソカ様も気にかけておられたようですから」
と、つい余計な情報まで出してしまった。
「え?母上が?」
それほどの大事か、とミカヅキが身を乗り出したのに慌てる。
「あ、そうではありませんわ。いつもの親族会議の内容をお話ししておく、という事のようでしたから」
まだ成人していないミカヅキは参加できない会議だ。
だが正当後継者としてその内容を知っておくように、と老侯爵がミカヅキとの時間を設けて話し合うのはいつもの事。
「ではなぜ、母上が」
「お館様が先にミソカ様と話し合いを持たれましたの。ミカヅキ様がご不在だったから、という事ですけれど」
「代理を母上に任せてしまったのでしょうか?何かしらの決定を母上が?」
「ああ、いえいえ、決定はお館様が。その事後報告ですけど、ほら、ミソカ様は小さな事も先送りにするのがお嫌いな方ですし、単に気にされているだけなのですけれど」
「じゃあそれはすぐに戻ってあげた方が良いよねっ」
「!?」
と、突然割り込んで来た声に驚いて、レアとミカヅキは同時に背後を振り返る。
悪びれもなくベンチの後ろから二人の会話に割り込んで、ニコニコしている少女が一人。
「お」
いくら人の目があるとはいえ。
「お前なあ、堂々と人の話立ち聞するなって言ってるだろ!いつも!」
「やだなあ、知らない人の話は立ち聞きしないようになったよ?」
「なったよ、じゃねえよ!それが普通なんだよ、最低限の人としての礼儀だからな?!あ、あと師匠にも言っとけよ?」
お前らそれだから困るんだよ、と、あり得ないほどの口汚さで罵られているにもかかわらず、はあい、と機嫌よく返事した少女がレアをみる。
「ごきげんよう、レア様!」
「ごきげんよう、…ウレイ様」
思わず、勢いに押されて返事をしてしまったレアであるが。
レアにとって問題はもう突然割り込んできたこの少女の神出鬼没さではない。
ミカヅキのあり得ないほどの変貌だ。
「ごきげんようじゃねえよ、まず謝れ!」
と、少女の頭を片手で引っ掴む。それに無理やり頭を下げさせられて少女が。
「ミカちゃんが深刻そうだったので立ち聞きあそばしてしまいました!どうもごめんあそばせデスわ」
ほほほー、と上品そうに笑ってみせるそれは何処まで本気なのかは分からないものの。
ミカヅキの様子を心配して、というのはよく分かった。
「やめろ、無理にあそばすな」
「えーだってミカちゃんのお屋敷の女の人、みんなこんな話し方だしー」
真剣さが通じないかと思って、と訴えているその姿に、思わず吹き出していた。
この一連の大事件。
公人として美しく誇り高くあるはずの侯爵家の跡取りが、下町の雑多な少年らと交わった結果がこれだ。
嘆かわしい、という悲愴感が微塵もない。少なくともレアにとっては、二人のやりとりは痛快にすぎた。
(ああ、そうなんだわ)
ミカヅキが友人を紹介すると言って、以前、侯爵家に連れて来たうちの一人。そうだ、名前は確かウレイ。ここにはいないがもう一人の少女がミオ、先ほど目にした少年がヒロ。
それはレアにとっても、息子のように見守って来たミカヅキが初めて友人という存在を認めた事がただ嬉しく、忘れようはずもない名前だ。
レアの笑いが収まるまで二人が不可解そうにこちらを見ているのも、可笑しくてたまらない。
ただ一度、儀式の中で対面しただけでこんな風に言葉を交わすことなどもうないだろうと思っていたのに。
(そう、ミカヅキ様は普通の少年であってはならないから)
あってはならないと定められた運命の中で、それでもミカヅキ自らが欲し掴み取ってきたものを排除し葬り去ろうとするのは。
命運を定め、それを自在に操る残酷な神などではない。
人間だ。
「大丈夫」
だからこそ、言える。
「大丈夫ですわ。ミカヅキ様を心配して下さっている真剣さは十分、伝わりましてよ」
そう言えば、ウレイとミカヅキが顔を見合わせ。
ほらね、と笑ったウレイにミカヅキが調子にのるな、と渋面を返す。
そのとても自然な関係が、これから先もずっと続いていくだろう。ミカヅキがそれを願い、仲間がそれを望む限り、叶える力は彼らの手の中にある。
かつての自分たちがそうであったように。
(ミカヅキ様は普通の少年だわ)
何も変わらない。上流で生まれ上流で育ち、その責任を果たす為に普通の少年であってはならない、という事。
レアの教育係であったばあやの真意が今なら解る。
上流の人間である自分たちがミカヅキを惑わせ、その責任を放棄させることなどあってはならない。それはミカヅキの為にはならず、結果ミカヅキを苦しめる事にしかならない。
いずれ全ての領民の命運をその手一つで動かす地位にいる人間が、そこから降りる道など見つけてしまってはならないのだ。
(ばあや様はミカヅキ様を慈しんでおられるからだわ)
厳しい教育の中で、一切のわき目を振る事なくその頂点を目指して成長してきた彼の姿は、それを支える全ての人間たちの慈愛によってその場に立つ。
彼の立つその場が、僅かでも揺らいではならない。揺らがせてはならないという使命を追って、自分たちは頂点を支えている。
かつて、一人の公女を守りたいと思い、その力を手にするために遥か高みまで上り詰めた自分は今。
同じ様に、ミカヅキを守りたいと思い、それを実現させようとする幼い雛たちを見ている。
ミカヅキを自分たちと変わらない普通の少年だと認める存在だからこそ、自分たちと変わらない少年が到達するその高みが、恐れを抱く場所ではないと思えるだろう。
それは若さに他ならない。
これからどれほどの困難と苦境に挑むのか、具体的に考えることもできないそれも強みに変えていく若さ。
彼らが絶望し、諦めてしまうことのない様にレアが出来ることは一つ。
侯爵家の人間が出来ることは、昔から変わらずに一つ。
ミカヅキを普通の少年にしてはならない。その足元を揺らがせてはならない。
遥か高みに立つことのみを教え込まれてきたミカヅキなら、揺るがぬ地盤があるだけで、自分を追い求めてくる存在を引き上げることができるはずだ。
それを願う。
レネーゼ侯爵家の女性陣の守りは、母なる祈り。
我が子の未来だけを望み、厳しくある。
侯爵家の紋章を掲げた馬車は、王城から正当後継者を連れて戻る。
急ぎでない、とはいったが、ミカヅキはとりあえず家に戻る事になった。
屋敷に戻るレアを馬車の乗車まで見送りにきてくれた二人だったが、すぐに後から戻ります、というミカヅキに対してウレイがその背を押し込んだ。
「もー今ここに馬車があるんだから、そんなこと言わないで一緒に乗せてもらったらいーじゃない」
お堅い格式より大事なことってあるでしょー?という言葉に説得されたらしいミカヅキが、同乗させていただいてよろしいでしょうか、と聞いて来た時にはわずかな驚きがあったものの。
レアにとっても断る資格などない。主人はミカヅキだ。
ただ侯爵家へ戻る道中、ミカヅキと二人きりの馬車内で一度だけ口を開いた。
「格式より大事なものとは、何を指しておいでだったのかしら」
普段、ミカヅキが心を許している仲間と何を共有し、何処を目指しているのか。
おそらく部外者の自分には理解することもできないだろうけれど、それでも聞いてみたかったのだ。
「ああ」
と、ミカヅキが先ほどの言葉を考える様子を見せ、レアを見た。
「恐らくは、母上のことかと」
まあ、と内心で驚く。
そう言えば、直前に「ミソカ様が気にしている」ということを伝えたのだったか。
それを優先してミカヅキに戻るよう勧めた、と受け取るのは自然な事。
(初めて会見した時も、あの子たちはミソカに一切相手にされない状況だったんだわ)
そしてそれはこれからも変わらないだろう。
正当後継者の母親である彼女は、家に背くことはない。背けないのではない。背かぬ事で、ミカヅキを守っているのだ。
それは、ミカヅキにとっては厳しいものだろうと思える。
親と子としての二人の間に、レアは立ち入ることができない。
それは許されない。
(ミソカを悲しませることになる)
ミカヅキは普通の少年であってはならない、とレアがお叱りを受けた日の夜。
ミソカが泣いた。
「レアはあの子が普通でなければ幸せでないと思っているの?わたくしはそんな非情な世界にあなたを縛り付けてしまったの?わたくしが、ただ、あなたにそばにいて欲しいと思ってしまっただけで」
違う。そんなつもりじゃない。そんなつもりで言ったのじゃない、とどんなに言葉を尽くしてもミソカの涙は止まらなかった。
レアを哀れんで、それよりももっと自分を責めて、ミソカが泣いたのは学生の時とこの夜だけ。
レアは知らなかったのだ。上流社会がどんなものか。そこで育つということがどんなことなのか。多くを学び、この世界の住人になるため必死に努力を重ねても、生まれたままのレアの根底は決してミソカと同じにはなれない。
休む事なく後継者教育を詰め込まれ、大人たちの要求がどれほどの高みを指そうともそれを成し遂げ、数多の難関を次々と超えていくミカヅキの毎日を目にしていて、ふとミカヅキがとった些細な行動が、レアには愛らしく映った。その年齢にふさわしく、子供らしい単純な行動が、珍しくて可愛らしくて、つい言ってしまったのだ。
「ミカヅキ様も普通の男の子ですもの」と。
その言葉が禁忌だという感覚さえもない。知識はどれほど高められても、心からの支配にはなり得ない。感情は、心は、知識だけで導かれるものではないのだ、とあの時、レアは思い知らされた。
どれほど時を過ごしても、きっとこれだけはミソカと分かり合えない。
生まれと育ち。人を作るのは育ちと考えます、と侯爵家の礼儀の講師にも言われた事。
成人まで民間人として育った自分には、同じ期間を公人として育ったミソカには決して追いつけない部分がある、と自分を戒めてここまできたつもりだが。
「ミソカ様は、お立場上、ミカヅキ様のご友人をお認めになることができないだけですわ」
つい、そう、ミカヅキに進言する。
レアにとって唯一無二はミソカだ。ミソカがいればこそ、ミソカの子だからこそ、ミカヅキの事も我が子の様に思えるのだから。
二人の橋渡しになれれば、という、今まで封印してきた思いがここにきて溢れてしまった。
それは王城で見たミカヅキの変化があったがゆえに。
その思いをミカヅキが汲み取れるとは思っていない。今日から始めるのだ、という細やかな初手のつもりで。
それは分かります、とミカヅキが返し、この話はここで終わるはずだった。
だが、ミカヅキは続けた。
「侯爵家でも、ほかの家にも、彼らを認められるとは考えていませんし、私自身、認めてもらわなくてもいいと思っています」
その意志は、冷えた言葉とは裏腹に、確かな熱量があった。
今までのミカヅキとは明らかに違う、遥か高み以外の一切を必要ないと言い切る様なそれではない、と感じ取ってレアは息を飲む。
続けられた言葉は、さらに温もりをもたらす。
「ただ、母上にだけは認めてもらわなくては、と思っています」
そのために、こうして急ぎ館に戻るのだ、とでもいう様な意志。
「まあ、どうして」
驚くレアに向けられたミカヅキの視線は、親を慕う子のそれだった。
「彼らが、母親に心配かけさせるものじゃない、というので」
情、というものが人を動かす。
正しき道にも、過ちの道にも、柵はなく、ただ情という流れに沿って人は動かされて、その先にあるものを見る。
彼らは、ミカヅキは、自分たちの保身のために動いたのではなかった。
ただ母親を安心させるために、その存在を認めさせるという純粋な動機に触れて、レアはそれ以上何も言うことが出来ない。
ミソカとミカヅキの間にいて何をすることも許されず耐えるしかなかった日々は、とっくに終わっていたのだと知る。
友人に支えられて成長するミカヅキが、ミソカも、その間に立たされるレアの事も、その情に巻き込んで行く。
「そういうことでしたら」
ミカヅキは知らない事。
自分の母が、学生時代に民間人と交流を持とうとした事。そして交流の先に希望を見た事、夫を亡くし子のために上流社会でただ一人嵐に立ち向かうためにその手でレアにすがったこと。
レアが民間出である事さえも耳に入れられぬ環境で育った彼には、想像さえも出来ないだろう。
「陰ながら応援させていただきますわ」
レアとミソカの間にある決して埋められぬ溝。
それさえもミカヅキが埋めてくれるのではないかという希望をみる。
それほどに成長したミカヅキは、ありがとうございます、と微笑む。
二度目のそれは、今度こそ確実に受け止めることが出来た。
レアに向けられた親愛。
そして、同じく親愛をむけられるべき相手が待つ場所へ、馬車は走る。
(待っていてミソカ。私たちが身を置く世界は決して非情なんかじゃない)
それが分かった。レアにも、今日やっと。
分かり得る希望が、今、深い深い場所へ誘われた自分たちをしっかりと結びつけようとしている。
食後、食器の後始末を前に、ミカは葛藤していた。
野営の食事後は各自が後始末をするので問題はない。
航海中は船に立派な厨房が備わっていることもあって、ヒロとミオがそれなりに食事を作る。
ならば役割分担として、後始末はウイとミカに振り分けられるのが自然の成り行きで。
当然、その役割分担に異議があるわけでもない。
だがしかし、これはなかなか。
と、厨房で一人、やる気が一ミリグラムも湧いてこない状況に不動を貫いていると
「はーい、お待たせ―!これで全部だよ」
残りの食器を集めて運んできたウイがそれを流し場に積み重ねる。
フルコース並みの食事だったわけでもないのに、4人分ともなると結構な汚れだ。
それらを視界に入れるのも拒否反応があり、流し場から距離を取ったまま動かないでいるのをウイが不思議そうに振り返る。
「どうしたの?」
「いや、うん」
ここまで旅をしてきて、一番に自分の潔癖さが度々障害になることはもう嫌というほど解っていたつもりだったが、そしてそれを何とかねじ伏せ、その場を乗り切ってきたと思っていたが、…まだ完遂には程遠い現実に絶望感さえもある。
そんな逃げ口上を長々述べたが。
ウイには、虚勢をあっさり見抜かれるのが常。
「食器洗うの、やなんだね?」
「…うん」
端から見抜かれると解っている以上、虚勢を張ることもなく、ただ素直にそれを肯定すれば。
ウイは笑った。
「いーよいーよ、じゃあウイが洗うから、ミカちゃんは綺麗になったのを拭いて片づけたらいーよ」
いつもウイが言うことだ。出来る事は出来る人がやれば良い。ミカ自身も、そのことに反対はない。むしろその方が効率がいい。
だが、旅をしてきて仲間意識は高まり、運命共同体ともいえるような間柄での生活部分に直結する役割分担で、それは通用しないのではないかという考えが芽生えてきたのも事実だ。
「いや、待て。覚悟を決めるから」
もう少し時間をくれ、と言うミカをあっさり無視して、ウイは食器の汚れを大きな葉で拭って落とす、という作業を始めてしまった。
「そんなの、待ってたら夜が明けちゃうよ」
とからかい気味に言われては何も言えない。
確かに自分で感じている以上に拒否感があるのか、ウイを手伝おうという気にもならない。
そんなミカを、ウイが振り返る。
「ウイはねえ、ミカちゃんのそういうところは好きなんだけど」
自分の事は自分で出来るようでなければ、というのは幼いころから課されたものだ。
そして自分の意志で下町に出てきたからには、その風俗や習慣に合わせなければ、というのも当然の事なのだが。
ウイは、それを指摘する。
「本当なら、ウイとしてはそういうのは応援しないといけないのかもしれないんだけど」
今はちょっと違う気がするんだよね、と作業を続けながらミカに語り掛ける。
「出来ないことがある、ってすごく大事だと思うんだよ」
「大事?出来ない事がか?」
思わず聞き返したミカに、ウイは頷いた。
なんでも出来て、誰の助けもいらなくて、全部が完璧な人間にならなくちゃ、って構えてるのがミカちゃんだけど。
「そんな完全完璧人間だと、他人に感謝したり、他人を尊敬したりする心が育つ隙が無いよ?」
その言葉は衝撃すぎる。
「心?!心って、育てるものなのか?!ていうか育つのか?!」
「そうだよ、体と一緒だよ。体が育つみたいに、心だって育つんだよ」
「はあ?!どこにあるんだよ、心!!」
そんな…体が育つように、身長が伸びるように、体重が増えるように、「育つ」などと言われても納得できない。
育つってなんだ、育つって。
「うーん、と、心が難しかったら、精神でもいいんだけど」
「精神だって見えねえじゃねーか!」
「あーん、えーと、…じゃあ脳」
「…脳、…脳か、うん、脳はあるな」
医学図鑑で見た。うん、ある。あれが育つ。…育つか。まあそうだな、髪が伸びるんだからまあ脳もなんかそれなりに…何か変化があってそれを育つ、と言う、…かな?
と一人で深刻に悩んでいると、ウイが笑った。
「ミカちゃんは見えるものが大事だからねー」
それはからかう響きではなく、少し困っているようにも感じられたので、言い返すことはしなかった。
黙ってウイの話に耳を傾ければ、ウイは子供に言い聞かせるように話し出す。
「ウイが汚れた食器を洗って、ミカちゃんはそれが出来ないって思ったら、代わってくれてありがとう、で良いんだよ」
それだけの事。それが感謝する心を育てるという事。
「自分では叶えられない事を叶えた人がいたら、すごいね、って称えれば良いんだよ」
それだけの事。それが尊敬する心を育てるという事。
出来ない事を卑下する前に、叶わない事で卑屈になる前に、まずは他人がいる世界を受け止めて賛美する。
世界は自分一人の物ではなく、自分は世界の一部なのだから。
「そうやって心を育てていかないと、すっごくギスギスした生きにくい人になっちゃうよ」
心を育てることを疎かにすれば、人はいつか暴走してしまう。
人は、一人ではないのだ。
「ご飯たべたり、鍛えるために運動したり、賢くなるために勉強したり、そういうのと一緒。心だってちゃんと自分で育ててあげるんだよ」
人に関わって多くの感情に揺さぶられて弱くも強くもある心、その根底にあるものを育てるのは、身体で鍛錬することと何ら変わりはないのだとウイは言う。
それは教師が言う事と同じようにも思えた。
自分を律し、自分を制する事ができるようであれ、と教育されてきた事が。
「今、ミカちゃんに必要なのは、それなんだと思うよ」
足りなかったという事か?
「俺の心が育てられていないと?」
「ミカちゃんだけじゃないよ、ヒロもミオちゃんも同じだよ」
育てられているかどうかは重要じゃないの、とウイはミカに言い聞かせる。
「今ここで、四人が一緒にいることが重要なんだよ」
自分以外の誰かがいる。誰かが手助けをしてくれる。困ったときに助けられる。助けられた事実に、心は感謝を育てる。
繰り返し繰り返し他人に感謝できる心はやがて大きく育ち、何の衒いもなく素直に他人を助ける。
「それを四人でやるんだよ」
四人で、と言って、立てた指をぐるぐる回して見せた。
「例えば勝ち負けだってそう。勝つことばっかり頑張って、勝つためだけに全力出して、勝つことしか考えない、それって凄く簡単なんだよね」
本当に難しいのは、負けることに向き合う事だ。
勝つことに費やした時間と同じだけ負けることに向き合う時間を費やすべきなのに、勝者ばかりが正しい世界では、敗者になる事から逃げて勝つことに執着する。
勝てばいい。どんな事をしても勝てばいい。敗者となる自分と向き合うのが恐ろしいからどんな手を使ってでも勝たなくてはならない。そんな風に世界が歪む。
「たぶん、ヒロが勝負事を苦手としてるのは、そういう所なんだと思うよ」
だから得意なミカちゃんと苦手なヒロが上手にぐるぐる回したらいい、とウイが言う。
それこそがヒロとミカが一緒にいる意味であり、お互いから学ぶべきところがあるはずなのだ。
「二人でできないところはミオちゃんも一緒にしたらいいし、ウイも混ざるし」
そうあるからこそ、ここに4人が必要なのだ。
まずは言葉が届き、手を繋げる相手がいる世界から、すべてが始まる。
「そうしてたら、ミカちゃんにも見えてくるよ」
心。
「……」
そう言われても、素直に納得できない。
心が見えるはずもない、という概念はそう簡単には崩せそうもない。
だが、今のミカに必要だ、というウイの話は解った気がする。
4人でいる事の意味。
貴族社会の中では体験することのできない重要な世界に身をおいて、それを助けてくれる仲間がいる意味。
出来ない事をできるようにならなくては、と一人心を無にしてできるようになったところで、得るものなど皿洗いの克服だけ。
皿洗いが必要になる未来など、ミカの生涯には不要だ。そんなものよりも目の前にある大事なものを見ろ、とウイは言うのか。
人は、一人ではない。嫌でも他人がいる。それらすべてを排除して生きていく事が出来るはずもない。
だから。
心を育てろ、と、今、指し示されている。
「わかった」
「あ、わかった?ふう、良かったー」
わざとらしく、ふう、とか言うそれは、今度はからかいの意味合いが強くて、さて何と言い返してやろうか、と思ったが。
「ありがとう」
と言ってみた。
「どういたしまして!」
とウイは笑顔を見せる。
「じゃあ出っ来るウイがテキ・パキと洗ってしまいますのでえ、後はよろしくぅ♪」
調子はずれな歌を歌うように軽く請け負いミカに背中を向けて、本格的に皿洗いの体勢に入るウイを見て、ミカは傍の椅子に腰かけた。
従者がいれば任せてしまえば良い事。
それらを従者ではない仲間に任せてはいけないと考えていたことが、覆される。
従者ではない仲間だからこそ、任せて頼らなくてはならない時もある。それに感謝と、尊敬を忘れないで。
自分にできない事を成す人間が集まって創り上げているのが世界であるという事を忘れないで、生きていく。
それが、今のミカに必要な事だ、と言ったウイの背中に光を見た時。
「ああー…、だからなんでウイ一人にさせるかなー…」
と、厨房を除きに来たヒロがぼやくのが聞こえた。
それにウイが答える。
「ダイジョーブ!今、ウイのターンだから!」
「ええー?そうなの?」
「ウイ無双!」
「ミカのターンはいつくんの?」
「このあとすぐ!お見逃しなく!」
ああそういう事、とヒロが笑う。
世界はぐるぐる回されている。
船旅が始まったころのお話
先のSS「隣り合う景色(往復)」に上手く盛り込めなかった部分です
書きなぐりのメモ状態なのでさらっと流します
■本を借りる話(ミカ視点)
中庭でのちょっとしたティータイムを終えて、今一度、先ほどの部屋に戻る。
ミオに確認すれば、借りて帰りたい本がある、という事だったのでそれを取りに行くためだ。
何冊でも好きに持ち出せば良いと言えば、ミオは三冊選んで来きた。
刺繍の本と、パッチワークの本、機織り機の本である。
刺繍とパッチワークはともかく、機織り機の本に至っては言葉につまるミカである。
「おまえ、これ…機織り機の構造の図解書だぞ?」
けっして機織り機で可愛い布やら美しい図案やらを織るための指南書ではない。
一から構造を説明し、一台組み立てるまでの設計図のようなものである。
それを言えば、解ってます解ってます、と焦ったようにミオが頷く。
私じゃなくてヒロ君に、とミオは言った。
ヒロの村では機織り機を使えるのは有数の権力者に限られており、ヒロの家族は手織りで作業するのだという話を聞かされていたのをずっと気にかけていたらしい。
「この本があればヒロ君だったら、自分で作れるんじゃないかと思いまして」
「あいつに自作させる気かよ…」
どれだけヒロに対する期待値が高いんだか、と呆れて二の句が継げない。
「私の簡単な説明だとうまく伝わらなくて…」
という話で、少なくとも以前にそれなりの話はしたらしいことがわかる。
「でもこの本なら図解とか載ってるし…、これを見ながら説明した方が解りやすいかと」
まったく同じものは作れなくても、ヒロなら仕組みさえ理解すれば適当に簡易的な織り機を作れるのではないか、というミオの主張には唸るしかない。
「む、無理でしょうか」
「まあ、やってみれば良いんじゃねーか」
自分は、創作については苦手分野だ。
ミオがどんな構想を描き、それをヒロがどうやって形にするのか、ミカには想像もつかない。
自身の分とミオの三冊、持ち出す本の題名を書きつけ、それを司書へと手渡す。
かしこまりまして、とそれを受け取った司書は、一冊の本を差し出した。
先日、街でミオが買ってきた刺繍の本である。
「こちら、検めさせていただいた所、既存の書物と内容にさほど違いはございませんでしたので」
保管している幾つかの書物と比べ、足りない内容だけを書き写し終えたので、持ち帰って構わないという。
それを受け取ってミカはミオに渡した。
「という事だから、お前の物にすればいい」
「ええーっ」
「いらないなら廃棄に回す」
「いらなくないですっ欲しいですっ」
「ん」
世界の刺繍図案、と仰々しい題名ではあるが、ほんの50頁ほどの薄い本だ。
おそらく書庫にある専門書に比べれば大した情報量でもないだろうと思っていたから、これは予想通り。
はなからミオの物になるだろうと思っていた。
「あ、ありがとう、ございます」
なんだか複雑そうにしているミオに、司書が言葉を添える。
「こちらこそ、市井で流通する書物の提供を有難うございました。専門書以外の書籍までは中々手が回りませんので、大変、役立つものでありましたよ」
「あ、そう、だったんですか」
おそらく司書の仕事を理解していないミオには、その言葉で十分だったのだろう。
受け取って良いのかどうか迷っていたようなミオが、やっと笑顔になった。
■馬車の座席の話
馬車に乗り込んで、これから城下町の方へ戻る。
馬車が動き出す前に、ミカは離れて座ろうとするミオを隣に座らせた。
先ほどのティータイムで、執事に言われたことが頭をよぎったからだ。
こういった席に慣れない婦女子は対面ではなく、隣に。という彼の提案。
おそらく、今からそう遠くない先には数々の家との見合いを設けられる事が増えていくのだろう事は解りきっている。
その為に、作法の教師から教わった通りにふるまうばかりが正しいのではなく、女性に対する扱いを見直せ、と彼が良いたいのだろうと思う。
実際、ミオはいつになく良く喋った。
街では宿の食堂で、自分たちの船では船内で、二人きりになる事があっても大抵静かに、それぞれ自分の趣味に没頭して時間を過ごす事の方が自然だと思っていたから驚いた、というのもある。
ウイやヒロといる時の様に、よどみなく、自分の村の習慣やこだわり、父の様子、家族の時間、そういったミカの知りえない話を聞かせてくれ、それに軽く相槌を打つだけで、ミオの話はどんどん広がっていったほどだ。
だから、ミオは対面にいるより隣にいる方が気が楽なのかと思い、そうさせたのだが。
中庭にいる時と違い、がちがちに固まって馬車に揺られている。いや、揺られまいと踏ん張っているのか。
「座り心地悪いのか」
城下町から出てきたときは、なにやら夢中で窓の外ばかりを見ていたミオが、真正面を向いたまま硬直しているようで、思わず声をかければ。
いえ!そういうわけでは!と、力んだ言葉が返ってくる。
居心地悪いんだな、と理解した。
「向かいが良いなら、あっちに座ってろよ」
と、辻で行き交う他の馬車待ちのために停車した隙にそう言えば、大人しくミオは向かいの席に移動して。
来た時と同じように、斜め向かいへ座り、そしてそのまま横にずれて座った。すなわちミカの対面に。
何をしているのだろうか、ただ黙ってその行動を追っていると、ミカの対面からまた斜め向かいに移動して。
「やっぱりここが良いです」
と言う。
それでようやく全部の席の座り心地を確かめていたのか、と解ったが。
「隣だとすごく仲良し、って感じがします」
馬車がまた走り出し、その揺れに足を踏ん張って、そっちは、とミカの対面の席を指す。
「なんだか果し合いをするというか、向き合うっていうのが対戦する準備っていうか」
そんな感じで、と言って。
「ここだと、無関係、って感じです」
と、それぞれの席についての感想を言うミオに、思わず絶句する。
なんだそれは。
座る位置で、そんなに関係性を細やかに分析する意味はなんなんだ。
というか、そんなに感想を呼び起こされる事か?たかが、席の、位置ひとつで!
「……」
ミカとしては、ミオがどこに座ろうとどうでも良い。ミオがどこにいようと同じで、それに対していちいち何かを思う事など一切ない。
なのにミオのそれはどういうことだ。
なんという繊細な生き物か!!という感想に尽きる。
自分とはまるで違う世界にいる生き物に遭遇したような…、そんな驚きでしかなかったのだが、ミオは違うように受け取ったらしい。
「あ!違うんです!ミカさんと仲良しが嫌だとか、無関係が良いとか、そういう事ではなくてっ」
「え?あ、…うん」
「なんか、座席ってそういう意味があるのかなあ、って思って」
ねえよ!そんな意味なんか!!
と、言いたいところをぐっと我慢する。
「不思議ですよね」
「お前がな」
というのは我慢できなかった。
「ええ?」
「俺、別にどうでも良いし…」
「えっ、そうなんですか?どこでもいっしょですか」
「…うん」
そう返せば、ミオが困ったように目線を彷徨わせる。
うーむ、しまった。また微妙な空気に突入しようとしているのか、これは。と考え、なぜ微妙な空気になるのか気づいた。
ウイとヒロがいないからだ。あの二人の介入がないから、こうしてミオと二人の会話は度々、とん挫する。
それで思った事が、一つ。
ミカは口を開いた。
「これは、いつもの座席と同じ形だ」
「え」
いつもの。4人が揃って、テーブルに着くときの、決まった席の配置だ。
「ウイがそこで」
とミオの隣を指し、俺がここで、と最後に隣を指す。
「ヒロがそこだ」
その意味を少し考えていたようなミオが、あ!本当だ!と、声を上げる。
ミオの隣はいつもウイで、対面はヒロだ。そして、ミオと自分は斜め向かいにいるのが、当たり前の光景で。
「あ、そっか、だから私ここが」
落ち着く配置なのだろう。
生きの馬車でお互いに何も言わず当然のようにそう座ったのも、実はいつもの習慣なのではないか。
「解りました、中庭でお茶をいただいた時は二人席でした!二人席だとミカさんの隣が良いんですけど」
4人席だといつもの場所が良いみたいです、と言われて、ただ頷く。
ミカにとっては、二人席だろうと4人席だろうと、別にどこの席に対しても執着もなく何ら変わりはないので、まあミオはそうなんだろうな、と言う程度。
だがミオは、その答えにたどり着いて、すっきりしているようだったが。
「あっ、だからって、いつもミカさんと無関係がいいとか思ってるわけじゃなくてっ」
「うん、それは解ったから」
「あ、そうですか」
無関係が良いと思っているわけじゃない事くらいは解る。
ミカのために訪問着を用意し、ミカのために慣れない馬車に乗って、人見知り全開で挙動不審になりながらもミカの家で半日を過ごし、今こうして帰路についているのだ。
ただミオはそういう性分なだけだろうと思う。
人との距離に繊細すぎて、自分のことがおろそかになりがちな。
「だから、好きにすれば良い」
自分は何も構わない。ミオはミオらしく、自由でいてくれて構わないのだ。
「はい」
馬車は速度を落とし、他の馬車の流れに掴まったようだ。
帰路の軽い渋滞に合わせ、人の歩くよりは少し早い程度に、窓の景色が流れる。
何気なく二人、窓の外に目をやって、同時に気づいた。
「あ、ウイちゃんと」
ヒロと師匠の姿をミカも認めたが。
あろうことか、ミオが窓の外に向かって手を振り呼びかけようとする。
「ば、かっ!それは好きにするんじゃねえ!!」
「はいいぃっ?」
馬車の中から外の人間に声をかけるなどはしたない、という事を理解しないミオは、いきなりのミカの叱責に飛び上がった。
もったいないので作った小話はあますことなくうpする所存
天使御一行様
|
愁(ウレイ) |
天界から落っこちた、元ウォルロ村の守護天使。 |
魔法使い |
|
緋色(ヒイロ) |
身一つで放浪する、善人の皮を2枚かぶった金の亡者。 |
武闘家 |
 |
三日月 |
金持ちの道楽で、優雅に各地を放浪するおぼっちゃま。 |
戦士 |
|
美桜(ミオウ) |
冒険者とは最も遠い生態でありながら、無謀に放浪。 |
僧侶 |