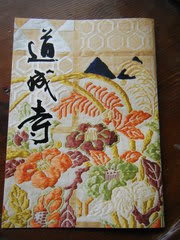今年も友枝さんの「観月能」を拝見しに、宮島に来ることができました。
友人2人は初めての「観月能」、もちろん広島も初めての土地。
過去4年間、広島市内を観光したことがなかったのですが、
友人たちの希望で宮島に入る前に「原爆ドーム」に行ってきました。
開演に間に合うかな?
時間が気になり、とうとう広島から宮島までタクシーを
使うことになりました・・・。
しかし何が幸いするかわかりません。おかげで宮島に到着した時、
大鳥居に夕日が差し込んでいて、友人のセミプロカメラマンは
こんなチャンス、めったに無いからと撮るべしと皆で写真撮影。

開演前、ここでもみんなで撮影!
友人たちのワクワク感、伝わってきました。
お誘いして大正解!

原爆ドームの建物、やはり近くでみると大迫力。
てっぺんに鷺がとまっていました。

翌日は紅葉谷まで歩き、ロープーウェイに乗り、
獅子岩の展望台に。
鹿ちゃん、こっち見てとみんなで撮影。

宮島は海も雲も特別に美しい。

5年目で初めて、町家通りを散策しました。
この角度から五重塔を見るのも初めて。
いろんな方と一緒に旅行すると、また新しい発見もあるものですね。
良かった、良かった^^
友人たちはお能も旅館の食事も最高だったと
大いに喜んでくれました。
帰りは広電に乗り、のんびりと1時間以上かけて広島市内へ。
電車内から観光できました。
原爆ドームには、また昨日の鷺がてっぺんにとまっていて驚きました!
実に楽しい旅行でした。
能「八島」のことはいずれ・・・。
どうぞ来年もまた来れますように・・・・。