昨年に続き高尾山を訪れた。高尾山のみを目的としたツアー登山等皆無に違いない。が、今回は、敢て「新ルート」と銘打ち、一味違う「高尾山」にした。四通八達した、高尾山で、何を今更「新ルート」等と思う向きもあるかも知れないが、歩いて歩けない所は少なくはない。
JR高尾駅北口に9時に集合、登山口の「日陰」に向かう。「日陰」の登山口は、「いろはの森」を抜けて、日影沢沿いに高尾山に至る道の一つ。平日だと言うのに、次から次へと、ザックを背負った人達が来る。ドピンカンの天気に、その日、思い立って来た人も多いに違いない。我々は、沢沿いに登る人達を尻目に、頂上から南西に延びる尾根に取りつく。いきなりの急登。「高尾山」と言う、イメージで来た方には、「ちょっと話が違うわ」と思ったかもしれない。人が歩く事を想定していない道は、倒木や深く積もった落ち葉、蜘蛛の巣等で歩き難い。30分程で林道に出る。一休みした後、20分程林道を東に辿り、尾根を乗り換える。そこからが、本格的な「急登」となる。アキレス腱が目一杯伸びる。巨木の自然林が続く。見上げれば、快晴の青空だが、見ている余裕はない。
綾線の先の木々の間に広がる空が、みるみる大きくなると、ようやくなだらかな道になり、ホッとする。間もなく、木漏れ日に溢れた小ピークでランチ。ここまで、誰にも会わなかった。30分程のランチを済ませ、乾いた落ち葉を踏みながら暫く歩くと、一般道に合流。ここからは、別世界が始まる。丁度、そこを歩いていた人達は、突然、来るはずのない所から現れた我々に、「何事!」と不審そうな目を向けた。ここからは、歩を進めるごとに人は増える。まさに、祭礼の夜店状態。そして、頂上。ジャーーン、そこは満員電車。頂上の広場が人で埋まっている。富士山の見える「展望台」には、カメラの砲列。我々もそれに加わったのは言うまでもない。
昨年、「Voyager Pratique Japon」と言う本がフランスのミシェランから発売された。日本版旅行ガイドである。4人の担当者が日本各地を2ヶ月ずつ、くまなく訪ね歩き、書き上げたと言う。そこで「高尾山」は三つ星に「輝いた」。三つ星は「必ず訪れるべき観光地」を意味する。三つ星の数に限れば東京の9つは京都の16に次いで、2位だ。そして、国内外の「観光客」が押し寄せた。昨年の秋、多い日で1日3万人。春夏秋冬、平均して1日7千人、年間250万人だそうだ。我々が訪ねた日、空はどこまでも青く、高く、房総半島までが見渡せる空気の澄んだ日、紅葉も真っ盛りなら「満員電車」もうなずける。下山のロープウェーの列は30分待ち。年間250万人訪れる山は、日本一だろう。それは、取りも直さず「世界一」でもある。
下山、我々は最初から、余り歩かれていない道を辿ると、決めていた。高尾山の北東の外れに「金比羅台」と言う場所がある。そこから「落合」へ、密やかな道が続いている。その道に一歩踏み入れると、誰もいない。このコントラストは一体何なのだろうか? そんな事を思いながら30分程歩くと下山口に着いた。そこから、高尾の駅まで、それ程、遠く感じる事はなかった。

















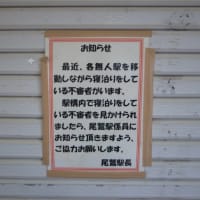




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます