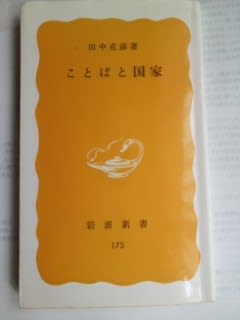
「ことばと国家」で著者が言わんとすることを私なりに整理してみました。
*の部分は著書からの引用と該当のページです。
第1章。「一つのことば」とは何か?
前半の部分では、ことばの数え方ということから、方言の上位にあるものとして、「国家とことば」に関係性を強く見ているが、後半部では、ソシュールの言語学、すなわち「ことばそれ自体」という考えを評価している。
*ある言葉が独立の言語であるのか、それともある言語に従属し、その下位単位をなす方言であるかという議論は、そのことばの話し手の置かれた政治状況と願望によって決定される。決して動植物の分類のように自然科学的客観主義によって一義的に決められるわけではない。世界の各地には、言語学の冷静な客観主義などは全く眼中に置かず、小さな小さな方言的なことばが、自分は独立の言語であるのだと主張することがある(P9)
*19世紀以来、言語と呼ばれることば、一定の資格付けを受けた言葉は、たいていが国家の言葉になっている。「言語を作るものは国家である。」あるいは、「国家がことばを作る」ということになる。(p21)
*19世紀以来の言語学は、それ自体としての言語を取り出すための努力の連続であった。
――言語学が科学になるためには、ことばに加えられている、あるいはことばに等級をつけて差別するあらゆる外的な権威を
はぎ取っていかなければならない。こうして、ことばから文字がはぎとられ、次には国家や民族が追放された。
しかし、もっとも重要な課題は話し手を追放することだった。(p22)
*ソシュールは、このような色あいを含まぬことばを取り出すために、「イデイオム(固有語)」という概念をつかい、それを話す色合いを含まぬ社会を「言語共同体」という概念を使うことで、―――ことばそのものを我々の前に置いてくれた。(p23~24)
第2章。「母語の発見」
ソシュールの2つの概念を踏まえて、ことばの本質として「まず、それは話されていなければならない。
―――文字は2次的に付け加わったものに過ぎない」とし、そこから「母親から学んだことば=母語」という考えにいたり、ローマ時代以来中世までのラテン語の支配からの脱出=母国語の成立の経緯を述べ、母語ゲルマン説、アイヌ語問題、在日韓国人の言語問題、イスラエルの言語問題などを示して、「ある言葉への愛着は国家への愛を伴う必要はない」としている。
*自分たちが話している言葉が「母語」であるという認識にたどり着くためには、母語でないことばがまずあって、それに対立する自分自身の言葉という自覚が生まれてこなければならなかった。その舞台は、書かれる
唯一の言葉すなわちラテン語と、決して書かれることのない日常の話しことばとの対立が現れえるローマ世界である。(p30)
*その話す個人とことばとの関係を示すには、どうしても母語がふさわしいのである。母語は、国家という言語外の政治権力からも、文化という民族のプレステージからも自由である。そして何よりも、国家、民族、言語、この3つの項目のつながりを断ち切って、言語を純粋に個人との関係でとらえる視点を提供してくれる。(p44)
第3章。「俗語が文法を所有する」
書かれる唯一の言葉であったラテン語は「文字の技術=文法」と呼ばれたが、1492年スペインのネブリーハが「カステリヤ語文法」を現し、「俗語の文法」を書いた。これは、「ラテン語支配からの脱出とスペインの諸国支配<アメリカ大陸、イベリア半島>の原動力」ともなった。
ただ、なぜ、ここで文法が自由な表現を妨げるとか、禁止の体系であるとか説明されているのかは、その後の展開とも結びつかず不明である。
*ラテン語は「文字の技術=文法」と呼ばれ、その習得には日常と切り離された特別の勉強を要するもので、その時間を手に入れることができるのは最上層の人たち=支配的地位を確実にし、安泰な状態を保つにはこの文字の技術が複雑であればあるほどそれだけ都合がいい。
(P54~55)
*ネブリーハは、国家の興亡と言語の興亡とがいかに深い関係にあるかを述べ、そのことを、「言語は常に帝国の伴侶である」と表現した。(p59)
第4章.「フランス革命と言語」
中世のフランスでは、南のオック語が優勢(吟遊詩人など)だったが、アルビ征服戦争などで北の勢力が強くなると同時に、北のオイル語が強くなり、それがラテン語と手を切ることにつながった。さらに、絶対王政は、フランス語の統一を推進したが、フランス革命も絶対王政の遺産を引き継いだという。
その理由が「法を平等に教授するためには、言語の平等が必要」というのは、面白い理屈だ。
*1539年にはヴィレール・コトレ勅令で、公的生活でのフランス語使用が決められ(p89)、1635年にはフランス語洗練のためのアカデミー・フランセーズが設立された。(P95)
*フランス革命直後の1793年には、「共和国のすべての子供はフランス語を話し、読み、書かねばならないと決定された。(P103)
第5章.「母語から国家語へ」
1539年の勅令において「母のことば」と呼ばれたフランス語は、フランス革命で「国家のことば」となったとされ、この章の前半では、「日本語」という言葉が、明治中期に日本――>日本国――>日本国語――
>日本語という経過で作られたのではないかとし、後半では「最後の授業」の舞台となったフランス・アルザス地方の言語事情を示して、国語と母語の問題を説明している。
明治期の国語や標準語の問題が明治中期以降であるのは、台湾や朝鮮という海外領土の問題が出てきたから
であろうか?
*明治27年、上田万年「国語と国家と」(p113)
*「最後の授業」は、まさに日本のアジア侵略のさなかに、「国語愛」の昂揚のための恰好の教材として用いられた。(p127)
第6章.「国語愛と外来語」
俗語が、文学を持ち、文法を持ち、法的保護を持ち、ついには言語ごとの国家という流れの中で、「特定の言語を母語とする民族は国家を求め、国家は固有の言語を求める」となり、さらには、俗語の讃美へとすすみ、その純粋性の追求に至るが、その道はフランスでは「純化主義」としてアカデミーによる「外来語の言い換え表」を作り、ドイツ語では「外来語でドイツ語を豊かにする」という言語的自由の道を選んだ。
翻って、わが日本語を見ると、あらゆる言葉に解放された「無国籍言語」という感じである。
第7章.「純粋言語と雑種言語」
前半では、純粋言語を追及するものとして、19世紀の生物学に導かれて作られたシュライヒアーの「印欧祖語理論」を紹介し、それが、ついには、ヒットラーの人種主義につながったとしている。そして、この考えに対抗したのが、ソビエト言語学(N・Ya・マル)の、「異なる言語間の接触<交叉>が、ことばの変化と発展の原動力となる」というものとしている。
後半では、雑種言語の問題から、ことばの社会的形態の問題すなわち、「隔絶言語」、「造成言語」について、ソ連、スイス、フランスの言語事情を示している。
この辺になると、著者は、マルを支持しているのか、スターリンを支持しているのかわからなくなる。
*「隔絶言語」=構造自体が他の言語から遠く離れている言語*「造成言語」=周辺言語からの距離を保つために絶えずその差異を強調することで造成しなければならない言語 (p162)
第8章.「国家を超えるイデイシュ語」
固有の言語を持たないユダヤ人は独立の民族とはみなしえないという考えに対し、カウツキ―はイデイシュ語の独立性を認め、その考えは、ソ連でも引き継がれた。
イデイシュ語がどのようにして作られ、それがユダヤ人社会の内外で差別的扱いを受けながらも、ユダヤ人の努力で国家抜きの「一大言語文化圏」となる過程が示されている。
ユダヤ人のなかでは、ヘブライ語を復活させる
運動とイデイシュ語に運命をかける取り組みとが続けられたが、多くのイデイッシュ語使用者がヒトラーによるガス室送りの犠牲となった。それは、「人種的純血主義の写しとしての、言語的純血主義の犠牲」であったとされている。
*1882年、E・B・イエフダは、「イスラエル復活協会」を作りもっぱらヘブライ語のみを話す同志を募った。現代ヘブライ語を2000年の眠りから呼び起こす最初の核で、わずか4家族だった。(P187)
*1897年、「ブンド」の結成。1905年、イデイシュ語を正式のユダヤ人語言語として宣言。
レーニンは、「ユダヤ人は、<民族に必要な>地域も共通の言語も持っていない」と反対(P189~191)
*1908年、チェルノヴィッツ「国際会議」――1つのユダヤ民族語
第9章.「ピジン語・クレオール語の挑戦」
アジアやアフリカに白人の植民地ができたとき
に、主人たる白人と現地人の間で崩れた言葉での意思疎通が行われた。それが「ピジン」語である。
やがて、ピジン語は、言語の違う現地人同士の意志疎通語となり、結婚し子供が生まれるとそれが母語(クレオーレ語)とな
る過程が説明されている。
やがて、それは、正書法を持ち、語彙の分析的明快さや文法の単純さで利用者が広がり、宣教新聞、政府広報紙、抒情詩集、短編小説、放送に使われるようになった。
*ピジン語の事例は、ラテン語から分立したロマンス語、アングロサクソン語とフランス語から生まれた英語も同じである(p205)
あとがき(著者が全体として言いたいこと)
言語は差異しか作らない。その差異を差別に転化させるのは、いつでも趣味の
*裁判官として君臨する作家、言語評論家、
*言語立法官としての文法家、漢字業者あるいは
*文法家精神に凝り固まった言語学者、
*さらに聞きかじりをおうむ返しに繰り返す一部のヒクツな新聞雑誌製作者等々
である。
(以上)
ブログ「笛吹朗人」(検索)
または http://blog.goo.ne.jp/tfujino_4
*の部分は著書からの引用と該当のページです。
第1章。「一つのことば」とは何か?
前半の部分では、ことばの数え方ということから、方言の上位にあるものとして、「国家とことば」に関係性を強く見ているが、後半部では、ソシュールの言語学、すなわち「ことばそれ自体」という考えを評価している。
*ある言葉が独立の言語であるのか、それともある言語に従属し、その下位単位をなす方言であるかという議論は、そのことばの話し手の置かれた政治状況と願望によって決定される。決して動植物の分類のように自然科学的客観主義によって一義的に決められるわけではない。世界の各地には、言語学の冷静な客観主義などは全く眼中に置かず、小さな小さな方言的なことばが、自分は独立の言語であるのだと主張することがある(P9)
*19世紀以来、言語と呼ばれることば、一定の資格付けを受けた言葉は、たいていが国家の言葉になっている。「言語を作るものは国家である。」あるいは、「国家がことばを作る」ということになる。(p21)
*19世紀以来の言語学は、それ自体としての言語を取り出すための努力の連続であった。
――言語学が科学になるためには、ことばに加えられている、あるいはことばに等級をつけて差別するあらゆる外的な権威を
はぎ取っていかなければならない。こうして、ことばから文字がはぎとられ、次には国家や民族が追放された。
しかし、もっとも重要な課題は話し手を追放することだった。(p22)
*ソシュールは、このような色あいを含まぬことばを取り出すために、「イデイオム(固有語)」という概念をつかい、それを話す色合いを含まぬ社会を「言語共同体」という概念を使うことで、―――ことばそのものを我々の前に置いてくれた。(p23~24)
第2章。「母語の発見」
ソシュールの2つの概念を踏まえて、ことばの本質として「まず、それは話されていなければならない。
―――文字は2次的に付け加わったものに過ぎない」とし、そこから「母親から学んだことば=母語」という考えにいたり、ローマ時代以来中世までのラテン語の支配からの脱出=母国語の成立の経緯を述べ、母語ゲルマン説、アイヌ語問題、在日韓国人の言語問題、イスラエルの言語問題などを示して、「ある言葉への愛着は国家への愛を伴う必要はない」としている。
*自分たちが話している言葉が「母語」であるという認識にたどり着くためには、母語でないことばがまずあって、それに対立する自分自身の言葉という自覚が生まれてこなければならなかった。その舞台は、書かれる
唯一の言葉すなわちラテン語と、決して書かれることのない日常の話しことばとの対立が現れえるローマ世界である。(p30)
*その話す個人とことばとの関係を示すには、どうしても母語がふさわしいのである。母語は、国家という言語外の政治権力からも、文化という民族のプレステージからも自由である。そして何よりも、国家、民族、言語、この3つの項目のつながりを断ち切って、言語を純粋に個人との関係でとらえる視点を提供してくれる。(p44)
第3章。「俗語が文法を所有する」
書かれる唯一の言葉であったラテン語は「文字の技術=文法」と呼ばれたが、1492年スペインのネブリーハが「カステリヤ語文法」を現し、「俗語の文法」を書いた。これは、「ラテン語支配からの脱出とスペインの諸国支配<アメリカ大陸、イベリア半島>の原動力」ともなった。
ただ、なぜ、ここで文法が自由な表現を妨げるとか、禁止の体系であるとか説明されているのかは、その後の展開とも結びつかず不明である。
*ラテン語は「文字の技術=文法」と呼ばれ、その習得には日常と切り離された特別の勉強を要するもので、その時間を手に入れることができるのは最上層の人たち=支配的地位を確実にし、安泰な状態を保つにはこの文字の技術が複雑であればあるほどそれだけ都合がいい。
(P54~55)
*ネブリーハは、国家の興亡と言語の興亡とがいかに深い関係にあるかを述べ、そのことを、「言語は常に帝国の伴侶である」と表現した。(p59)
第4章.「フランス革命と言語」
中世のフランスでは、南のオック語が優勢(吟遊詩人など)だったが、アルビ征服戦争などで北の勢力が強くなると同時に、北のオイル語が強くなり、それがラテン語と手を切ることにつながった。さらに、絶対王政は、フランス語の統一を推進したが、フランス革命も絶対王政の遺産を引き継いだという。
その理由が「法を平等に教授するためには、言語の平等が必要」というのは、面白い理屈だ。
*1539年にはヴィレール・コトレ勅令で、公的生活でのフランス語使用が決められ(p89)、1635年にはフランス語洗練のためのアカデミー・フランセーズが設立された。(P95)
*フランス革命直後の1793年には、「共和国のすべての子供はフランス語を話し、読み、書かねばならないと決定された。(P103)
第5章.「母語から国家語へ」
1539年の勅令において「母のことば」と呼ばれたフランス語は、フランス革命で「国家のことば」となったとされ、この章の前半では、「日本語」という言葉が、明治中期に日本――>日本国――>日本国語――
>日本語という経過で作られたのではないかとし、後半では「最後の授業」の舞台となったフランス・アルザス地方の言語事情を示して、国語と母語の問題を説明している。
明治期の国語や標準語の問題が明治中期以降であるのは、台湾や朝鮮という海外領土の問題が出てきたから
であろうか?
*明治27年、上田万年「国語と国家と」(p113)
*「最後の授業」は、まさに日本のアジア侵略のさなかに、「国語愛」の昂揚のための恰好の教材として用いられた。(p127)
第6章.「国語愛と外来語」
俗語が、文学を持ち、文法を持ち、法的保護を持ち、ついには言語ごとの国家という流れの中で、「特定の言語を母語とする民族は国家を求め、国家は固有の言語を求める」となり、さらには、俗語の讃美へとすすみ、その純粋性の追求に至るが、その道はフランスでは「純化主義」としてアカデミーによる「外来語の言い換え表」を作り、ドイツ語では「外来語でドイツ語を豊かにする」という言語的自由の道を選んだ。
翻って、わが日本語を見ると、あらゆる言葉に解放された「無国籍言語」という感じである。
第7章.「純粋言語と雑種言語」
前半では、純粋言語を追及するものとして、19世紀の生物学に導かれて作られたシュライヒアーの「印欧祖語理論」を紹介し、それが、ついには、ヒットラーの人種主義につながったとしている。そして、この考えに対抗したのが、ソビエト言語学(N・Ya・マル)の、「異なる言語間の接触<交叉>が、ことばの変化と発展の原動力となる」というものとしている。
後半では、雑種言語の問題から、ことばの社会的形態の問題すなわち、「隔絶言語」、「造成言語」について、ソ連、スイス、フランスの言語事情を示している。
この辺になると、著者は、マルを支持しているのか、スターリンを支持しているのかわからなくなる。
*「隔絶言語」=構造自体が他の言語から遠く離れている言語*「造成言語」=周辺言語からの距離を保つために絶えずその差異を強調することで造成しなければならない言語 (p162)
第8章.「国家を超えるイデイシュ語」
固有の言語を持たないユダヤ人は独立の民族とはみなしえないという考えに対し、カウツキ―はイデイシュ語の独立性を認め、その考えは、ソ連でも引き継がれた。
イデイシュ語がどのようにして作られ、それがユダヤ人社会の内外で差別的扱いを受けながらも、ユダヤ人の努力で国家抜きの「一大言語文化圏」となる過程が示されている。
ユダヤ人のなかでは、ヘブライ語を復活させる
運動とイデイシュ語に運命をかける取り組みとが続けられたが、多くのイデイッシュ語使用者がヒトラーによるガス室送りの犠牲となった。それは、「人種的純血主義の写しとしての、言語的純血主義の犠牲」であったとされている。
*1882年、E・B・イエフダは、「イスラエル復活協会」を作りもっぱらヘブライ語のみを話す同志を募った。現代ヘブライ語を2000年の眠りから呼び起こす最初の核で、わずか4家族だった。(P187)
*1897年、「ブンド」の結成。1905年、イデイシュ語を正式のユダヤ人語言語として宣言。
レーニンは、「ユダヤ人は、<民族に必要な>地域も共通の言語も持っていない」と反対(P189~191)
*1908年、チェルノヴィッツ「国際会議」――1つのユダヤ民族語
第9章.「ピジン語・クレオール語の挑戦」
アジアやアフリカに白人の植民地ができたとき
に、主人たる白人と現地人の間で崩れた言葉での意思疎通が行われた。それが「ピジン」語である。
やがて、ピジン語は、言語の違う現地人同士の意志疎通語となり、結婚し子供が生まれるとそれが母語(クレオーレ語)とな
る過程が説明されている。
やがて、それは、正書法を持ち、語彙の分析的明快さや文法の単純さで利用者が広がり、宣教新聞、政府広報紙、抒情詩集、短編小説、放送に使われるようになった。
*ピジン語の事例は、ラテン語から分立したロマンス語、アングロサクソン語とフランス語から生まれた英語も同じである(p205)
あとがき(著者が全体として言いたいこと)
言語は差異しか作らない。その差異を差別に転化させるのは、いつでも趣味の
*裁判官として君臨する作家、言語評論家、
*言語立法官としての文法家、漢字業者あるいは
*文法家精神に凝り固まった言語学者、
*さらに聞きかじりをおうむ返しに繰り返す一部のヒクツな新聞雑誌製作者等々
である。
(以上)
ブログ「笛吹朗人」(検索)
または http://blog.goo.ne.jp/tfujino_4













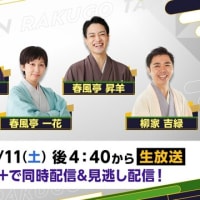






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます