アル中の話ばかり書いてもつまらないのでたまには違う話を。
表題の通り自分のバイクの紹介でもしようと思う。今まではブログで自分のバイクが特定されてしまうような投稿というのは、損になることはあれ得になることなど一つもないと思っていたのであまりしなかった。だってさ、たとえば近所のドラスタの駐輪場とかでバイク停めてるときにさ、
「あ、あのバイク知ってる、人骨とかいうバカのだぜ、ネットで晒されてるの見たことあるもん」
と後ろ指差されてたら嫌ではないか?
なのだが、最近はションボリ続きであまりバイクにも乗らないため、ま良っかという感じになった。
ということでぼくのVTR250のお披露目である。こういう時はとりあえずカスタムポイントを紹介するものと理解している。「カスタム」というのは要するに自分みたいなヘタレなんちゃってライダーにとっては「無用の改造」のことを指す。自称控えめなぼくの性格を反映し、人骨号は原則フルノーマルであり大したカスタムは無い。それでも若干の部品を換えているので、紹介しがてらしょぼいインプレでもしてみようと思う。
※ ※ ※

1.ヘッドライトとメーター
以前書いたとおりであるが、転倒でフロント近辺を大分壊してしまった。メーターカバーは経済的という理由でメッキされていない他車種(初期型?のホーネット)のものを流用し、ヘッドライトはレイブリッグ製のマルチリフレクターが入っている。
マルチリフレクターを入れると、ヘッドライトの照射範囲の輪郭がとってもクッキリとする。夜間の視界がどういう感じかというと、照らされているところはかなり明るく照らされ、いっぽう照射範囲の外は真っ暗…といったところである。なお日本国内が左側通行であるせいだと思うが、ヘッドライト正面より右側の照射距離が短く、左半分は長く、かつ左に行けば行くほど長くなる(文章だと分かりにくいですね…)。とにかく、まるでペンキで塗り分けたかのように照らされた輪郭がハッキリと見えるので、マルチリフクレクター交換後はその効果をはっきりと体感できるだろう。またカットが刻まれていないレンズのせいでフロントマスクの印象が違ってくるという効果も大きいといえる。
なお最近バルブを白っぽいのに変えた。なんてヤツだったか忘れたがPIAAというメーカーので「HIDを凌ぐホワイトブルー光」とかいう謳い文句であった気がする。しかしれっきとしたハロゲンバルブである。以前こういう白色系のバルブはDQNっぽくて好きじゃなかったのだが、
1.自家用車を買い換えた際にHIDが入り、素直にその明るさを認めた。
2.自分がDQNそのものであると自覚するに至った。
上記2点の理由から交換したものだ。
なお夜間走行時のヘッドライト光は確かに白っぽくなるが、HIDのそれとは全く別物であることを付記しておこう。
ホーネット用のメッキされていないメーターカバーであるが、始めのうちは梨地っぽい樹脂表面が中々ステキであったが、やがてバイクカバーと擦れて写真のようにテカテカになった。
※ ※ ※

2.ハンドルバー
同じく転倒で曲げたので交換。近所のラフローでHARDYとかいうメーカーのハンドルが純正より安かったので、これを採り入れた。購入の決め手になったのはその値段の他、クランプ部がちゃんとギザギザになっていたことがぼくのハートをグッと掴んで離さなかったためだ。
ぼくのVTRは3型モデルであり、1型2型と違ってかなりアップ&手前気味のハンドルが標準装備されていた。VTRに出会うまで4台も続けてセパハンに乗ってたことへの慣れもあって「低い方が良いよなあ~」と思っていたので、交換は丁度良い機会だと思うことにした。程よい寸法のものを選ぶべく、現物合わせをするために転倒で曲がったハンドルを店まで持っていったりしたっけ。しかし、取り付けた結果低さは理想的だったのものの、左右の幅が明らかに広すぎ。まあこれは好みの問題もあるだろうが、個人的には素直に1型か2型の純正を買えば良かったと後悔している。ちなみに以前乗っていた3型カタナのハンドルポジション(純正)がこんな感じだった気がした。「なんか懐かしいからこのままで良いや」と自分に言い聞かせ今日に至っている。
なお純正ハンドルバーには左右のスイッチボックスの位置を固定するための穴が開いていたが、当然社外品であるこのHARDYにはそんな穴は無い。よって交換するためには
1.ハンドルバーに穴を開ける
2.スイッチボックスの突起を削除する
の2択いずれかを容れるしかない。ぼくは当然2がラクだろうと短絡的に考え、まず左手のスイッチボックスの突起をニッパでえぐり取った。ところが右手つまりスロットル側のスイッチボックスの突起にニッパを立てると「がりっ」という鈍い反応。何度やっても同じ。と…取れない。何故か金属製の突起が埋め込まれてて外せないのだ。プライヤで引っこ抜こうとしたがダメだった。
そういうわけで、結局このHARDYのハンドルバーを取り付けるに当たっては右側だけハンドルに穴を開けるという非常に中途半端な段取りを踏むことになってしまった。しかも当時はまだ電動ドリルというものを所持していなかったため、わざわざ実家まで行き父親にドリルを借りて穴を開けた。何はともあれ、ハンドルという左右のバランスを司る大事なパーツを、こともあろうか左右非対称(アダルトに言えばアンシンメトリー)にしちまったことを悔やんだ記憶がある。一晩くらいだけど。
※ ※ ※

3.ダブルホーン
こいつは以前乗っていたVT250FEというバイクにプチカスタムとして取り付けて使用していたものを、この人骨号へ引き継いだものである。当時の話をしよう。
3型カタナに乗っていたことがあったということは上述の通りであるが、この3型カタナというバイクで初めて体験したのは何もリトラクタブルライトばかりではなかった。「なんでこのバイクは、クルマのクラクションみたいな立派な音が鳴るのさ?!」初めてダブルホーンの音を聞いて、自称ミュージシャンくずれであるぼくはその音色に魅せられたのだ。少なくとも当時ウチにあった軽自動車(初期型のワゴンR)の音色よりも立派だった。しかし当時はダブルホーンなんて知らなかったから理由が分からなかった。
やがてカタナからVT250FEに乗り換えた。またショボくなってしまったホーンの音に不満を持っていたところ、FEの兄弟車種といえるVT250Zに、VT250FEには装備されていない「ダブルホーン」なるものが採用されていることを知った。当時の雑誌かなんかを読み漁っていてたまたまこのVT250Zの特集が組まれているのを目にしたのだが、その記事の文中に「このダブルホーンが意外にクルマみたいな良い音をさせる~」みたいなくだりを見つけ、「これに違いない!」とひらめいた。ひらめいた瞬間、自分は天才に違いないと思ったほど、ぼくはバカである。
ヤフオクでバラ売りされていたVT250Zのダブルホーンを速攻落札し、12V電源に繋いでみたところ案の定クルマのクラクションっぽい良い音がした。小躍りしたのは言うまでも無い。あとはVT250FEに取り付けるだけである。

VT250Zのホーン(画像はヤフオクから勝手に拾いました、すいません)
FEとZは「ハーフカウル付き」か「ネイキッド」かどうかだけが違いの兄弟車だから(現在で言えばスーパーフォアとスーパーボルドールの関係にあたる)、当然ポン付けOKだとばかり思っていたのだが、そうは問屋が卸さなかった。このダブルホーン、本来はおそらくステーごとステムに取り付けるものと思われたが、VT250FEのステムにはこいつを取り付けるボルト穴も無ければスペース的にもカウルに干渉してムリだったのだ。
しかしその程度で諦めるわけはない。写真でご覧いただける通り、このホーンには装飾性を持たせるために豪華な(無駄な)パーツがふんだんに盛り込まれているのがお分かりいただけるだろう。だがぼくとしては見た目なんかはどうでも良く、むしろホーンなんて外部から見えなくて構わない。音が鳴りさえすれば良いわけだ。よってまずこいつら装飾パーツを全部撤去し、適当なステーを自作しつつ、試行錯誤の末に無事VT250FEに装着することができた。タテに2個重ねるような変則的な取り付けであったが…。
その後現在のVTR250人骨号を購入することになり、散々可愛がったVT250FEも手放した。どうも絶版車というのは絶版であることのデメリットばかりが目に付いてしまい、性に合わなかったためだ。だけど今でもVT250FEは最高のマシンだったと思っているし、愛着のあまり外装全部をはじめとした多くの関連パーツが手放せないでいる。その中の一つがこのホーンだった。VTRも最初の半年はそのままで乗っていたが、やがてなんとかこのホーンを活用できないものだろうかと考えたのは当然の成り行きであった。
VTR250はVT250Zと同様ネイキッドマシンであるからして、当初はこのハデハデの装飾ごと何とか移植できないかと考えたのだが、スペースの都合上やっぱり無理だった。しかし偶然なことに、上に貼り付けたVT250Zのホーンの写真の、一番下に映ってるステーのボルト幅(確か50mmくらいだった)が、VTR250のラジエター上部ステーの2本のボルトの幅と奇跡的に完全一致!するのだ。「ラジエター上部」という位置は、ホーンの設置場所としても申し分ないではないか。結果、銀メッキのお飾りホーンリングを撤去した上で2つのホーンの間隔を詰めてセットするだけで、フォークとの干渉も無くポン付けOKということが判明。配線はその辺で買ってきた2又があればOKである。若干ながらラジエターを遮る位置であることから冷却性能の劣化を懸念したのだが、結果として水温計を読む限りではこの位置にホーンが在っても無くても全く影響なく、問題なく真夏を乗り切った。おかげで今日も気持ち良くピッピとクラクションを慣らしながらVTRを運転することができるわけである。
ちなみにぼくのホーンの主な使い道は、狭くて見えない路地からの歩行者等の飛び出しに対する安全確認の、補助としてである。まあこれでも本来の使い方とは言えないが、いくらぼくがDQNでも煽ったりするのに使うわけではないので安心してほしい(誰が?)。
またこれも余談だけど、もしこのカスタムのマネをしたい人がいた場合のアドバイス。ぼくはVT250Zのを流用したわけだけど、多分VTZ250のもOKだしそちらのが入手しやすいと思います。
※ ※ ※

4.ツーリング用フック
見た目のまんまにつき説明省略。ナンバープレート取り付けボルトに置き換えるグラブ型のフックだ。樹脂製のリアフェンダーに荷重をかけるわけだから、最初はあまり使えなそうな気がしていたのだが、意外にも実際にはかなりのテンションに耐えることができる。荷かけフックとしての役目を十分果たしてくれるので、年に1度くらいの大荷物ツーリング時にはかなり便利です。
※ ※ ※

5.アジャスタブルブレーキレバー流用
一番最近装着したのがコレ。2006年の10月くらいに仕事サボって伊香保だか草津の方へツーリングに逝ったのだが、確かその前日に付けた。
2004年秋に単独でキャンプツーリングに出かけたが、キャンプ場で酔っ払ってバイクを倒した際にブレーキレバーがへにゃっと曲がり微妙に外側に反った状態となっていた。ぼくはレバーの位置は遠いほうが良いので(ブレーキレバーは中指・薬指・小指の3本がけ)それほど気にしていなかったが、とは言えあまりに遠すぎる気もしつつ(小指が届かなかったりする)、かれこれ2年が過ぎていたところであった。
実はこれ定番カスタムらしく、事前にネットで知識として覚えていたためトライしたものである。流用車種は例によってホーネットだかCB400SF(NC31の方)だったかうろ覚えだが、要するにホンダの方針としてはVTRには共用パーツ部分であっても極力安いものを選ぶ、ということなのだろう。おかげでこういったプチカスタムという奇妙な喜び?優越感?をもたらす効果があるのは、なにやら皮肉めいている。
ぼくは確か近所のライコだかナップスだかでホーネット用の純正を偶然見つけて買ってきたものだが、その時ホーネット用が2種類あって「アレそこまでは聞いていない、どっちなのだろう?」という2択に遭遇した。2種類両方が在庫していたので、果たして何が違うのか手にとって比べてみた。違うのはレバー部の長さだけのようである。ホーネットでいうところの古いモデル用が短く、最近のモデル用のが長いようだ。多分短いほうでアタリだろうと目星を付け購入したが、果たせるかなその通りであった。長いほうでも付くであろうが、どんな感じになるのかは読めない。案外違和感ないのかもしれない。
※ ※ ※
という感じがぼくのVTRの全てである。タイヤとかブレーキパッドとかオイルみたいな消耗品については今回何も書かなかった。今後はいま流行りの「リムテープ」でも貼ってみようかとミーハーな妄想をしている。購入時からあまり気に入らなかった点のひとつが「地味すぎる黒ホイール」だったので(それでもカラーオーダーする気は無かったのだが)、渡りに船的な流行だと思う。
ちなみにこのVTR人骨号の今後についてなのだが、実は果たさなくてはいけない野望がひとつある。
それがサーキットデビュー!バイクに乗るものとして一度はやってみないと気が済まないのだ。
しかしウデもヘタッピならばイベントに参加する人脈もないしツレもいないわけですから、中々踏み出せないのだ。
いっぽうサーキットを走るとなると反射的に連想するのが転倒である。これは確信なのだが、ぼくは多分サーキットに行ったら派手にコケる。そしてこれも確信だが、乗っていたバイクは大破するはずだ。いっぽうのぼくのカラダは、これまた根拠の無い確信なのだが、無傷なのだ。
これがぼくがこのVTR人骨号とサヨナラになってしまう唯一のシナリオなのだ。その日までぼくはコイツに乗り続けるであろう。乗り換えるのは、再起不能なまでに壊してしまったあとだ。
遠からずタイヤを交換しなければならないが、その際は潔くラジアルでも履いて(サーキットにはラジアルで臨む、これも決められたストーリーである)いよいよ終章に近づけて自らの尻に火を放ちたい今日この頃である。
とか言いながら何年も過ぎてしまいそうな気も、する…。
表題の通り自分のバイクの紹介でもしようと思う。今まではブログで自分のバイクが特定されてしまうような投稿というのは、損になることはあれ得になることなど一つもないと思っていたのであまりしなかった。だってさ、たとえば近所のドラスタの駐輪場とかでバイク停めてるときにさ、
「あ、あのバイク知ってる、人骨とかいうバカのだぜ、ネットで晒されてるの見たことあるもん」
と後ろ指差されてたら嫌ではないか?
なのだが、最近はションボリ続きであまりバイクにも乗らないため、ま良っかという感じになった。
ということでぼくのVTR250のお披露目である。こういう時はとりあえずカスタムポイントを紹介するものと理解している。「カスタム」というのは要するに自分みたいなヘタレなんちゃってライダーにとっては「無用の改造」のことを指す。自称控えめなぼくの性格を反映し、人骨号は原則フルノーマルであり大したカスタムは無い。それでも若干の部品を換えているので、紹介しがてらしょぼいインプレでもしてみようと思う。

1.ヘッドライトとメーター
以前書いたとおりであるが、転倒でフロント近辺を大分壊してしまった。メーターカバーは経済的という理由でメッキされていない他車種(初期型?のホーネット)のものを流用し、ヘッドライトはレイブリッグ製のマルチリフレクターが入っている。
マルチリフレクターを入れると、ヘッドライトの照射範囲の輪郭がとってもクッキリとする。夜間の視界がどういう感じかというと、照らされているところはかなり明るく照らされ、いっぽう照射範囲の外は真っ暗…といったところである。なお日本国内が左側通行であるせいだと思うが、ヘッドライト正面より右側の照射距離が短く、左半分は長く、かつ左に行けば行くほど長くなる(文章だと分かりにくいですね…)。とにかく、まるでペンキで塗り分けたかのように照らされた輪郭がハッキリと見えるので、マルチリフクレクター交換後はその効果をはっきりと体感できるだろう。またカットが刻まれていないレンズのせいでフロントマスクの印象が違ってくるという効果も大きいといえる。
なお最近バルブを白っぽいのに変えた。なんてヤツだったか忘れたがPIAAというメーカーので「HIDを凌ぐホワイトブルー光」とかいう謳い文句であった気がする。しかしれっきとしたハロゲンバルブである。以前こういう白色系のバルブはDQNっぽくて好きじゃなかったのだが、
1.自家用車を買い換えた際にHIDが入り、素直にその明るさを認めた。
2.自分がDQNそのものであると自覚するに至った。
上記2点の理由から交換したものだ。
なお夜間走行時のヘッドライト光は確かに白っぽくなるが、HIDのそれとは全く別物であることを付記しておこう。
ホーネット用のメッキされていないメーターカバーであるが、始めのうちは梨地っぽい樹脂表面が中々ステキであったが、やがてバイクカバーと擦れて写真のようにテカテカになった。

2.ハンドルバー
同じく転倒で曲げたので交換。近所のラフローでHARDYとかいうメーカーのハンドルが純正より安かったので、これを採り入れた。購入の決め手になったのはその値段の他、クランプ部がちゃんとギザギザになっていたことがぼくのハートをグッと掴んで離さなかったためだ。
ぼくのVTRは3型モデルであり、1型2型と違ってかなりアップ&手前気味のハンドルが標準装備されていた。VTRに出会うまで4台も続けてセパハンに乗ってたことへの慣れもあって「低い方が良いよなあ~」と思っていたので、交換は丁度良い機会だと思うことにした。程よい寸法のものを選ぶべく、現物合わせをするために転倒で曲がったハンドルを店まで持っていったりしたっけ。しかし、取り付けた結果低さは理想的だったのものの、左右の幅が明らかに広すぎ。まあこれは好みの問題もあるだろうが、個人的には素直に1型か2型の純正を買えば良かったと後悔している。ちなみに以前乗っていた3型カタナのハンドルポジション(純正)がこんな感じだった気がした。「なんか懐かしいからこのままで良いや」と自分に言い聞かせ今日に至っている。
なお純正ハンドルバーには左右のスイッチボックスの位置を固定するための穴が開いていたが、当然社外品であるこのHARDYにはそんな穴は無い。よって交換するためには
1.ハンドルバーに穴を開ける
2.スイッチボックスの突起を削除する
の2択いずれかを容れるしかない。ぼくは当然2がラクだろうと短絡的に考え、まず左手のスイッチボックスの突起をニッパでえぐり取った。ところが右手つまりスロットル側のスイッチボックスの突起にニッパを立てると「がりっ」という鈍い反応。何度やっても同じ。と…取れない。何故か金属製の突起が埋め込まれてて外せないのだ。プライヤで引っこ抜こうとしたがダメだった。
そういうわけで、結局このHARDYのハンドルバーを取り付けるに当たっては右側だけハンドルに穴を開けるという非常に中途半端な段取りを踏むことになってしまった。しかも当時はまだ電動ドリルというものを所持していなかったため、わざわざ実家まで行き父親にドリルを借りて穴を開けた。何はともあれ、ハンドルという左右のバランスを司る大事なパーツを、こともあろうか左右非対称(アダルトに言えばアンシンメトリー)にしちまったことを悔やんだ記憶がある。一晩くらいだけど。

3.ダブルホーン
こいつは以前乗っていたVT250FEというバイクにプチカスタムとして取り付けて使用していたものを、この人骨号へ引き継いだものである。当時の話をしよう。
3型カタナに乗っていたことがあったということは上述の通りであるが、この3型カタナというバイクで初めて体験したのは何もリトラクタブルライトばかりではなかった。「なんでこのバイクは、クルマのクラクションみたいな立派な音が鳴るのさ?!」初めてダブルホーンの音を聞いて、自称ミュージシャンくずれであるぼくはその音色に魅せられたのだ。少なくとも当時ウチにあった軽自動車(初期型のワゴンR)の音色よりも立派だった。しかし当時はダブルホーンなんて知らなかったから理由が分からなかった。
やがてカタナからVT250FEに乗り換えた。またショボくなってしまったホーンの音に不満を持っていたところ、FEの兄弟車種といえるVT250Zに、VT250FEには装備されていない「ダブルホーン」なるものが採用されていることを知った。当時の雑誌かなんかを読み漁っていてたまたまこのVT250Zの特集が組まれているのを目にしたのだが、その記事の文中に「このダブルホーンが意外にクルマみたいな良い音をさせる~」みたいなくだりを見つけ、「これに違いない!」とひらめいた。ひらめいた瞬間、自分は天才に違いないと思ったほど、ぼくはバカである。
ヤフオクでバラ売りされていたVT250Zのダブルホーンを速攻落札し、12V電源に繋いでみたところ案の定クルマのクラクションっぽい良い音がした。小躍りしたのは言うまでも無い。あとはVT250FEに取り付けるだけである。

VT250Zのホーン(画像はヤフオクから勝手に拾いました、すいません)
FEとZは「ハーフカウル付き」か「ネイキッド」かどうかだけが違いの兄弟車だから(現在で言えばスーパーフォアとスーパーボルドールの関係にあたる)、当然ポン付けOKだとばかり思っていたのだが、そうは問屋が卸さなかった。このダブルホーン、本来はおそらくステーごとステムに取り付けるものと思われたが、VT250FEのステムにはこいつを取り付けるボルト穴も無ければスペース的にもカウルに干渉してムリだったのだ。
しかしその程度で諦めるわけはない。写真でご覧いただける通り、このホーンには装飾性を持たせるために豪華な(無駄な)パーツがふんだんに盛り込まれているのがお分かりいただけるだろう。だがぼくとしては見た目なんかはどうでも良く、むしろホーンなんて外部から見えなくて構わない。音が鳴りさえすれば良いわけだ。よってまずこいつら装飾パーツを全部撤去し、適当なステーを自作しつつ、試行錯誤の末に無事VT250FEに装着することができた。タテに2個重ねるような変則的な取り付けであったが…。
その後現在のVTR250人骨号を購入することになり、散々可愛がったVT250FEも手放した。どうも絶版車というのは絶版であることのデメリットばかりが目に付いてしまい、性に合わなかったためだ。だけど今でもVT250FEは最高のマシンだったと思っているし、愛着のあまり外装全部をはじめとした多くの関連パーツが手放せないでいる。その中の一つがこのホーンだった。VTRも最初の半年はそのままで乗っていたが、やがてなんとかこのホーンを活用できないものだろうかと考えたのは当然の成り行きであった。
VTR250はVT250Zと同様ネイキッドマシンであるからして、当初はこのハデハデの装飾ごと何とか移植できないかと考えたのだが、スペースの都合上やっぱり無理だった。しかし偶然なことに、上に貼り付けたVT250Zのホーンの写真の、一番下に映ってるステーのボルト幅(確か50mmくらいだった)が、VTR250のラジエター上部ステーの2本のボルトの幅と奇跡的に完全一致!するのだ。「ラジエター上部」という位置は、ホーンの設置場所としても申し分ないではないか。結果、銀メッキのお飾りホーンリングを撤去した上で2つのホーンの間隔を詰めてセットするだけで、フォークとの干渉も無くポン付けOKということが判明。配線はその辺で買ってきた2又があればOKである。若干ながらラジエターを遮る位置であることから冷却性能の劣化を懸念したのだが、結果として水温計を読む限りではこの位置にホーンが在っても無くても全く影響なく、問題なく真夏を乗り切った。おかげで今日も気持ち良くピッピとクラクションを慣らしながらVTRを運転することができるわけである。
ちなみにぼくのホーンの主な使い道は、狭くて見えない路地からの歩行者等の飛び出しに対する安全確認の、補助としてである。まあこれでも本来の使い方とは言えないが、いくらぼくがDQNでも煽ったりするのに使うわけではないので安心してほしい(誰が?)。
またこれも余談だけど、もしこのカスタムのマネをしたい人がいた場合のアドバイス。ぼくはVT250Zのを流用したわけだけど、多分VTZ250のもOKだしそちらのが入手しやすいと思います。

4.ツーリング用フック
見た目のまんまにつき説明省略。ナンバープレート取り付けボルトに置き換えるグラブ型のフックだ。樹脂製のリアフェンダーに荷重をかけるわけだから、最初はあまり使えなそうな気がしていたのだが、意外にも実際にはかなりのテンションに耐えることができる。荷かけフックとしての役目を十分果たしてくれるので、年に1度くらいの大荷物ツーリング時にはかなり便利です。

5.アジャスタブルブレーキレバー流用
一番最近装着したのがコレ。2006年の10月くらいに仕事サボって伊香保だか草津の方へツーリングに逝ったのだが、確かその前日に付けた。
2004年秋に単独でキャンプツーリングに出かけたが、キャンプ場で酔っ払ってバイクを倒した際にブレーキレバーがへにゃっと曲がり微妙に外側に反った状態となっていた。ぼくはレバーの位置は遠いほうが良いので(ブレーキレバーは中指・薬指・小指の3本がけ)それほど気にしていなかったが、とは言えあまりに遠すぎる気もしつつ(小指が届かなかったりする)、かれこれ2年が過ぎていたところであった。
実はこれ定番カスタムらしく、事前にネットで知識として覚えていたためトライしたものである。流用車種は例によってホーネットだかCB400SF(NC31の方)だったかうろ覚えだが、要するにホンダの方針としてはVTRには共用パーツ部分であっても極力安いものを選ぶ、ということなのだろう。おかげでこういったプチカスタムという奇妙な喜び?優越感?をもたらす効果があるのは、なにやら皮肉めいている。
ぼくは確か近所のライコだかナップスだかでホーネット用の純正を偶然見つけて買ってきたものだが、その時ホーネット用が2種類あって「アレそこまでは聞いていない、どっちなのだろう?」という2択に遭遇した。2種類両方が在庫していたので、果たして何が違うのか手にとって比べてみた。違うのはレバー部の長さだけのようである。ホーネットでいうところの古いモデル用が短く、最近のモデル用のが長いようだ。多分短いほうでアタリだろうと目星を付け購入したが、果たせるかなその通りであった。長いほうでも付くであろうが、どんな感じになるのかは読めない。案外違和感ないのかもしれない。
という感じがぼくのVTRの全てである。タイヤとかブレーキパッドとかオイルみたいな消耗品については今回何も書かなかった。今後はいま流行りの「リムテープ」でも貼ってみようかとミーハーな妄想をしている。購入時からあまり気に入らなかった点のひとつが「地味すぎる黒ホイール」だったので(それでもカラーオーダーする気は無かったのだが)、渡りに船的な流行だと思う。
ちなみにこのVTR人骨号の今後についてなのだが、実は果たさなくてはいけない野望がひとつある。
それがサーキットデビュー!バイクに乗るものとして一度はやってみないと気が済まないのだ。
しかしウデもヘタッピならばイベントに参加する人脈もないしツレもいないわけですから、中々踏み出せないのだ。
いっぽうサーキットを走るとなると反射的に連想するのが転倒である。これは確信なのだが、ぼくは多分サーキットに行ったら派手にコケる。そしてこれも確信だが、乗っていたバイクは大破するはずだ。いっぽうのぼくのカラダは、これまた根拠の無い確信なのだが、無傷なのだ。
これがぼくがこのVTR人骨号とサヨナラになってしまう唯一のシナリオなのだ。その日までぼくはコイツに乗り続けるであろう。乗り換えるのは、再起不能なまでに壊してしまったあとだ。
遠からずタイヤを交換しなければならないが、その際は潔くラジアルでも履いて(サーキットにはラジアルで臨む、これも決められたストーリーである)いよいよ終章に近づけて自らの尻に火を放ちたい今日この頃である。
とか言いながら何年も過ぎてしまいそうな気も、する…。















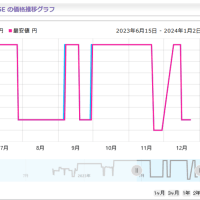




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます