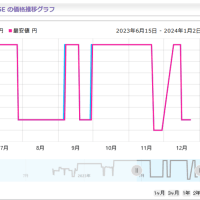ハイ。手術したくて仕方ない、何でも切っちゃう人骨クリニックだよ。
この一週間は、とりあえずキャブのインナーパーツの値段を調べてウキウキしていたりした。カワサキはホームページ上で純正パーツが検索ができるので、パーツリスト不要なのが良いところだ。弟のバリオスは98年式のB2型というらしい。
土日が来たのでバリオスⅡを診察した。では故障箇所を探ってみるか。1週間ぶりの始動である。今日はメチャクチャ寒いのだが、相変わらず「チョーク全開」「アクセル全閉」で一発始動。しばらくエンジンを暖める。
続いて雑巾を取り出し、濡らす。軽く絞っただけのびちょびちょの状態が良い。この濡れ雑巾を、エンジンに近いエキパイに軽く押し当てるのだ。エキパイは熱したフライパン状態なので、雑巾の水分がジューと蒸発する。エキパイは各気筒から4本出ているので、1本ずつこれを試す。寝ている気筒があるバヤイはジューと来ないか、他と比べて蒸発の具合が弱々しいのだ。不具合箇所を特定するひとつの手段である。
結果、アイドリング時も中域まで回した時も、全気筒とも均一に燃えている様子。この方法だけでは何とも言えないが、特定の気筒が寝ぼけているというわけではない予感がする。
続いてプラグの様子を見てみよう。プラグの焼け色からも、気筒ごとの様子がつかめる。
タンクを付けたままでは出来なそうなので、外装をバラしにかかる。まずはガソリンタンク。要領はVTRと同じだが、かなり外しやすい。

ガソリンコック
ガソリンコックからガソリンホースと負圧ホースを取り除く。いずれもクリップが太く、プライヤーでつまむ作業が楽だ。

燃料計のカプラー
このバリオスには燃料計が付いている。燃料計はタンク内にフロート(浮き)が入っていて、ガソリン残量によって変化するフロートの高さを電気の抵抗値だかなんかに変えて、メーターに送るというのが一般的な仕組みだったと思う。
とにかくタンクに繋がる燃料計の配線カプラーがここにあるのでこれを引き抜く。このカプラーも非常に取り外ししやすい形だ。自分はこの形のカプラーを初めて見た。
あとは、タンクキャップからのブローのホースと、もう1本何かのホースがぶらさがってスイングアームの所へ解放されているので、これをスイングアームから引っこ抜いて、タンクを持ち上げた時に引っかからないようにしておく。
タンクのボルトは後ろ側1本だけで、タンク前方はというと、フレームの突起へはめ込んであった。あとは後方へずらしながら持ち上げればタンクが外せる。

タンク除去
タンクを取り外すと、エアクリボックスとイグニッションコイルが目に飛び込む。エアクリボックスの上部をメインハーネスとキャブレターのオーバーフロウホースが血管のように這っていた。
だいぶ砂埃を被っているので、さっき使った雑巾でふき取る。
コイルの端子の抵抗値を測定。2個とも2.9Ω(単位不明)程度で安定。正常値は知らないけど、2個とも同じだから多分コイルは問題なしだろう。

ヘッドカバー付近
各部を目視。キャブレターに取り付けられている「K-TRIC」とか言うのはトルクス(の真ん中に、さらに穴が開いてるヤツ)のφ20だが、これ以外にキャブ撤去までに特殊工具は要らなさそうだ。
実はトルクスのソケットは1本しか持っていない。今回は奮発して電動ドライバー用のビットセットにて、各サイズを購入。当面他に使用する予定がないのだが、アダプタがあるのでレンチでも回せるから色々つぶしが利くだろう。
またシリンダヘッドカバーの後部にオイルにじみがあった。まあこの程度なら放って置いてもさしあたり問題は無いと思う。
プラグキャップを抜きに掛かる。車両にまたがった状態で左からみて1番2番3番4番の順だ。2つのイグニッションコイルは1番3番と、2番4番で共用。直列4気筒はみんなこうなっている(と思う)。
このプラグキャップ、とっても長くてむちゃくちゃ奥まで刺さっている。プラグがあるのは、ヘッドカバー上面から覗くと底の底。同じ直4でも空冷だとヘッドカバーがプラグを避けるように窪んでいて、ヘッドまで直接届くものなんだけど、水冷4気筒はみんなこうなんだろうか。以前水冷400カタナに乗っていたが、あの頃はメンテはしなかったので分からなかった。
プラグは全く見えない所にあるので手探りでプラグレンチを入れる。プラグレンチは専用設計されている車載品を使うのが一番便利なのでこれを使う。車載工具はみんなカスかと思うと、意外に使える専用設計品が混じっています。バリオスの車載プラグレンチは真ん中で2つに折れるタイプ。最初はユニバーサルジョイントなのかと思ったが、単純に2つに折れるだけ。プラグホールの奥行が深いので当然長いプラグレンチが要るのだけど、ヘッドカバー上部には長いレンチを入れる隙間が無いせいだと分かった。

2番狭すぎ
とにかく狭い。特に2番には手が届かない。まずラジエターの両サイドにあるジャマなシュラウドカバーを外す。ラジエター本体も、ファンモータのコネクタと水温計のコネクタを抜き、固定ネジを全部外して幾分動くようにし、それからステムに固定されていたホーンまで外して、何とか手をねじこんだ。多分ここまでやらなくても出来るのだと思うが、作業性確保のためには多少余計なところまでバラすことを厭わない。オーナーならばもっと手際良くやる方法を知っているんだと思うが、是非もなし。これでもなおラジエターのホースが非常にジャマである。
で、なんとか取り外したスパークプラグ。各気筒の状態を判断したいので、発掘後は元々の位置どおりに並べていく。遺跡から発掘される人骨もこのように丁寧に扱うのに違いあるまい。

摘出したスパークプラグ。右から1番、2番、3番、4番。
こ…これは…!被っている!4本中3本がビチョビチョである。
写真でお分かりいただけるだろうか。向かって右から数えて1番~4番の順に並んでいるのだが、3番がかろうじて茶色っぽいものの、残りの3つはビチョビチョだ。2ストロークのプラグはしばしばこんな感じになるが、4ストでこの濡れ具合はエロすぎる。
私が1発始動の上ちゃんと回してテストランした後でこの状態なので、「エンジンがかからない」と言っていた弟に限っては、どれだけビチョビチョにしていたことだろうか。
このプラグが不調の原因である可能性は大いにある。また、仮にプラグが原因ではなかったとしても、このプラグは再使用しない方が良いだろう。よって買い替え決定である。
ついでにエアクリーナーも外してみておく。現在総走行2万kmチョイだが、過去に自分が1回交換した記憶がある。汚れの程度は、黄色いエレメントが若干黒ずんでいる。交換時期には早いだろうが、こいつも一応換えておくべきか。

エアクリーナーエレメント
ひとまずVTRで用品店へ走り、プラグを4本購入する。全て差替えたあと、試運転する。
暖機終了後、エンジンは軽く吹けるし、ぼこつきもなし。アイドリングも安定したまんま。
もしかして終了?
土曜のヨル、弟を呼び出し試運転をしてもらう。自分よりも、オーナーである弟本人に判断してもらうのが良い。
弟「絶好調!直ったよ!」
骨「(もう終了かよ~!!)念のためキャブもばらしとかない?」
弟「いや、いい」
プラグ交換だけで終了してしまった。自分としては、工具まで買ってかなり張り切っていたのだが何ともお粗末な結末であった。
おそらくこうなった原因は、エンジンのかけ方が悪かったことにあると思う。操作ミスのせいでエンジンを始動できず、アクセルオープンでむやみにセルばかり回して生ガスを溜め込んだのに相違あるまい。
「チョークを引いたら、アクセルには触らずそのままセルボタンを押すように」
と、単なる基本操作法を説明する。普段は真冬でも全くチョークを使わず、アクセルのみで始動していたという。仮にチョークを引いてもアクセルは常に開だったそうだ。
また、「暖機運転」のつもりで始動直後は敢えて回し気味にして走っていたらしい。おまえ中学生かよ~と情けなくなる。
このヨルは、直ったかどうかの確認を取るために弟を呼んだだけで、引渡しの準備が出来ていなかった。外装が全部外れているし、エアクリも交換しておきたい。
翌日それらの作業を終え、引渡し終了。部品代5,000円だけ頂く。
今回は始動の仕方を指導して終了であった。
この一週間は、とりあえずキャブのインナーパーツの値段を調べてウキウキしていたりした。カワサキはホームページ上で純正パーツが検索ができるので、パーツリスト不要なのが良いところだ。弟のバリオスは98年式のB2型というらしい。
土日が来たのでバリオスⅡを診察した。では故障箇所を探ってみるか。1週間ぶりの始動である。今日はメチャクチャ寒いのだが、相変わらず「チョーク全開」「アクセル全閉」で一発始動。しばらくエンジンを暖める。
続いて雑巾を取り出し、濡らす。軽く絞っただけのびちょびちょの状態が良い。この濡れ雑巾を、エンジンに近いエキパイに軽く押し当てるのだ。エキパイは熱したフライパン状態なので、雑巾の水分がジューと蒸発する。エキパイは各気筒から4本出ているので、1本ずつこれを試す。寝ている気筒があるバヤイはジューと来ないか、他と比べて蒸発の具合が弱々しいのだ。不具合箇所を特定するひとつの手段である。
結果、アイドリング時も中域まで回した時も、全気筒とも均一に燃えている様子。この方法だけでは何とも言えないが、特定の気筒が寝ぼけているというわけではない予感がする。
続いてプラグの様子を見てみよう。プラグの焼け色からも、気筒ごとの様子がつかめる。
タンクを付けたままでは出来なそうなので、外装をバラしにかかる。まずはガソリンタンク。要領はVTRと同じだが、かなり外しやすい。

ガソリンコック
ガソリンコックからガソリンホースと負圧ホースを取り除く。いずれもクリップが太く、プライヤーでつまむ作業が楽だ。

燃料計のカプラー
このバリオスには燃料計が付いている。燃料計はタンク内にフロート(浮き)が入っていて、ガソリン残量によって変化するフロートの高さを電気の抵抗値だかなんかに変えて、メーターに送るというのが一般的な仕組みだったと思う。
とにかくタンクに繋がる燃料計の配線カプラーがここにあるのでこれを引き抜く。このカプラーも非常に取り外ししやすい形だ。自分はこの形のカプラーを初めて見た。
あとは、タンクキャップからのブローのホースと、もう1本何かのホースがぶらさがってスイングアームの所へ解放されているので、これをスイングアームから引っこ抜いて、タンクを持ち上げた時に引っかからないようにしておく。
タンクのボルトは後ろ側1本だけで、タンク前方はというと、フレームの突起へはめ込んであった。あとは後方へずらしながら持ち上げればタンクが外せる。

タンク除去
タンクを取り外すと、エアクリボックスとイグニッションコイルが目に飛び込む。エアクリボックスの上部をメインハーネスとキャブレターのオーバーフロウホースが血管のように這っていた。
だいぶ砂埃を被っているので、さっき使った雑巾でふき取る。
コイルの端子の抵抗値を測定。2個とも2.9Ω(単位不明)程度で安定。正常値は知らないけど、2個とも同じだから多分コイルは問題なしだろう。

ヘッドカバー付近
各部を目視。キャブレターに取り付けられている「K-TRIC」とか言うのはトルクス(の真ん中に、さらに穴が開いてるヤツ)のφ20だが、これ以外にキャブ撤去までに特殊工具は要らなさそうだ。
実はトルクスのソケットは1本しか持っていない。今回は奮発して電動ドライバー用のビットセットにて、各サイズを購入。当面他に使用する予定がないのだが、アダプタがあるのでレンチでも回せるから色々つぶしが利くだろう。
またシリンダヘッドカバーの後部にオイルにじみがあった。まあこの程度なら放って置いてもさしあたり問題は無いと思う。
プラグキャップを抜きに掛かる。車両にまたがった状態で左からみて1番2番3番4番の順だ。2つのイグニッションコイルは1番3番と、2番4番で共用。直列4気筒はみんなこうなっている(と思う)。
このプラグキャップ、とっても長くてむちゃくちゃ奥まで刺さっている。プラグがあるのは、ヘッドカバー上面から覗くと底の底。同じ直4でも空冷だとヘッドカバーがプラグを避けるように窪んでいて、ヘッドまで直接届くものなんだけど、水冷4気筒はみんなこうなんだろうか。以前水冷400カタナに乗っていたが、あの頃はメンテはしなかったので分からなかった。
プラグは全く見えない所にあるので手探りでプラグレンチを入れる。プラグレンチは専用設計されている車載品を使うのが一番便利なのでこれを使う。車載工具はみんなカスかと思うと、意外に使える専用設計品が混じっています。バリオスの車載プラグレンチは真ん中で2つに折れるタイプ。最初はユニバーサルジョイントなのかと思ったが、単純に2つに折れるだけ。プラグホールの奥行が深いので当然長いプラグレンチが要るのだけど、ヘッドカバー上部には長いレンチを入れる隙間が無いせいだと分かった。

2番狭すぎ
とにかく狭い。特に2番には手が届かない。まずラジエターの両サイドにあるジャマなシュラウドカバーを外す。ラジエター本体も、ファンモータのコネクタと水温計のコネクタを抜き、固定ネジを全部外して幾分動くようにし、それからステムに固定されていたホーンまで外して、何とか手をねじこんだ。多分ここまでやらなくても出来るのだと思うが、作業性確保のためには多少余計なところまでバラすことを厭わない。オーナーならばもっと手際良くやる方法を知っているんだと思うが、是非もなし。これでもなおラジエターのホースが非常にジャマである。
で、なんとか取り外したスパークプラグ。各気筒の状態を判断したいので、発掘後は元々の位置どおりに並べていく。遺跡から発掘される人骨もこのように丁寧に扱うのに違いあるまい。

摘出したスパークプラグ。右から1番、2番、3番、4番。
こ…これは…!被っている!4本中3本がビチョビチョである。
写真でお分かりいただけるだろうか。向かって右から数えて1番~4番の順に並んでいるのだが、3番がかろうじて茶色っぽいものの、残りの3つはビチョビチョだ。2ストロークのプラグはしばしばこんな感じになるが、4ストでこの濡れ具合はエロすぎる。
私が1発始動の上ちゃんと回してテストランした後でこの状態なので、「エンジンがかからない」と言っていた弟に限っては、どれだけビチョビチョにしていたことだろうか。
このプラグが不調の原因である可能性は大いにある。また、仮にプラグが原因ではなかったとしても、このプラグは再使用しない方が良いだろう。よって買い替え決定である。
ついでにエアクリーナーも外してみておく。現在総走行2万kmチョイだが、過去に自分が1回交換した記憶がある。汚れの程度は、黄色いエレメントが若干黒ずんでいる。交換時期には早いだろうが、こいつも一応換えておくべきか。

エアクリーナーエレメント
ひとまずVTRで用品店へ走り、プラグを4本購入する。全て差替えたあと、試運転する。
暖機終了後、エンジンは軽く吹けるし、ぼこつきもなし。アイドリングも安定したまんま。
もしかして終了?
土曜のヨル、弟を呼び出し試運転をしてもらう。自分よりも、オーナーである弟本人に判断してもらうのが良い。
弟「絶好調!直ったよ!」
骨「(もう終了かよ~!!)念のためキャブもばらしとかない?」
弟「いや、いい」
プラグ交換だけで終了してしまった。自分としては、工具まで買ってかなり張り切っていたのだが何ともお粗末な結末であった。
おそらくこうなった原因は、エンジンのかけ方が悪かったことにあると思う。操作ミスのせいでエンジンを始動できず、アクセルオープンでむやみにセルばかり回して生ガスを溜め込んだのに相違あるまい。
「チョークを引いたら、アクセルには触らずそのままセルボタンを押すように」
と、単なる基本操作法を説明する。普段は真冬でも全くチョークを使わず、アクセルのみで始動していたという。仮にチョークを引いてもアクセルは常に開だったそうだ。
また、「暖機運転」のつもりで始動直後は敢えて回し気味にして走っていたらしい。おまえ中学生かよ~と情けなくなる。
このヨルは、直ったかどうかの確認を取るために弟を呼んだだけで、引渡しの準備が出来ていなかった。外装が全部外れているし、エアクリも交換しておきたい。
翌日それらの作業を終え、引渡し終了。部品代5,000円だけ頂く。
今回は始動の仕方を指導して終了であった。