緒戦の大勝、そして暗転 ほか)
第2章 日米開戦決断と記憶―1941年(昭和16年)(国力と精神力
「泥沼」からの脱出めざして南進へ ほか)
第3章 日中戦争長期化の誤算―1937年(昭和12年)(長江をさかのぼって
自衛と膺懲 ほか)
第4章 満州事変暴走の原点―1933年(昭和8年)(「起こった」と「起こされた」
「満蒙」の誕生 ほか)

「あの戦争は何だったのか 大人のための歴史教科書」保阪正康
読み返し。
P105
私は、この戦争が決定的に愚かだったと思う、大きな一つの理由がある。それは、「この戦争はいつ終わりにするのか」をまるで考えていなかったことだ。
P228
“勝ち戦”に乗じて日本の領土が欲しかったスターリンは、トルーマンに「我々は関東軍を掌握し、北海道方面に侵攻している。ソ連の制圧地域として北海道を認めて欲しい」と要求していた。しかし、トルーマンは、決してそれを認めなかった。スターリンはもう一度、「北海道が欲しい」と重ねて訴えるが、やはり断られてしまう。ならばと、「領土の代わりに、関東軍の兵を労働力としてもらう」と勝手に決めてしまった節があるのだ。
こうして「シベリア抑留」が行われた。
P234
「戦争が終わった日」は、8月15日ではない。ミズーリ号で「降伏文書」に正式調印した9月2日がそうである。いってみれば8月15日は、単に日本が「まーけた!」といっただけにすぎない日なのだ。
世界の教科書でも、みんな第2次世界大戦が終了したのは、9月2日と書かれている。
【ネット上の紹介】
戦後六十年の間、太平洋戦争は様々に語られ、記されてきた。だが、本当にその全体像を明確に捉えたものがあったといえるだろうか―。旧日本軍の構造から説き起こし、どうして戦争を始めなければならなかったのか、引き起こした“真の黒幕”とは誰だったのか、なぜ無謀な戦いを続けざるをえなかったのか、その実態を炙り出す。単純な善悪二元論を排し、「あの戦争」を歴史の中に位置づける唯一無二の試み。
[目次]
第1章 旧日本軍のメカニズム(職業軍人への道
一般兵を募る「徴兵制」の仕組み ほか)
第2章 開戦に至るまでのターニングポイント(発言せざる天皇が怒った「二・二六事件」
坂を転げ落ちるように―「真珠湾」に至るまで)
第3章 快進撃から泥沼へ(「この戦争はなぜ続けるのか」―二つの決定的敗戦
曖昧な“真ん中”、昭和十八年)
第4章 敗戦へ―「負け方」の研究(もはやレールに乗って走るだけ
そして天皇が動いた)
第5章 八月十五日は「終戦記念日」ではない―戦後の日本

「戦後和解」小菅信子
2006年 第27回 石橋湛山賞受賞作品。
P81・・・東京裁判主席検察官・ジョセフ・キーナンの言葉
侵略謀議のかどで裁判にかけられるものがあるとすれば、それは日本の裕仁天皇ではなく、スターリン・ソ連首相である。
P180
サンフランシスコ講和には、参加に強い意欲を示した韓国政府も、対日参戦国ではないとして招請されなかった。
P189
1985年の中曽根首相の(靖国神社)公式参拝は、終戦から40年であり、時を同じくして「抗日戦争40周年」を迎え国内でさまざまなイベントを展開しつつあった中国を刺激した。(中略)
今日に続く日中間の靖国神社参拝問題の端緒はこのときの対立に遡ることができる。
P209
大躍進や文化大革命のような社会主義国家の失敗が政権のいわば正当性を喪失させていったのに対して、抗日戦争の勝利の記憶は、政権の正当性の、おそらくは唯一にして最大の拠り所となっている。
【ネット上の紹介】
第二次世界大戦が終わり六〇年が過ぎ、戦争を直接記憶している人も少なくなった。だがいまだに戦争についての歴史認識をめぐり、近隣諸国との軋轢は絶えない。日本はいつ「戦争」の呪縛から解き放たれるのか―。一九九〇年代後半まで、日本軍による捕虜処遇問題で悪化していた英国との関係はなぜ好転し、ここにきて中国との関係はなぜ悪化したのか。講和の歴史を辿り、日英・日中の関係を比較し、和解の可能性を探る。
序章 「戦後和解」とは何か
第1章 忘却から戦争犯罪裁判へ(神の前での講和
揺らぐ忘却―制裁の登場
勝者が敗者を裁く時代へ)
第2章 日本とドイツの異なる戦後(ドイツの選択
不完全だった東京裁判
曖昧化する日本の戦争責任)
第3章 英国との関係修復(日英関係に刺さった棘
さまざまな和解のかたち)
終章 日中和解の可能性

「池上彰の世界から見る平成史」
朝鮮戦争 1950年6月-1953年7月休戦
ベトナム戦争 1960年-1975年
アフガニスタン侵攻 1979年-1989年
P46
1991年12月、ついにソ連が崩壊します。(中略)
西側諸国は「資本主義の勝利」だと思いました。(中略)
西側諸国は、自分たちの国が、ソ連の仲間になったら困ると思えばこそ、政府は福祉を充実させ、労働者を大切にしてきました。
しかし、社会主義が失敗し、もう敵がいなくなったと思えばやりたい放題です。(中略)
東側の安い労働力を使って、稼ぎたいだけ稼ぐ。こうして自国の中間層が消滅し、格差が広がっていきます。
社会主義の崩壊は、資本主義の暴走を生んだのです。
P62
米ソの冷戦は1945年のヤルタ会談から始まり、1989年のマルタ会談をもって終結しました。よく「ヤルタからマルタへ」といわれます。
P74
中東はアラブ人が圧倒的に多いのですが、イランはペルシャ人の国。犬猿の仲です。
イラクにしてみれば、アラブ人を代表してイランに戦争をふっかけてやったのに、クェートは知らん顔。イラクとクェートの国境地帯の油田は地下で繋がっているので、「自国の資源が盗まれている」というわけです。(中略)
イラクは撤退しなかったので、アメリカ軍を中心として多国籍軍はイラクを攻撃します。これが「湾岸戦争」です。
P123
北朝鮮では金日成(キムイルソン)→金正日(キムジョンイル)→金正恩(キムジョンウン)と3代世襲が続いています。社会主義国では常識的にありえません。北朝鮮をつくったのはソ連ですが、ソ連ではレーニンやスターリンの息子が指導者になっていません。
P131
郵政民営化はアメリカの要望でもありました。当時、郵便貯金と簡易保険に入っているお金が全部で350兆円。民営化が実現すれば、このお金が民間に流れます。(後略)(アメリカの郵政事業は国営です)
【ネット上の紹介】
平成時代が31年で終わりを迎える。平成のスタートは、東西冷戦終結とも重なり、新たな世界と歩みを同じくした時代だ。日本の大きな分岐点となった激動の平成時代を世界との関わり、51のニュースから読み解く、知らないと恥をかく世界の大問題・特別版。
プロローグ 東西冷戦終結と平成の始まり―東西冷戦の歴史と世界の関係を理解しておこう(「平成」じゃない平成がスタート
すべてはスターリンの“裏切り”から始まった
ベルリンの壁は、恥ずかしい壁?
冷戦への決定打「トルーマン・ドクトリン」 ほか)
世界から見る平成史(昭和天皇崩御の裏で…
いまの選挙制度につながる事件
消費税は平成の幕開けとともに
劉暁波と天安門事件 ほか)

「それでも、日本人は「戦争」を選んだ」加藤陽子
以前読んだ本の再読。
調べたら2014年に読んでいる。
もう10年近く経つのか。
(前回は単行本、今回は文庫本で読んだ・・・ページ番号は新潮文庫版に変更した)
内容は、序章+5章ある。
序章 日本近現代史を考える
1章 日清戦争―「侵略・被侵略」では見えてこないもの
2章 日露戦争―朝鮮か満州か、それが問題
3章 第一次世界大戦―日本が抱いた主観的な挫折
4章 満州事変と日中戦争―日本切腹、中国介錯論
5章 太平洋戦争―戦死者の死に場所を教えられなかった国
P54
戦前期の憲法原理は一言で言えば「国体」でした。「天皇制」といいかえてもかまいません。
P75、なぜトロツキーでなく、スターリンが選ばれたのか?
この人たち(ボリシェビキ)は、1789年に起きたフランス革命が、ナポレオンという戦争の天才、軍事的なリーダーシップを持ったカリスマの登場によって変質した結果、ヨーロッパが長い間、戦争状態になったと考えていました。
(中略)
レーニンが死んだとき、軍事的なカリスマ性を持っていたトロツキーではなく、国内に向けた支配をきっちりやりそうな人、ということでスターリンを後継者として選んでしまうのです。
(中略)
一つの事件は全く関係のないように見える他の事件に影響を与え、教訓をもたらすものなのです。しかも、此処が大切なところですが、これが人類のためになる教訓、あるいは正しい選択であるとは限らない。
P92、ベトナム戦争の遠因
満州事変、日中戦争の時期においてアメリカは、中国の巨大な市場が日本によって独占されるのではないか、門戸開放政策が守られないのではないかと考え、中国国民政策を支持してきたわけです。それが、せっかく敵であった日本が倒れたというのに、また戦中期に大変な額の対中援助を行ったのに、49年以降の中国が共産化してしまった。
これはアメリカにとっては、嘆きであったでしょう。10億の国民にコルゲート歯磨き1本売っただけで、10億本分儲かる、とはよく言われた冗談ですが。こういった景気のよい資本主義的な進出ができなくなる。この中国喪失の体験により、アメリカ人のなかに非常に大きなトラウマが生まれました。戦争の最後の部分で、内戦がその国を支配しそうになったとき、あくまで介入して、自らの望む体制つくりあげなければならない、このような教訓が導きだされました。ですから、北ベトナムと南ベトナムが対立したとき、南ベトナムを傀儡化して間接的に北ベトナムを支配するのに止まるではなく、北ベトナム自体を倒そうとするわけです。
以上が、ベトナム戦争にアメリカが深入りした際、歴史を誤用したという、アーネスト・メイの解釈です。
P104
日本側が早く不平等条約を廃止してくださいと言い続けたとき、列強が「それでは商法、民法を編纂してくださいというのは、ある意味、正統な言い分ではあったわけですね。
P163
戦争には勝ったはずなのに、ロシア、ドイツ、フランスが文句をつけたからといって中国に遼東半島を返さなければならなくなった。これは戦争には強くても、外交が弱かったせいだ。政府が弱腰なために、国民が血を流して得たものを勝手に返してしまった。政府がそういう勝手なことをできてしまうのは、国民に選挙権が十分になかったからだ、との考えを抱いたというわけです。(こうして普通選挙への運動が高まる)
P195、日露戦争の原因
日露戦争が起きたのはなぜかという質問への答え方には、時代とともにかなり変化があったのです。
(中略)
戦争を避けようとしていたのはむしろ日本で、戦争を、より積極的に訴えたのはロシアだという結論になりそうです。(2005年国際会議、ルコイヤノフ先生の報告)
P204
日清戦争は帝国主義時代の代理戦争でしたが、日露戦争もやはり代理戦争です。ロシアに財政的援助を与えるのがドイツ・フランス、日本に財政的援助を与えるのがイギリス・アメリカです。
P211
ロシアが黒竜江省、吉林省、遼寧省という3つの省を占領していたことで排除されていた国々が平等に満洲に入れるようになった。(中略)「さあ、帝国主義のみなさん、いらっしゃい」と中国東北部を開いた。これが日露戦争でした。
P218
日露戦後、増税がなされたことで、選挙資格を制限する直接税10円を結果的に払う層が1.6倍になり、選挙権を持つ人が150万を超えたこと、これが大切なポイントです。
P279、血脈について
吉田茂は自分の妻のお父さんが、パリ講和会議で次席全権大使を務める牧野伸顕だった。(中略)岳父である牧野に連れて行ってくれと頼み、1918年にパリに旅立つのです。(牧野伸顕は大久保利通の二男である。麻生太郎は牧野伸顕の曾孫・・・権力者の血脈が絡まり合っている)
P283、ケインズ「あなたたちアメリカ人は折れた葦です」
ケインズは、ドイツから取り立てるべき賠償金の額をできるだけ少なくするとともに、アメリカに対して英仏が負っている戦債の支払い条件を緩和するよう求めたのです。しかしアメリカ側は、このような経済学が支持する妥当な計画に背を向け、とにかく英仏からの戦債返済を第一とする計画を、パリ講和会議において主張したのです。
1919年の時点で、ケインズの言うとおりに、寛容な賠償額をドイツに課していれば、あるいは29年の世界恐慌はなかったのではないか、このように予想したい誘惑にかられてしまいます。そうであれば、第二次世界大戦も起こらなかったかもしれません。けれども、ケインズの案は通らなかった。その結果ケインズは「あなたたちアメリカ人は折れた葦です」という手紙を残してパリを去ることになりました。
(「折れた葦」=旧約聖書「イザヤ書」;「折れた葦の杖を頼みにしているが、それは、寄りかかる者の手を刺し通すだけだ」)
P304
盧溝橋は、12世紀末につくられた、北京郊外の永定河に架けられた橋で、マルコ・ポーロが『東方見聞録』でその美しさを称えたことで有名です。
P299、関東軍とは?
満州事変のほうは、二年前の29年から、関東軍参謀の石原莞爾らによって、しっかりと事前に準備された計画でした。関東軍というのは、日露戦後、ロシアから日本が獲得した関東州(中心地域は旅順・大連です)の防備と、これまたロシアから譲渡された中東鉄道南支線、日本はこの鉄道に南満州鉄道と名前をつけましたが、この鉄道保護を任務として置かれた軍隊のことをいいます。
P313
長谷部恭男先生の説・・・どんな時に戦争が起きるか?
ある国の国民が、ある相手国に対して、「あの国は我々の国に対して、我々の生存を脅かすことをしている」あるいは、「あの国は我々の国に対して、我々の過去の歴史を否定するようなことをしている」といった認識を強く抱くようになっていた場合、戦争が起こる傾向がある、と。
P315、満州とは?
満州というのは「あて字」で、もともとはManjju(マンジュ)と発音する民族が住んでいた地域に対し、ヨーロッパ人や日本人などが、その発音に漢字の音をあてて「満洲」と書き、それが慣用的に戦後の日本では「満州」と表記されるようになったものだといいます。
P377
本来、中国の華中地域、上海や杭州などは、満洲や中国の河北地域との密接な経済関係のうえに繁栄していた。中国で有名な浙江財閥というのは、こうした上海や杭州などの豊かな地域を背景にした財閥でありました。軍事的な指導者であった蒋介石を永剤的に支えていたのは、渦中の浙江財閥だったのです。(宋嘉澍は、浙江財閥の創始者。娘の美齢は、蒋介石の妻となる。姉の慶齢は孫文の妻)
P379、日本切腹、中国介錯!
日中戦争が始まる前の1935年、胡適は「日本切腹、中国介錯論」を唱えます。すごいネーミングですよね。日本の切腹を中国が介錯するのだと。
P386
汪兆銘の夫人はなかなか豪傑で、汪兆銘が中国人の敵、すなわち漢奸だと批判されたときに、「蒋介石は英米を選んだ、毛沢東はソ連を選んだ、自分の夫・汪兆銘は日本を選んだ、そこにどのような違いがあるのか」と反論したといいます。
P459
日本古来の慰霊の考え方というのは、若い男性が、未婚のまま子孫を残すこともなく郷土から離れて異郷で人知れず非業の死を遂げると、こうした魂はたたる、と考えられていたのですね。つまり、戦争などで外国で戦死した青年の魂は、死んだ場所死んだ時を明らかにして葬ってあげなければならない。
P466-467、分村移民について
国や県は、ある村が村ぐるみで満州に移民すれば、これこれの特別助成金、別途助成金を、村の道路整備や産業振興のためにあげますよ、という政策を打ちだします。
このような仕組みによる移民を分村移民というのですが、助成金をもらわなければ経営が苦しい村々が、県の移民行政を担当する拓務主事などの熱心な誘いにのせられて分村移民に応じ、結果的に引揚げの課程で多くの犠牲を出していることがわかっている。
(中略)
満州からの引き揚げといったとき、我々はすぐに、ソ連軍侵攻の過酷さ、開拓移民に通告することなく撤退した関東軍を批判しがちなのですが、その前に思いださなければならないことは、分村移民をすすめる際に国や県がなにをしたかということです。
P469-470、日本とドイツの食糧事情について
戦時中の日本は国民の食糧を最も軽視した国の一つだと思います。敗戦間近の頃の国民の摂取カロリーは、1933年時点の6割に落ちていた。40年段階で農民が41%もいた日本で、なぜこのようなことが起きたのでしょうか。日本の農業は労働集約型です。そのような国なのに、農民には徴集猶予がほとんどありませんでした。(中略)
それにくらべてドイツは違っていました。ドイツの国土は日本にもまして破壊されましたが、45年3月、降伏する2ヶ月前までのエネルギー消費量は、なんと33年の1、2割増しでした。むしろ戦前よりよかったのです。
【満蒙とはどこか?】P316

満州事変・・・柳条湖は奉天の近く
日中戦争・・・盧溝橋は北京郊外
【感想と疑問】
本作品は、中高校生を相手に、5日間にわたって講義した記録。
非常に丁寧、分かりやすく説明されている。
単に講義するだけでなく、質問が出て、高校生が答える、という授業形式。
一方通行でなく、双方向の関係。
よく、ついていった、と思う。
栄光学園・歴史研究部のメンバーを相手にしている。
加藤先生は桜陰高校出身・・・女子校では全国トップの進学校。
でも、どうして桜陰で「授業」しなかったんだろう?
男子校で授業したかった?
編集部担当者の都合?

「あの戦争は何だったのか 大人のための歴史教科書」保阪正康
2014年に読んだ本の再読。
P21
島国である日本の主力は飽くまでも海軍であるとされた。主に薩摩藩の多い海軍、長州藩の多い陸軍との力関係も影響していた。だが明治10年、西南の役が起こる。皮肉にも薩摩の西郷隆盛が起こした西南の役により、陸軍の重要さが認識されていったのである。
P42
太平洋戦争下では、日中戦争後の昭和12年に「大本営」が設置されている。「大本営陸軍部」と「参謀本部」、「大本営海軍部」と「軍令部」、それぞれ用語として両方使われた。紛らわしいのであるが、どちらもほぼ同義語と考えていい。
P55
太平洋戦争開戦前の日米の戦力比は、陸軍省戦備課が内々に試算すると、その総合力は何と1対10であったという。米国を相手に戦争するに当って、首相、陸相の東條英機が、その国力差、戦力比の分析に、いかに甘い考えを持っていたかが今では明らかになっている。(東條英機は「精神力で勝っているはずだから、五分五分で戦える」、としたそうだ)
P78
「北進」論者、「南進」論者とも、それぞれ強い拘りがあった。「北進」論者は、主に陸軍に多かった。
P86
太平洋戦争において「武力発動」できたのは、唯一海軍だけであった。いくら行く軍が、南洋諸島や東南アジアで「武力発動」をしたくても、海軍の護衛で運んでもらえなければ、始めようがない。
P88
私が見るところ、海軍での1番の首謀者は、海軍省軍務局にいた石川信吾や岡敬純、あるいは軍令部作戦課にいた富岡定俊、神重徳といった辺りの軍官僚たちだと思う。
P92
東條の秘書官だった赤松はこうも言っていた。
「あの戦争は、陸軍だけが悪者になっているね。しかも東條さんはその中でも悪人中の悪人という始末だ。だが、僕ら陸軍の軍人には大いに異論がある。あの戦争を始めたのは海軍さんだよ・・・・・・」
P105
私は、この戦争が決定的に愚かだったと思う、大きな一つの理由がある。それは、「この戦争はいつ終わりにするのか」をまるで考えていなかったことだ。
P111
ミッドウェーで生き残った者たちは日本に戻ると幽閉状態におかれた。
P120
例えば、もし「ミッドウェー海戦」で戦争を終結していたら・・・・・・。もちろん、これはありえない歴史上の「イフ」である。しかし、吉田茂がひそかに和平工作を模索しているなど、その時点で全く可能性がゼロだったとは言い切れない。
「戦争を終結させる」とはいわない、なにせまともに「戦争の終結」像すらも日本の首脳部は考えていなかったのだから。でも、せめて“綻び”が出始めた昭和17年末の段階で、「このままの戦い方でいいのか」、あるいはもっと単純に「この戦争は何のために戦っているのか」と、どうして立ち止まって、誰も顧みなかったのか。
P121-122
資料に目を通していて痛感した。軍指導者たちは“戦争を戦っている”のではなく、”自己満足”しているだけなのだと。おかしな美学に酔い、1人悦に入ってしまっているだけなのだ。兵士たちはそれぞれの戦闘地域で飢えや病で死んでいるのに、である。
挙げ句の果てが、「陸軍」と「海軍」の足の引っ張り合いであった。
「日本は太平洋戦争において、本当はアメリカと戦っているのではない。陸軍と海軍が戦っていた、その合い間にアメリカと戦っていた・・・・・・」などと揶揄されてしまう所以である。
P148
昭和18年に戦況が悪化すると、東條の演説や側近への話には筋道の通らない論理が含まれるようになった。たとえば、「戦争が終わるということは、戦いが終わった時のこと、それは我々が勝つということだ。そして、我々が戦争に勝つということは、結局、“我々が負けない”ということである」、という意味不明のことさえ口にした。あるいは「戦争は負けたと思ったときは負け。そのときに彼我の差がでる」とも言うのである。
P150
十月に、陸軍の飛行学校に、学生たちへのねぎらいも込めて、視察に行った時のこと。東條は学生に「B-29が飛んできたとする。そうしたら、君は何で打ち落とすか」と問い掛けた。問い掛けられた学生は教科書通りに「15センチ高射砲で撃ち落とします」と答えると、東條は「違う、そうじゃない。精神力で打ち落すんだ」と語ったという。(じゃ、手本を見せてください、って)
P172
牟田口(廉也)は、実は泥沼の日中戦争のきっかけとなった盧溝橋事件をおこした部隊の連隊長であった。日頃から「支那事変はわしの一発で始まった。だから大東亜戦争はわしがかたをつけねばならん」というのが牟田口の口癖であった。
(その牟田口が考えた作戦が、悪評高い「インパール作戦」だ)
P179
私はインパール作戦で辛うじて生きのこった兵士たちに取材を試みたことがある。彼らの大半は数珠をにぎりしめて私の取材に応じた。そして私がひとたび牟田口の名を口にするや、体をふるわせ、「あんな軍人が畳の上で死んだことは許されない」と悪しざまに罵ることでも共通していた。
P204
4月28日、パルチザンに捕まったムッソリーニは銃殺処刑、逆さ吊りにされ晒された。4月30日、ドイツでは、ソ連がベルリン市内まで侵攻。その最中、ヒトラーは官邸の地下壕で拳銃自殺をしている。
P228
“勝ち戦”に乗じて日本の領土が欲しかったスターリンは、トルーマンに「我々は関東軍を掌握し、北海道方面に侵攻している。ソ連の制圧地域として北海道を認めて欲しい」と要求していた。しかし、トルーマンは、決してそれを認めなかった。スターリンはもう一度、「北海道が欲しい」と重ねて訴えるが、やはり断られてしまう。ならばと、「領土の代わりに、関東軍の兵を労働力としてもらう」と勝手に決めてしまった節があるのだ。
こうして「シベリア抑留」が行われた。
P222-223
歴史に他の選択肢はないが、「原爆」を落とされ、負けた。その結果、アメリカに占領されてよかったという見方もできる――。
(結果として、そうかもしれないが違和感を感じる。広島や長崎の方に、「原爆を落とされてよかった」、と言えるのか?)
P234
「戦争が終わった日」は、8月15日ではない。ミズーリ号で「降伏文書」に正式調印した9月2日がそうである。いってみれば8月15日は、単に日本が「まーけた!」といっただけにすぎない日なのだ。
世界の教科書でも、みんな第2次世界大戦が終了したのは、9月2日と書かれている。
【言葉の説明】P52
八紘一宇・・・日本書紀、神武天皇が大和橿原に都を定めた詔に出てくる言葉
「八紘」とは「四方と四隅」を表し、八方のはるかに遠い果てを指す。「一宇」は一つの家のことである。つまり、「地の果てまで一つの家のようにまとめて天皇の統治下におく」という意味となる。
東條英機の「戦陣訓」P70
有名な一節・・・「生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ」表現は島崎藤村が推敲したとされる。
この思想のために、多くの軍人、兵士たちが玉砕の憂き目にあったのである。
【残念な点】
当時のメディアと大衆の動向に触れていない。
文献も掲載されていない。そこが残念。
本書は、保阪正康作品の中でもよく読まれている人気作品。
一度は読んでおいて損はない。
【ネット上の紹介】
戦後六十年の間、太平洋戦争は様々に語られ、記されてきた。だが、本当にその全体像を明確に捉えたものがあったといえるだろうか―。旧日本軍の構造から説き起こし、どうして戦争を始めなければならなかったのか、引き起こした“真の黒幕”とは誰だったのか、なぜ無謀な戦いを続けざるをえなかったのか、その実態を炙り出す。単純な善悪二元論を排し、「あの戦争」を歴史の中に位置づける唯一無二の試み。
[目次]
第1章 旧日本軍のメカニズム(職業軍人への道
一般兵を募る「徴兵制」の仕組み ほか)
第2章 開戦に至るまでのターニングポイント(発言せざる天皇が怒った「二・二六事件」
坂を転げ落ちるように―「真珠湾」に至るまで)
第3章 快進撃から泥沼へ(「この戦争はなぜ続けるのか」―二つの決定的敗戦
曖昧な“真ん中”、昭和十八年)
第4章 敗戦へ―「負け方」の研究(もはやレールに乗って走るだけ
そして天皇が動いた)
第5章 八月十五日は「終戦記念日」ではない―戦後の日本

「昭和史 戦後篇」半藤一利
読み返し。
先日の『戦前編』に続き、『戦後編』も読んだ。
敗戦後の変わり身の早さについて
P19
今日まで「一億玉砕」「戦士であるおまえたちがそんなだらしないことでどうする」と横ビンタ張っていた人たちが、次の日から「これからはアメリカだ」「民主主義だ」なんて言い出すんですから、その変わり身の早さにも驚かざるを得ません。
特殊慰安施設協会・RAAの売春婦募集について
P20
特殊慰安施設協会(RAA)がつくられ、すぐ「慰安婦募集」です。いいですか、終戦の3日後ですよ。
「営業に必要なる婦女子は、芸妓・公私娼妓・女給・酌婦・常習密売淫犯らを優先的に之を充足するものとす」
そういうプロの人たちを中心に集めたいということです。内務省の橋下政美警保局長が18日、各府県の長官(当時は県知事を長官と言いました)に、占領軍のためのサービスガールを集めたいと指示を与え、その命を受けた警察署長は八方手を尽くして、「国家のために売春を斡旋してくれ」と頼み回ったというんです。およそ売春を取り締まらなきゃいけない立場の警察が「売春をやってくれ」と頼み回ったなど日本ではじめてのケースだと思います。
(中略)
「池田さんの『いくら必要か』という質問に野本さんが『一億円ぐらい』と答えると、池田さんは『一億円で純潔が守れるなら安い』といわれた」これはあくまで「良家の子女」の純潔です。ちなみに池田さんというのは、当時の大蔵省主税局長でのちの首相、池田勇人です。
P41
天皇とマッカーサー元帥の会話(皇太子(現天皇)の家庭教師を務めたバイニング夫人日記より)
元帥「戦争責任をおとりになるか」
天皇「その質問に答える前に、私のほうから話をしたい」
元帥「どうぞ。お話なさい」
天皇「あなたが私をどのようにしようともかまわない。私はそれを受け入れる。私を絞首刑にしてもかまわない」
これは原文では、You may hang me.となっています。
P71
一方マスコミ・新聞はどうだったのか?・・・作家の高見順さんが次のように怒っている
「新聞は、今までの新聞の態度に対して、国民にいささかも謝罪するところがない。詫びる一片の記事も掲げない。手の裏を返すような記事をのせながら、態度は依然として訓戒的である。(後略)」
P75
11月28日の臨時議会での陸相・下村定大将の謝罪演説
進歩党・斉藤隆夫さんが「日本をこのような事態に導いたことについて陸軍および海軍大臣に所見をうかがいたい」と問う。
「(前略)今回のごとき悲痛な状態を、国家にもたらしましたことは、何とも申しわけありませぬ」
つまり、陸軍が悪かったとはっきり言ったわけで、それまで野次がとんでいた議場もこのへんからしーんとなりまして、なかには「もうわかった、やめろよ」といった言葉さえ聞かれたといいます。下村さんはそれでも続けました。
「私は陸軍の最後にあたりまして、議会を通じてこの点につき、全国民諸君に衷心からお詫びを申し上げます。陸軍を解体いたします(後略)」
P158
一説に、幣原(喜重郎)さんが「今後はこういう平和日本にしたい」ということをマッカーサーに言い、感動したマッカーサーが「それはすばらしい。原子爆弾などという殺人兵器でもって戦争を続けていれば人類は滅亡する。日本が率先して軍備を全部捨て、戦争をしないと世界中に宣言するのはすばらしいことだ」と賛同し、それを新しい憲法の中に盛り込んだ――とされてます。いや、逆に幣原さんではなくマッカーサーから言い出したのだという説もあります。
P199
GHQ案・新憲法について、国会でのやりとり
リベラル派だとか社会党には「GHQ案で日本の国はよくなる」と喜ぶ人もいました。面白いのは、共産党がなぜか「軍隊を持たない」「戦争放棄」の条項に猛反対をしたんです。これでは国民の権利である自衛戦争も認められないではないか、と。今の共産党とはずいぶん違いますね。(共産党は戦中戦後、一貫した態度をとっている、と思っていたが、そうではなかった)
P220
ではどうやって、A級戦犯の28人を決めたのか?(中略)検事団にとって非常に役に立った人物が2人いて、1人が自身もA級戦犯である内大臣の木戸幸一さん、もう1人がかつての兵務局長の田中隆吉さんです。
P228
さて、被告席に並んだA級戦犯28人を見ますと、なんと陸軍軍人が15人もいます。それもほとんど軍政方面つまり陸軍省関係で、参謀本部関係はきれいに除外されています。(日本人自身の手で裁判していたら、偏りを少しは解消できたかもしれない)
P245
ちなみにBC級戦犯について申しますと、5702人が告訴され、裁判ののち984人に死刑が執行されました。これは法廷ではなく国別で裁いたもので、イギリスとオランダが一番多いことから、その憎しみの強さがうかがわれます。そして死刑になったすべての人が、靖国神社に祀られました。
(フランス人作家・ピエール・ブールは、「戦場にかける橋」の著者である。戦時中、日本人の捕虜になっている。さらに、この作家は、「猿の惑星」も著している。故に、猿の惑星の「サル」とは「日本人」のこと、と言われている・・・真偽不明)
P238
巣鴨に入れられていた準A級戦犯に鮎川義介(日産コンツェルン創始者)という人がいました。(中略)巣鴨時代には退屈でしょうがなかったので、芝居を作ってみた。配役は、チャーチルが「やり手婆あ」、ルーズベルトは「大金持ちの若旦那」、ヒトラーが「大山師」、スターリンは「因業高利貸し」・・・うまいですね。(中略)これを戦犯の皆が喜んで聞いていたそうです。
P245
東京裁判の意味
①日本人の現代史を裁くため、裏返せば、連合国のやってきたことが正義だったと再確認するためだ、と。
かつて植民地をさんざんつくってきた帝国主義は19世紀の話であって、それを20世紀においてやった日本の考え方は侵略的性格をもつ間違った戦争観であった、と。
②自国民を納得させるための一種の復讐の儀式
③何も知らされていなかった日本国民に事実を教え、侵略的軍閥の罪状を明らかにし、啓蒙すること。
(これを読んでいて思いだすのが、香港返還の際のイギリスのコメント、である。一片の謝罪もなく、「さすが大英帝国」、と私は感じた)
P286
希代の強姦間・小平義雄の死刑について
買い出しなどに出ていた女性をだまして物を奪い、数十人を強姦し、しかも7人を殺した挙句、捕まってこう言ったそうです。「中国従軍の時に覚えたあの味が忘れられなかった」。(小平義雄は特殊な例と思いたいが、戦争の狂気を引き摺りつづけた人は他にもいた、と思う。この当時PTSDという言葉はなかった)
P306
昭和26年4月11日、突如、マッカーサー元帥がトルーマン大統領により罷免された、最高司令官をクビになったという報せがラジオの臨時ニュースで流れました。いやまあ、私など腰が抜けるほど驚きました。
(マッカーサーが解任された時、皆が驚いたという。上村一夫さんの「サチコの幸」は昭和25-26年頃を描いている。第二巻P172に次のように書かれている)
「マッカーサーとかけて何ととく?」
「“へそ”ととく・・・・・・」
「そのココロは?」
「“チン”の上にある・・・・・・」と
いうぐらいエライ人だと思っていたのが
いとも簡単にクビになってしまったのですから・・・・・・ 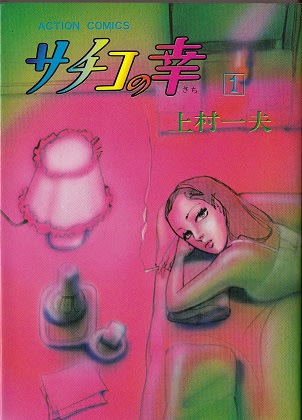
P346
天皇の退位について
天皇陛下はご自分で「退位」について発言されたことが大きく言って3度あります。
①終戦直後の8月29日
②東京裁判の判決が出た時
③講和会議の調印後、国家が独立した時
P350
昭和26年9月8日サンフランシスコ講和条約が締結され、日本は占領が終わり、国家主権を取り戻して独立国となることが世界的に認められました。
吉田茂首相の演説
「外交の権力をもっていない国は亡びるともいいますが、この条約によって国際社会に戻ることになった日本は、真に外交能力をもつ国になりたい」
P475
この年の生活といいますと、昭和30年に発足した日本住宅公団による公団住宅ができはじめます。今では公団住宅というと長屋のようなイメージがありますが、当時は高嶺の花で、ぼこ、ぼこ、と日当たりのいいところに達つじゃありませんか、入れるなんて夢のまた夢のような話でした。家賃は2LDKで3,500円から4,800円、申し込み資格は平均月収25,000円以上(所帯用)。念のために申しますと、当時の国家公務員の上級職の初任給は9,200円でした。この時はやった「ダンチ族」という言葉を命名した「週刊朝日」の7月20日号の調査結果によると、30代の夫婦、子供は1人か2人の核家族で、月収が2~3万円、「電機洗濯機が2軒に1台、電気冷蔵庫は7軒に1台、電気釜は3軒に1台・・・・・・」あったということです。ダンチ族は当時、ものすごいエリートだったのです。
昭和20年代と30年代について
P477
ではその時、なくなったのは何か。戦前から昭和20年代までの日常生活品です。ちゃぶ台、たらい、火鉢、アンカ、柱時計、蚊帳、蠅たたき、家の外に置いてあったゴミ箱、そして縁側(後略)。
戦後、歴代首相の命題
P500
吉田茂、再軍備せず、講和条約を結ぶ
鳩山、ソ連との国交回復
石橋、病で倒れ特になし
岸信介、安保条約の改定
池田、高度経済成長の実現
佐藤、沖縄問題の解決
P528
1970年万国博覧会
「月の石」に人気が殺到して、長蛇の列になった。
「人類の進歩と調和」をテーマにした万博を、これぞ「人類の辛抱と長蛇」の結果であった、なんて冷やかす人もいたわけです。
P536
47年(1972)5月15日、沖縄の施政権が日本に完全に返還され、沖縄県が発足しました。戦後26年たって、ようやく1道1都2府42県が「43県」になったのです。(中略)ともかくこの沖縄返還で日本の戦後は一応、終わったとみていいのではないかと思います。
P566
昭和天皇・マッカーサ会談
| 期日 | 通訳 | テーマ | ||
| ① | 20年 | 9月27日 | 奥村勝蔵 | 天皇の戦争責任 |
| ② | 21年 | 5月31日 | 寺崎英成 | 食糧援助、東京裁判 |
| ③ | 21年 | 10月16日 | 寺崎英成 | 食糧援助、憲法9条、地方巡幸・・・ |
| ④ | 22年 | 5月6日 | 奥村勝蔵 | 新憲法下での選挙、日本の安全保障、日本経済の現状・・・ |
| ⑤ | 22年 | 11月14日 | 寺崎英成 | 沖縄問題 |
| ⑥ | 23年 | 5月6日 | GHQ | |
| ⑦ | 24年 | 1月10日 | GHQ | |
| ⑧ | 24年 | 7月8日 | 松井明 | 国内の治安 |
| ⑨ | 24年 | 11月25日 | 松井明 | 講話問題、シベリア抑留、ソ連の原爆開発・・・ |
| ⑩ | 25年 | 4月18日 | 松井明 | 共産圏の脅威? |
| ⑪ | 26年 | 4月15日 | 松井明 | 儀礼的(お別れ) |
【おまけ】
昭和天皇の口癖は、「あ、そう」であるが、米国人には、挑発的な侮蔑語“asshole"と聞こえたようだ。
また、昭和天皇と関係ないが、日本人の発音で“I love you”と言うと、“I rub you" (こすりたい)と聞こえる。
私も、知らずに、この種の誤りをしているかもしれない。
【参考リンク】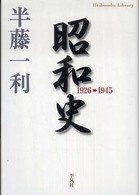
「昭和史 1926-1945」半藤一利
【ネット上の紹介】
授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博した「昭和史」シリーズ完結篇。焼け跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細にたどる。世界的な金融危機で先の見えない混沌のなか、現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の役割、そして明日を考えるために。毎日出版文化賞特別賞受賞。講演録「昭和天皇・マッカーサー会談秘話」を増補。
[目次]
天皇・マッカーサー会談にはじまる戦後―敗戦と「一億総懺悔」
無策の政府に突きつけられる苛烈な占領政策―GHQによる軍国主義の解体
飢餓で“精神”を喪失した日本人―政党、ジャーナリズムの復活
憲法改正問題をめぐって右往左往―「松本委員会」の模索
人間宣言、公職追放そして戦争放棄―共産党人気、平和憲法の萌芽
「自分は象徴でいい」と第二の聖断―GHQ憲法草案を受け入れる
「東京裁判」の判決が下りるまで―冷戦のなか、徹底的に裁かれた現代日本史
恐るべきGHQの急旋回で…―改革より復興、ドッジ・ラインの功罪
朝鮮戦争は“神風”であったか―吹き荒れるレッド・パージと「特需」の嵐
新しい独立国日本への船出―講和条約への模索
混迷する世相・さまざまな事件―基地問題、核問題への抵抗
いわゆる「五五年体制」ができた日―吉田ドクトリンから保守合同へ
「もはや戦後ではない」―改憲・再軍備の強硬路線へ
六〇年安保闘争のあとにきたもの―ミッチーブーム、そして政治闘争の終幕
嵐のごとき高度経済成長―オリンピックと新幹線
昭和元禄の“ツケ”―団塊パワーの噴出と三島事件
日本はこれからどうなるのか―戦後史の教訓
昭和天皇・マッカーサー会談秘話
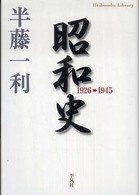
「昭和史 1926-1945」半藤一利
読み返し。
毎日出版文化賞特別賞受賞。
昭和史の決定版、文章も読みやすい。
満州事変について
P81
この人たち(本庄繁・石原莞爾・三宅光治・板垣征四郎)は本来、大元帥命令なくして戦争をはじめた重罪人で、陸軍刑法に従えば死刑のはずなんです。
(中略)
昭和がダメになったのは、この瞬間だというのが、私の思いであります。
上海事変
P96
中央からもらった2万円で、自分の愛人で「東洋のマタ・ハリ」と言われている川島芳子も使って中国人に金をまき、事件を起こす算段をしました。そして1月18日、ついに事件はおきます。日蓮宗の坊さん2人が信徒3人を連れて上海の街を「南無妙法蓮華経」と托鉢して歩いている時、抗日運動が盛んな頃ですから、反日分子――といってもそう装わせた中国人――がそれを襲撃し、結果としては2人が死に3人が重症を負うという殺人事件になりました。
この無法をチャンスとした日本軍は、「犯人をだせ」と厳重抗議をします。中国側は覚えがありませんから「何を言うか」ともみ合って一触即発になります。向こうは反日で燃えてますし、こっちはやる気じゅうぶんというか元々そのつもりなんですから、あっという間に火を噴いて、10日後、中国軍と日本軍が弾を撃ち合う大事件に発展したのです。
今話したことはのちにわかったことで、当時はまさか日本軍の謀略で田中隆吉と川島芳子が組んでしかけたなんて誰も知りませんから「やっぱりはじまったか」と日本人の皆が思った。
2.26事件
P159
私は生き残った少尉4人に戦後もずっと後に会いまして「殺すことはなかったんじゃないですか」と聞いたところ、4人共「そうなんだよなあ」と、どうも後悔していたようです。
P177
この年の5月18日、かの有名な「安部定事件」が起きます。(中略)
ちょうどこの時に、チャップリンとフランスの詩人ジャン・コクトーが来日しましたが、ともにあまり騒がれないほど国民は安部定事件の話題で沸いていました。
P181
西安というのは、唐の時代(618~907)の世界的大都市だった長安で、始皇帝の墓や兵馬俑、三蔵法師が仏教の経典を持って来て納めたという大雁塔などがあります。その街はずれの温泉「華清地」で玄宗皇帝と楊貴妃が喋々喃々やっていたという話もあり、今は大歓楽地になっています。(その華清地の裏山に、蒋介石が軟禁された穴倉が残っているそうだ=即ち「西安事件」)
P182
西安事件とは、中国のナショナリズムが一つになって誕生する、まさに対日抗戦を可能にする歴史の転換点だったのです。
しかし日本は、この情報が伝わってきたにも関わらず、中国が今や一つになろうとしていることをまったく理解していませんでした。
昭和12年、野上弥生子さん、年頭の新聞紙上での挨拶
P183
「(前略)洪水があっても、大地震があっても、暴風雨があっても、・・・・・・コレラとペストがいっしょにはやっても、よろしゅうございます。どうか戦争だけはございませんように・・・・・・」
盧溝橋事件の際の牟田口廉也
P188
「敵に撃たれたら撃て、断固戦闘するも差し支えなし」
まさしく抗戦命令です。こういう命令は、ほんとうはその上の旅団長にきちんとしらせるかたちをとって、統帥命令といいいますか、天皇命令にしないまでも、参謀本部命令にしないといけないのですが、牟田口さんは独断命令を一木大隊長に下したのです。
トラウトマン和平工作は昭和13年1月15日で打ち切られてしまうその翌日
P206
1月16日、近衛さんは声明を発します。これが有名な「国民党政府を相手にせず」、つまり国民政府を政府としては認めない、もう和平なんてしないというもので、これでは戦っている当事者は最後までやらざるを得なくなってしまいます。実に馬鹿げた話で、せっかく参謀本部が乗り気だったのに、政府が強行でぽしゃってしまったのです。(近衛文麿は昭和20年12月、服毒自殺している)
南京大虐殺
P197-201
その根拠は・・・
旧日本軍の集まりである偕行社「南京戦史」
いわゆる不法な行為によって殺されたとすれば、三万強がその数ということになりましょうか。
(中略)
ただ、中国が言うように三十万人を殺したというのは、東京裁判でもそう言われたのですが、あり得ない話です。当時、南京の市民が疎開して三十万もいなかったし、軍隊もそんなにいるはずはないのですから。
(比較の問題じゃないけど、文化大革命では40万人から1000万人以上と言われる)
P236
この戦い(ノモンハン事件)を指揮した関東軍の参謀が、服部卓四郎中佐と辻政信少佐でした。(中略)二人とものほほんとしたことを言っていますが、そこからは責任のセの字も読み取れません。まことにひどい話です。
P238
つまりノモンハン事件で膨大な被害を被らせた二人が再び参謀本部に戻って「今度は南だ」と南進政策――これはイギリス、アメリカとの正面衝突を意味します――を、「こんどこそ大丈夫」と言わんばかりに推進したのです。
P239
作戦課長・服部卓四郎大佐「サイパンの戦闘でわが陸軍の装備の悪いことがほんとうによくわかった・・・(後略)」
何たることか、ノモンハンの時にすでにわかっていたではないか(後略)。
・・・学習能力のない陸軍だった。
三国同盟が結ばれた時の西園寺公望の言葉
P319
「これで日本は滅びるだろう。これでお前たちは畳の上で死ねないことになったよ。その覚悟を今からしておけよ」
P356
『昭和天皇独白録』には「・・・・・・国際信義を無視するもので、こんな大臣は困るから私は近衛に松岡を罷める様に云ったが、・・・・・・」と驚くようなことが記されている。
P356
私などは調べれば調べるほど、近衛はこりゃだめな宰相だと思うのですが、昭和天皇はそうじゃなかったんですねえ。
ミッドウェー海戦について
P405
山本五十六の部下であった黒島亀人先任参謀がこう断言しているのです。
「作戦は少しも間違っていなかった。機動部隊指揮官の南雲中将が、あらゆる機会を捉えて、アメリカ空母を攻撃するようにという連合艦隊の命令を正しく実行していたら、この海戦は日本海軍が勝利をおさめていたことであろう」
P469
すでに7月24日、ポツダム宣言が出る前に、(原爆)投下命令が出されていたのです。(鈴木貫太郎は、ポツダム宣言に対して「黙殺」すると言明したが、どう訳したのかよく問題になる――ignore なのか、reject なのか?、と。しかし、既に投下命令が出ていたのなら、どうしようもない。「歴史をかえた誤訳」鳥飼玖美)
著者・半藤一利さんの感想&結論
P498
それにしても何とアホな戦争をしたものか。この長い授業の最後には、この一語のみがあるというほかはないのです。ほかの結論はありません。
歴史からの教訓
P503
①国民的熱狂をつくってはいけない
②具体的な理性的な方法論を検討せねばならない(希望的観測に頼ってはいけない)
③日本型タコツボ社会における小集団主義の弊害・・・参謀本部と軍令部は小集団エリート主義の弊害そのもの
④ポツダム宣言の受諾が意志の表明でしかなく、終戦はきちんと降伏文書の調印をしなければ完璧なものにならないという国際的常識を、理解していなかった
⑤対症療法で、その場その場のごまかし的な方策で処理してしまった
南進について・・・
P529
根拠なき自己過信、驕慢な無知、底知れない無責任と評するのは容易です。けれども、よく考えると、いまの日本も同じようなことをやっているのじゃないかと、・・・(後略)
ノモンハンの教訓
P533
①失敗を率直に認めず、その失敗から何も教訓を学ばないという態度
②情報というものを軽視し、非常に「驕慢な無知」に支配されていた
③「底知れぬ無責任」勇猛敢闘させるようなものであれば、失敗しても責任が問われなかった
【参考図書】
「地図と写真でみる半藤一利昭和史1926-1945」
「昭和史裁判」半藤一利/加藤陽子
「昭和の名将と愚将」半藤一利・保阪正康

「昭和史 戦後篇」半藤一利
「歴史認識」とは何か 対立の構図を超えて」大沼保昭/江川紹子
「それでも、日本人は「戦争」を選んだ」加藤陽子
【ネット上の紹介】
授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博した「昭和史」シリーズ戦前・戦中篇。日本人はなぜ戦争を繰り返したのか―。すべての大事件の前には必ず小事件が起こるもの。国民的熱狂の危険、抽象的観念論への傾倒など、本書に記された5つの教訓は、現在もなお生きている。毎日出版文化賞特別賞受賞。講演録「ノモンハン事件から学ぶもの」を増補。
[目次]
昭和史の根底には“赤い夕陽の満州”があった―日露戦争に勝った意味
昭和は“陰謀”と“魔法の杖”で開幕した―張作霖爆殺と統帥権干犯
昭和がダメになったスタートの満州事変―関東軍の野望、満州国の建国
満州国は日本を“栄光ある孤立”に導いた―五・一五事件から国際連盟脱退まで
軍国主義への道はかく整備されていく―陸軍の派閥争い、天皇機関説
二・二六事件の眼目は「宮城占拠計画」にあった―大股で戦争体制へ
日中戦争・旗行列提灯行列の波は続いたが…―盧溝橋事件、南京事件
政府も軍部も強気一点張り、そしてノモンハン―軍縮脱退、国家総動員法
第二次大戦の勃発があらゆる問題を吹き飛ばした―米英との対立、ドイツへの接近
なぜ海軍は三国同盟をイエスと言ったか―ひた走る軍事国家への道
独ソの政略に振り回されるなか、南進論の大合唱―ドイツのソ連進攻
四つの御前会議、かくて戦争は決断された―太平洋戦争開戦前夜
栄光から悲惨へ、その逆転はあまりにも早かった―つかの間の「連勝」
大日本帝国にもはや勝機がなくなって…―ガダルカナル、インパール、サイパンの悲劇から特攻隊出撃へ
日本降伏を前に、駆け引きに狂奔する米国とソ連―ヤルタ会談、東京大空襲、沖縄本島決戦、そしてドイツ降伏
「堪ヘ難キヲ堪ヘ、忍ビ難キヲ忍ビ…」―ポツダム宣言受諾、終戦
三百十万の死者が語りかけてくれるものは?―昭和史二十年の教訓
ノモンハン事件から学ぶもの

「昭和史裁判」半藤一利/加藤陽子
以前(2018年)読んだ本の読み返し。
前回読んだ「昭和の名将と愚将」は、軍人を対象としていた。
今回は、文官たちを俎上に載せてその功罪を問う。
検事役が半藤一利さん、弁護人が加藤陽子さん。
二人が議論しながら、心情や状況を掘り下げていく。
こうして「日本のいちばん長い昭和反省会」が始まった。
第1章 広田弘毅↓
昭和23年、A級戦犯として絞首刑執行される(70歳)
第2章 近衛文麿↓
昭和20年12月、服毒自殺(55歳)
第3章 松岡洋右↓
東京裁判の判決を待たず結核で死去(66歳)
辞世「悔いもなく怨みもなくて行く黄泉(よみじ)」
第4章 木戸幸一↓
A級戦犯となるが、後に仮釈放される
昭和52年、宮内庁病院にて87歳で死去(肝硬変)
第5章 昭和天皇↓
P94
半藤:ほとんどの日本人に理解できない。なぜなら、自分は天皇の次に偉いと思っているんだ、と
P96
加藤:なにしろ五摂家です。天皇の前で椅子に深く腰掛けて、足までくんでおしゃべりしたというのは近衛さんだけだったという逸話はゆうめいですね。
P100
加藤:政治家の死というのは、お金の切れ目なのだということを感じたと、近衛自身が記しています。
P120
半藤:昭和20年の太平洋戦争間際にトップに立った人たちはみんな、みんなと言っても参謀本部と軍令部は別ですよ、それ以外の人たちは、このまま戦い続けて国内が混乱し、ついに共産革命が起きたらどうしょうかということを本気で心配するんです。そうならないためにも早く降伏したほうがいいと、こうなるわけですね。木戸、近衛はもちろんですが、海相の米内光政も、実はそれを心配したのです。
P127
半藤:近衛は遺書で「僕は支那事変以来、多くの政治上の過誤を犯した」と自ら認めておりますが、その失敗の責任はあまりに大きい。泰淳は同情したかもしれないけれど、天皇はこれを許さないのです。
P184-185
加藤:蒋介石にとっては戦争の責任者の断罪などどうでもいいのです。中国における日本人の個人の私有財産も含めた日本の現物財産、あれをとにかく置いていってくれればいいと。
P194
加藤:当時、上海の日本人社会には序列というのがありまして、いちばん偉いのが外務省。次が日銀や横浜正金といった銀行系です。三井物産はそのつぎだったようですね。
P205
加藤:「フリードリヒ大王や、ナポレオンのような行動、極端に云えば、マキャベリズムのようなことはしたくないね」ということを天皇がおっしゃったと内大臣の木戸幸一は日記に記していますが、これは南部仏印進駐についてのコメントです。
P220
半藤:松岡(洋右)がやったことのなかで国際連盟脱退は、最大のまちがいであったと私は思っています。
P227
半藤:それにしても、天皇はなぜあれほど松岡を嫌ったのか。昭和天皇という人は不思議なくらい個人の悪口は言わない人なのですが。
P233
半藤:「東亜新秩序」というのは近衛文麿がいいだした言葉ですが、では「大東亜共栄圏」はだれがいいだしたかといいますと、これが松岡なんです。昭和15年(1940)8月1日だそうですよ。
P252
半藤:木戸と近衛は学習院、京都大学法学部の同級生。この同級生づき合いと華族ネットワークが木戸を表舞台に押し出したわけですね。
P265
加藤:幕府と協調していくことを決めた瞬間、もしくは長州藩に宮中側近を変えられてしまった瞬間に、孝明天皇はすべての権力を奪われてしまった。そういうイメージが西園寺と木戸のあいだには共有されています。だからこそ親政には反対だった。親政で突破しても陸軍が言うことを聞かなかったらおしまいだという認識だったのです。
P267
半藤:日本の国のためにはこれからという大事というときに悪い人(木戸幸一)を選びましたね。陸軍にはおべっかを使い、右翼には色目を使うような人が速記にいたということは、まことによくなかった。
P295
加藤:「戦争中は羊を飼って自家製の食物での食事療法をしていました」と、のちに秩父宮妃殿下が語っていますが、秩父宮夫妻も白州次郎・正子夫妻と同じようなライフスタイルで戦中を過ごしていたのですね。白州夫妻は太平洋戦争が始まると、あっという間に鶴川の田舎に引っ込んで、お米や麦やジャガイモを作って暮らすわけですから。これが真の上流階級の、第二次世界大戦期の過ごし方でした。(武蔵と相模の間に位置することから、無愛想をもじって邸を「武相荘」と命名した。いまでは一般公開されている)
P323
半藤:じつは海軍は情けないことに、潜水艦の実践的な使い方を知らなかったのです。第一次世界大戦のドイツ潜水艦の猛威にイギリスが音を上げたという戦訓がありながら、潜水艦は輸送船を狙うべきものだということに気づいていなかった。(中略)それには理由がありまして、日本海軍は敵の艦船を撃沈しても、輸送船は1点なんです。いっぽう戦艦は10点。高得点なのは戦艦と航空母艦でして、つまり論功行賞のためには輸送船なんか沈めてもたいして稼ぎにならなかったわけです。(日本の点数主義の根は深い)
P330
加藤:天皇は、終戦に持ち込むには戦果を上げてからでないと内乱になると思っていました。そんな天皇に引導を渡したのが貞明皇太后でした。皇太后が自分は疎開しない、と言ったときです。
P332
加藤:戦争責任については、政治的責任と道義的責任という分け方で考えるのが通常の発想です。天皇に政治的責任がないのはむろんのことです。けれども「天皇陛下の御ために」と、死んでいった将兵の家族に対しては申し開きがたたないという意味で、道義的責任はあるのではないかという議論。
天皇の無答責について
P389
注釈:つまり政治的、行政的な責任は政府が有しており、君主個人に帰するものではないというわけである。いっぽう昭和天皇の戦争責任を「有り」とする立場からは、天皇は開戦を承認し、終戦を決断しており、政治的決定過程において最終的な決定権者としてふるまっているとする。そのことからも政治的責任があるとされる。
P398
半藤:木戸と近衛は仲がいいように思われがちですが、じっさいは違ったのでしょう。
P402
半藤:天皇がいつも総理大臣に言う言葉が、3つありました。国際協調と、憲法遵守、そして経済の安定です。
【おまけ/ツーショット特集】
このツーショットはレア ↓
(蒋介石と毛沢東)
近衛は長身だ ↓
(近衛は片手をポケットに入れている)
近衛と木戸 ↓
(近衛は両手をポケットに入れている)
木戸は152cm、近衛は180cm
【参考図書】
「昭和の名将と愚将」半藤一利・保阪正康 

「昭和史 1926-1945」半藤一利
「昭和史 戦後篇」半藤一利
「歴史認識」とは何か 対立の構図を超えて」大沼保昭/江川紹子
【ネット上の紹介】
「軍部が悪い」だけでは済まされない。松岡洋右、広田弘毅、近衛文麿ら70年前のリーダーたちは、なにをどう判断し、どこで間違ったのか―昭和史研究のツートップ・半藤さんと加藤さんが、あの戦争を呼び込んだリーダー達(番外編昭和天皇)を俎上に載せて、とことん語ります。あえて軍人を避けての徹底検証は本邦初の試み!
第1章 広田弘毅(開廷に先立って
東京裁判と『落日燃ゆ』 ほか)
第2章 近衛文麿(天皇の次に偉い男
金はなかった、人気があった ほか)
第3章 松岡洋右(外務省「大陸派」
伏魔殿、帝国外務省 ほか)
第4章 木戸幸一(自称「野武士」、ゴルフはハンディ「10」
名家の坊やが抱えたルサンチマン ほか)
第5章 昭和天皇(初陣の日中戦争
勃発からひと月で海軍の戦争に ほか)

「歴史認識」とは何か 対立の構図を超えて」大沼保昭/江川紹子
以前(2016年)読んで勉強になったので、再読した。
聞き手が江川紹子さんで、大沼保昭さんがレクチャーする形式。
P4
東京裁判は、日本という国家を裁く裁判ではなく、あくまでも戦争の主要責任者の個人的な刑事責任を裁く裁判でした。
P15
米国の原爆投下とかソ連の日ソ中立条約侵犯など、連合国側の違法行為を弁護側が取り上げようとしても、この裁判(東京裁判)には関連性がないということで、許されなかったことです。
P17
中国政府が犠牲者の数を過大に主張してきたことは冷静に批判すべきですが、南京で日本軍が虐殺行為を犯してしまったことそれ自体は認めるべきでしょう。東京裁判でこの責任を問われて死刑になった松井石根大将も、部下たちのこの戦争違反を阻止できなかったことを深く悔いていたのです。
P23
日本国民は、自国民に300万以上の犠牲を強いた指導者を、自分たちで裁くことをしなかった。他者が裁いた裁判を、あるいは肯定し、あるいは批判し否定するということで終えてしまっている。
P65
中国共産党の立場は、日本の人民も中国の人民と同じく日本の軍国主義の犠牲者であって、賠償を請求すれば同じ被害者の日本人民に払わせることになる、というものでした。(中略)この立場はその後ずっと一貫していて、日本の首相の靖国神社参拝に中国政府が神経を尖らせるのも、このためです。
P71
悠久の文明大国である中国が、1840年のアヘン戦争から欧米列強と日本から侵略され、辱められてきという意識が徹底しています。「国恥百年」ということばは全国民に共有されており、1915年の対華21ヵ条要求を受諾した5月9日、1937年に日中戦争が勃発した7月7日、1931年に満州事変が勃発した9月18日などは、「国恥日」とされている。
P78
占領軍が敗戦後、戦争を「大東亜戦争」と呼ぶのを禁止して、「太平洋戦争」で統一されます。
P122
日本ばかり責めるけれど、韓国にも慰安婦はいたではないか。ベトナム戦争のとき派兵された韓国軍はベトナムで一体どれほどひどいことをやったんだ。中国は、南京大虐殺だと日本をさんざん非難するけれど、自分のところであれだけ人民弾圧をやっているではないか。毛沢東は大躍進や文化大革命で自国民を何百万人死なせたんだ。チベットやウイグルでの大規模な抑圧、人権侵害は何なんだ。そういうことをやっていながら日本を批判できるのか。あるいは、欧米はあれだけ列強として植民地支配をやっておきながら、日本に説教を垂れるのか。自分たちは、旧植民地の膨大な数の人々に、日本のように反省を示して謝罪をしたのか。これは、素朴な、人としてごくあたりまえの不公平感だとおもうのです。
もちろん、他国が悪いことをやっているからといって、日本が悪いことをやってもいい、ということにはならない。そういった居直りは自らを貶めるものでしかない。ただ、日本もこれまでそれなりに過去の行為を反省してきたのだから、中国や韓国もそこをちゃんとみて、わが身を振り返りながら日本に接してほしい。
P128
同報告書(クマラスワミ報告)には、後に虚偽と判明した吉田清治氏の女性「奴隷狩り」証言も記載されています。2014年に『朝日新聞』が吉田証言の記事を取り消したあと、日本政府はクマラスワミ氏に修正を求めましたが、同氏は吉田証言だけが根拠ではないといって応じませんでした。(慰安婦問題は、吉田清治氏、植村隆 氏のような人物がいたせいで、よけいこじれてしまった。マスコミも、その証言をそのまま信じて報道拡散して、日韓関係をより悪化させた)
P138
慰安婦問題にかぎらず、第二次大戦と植民地支配にかかわる諸問題について、日本は法的責任を認めないが、ドイツは認めた、ということもよくいわれますが、これは誤りです。ドイツが認めてきたのも道義的責任です。
P162
日本の首相が元慰安婦のところへ行き、深々と頭を下げてその手を握り、その様子がメディアを通して広く伝えられれば、元慰安婦の方々の多くの満足も得られるし、韓国国内でも国際社会でも、慰安婦問題で傷ついた日本の名誉は大きく回復される(後略)
(キスまでしなくてもハグのような象徴的なパフォーマンスは必要、かもしれない。ヴィリー・ブラント西独首相が1970年にポーランド・ワルシャワを訪問した際、ゲットー・英雄記念碑の前で跪いて黙祷を捧げたそうだ。こういう分かりやすい形で反省と謝罪を表現して、国際社会で評価された。←P195、日本のリーダーに必要なのは、メディアを意識したパフォーマンスかも。こういったことを早くにやっておけば、ここまで日韓関係が、こじれなかったかもしれない)
©Bundesregierung Photo: Engelbert Reineke
ワルシャワでひざまずいたブラント Brandts Warschauer Kniefall
P166
植民地支配のために現地の人々を制圧することも、「野蛮人をキリスト教化する」などの論理で正当化されていました。
P168
スペイン、ポルトガルに続いて、オランダ、英、仏、ベルギー、ドイツ、ロシア、さらに米国も世界各地を植民地化した。こうした国々には植民地支配が悪であるという観念はほとんどなかったし、そういう国々がつくり運用した国際法も、植民地支配を認め、むしろその道具として機能した。19世紀後半には、欧米の白人の間で、自分たちのすぐれた文明をアジアやアフリカの「未開」「野蛮な民族」にもたらす尊い義務がある、という考えが流布します。
P170
19世紀から20世紀初頭の欧米中心的な国際社会で、戦争は国家政策のひとつと考えられていました。外交の延長線上に戦争があり、外交と戦争を組み合わせて国家利益を実現するというのが、ヨーロッパの古典的な国際関係だったわけです。
P172
1920年代に戦争を違法化すべきだという運動が盛り上がり、1928年に不戦条約が結ばれる。これで戦争が国際法上はじめて、原則として禁止されました。世界が戦争を違法なものにしようとして、国際法上画期的といってよい成果が出た。
しかしその三年後に、日本が満州事変をおこしてしまったのです。
P186
そもそも国連は、米英仏中ロという軍事大国のいずれかが違法な武力行使をおこなっても、それを制裁によってやめさせることはできない。実際、ソ連のハンガリー、チェコ、アフガニスタンへの武力行使、米国のベトナムやカリブ海諸国への武力行使やその威嚇、英仏のエジプトへの武力行使、中国のベトナムへの武力行使など、米英仏中ロは、自分たちが主導してつくった国連憲章に違反する武力行使をしばしばおこなってきました。
P192
かつての欧米列強は、日本とドイツを批判することはやっても、自分たちの植民地支配責任や帝国主義政策、他国への侵略行為に関しては、ほとんど反省の意を表していない。典型は米国で、ベトナム戦争であれだけ枯れ葉剤を使い、その結果多くの障碍児が生まれるような残虐なことをしておきながら、ベトナムに対してまったく謝罪していません。フィリピンを植民地支配したという意識もない。フランスにしてもイギリスにしても、植民地支配についての責任意識、帝国主義的外交への反省は知識人もほとんどないし、かつての植民地支配への謝罪も、日本に比べてきわめて限られたものでしかない。(オーストラリア、ニュージーランドも日本の捕鯨を激しく批判するが、自分たちは先住民を絶滅の危機に追いやっている。どーいうこと?)
P198
異民族支配それ自体が悪という意識が高まるのは、ナショナリズムが重要な意味をもつようになった19世紀以降のことなのです。それ以前は異「民族」――「民族」という意識自体、基本的に近代以降のものです――支配は、世界各地でどこにもあある現象でした。
P199
香港は1997年に中国に返還されますが、当時、欧米の発想が支配的な国際社会の感心は、もっぱら「英国が育て上げた香港の民主主義が、共産党独裁の中国の下で維持されるだろうか」というものでした。(中略)
返還式典でも、アヘン戦争の流血や植民に支配についての英国からの謝罪はありませんでした。最後の総督だったクリストファー・パッテン氏は記者会見で、「(英国が香港の)民主制度を発展させた」と述べ、過去1世紀半に及んだ植民地支配について謝罪しないのかと聞かれると、「アヘン貿易まで正当化しようとは思わないが、一体、今何を謝罪するのか。この未来志向の都市で、19世紀の話をするのは驚くべきことだ」と述べています。(1997年といえば、鄧小平氏が亡くなった年。気になって香港に行ってきたので覚えている。返還の時のスピーチも、気にして新聞を読んだけど、「謝罪の言葉がないなあ」「むしろ、自らの統治について自画自賛だし」と、感じた)
P208
ある在日韓国人が、「韓国の三大紙(『朝鮮日報』『中央日報』『東亜日報』は、日本の『産経』みたいなもの」と語っていましたが、これは言い得て妙です。(対日批判をした方が発行部数が伸びるのだろうか?韓国メディアは反日を煽ってばかり。だから、「日本のメディアは韓国メディアへの働きかけに努めてほしい」と著者は語っている)
【ネット上の紹介】
日中・日韓関係を極端に悪化させる歴史認識問題。なぜ過去をめぐる認識に違いが生じるのか、一致させることはできないのか。本書では、韓国併合、満洲事変から、東京裁判、日韓基本条約と日中国交正常化、慰安婦問題に至るまで、歴史的事実が歴史認識問題に転化する経緯、背景を具体的に検証。あわせて、英仏など欧米諸国が果たしていない植民地支配責任を提起し、日本の取り組みが先駆となることを指摘する。
[目次]
第1章 東京裁判―国際社会の「裁き」と日本の受け止め方(ニュルンベルク裁判と東京裁判
「勝者の裁き」と「アジアの不在」 ほか)
第2章 サンフランシスコ平和条約と日韓・日中の「正常化」―戦争と植民地支配の「後始末」(サンフランシスコ平和条約とは何か
寛大だった連合国との講和 ほか)
第3章 戦争責任と戦後責任(「敗戦責任」から「戦争責任」へ
被害者意識と加害者認識 ほか)
第4章 慰安婦問題と新たな状況―一九九〇年代から二十一世紀(なぜ慰安婦問だけが注目されるのか
慰安婦問題は日韓問題? ほか)
第5章 二十一世紀世界と「歴史認識」(十九世紀までの戦争観と植民地観
第一次世界大戦と戦争の違法化 ほか)

「昭和の名将と愚将」半藤一利・保阪正康
これは再読。
レベルの高い対談だったので、読み返したくなった。
やはり良かった。
P18
半藤:日本人は今でこそ最後の一兵まで戦い、絶対に降伏しないと思われているが、本来はそんなことはなく、戦国時代では誰も玉砕せずに主将が腹を切るとすぐ城を明け渡している。だから、日本人はメンツが大切なのであって、それさえ留意すれば降伏するはずだ、と言う認識がアメリカ側にはあったんですよ。だから、特攻とか玉砕というのは、日本の文化にはないわけで、どこかで日本人は変調をきたしたに違いない。
P20
保阪:松岡洋右は国際連盟を脱退して帰国したときに横浜で大歓迎を受けています。
半藤:国連脱退は言ってしまえば新聞が推進した。
P18
半藤:薩長は攘夷を決行しようとして、薩英戦争や下関戦争で、列強にコテンパンに負けます。このままではダメだから、文明を取り入れて、富国強兵をしてから改めて攘夷をしようと方針転換をするんです。これは西郷隆盛も言っています。そして明治維新以降も、攘夷の精神は死んでいない。
(中略)
だから、昭和の初めあたりから、列強入りした日本に欧米から圧力がかかると、実際にはたいした外圧ではなくて日本が自ら招いたものにもかかわらず、すぐに過剰反応している。
P52
半藤:小畑敏四郎は軍令畑で「作戦の鬼」と呼ばれた人だから、とにかく対ソ戦略を進めようとするのに対して、永田鉄山は、国力の増強を第一に考えて、満洲、ついで中国の権益を抑えて、対ソ戦はそれからだという意見。だから、最後には大喧嘩になってしまう。
保阪:この違いが後に、小畑は皇道派、永田は統制派と分かれていくんですね。
半藤:2.26事件で討伐されて皇道派が力を失うと、統制派が力を持ち始めて「中国一撃論」を主張し始める。これは石原の意見と対立してくる。それで杉山元が天皇に「1ヶ月で片付きます」といって日中戦争に突入するんですが、永田が生きていたら、果たして日中戦争まで入っていったのか・・・・・・。(中略)
東條は、その後、永田の後継者という看板を背負って登場してきますが、思想まで継承しようとしたとは到底思えませんね。その意味では永田を利用したとも言えます。
P62
半藤:米内(光政)、山本(五十六)、井上(茂美)というのは会社組織にたとえるなら、米内がのんびり社長、山本が歯に衣を着せぬ専務、井上が厳格な経理部長といったところですよ。(2.26事件当夜、米内は、築地の芸者のところにいて、横須賀鎮守府指令府にいなかった。カミソリと言われた井上が万事心得ていたので、米内がいるかのように振る舞って事なきを得た・・・P61)
P71
半藤:私は太平洋戦争は薩長が始めて、賊軍が終わらせたという持論なんです。(米内光政=盛岡藩、井上成美=仙台藩、鈴木貫太郎=関宿藩、山本五十六=長岡藩)
P94
半藤:勇士の勇敢敢闘は作戦のまずさを補うことはできない。作戦がいくら巧緻でも大本営の戦略の失敗を補うことは誰もできないんです。
P108
半藤:開戦前に軍令部が、山本(五十六)の下につける参謀長を宇垣纏にしようとした際に、山本が「宇垣は日独伊三国同盟に賛成した」という理由で大反対をして、かわりに伊藤(整一)が参謀長になったという経緯がある。四ヶ月後、今度は永野(修身)が伊藤を軍令部次長にほしがったときには、さすがに山本も反対できなかった。二度目ですからね。それで仕方なく伊藤の軍令部次長就任を承認したんです。しかし、その伊藤の後任の参謀長として来たのがけっきょく宇垣纏(笑)。だから、開戦直前になって司令長官と参謀長は口もきかないほどの間柄という妙な人事構成になった。
P111
半藤:彼(伊藤整一)が名将と呼べるのはやはり「大和」での出処進退が見事だったという点につきる。若い人を助けて、自分だけ死んだことによってすべてチャラになってしまった。
保阪:軍人は、死ぬことで責任を取れるんですね。
P113
保阪:しかし、伊藤も「大和」の出撃には当初「無謀ではないか」と反対しますよね。
半藤:ええ。命令する草鹿(龍之介)のほうも承服しかねているから、なかなか説得できない。それで最後に草鹿が、有名な「一億総特攻の魁となっていただきたい」という台詞を言うと、「わかった。作戦の成否はどうでもいいということなんだな」と伊藤は実に穏やかな顔をして承服したそうです。
P134
半藤:牟田口(廉也)さんが撤退させなかったのは、たぶん勲章が欲しかったからだと思いますよ。なにせ「牟田口閣下の好きなもの、1に勲章、2にメーマ、3に新聞記者」と陰口を叩かれていたそうです。メーマとはビルマ語で女性に意味です。ビルマ女性が大好きだった。3番目は、新聞記者に大口を叩くのが好きだという意味です。
保阪:インパール作戦に従軍した京都の部隊の兵士たちに話を聞いたことがあるんですが、牟田口の名前が出た途端、激高する人もいましたね。仲間が「水、水」とうわごとを言いながらバタバタと死んでいったというような悲惨な話を数珠を握り締めながら語るんですが、その人は「牟田口が畳の上で死ぬのだけは許せない」と言ってました。
半藤:インパール作戦は、どのくらい亡くなったんでしょうかね。
保阪:8万人行って、7万人近くの兵士が死んだという話もあるそうです。とにかく白骨街道といわれるほど相当な数の人が死んでますよね。
「生きて虜囚の辱めを受けず…」が有名な「戦陣訓」について
P158
軍人勅諭があるのに、また「戦陣訓」なんて、屋上屋を重ねるようなことをしたのは、東條の周りにいた師団長クラスの連中が、ゴマすりのために作らせたという側面があるように思う。
(中略)
石原莞爾なんかは部下に読むなと言っていたそうですからね。
P170
半藤:山本が死んだとき、新橋の芸者さんで恋人だった河合千代子さんという人がいるんですが、この人が山本五十六が書いたラブレターを持っていたんです。(中略)これらがまことに人間味があって面白いんですよ。千代子と一緒に出かけたことのある安芸の宮島から、山本が手紙を書いているんですが、「鹿がクウクウといっとったからウンヨシヨシと言ってやりました」とか何とか(笑)。
ノモンハン事件
P177
保阪:この要綱を実際に起案したのがほかでもない、関東軍司令部作戦課の辻政信ですよ。それを作戦主任の服部卓四郎が承認した。そして、このとき大本営の参謀本部作戦課長はというと、稲田正純でしたね。
半藤:ええそうです。司馬遼太郎さんが後年ノモンハン事件を書こうとしたとき、たしか昭和50年ごろでしたか、稲田正純の話を聞きたいというので私と一緒に会いに行ったことがあるんですよ。(中略)「こんなやつが作戦課長だったのかと心底あきれた」という司馬さんの言葉を覚えていますよ。
シンガポール華僑虐殺事件
P188
半藤:日本軍ではその数6千人、華僑側では4万人と言っています。(中略)
保阪:あれは、抗日分子が後方攪乱を行って占領ができなくなるのを阻止するという理屈、ただ一点で行われた蛮行でした。この粛清計画を立案したのが辻政信その人。
インパール作戦
P198
半藤:この作戦には不人気となっていった東條英機内閣への全国民の信頼を再燃させるために、という政治的な意図があった。そして川辺と牟田口は盧溝橋事件のときの旅団長と連隊長でした。ビルマでこの愚将コンビがふたたび出会って最悪の大作戦を推進したのです。
(中略)
保阪:牟田口は前線から離れた「ビルマの軽井沢」と呼ばれた地域で栄華を極めた生活をしているといううわさは矢のように前線の兵士に伝わってきたようですし、実際に牟田口はそこからひたすら「前進あるのみ」と命令をだしていた。
P194
しかし結局服部(卓四郎)は戦後、再軍備の最高の旗振り役になりましたね。「服部機関」が中心になって、再軍備の路線を突っ走っていった。
P247
保阪:これは学徒でいった整備兵の人から聞いた話ですが、知覧でも、搭乗前に失禁したり失神したりする特攻隊員がいたというのです。それを抱え込んで無理やり乗せたというですね。その人も怖気づいた兵隊を抱え込んで飛行機に乗せたことがあり、そのことがいまでも心の傷として残っていて消えない、と言っておられました。ご存じの通り、特攻隊員の遺書は悲惨そのものですよ。「こんな作戦をする国が勝つわけがない。けれどいかざるを得ない」とか・・・・・・。
P252
保阪:僕は「特攻」というのは文化に対する挑戦だと思っています。あの時代の指導者の、文化に対する無礼きわまりない挑戦だったと。
半藤:「特攻」に対する考察がし尽くされぬままなら、日本は軍隊なんかつくっちゃいかんと思いますよ。
【参考図書】


「昭和史 1926-1945」半藤一利
「昭和史 戦後篇」半藤一利
【ネット上の紹介】
責任感、リーダーシップ、戦略の有無、知性、人望…昭和の代表的軍人二十二人を俎上に載せて、敗軍の将たちの人物にあえて評価を下す。リーダーたるには何が必要なのか。
名将篇(栗林忠道
石原莞爾と永田鉄山
米内光政と山口多聞
山下奉文と武藤章
伊藤整一と小沢治三郎
宮崎繁三郎と小野寺信
今村均と山本五十六)
愚将篇(服部卓四郎と辻政信
牟田口廉也と瀬島龍三
石川信吾と岡敬純
特攻隊の責任者―大西瀧治郎・冨永恭次・菅原道大)

「封印されていた文書(ドシエ)」麻生幾
昭和の重大事件が取りあげられ、掘り起こされている。
P392
金丸:北海道を始めとする道路や空港の建設、整備新幹線の建設など国の発展につながる基礎整備など大規模公共事業に私が全力を傾けていたので、ゼネコン関係などからは感謝されていました。またいわゆる建設族であるととともに、運輸族、郵政族であったことからも、毎年のお歳暮やお中元に裏献金を頂いていとではないかと思います。
下山事件の頃の警視庁
P400
1係は「殺し」、2係は「タタキ(強盗)」、3係は「進駐軍(連合軍)関係の犯罪」と別れていた。現在の捜査第1課では20もの係に分かれ、計約240名の捜査員が存在することと比べれば、まだ戦後の混乱期であるとはいえ、現在の所轄警察署並みの陣容だった。
ミグ25が函館に強行着陸した事件
P503
「亡命の理由、率直に聞かせてもらいないか?」
ベレンコは語った。
「軍では全く昇格しなかったし、同期の連中が昇格してゆくのに、自分がいかにホサれていたか」
「それだけか?」
「ベレンコは1度口を閉じた後、淡々とした口調で言った。
「それに妻にも我慢ならなかった・・・・・」
(亡命の理由が妻への腹いせ、って?!・・・日米露軍事衝突で、あやうく第3次大戦か!って言われたのに)
【ネット上の紹介】
ホテルニュージャパン火災と戦った消防隊の秘められたオペレーション、あさま山荘事件で封印されていた死闘の真実、そして三菱銀行「梅川事件」の鬼気迫る犯行内容―日本人を驚愕させたあの事件は、重大な事実が伏せられていた!トップ・シークレットを追って、衝撃的な文書や証言を引き出し、10大事件の全貌と真相に迫った傑作ドラマ。
序章 アメリカ同時多発テロ―封印されたはずの文書
三菱銀行事件犯人「梅川昭美」VS大阪府警捜査第1課
幻のオウムVS自衛隊治安出動
あさま山荘銃撃攻防―未公開資料の全貌
ホテルニュージャパン大火災埋もれたままの消防隊六百七十七名全記録
特捜部VS田中総理 知られざる密室の攻防
ペルー日本大使公邸事件―存在しなかった「国家の決断」
金丸逮捕劇の知られざる真実
下山事件50年目の解決
ベレンコ亡命で第3次世界大戦への悪夢
北朝鮮「侵入船」を迎え撃った緊迫の8時間

【関連図書】・・・昭和史と言えば、先にこちらを押さえるべき、と思う。

「昭和史 1926-1945」半藤一利
「昭和史 戦後篇」半藤一利
「昭和史裁判」半藤一利/加藤陽子
「それでも、日本人は「戦争」を選んだ」加藤陽子


「地図と写真でみる半藤一利昭和史1926-1945」
半藤一利さんの「昭和史」の副読本とも言うべき作品。
写真と画像多数掲載により、理解しやすい。
有名な203高地の位置も知ることができた ↓
P32
のちに日本が軍縮条約から脱退してしまい、結果的に自由に軍艦をつくれるようになったが、海軍は、従来通りの超弩級戦艦中心の軍備を整えるべきだという「艦隊派」と、大きな軍艦などこれからは無用であり、そのぶん「中攻」を核とした航空兵力を整えるべきだとする「条約派」に分かれることになった。
もっとも、軍艦を自由につくれないということは、それだけ艦長や○○長といった役職(ポスト)が減ることと直結する。恩給(年金)にも関係してくるだろう。
海軍であろうと陸軍であろうと、公務員という立場を考えると、それだけで「反対」の声があがるのは今も昔も変わらない悪癖なのかもしれない。(国の命運が「恩給」に左右されたのね)
P47
(ノモンハン事件の)本質的な失敗は小松原(道太郎)のソ連軍への過小評価にあった。とりわけ火力差は圧倒的で、ソ連軍が多数の戦車を投入したのに対して日本はゼロ。化学戦車の火炎放射も日本軍を苦しめた。これに対して辻(政信)は、「師団の団結が薄弱であること、対戦車戦闘の未熟さ」と責任を現場に押しつけている。(中略)辻はのちにマレー作戦の際に作戦参謀でありながら任務を放棄し命令系統を無視して第一線で指揮をとり、また無理な作戦計画を立てて失敗している。(「昭和の名将と愚将」の愚将篇のなかで、牟田口廉也、服部卓四郎、辻政信が挙げられている・・・「昭和の名将と愚将」半藤一利・保阪正康)
P56
ハル・ノートを提示した段階で戦争を覚悟していたルーズベルトは、自らの陸海軍に対しそれぞれの長官を通じて現場部隊指揮官にまで、さらなる条件をつけた。最初の一撃を必ず日本側に行わせることだ。これは、アメリカ国民向けに「日本が悪く、アメリカは正しい」を強調し、開戦に賛同させるためのルーズベルトの「最後の仕上げ」だったといってよかろう。
P64
昭和天皇は、張作霖爆殺事件に関する田中義一首相への問責、2.26事件における反乱軍に対する討伐命令、そして終戦の聖断という3つの局面で、政治への関与を見せている。
P77
「太平洋戦争でこれほど被害の少ない戦いはない。レーダー開発に長い時間と費用を費やしたことが無駄でなかったと証明された」と旗艦空母「レキシントン」の戦闘報告書にまとめられている。
P92
天皇は終戦の詔勅を用意するよう内閣に命じ、ラジオを通じて全国民にポツダム宣言受け入れを直接伝えると決断した。
この結果に、陸軍では阿南陸相に辞任を迫る動きがさらに起こったが、阿南は「聖断が下った以上、陸軍は一糸乱れず承詔必謹を貫くべき」として動かなかった。これが本来の統帥権尊重の姿勢だろう。(阿南は徹底抗戦派と言われることもあるが、これを読むとそうではないように感じる。なお、阿南は終戦の際に自決している。Wikipediaによると人柄について次のようにふれている。『陸軍でも家庭でも、大声をあげることも、他人を叱ることもほとんどなく、(中略)たまにする夫婦喧嘩でも先に折れるのは常に阿南の方であった』)

【関連図書】





「昭和史 1926-1945」半藤一利
「昭和史 戦後篇」半藤一利
「世界史のなかの昭和史」半藤一利
「昭和の名将と愚将」半藤一利・保阪正康
「B面昭和史1926-1945」半藤一利