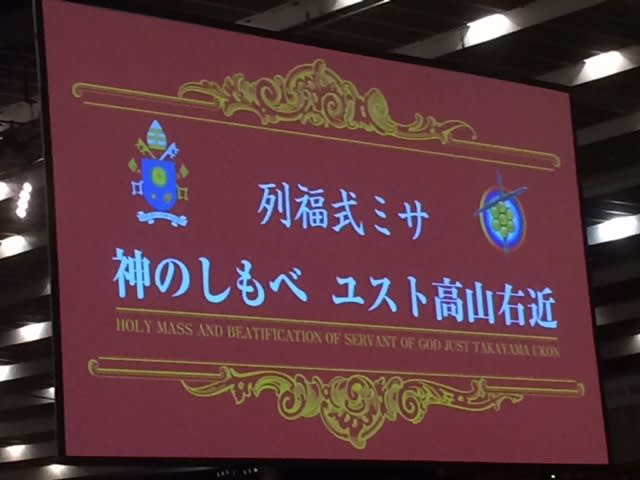「悠遠の人 高山右近」by 塩見弘子
史実を踏み外さないようにはしながらも、歴史書というよりも小説かな?
それは別に悪いことではなく、小説っぽい仕立て故に、その時々の右近の気持ちを書き綴る部分が多く、右近の想いを推し量るのに手がかりとなる言葉がたくさんあった。
.

史実を踏み外さないようにはしながらも、歴史書というよりも小説かな?
それは別に悪いことではなく、小説っぽい仕立て故に、その時々の右近の気持ちを書き綴る部分が多く、右近の想いを推し量るのに手がかりとなる言葉がたくさんあった。
.