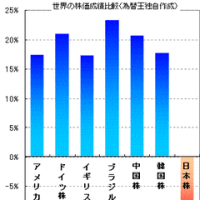マスターの実演に見入る観客
河端「やあ、こんにちは。なんだか春めいてきたね。」
道端「はい。暖かいですね。今日は、先日お約束の話を、」
河端「ああ、オウムか。」
道端「いえ。オウムじゃなくて、あんでるせんです。」
河端「あんでるせん?」
道端「はい。雲仙普賢岳が噴火した後ですから、もうずいぶん前のことです。ちょうど梅の咲く今頃の季節でした。同僚と長崎のあんでるせんという喫茶店に行ったことがあります。他の用事のついででした。雑誌などでマスターが超能力で評判でしたので、ひやかしにいったような次第です。」
河端「超能力喫茶か。すごいな。」
道端「はい。一階がマスターの親御さんのやっている果物屋さんで、二階が喫茶店でした。喫茶店の前の道路には10時の開店前から、お客さんが列を作っていました。みんなマスターの超能力を見るのが目的です。」
河端「料金は?」
道端「マスターが超能力を披露する時間は決まっていました。その時間に来店して、飲み物とケーキを注文すれば無料で見学OKでした。」
河端「なかなか良心的だな。」
道端「はい。ケーキも美味しかったです。コーヒーとケーキを賞味して、しばらく待ちくたびれた頃に午前の実演でした。写真を示しましたが、喫茶店一杯の人が、カウンターの回りに詰め掛けて、固唾を呑んで、マスターの実演を見守ってました。」
河端「実演はどうだったんだい。」
道端「なかなか見事でした。お客さんが適当に入れた電卓の番号を当てたり、空中に紙幣を浮かせたり、つぎからつぎへと繰り出しました。間近で見てても、種もしかけもありそうには見えません。話術も淡々とユーモラスで巧みでした。コインを小さな口の瓶に入れるときなど、分子の間は実際はすかすかで、こうやってその間をうまく合わすとなどといって、やってました。先日、お客さんがうっかり瓶に手を通してしまって後で困った、ちよっとやってみますか、などと話しかけられたお客さんは、怖がって手をひっこめてました。」
河端「なるほど。道端君はすなおな観客でもなさそうだがな。」
道端「はい。はじめは疑いの気持ちで種を見破ってやろうと見てました。瓶の実演でも、では、私が手を出してちょっとやってみましょうかと言おうとしたのですが、とどまりました。」
河端「なぜだい。」
道端「大勢のお客さんが夢中になっているに水をさすような気がしてためらわれたからです。それに、もしかして抜けなくなったらと、ちらと思ってしまいました。」
河端「ちらとか?」
道端「はあ。それで、マスターも後ろで疑わしそうにしているのがいるなとでも思ったのかもしれません。マスターから指名されました。」
河端「いよいよ道端君が実験台か。」
道端「はい。そうです。小さな紙と筆記具を渡され、自分しか知らないことを書くようにいわれました。私は、周りに覗いている人とか、隠しカメラとかないか注意して、絶対に見られないように、しっかり自分の体の前にガードして書きました。そしてそのまま何重にも折りたたみました。」
河端「それで。」
道端「マスターは折りたたんだ紙をうけとり、みんなの前で串にさして燃やしてしまいました。それから、さっき書いたことをイメージするように言われました。頭の中のイメージを読むからというわけです。」
河端「どうだったんだ。」
道端「全部当てられてしまいました。ショックでした。」
河端「なんか恥ずかしい事でも書いたのか。」
道端「違います。生年月日とか、そんなことだけです。透視能力は本当にあるのではと思いました。観念動力もあるだろうと思いました。」
河端「すこしは疑問には思わなかったのか。」
道端「はい。根がまじめなものですから。実演が終わった後で、マスターに素晴らしいですね、これを何か実用できませんかなどとたずねました。そしたら、マスターもなかなかです。医学部の先生がこの能力をマイクロサージェリーに使えないかとなどと言ってました。ますます感心しました。」
河端「実にまじめでよろしいな。」
道端「それで、一階の果物屋さんの両親のところへも挨拶にいきました。お宅の息子さんはすごいですねと。そしたら、うちのは昔からああいう事が好きでと、きまりの悪いような表情をしていました。」
河端「しかし、何事にも批判的な道端君が、なんでまたそう簡単に信じてしまったのかな。」
道端「実は、喫茶店に行く途中で同僚と、ブライアン・ジョゼフソンの話だの、アインシュタイン・ポドルスキー・ローゼンのパラドックスだの、量子的ゆらぎの自己組織化の可能性もなどと、しち難しい話をして、頭がくらくらしてたのがいけなかったかもしれません。喫茶店のお客さんの奇跡の顕現を待ち望むような熱気の影響もあったと思います。」
河端「なるほど。それでその後どうなったんだい。」
道端「世界観の根底をゆさぶられるような思いでした。マスターだけではない、超能力をもった人が念じたら、知らないうちに心臓がとまるかもしれない。そういう不可解な力が飛び交う世界は、底が抜けたようで恐ろしいと思いました。一方で、もし超能力が本当なら、応用範囲はものすごいと思いました。だからオウムの弟子の気持ちがわかります。ただ冷静になってみると、そんなすごい能力が本当なら、なにを悲しくて喫茶店のケーキの付録にするんだろうとか、当たり前の疑問もうかんできました。それに、マスターの両親の言葉やきまりの悪いような表情がどうもひっかかりました。」
河端「やっと気がついたか。」
道端「マスターの実演の解説がないか探してみました。そしたら、ミスター・マリックの超魔術や手品の本にほとんど仕掛けが書いてありました。分かってみると単純なものばかりでした。」
河端「道端君の透視はどんな仕掛けだったんだい。」
道端「たぶん紙の台にカーボンか何かあって、台に書いたことがうつしとられたと思います。串にさして燃やしてたり、紙に注意を誘導していましたから。鍵に紙縒りで紙をしこみ、箱を開けるときに紙が箱に落ちるようにするなど、似たような手品は他にもあります。この場合も箱に注意を誘導します。鍵はノーマークで、そこに助手がしこみます。」
河端「そんなところかな。」
道端「そんなこんなで一時期、手品に凝りました。コインを2つに割って周りをゴムでとめた道具なども買いました。小さな口の瓶のなかにコインを入れるマジックのネタです。家族の前でやったら、ちょっとそれ見せろで、すぐにネタばれでした。そこで、知り合いの米国人と一緒に喫茶店にいって、実はこの人は物理学者(これは本当)で私の超能力を調べにきた、物質は分子の間は実際はすかすかで、こうやってその間をうまく合わすとなどと、アンデルセンのマスターのトークを真似してやってみました。大成功でした。その喫茶店の美しい女主人は、まじまじと驚嘆の眼で私を見つめていました。すっかり信じてしまったみたいです。」
河端「道端君も隅に置けないな。」
道端「いえ。その場でちゃんと種明かしをしました。」
河端「そうか。今日、話しを聴いてみて、超能力のトリックは、科学者なんかが案外だまされて、マジシャンの方が見抜くという理由がわかったよ。うっかりふつうに考えると脇の抜け道には気づかないからな。」
道端「はい。その意味でいわゆる超能力者とか、マジシャンは、すぐれた心理技術者だと思います。そういうのを除いて、ぎりぎり本当の超能力があるか、ないかですが、確かヒュームは奇跡論で、奇跡とされる事象の存在を認定するか否かの基準として、奇跡とされる事象が存在するという報告が誤りである確率Aと、その奇跡とされる事象が既存の知識体系に照らして存在しうる確率Bを比較して、確率Aが確率Bより小さい場合にのみ、存在を認定しようといっていたと記憶します。」
河端「奇跡の確率論は難しいな。確率Bの見積もりは人によって違うだろう。」
道端「はい。単純に言えば、科学的な常識外の事象には、事象の報告が誤りでないという検証がより厳しく求められることになります。この点で、いわゆる超能力の報告は再現性がなく失格だと思います。もし再現性があったら、応用も可能でしょうし、日の目をみないことはないでしょう。それを、こそこそ、いいわけがましく、あったように示すのは、結局のところ、ないからだと判断した方が妥当でしょう。とにかく、ありそうで、なさそうでと、思わせぶりなのは気に入りません。あるなら、あるで、きっちり出してほしいです。」
河端「その辺がオカルトなんだろうな。」
道端「江戸時代の哲学者、三浦梅園は「枯木に花咲くより、生木に花咲くに驚け」と言っています。至言だと思います。花が咲いて、それを見てといった、日々繰りかえされる出来事こそ、驚嘆すべき宇宙の不思議だと思います。それをそう思わないのは、たんに慣れっこになっただけです。」
河端「それをそう思うには、それなりの認識の前提も必要なんだろうな。今日は、道端君の体験談なかなか面白かったよ。確率論だの、ややこしい話はまたにしよう。」
道端「はい。わかりました」
河端「やあ、こんにちは。なんだか春めいてきたね。」
道端「はい。暖かいですね。今日は、先日お約束の話を、」
河端「ああ、オウムか。」
道端「いえ。オウムじゃなくて、あんでるせんです。」
河端「あんでるせん?」
道端「はい。雲仙普賢岳が噴火した後ですから、もうずいぶん前のことです。ちょうど梅の咲く今頃の季節でした。同僚と長崎のあんでるせんという喫茶店に行ったことがあります。他の用事のついででした。雑誌などでマスターが超能力で評判でしたので、ひやかしにいったような次第です。」
河端「超能力喫茶か。すごいな。」
道端「はい。一階がマスターの親御さんのやっている果物屋さんで、二階が喫茶店でした。喫茶店の前の道路には10時の開店前から、お客さんが列を作っていました。みんなマスターの超能力を見るのが目的です。」
河端「料金は?」
道端「マスターが超能力を披露する時間は決まっていました。その時間に来店して、飲み物とケーキを注文すれば無料で見学OKでした。」
河端「なかなか良心的だな。」
道端「はい。ケーキも美味しかったです。コーヒーとケーキを賞味して、しばらく待ちくたびれた頃に午前の実演でした。写真を示しましたが、喫茶店一杯の人が、カウンターの回りに詰め掛けて、固唾を呑んで、マスターの実演を見守ってました。」
河端「実演はどうだったんだい。」
道端「なかなか見事でした。お客さんが適当に入れた電卓の番号を当てたり、空中に紙幣を浮かせたり、つぎからつぎへと繰り出しました。間近で見てても、種もしかけもありそうには見えません。話術も淡々とユーモラスで巧みでした。コインを小さな口の瓶に入れるときなど、分子の間は実際はすかすかで、こうやってその間をうまく合わすとなどといって、やってました。先日、お客さんがうっかり瓶に手を通してしまって後で困った、ちよっとやってみますか、などと話しかけられたお客さんは、怖がって手をひっこめてました。」
河端「なるほど。道端君はすなおな観客でもなさそうだがな。」
道端「はい。はじめは疑いの気持ちで種を見破ってやろうと見てました。瓶の実演でも、では、私が手を出してちょっとやってみましょうかと言おうとしたのですが、とどまりました。」
河端「なぜだい。」
道端「大勢のお客さんが夢中になっているに水をさすような気がしてためらわれたからです。それに、もしかして抜けなくなったらと、ちらと思ってしまいました。」
河端「ちらとか?」
道端「はあ。それで、マスターも後ろで疑わしそうにしているのがいるなとでも思ったのかもしれません。マスターから指名されました。」
河端「いよいよ道端君が実験台か。」
道端「はい。そうです。小さな紙と筆記具を渡され、自分しか知らないことを書くようにいわれました。私は、周りに覗いている人とか、隠しカメラとかないか注意して、絶対に見られないように、しっかり自分の体の前にガードして書きました。そしてそのまま何重にも折りたたみました。」
河端「それで。」
道端「マスターは折りたたんだ紙をうけとり、みんなの前で串にさして燃やしてしまいました。それから、さっき書いたことをイメージするように言われました。頭の中のイメージを読むからというわけです。」
河端「どうだったんだ。」
道端「全部当てられてしまいました。ショックでした。」
河端「なんか恥ずかしい事でも書いたのか。」
道端「違います。生年月日とか、そんなことだけです。透視能力は本当にあるのではと思いました。観念動力もあるだろうと思いました。」
河端「すこしは疑問には思わなかったのか。」
道端「はい。根がまじめなものですから。実演が終わった後で、マスターに素晴らしいですね、これを何か実用できませんかなどとたずねました。そしたら、マスターもなかなかです。医学部の先生がこの能力をマイクロサージェリーに使えないかとなどと言ってました。ますます感心しました。」
河端「実にまじめでよろしいな。」
道端「それで、一階の果物屋さんの両親のところへも挨拶にいきました。お宅の息子さんはすごいですねと。そしたら、うちのは昔からああいう事が好きでと、きまりの悪いような表情をしていました。」
河端「しかし、何事にも批判的な道端君が、なんでまたそう簡単に信じてしまったのかな。」
道端「実は、喫茶店に行く途中で同僚と、ブライアン・ジョゼフソンの話だの、アインシュタイン・ポドルスキー・ローゼンのパラドックスだの、量子的ゆらぎの自己組織化の可能性もなどと、しち難しい話をして、頭がくらくらしてたのがいけなかったかもしれません。喫茶店のお客さんの奇跡の顕現を待ち望むような熱気の影響もあったと思います。」
河端「なるほど。それでその後どうなったんだい。」
道端「世界観の根底をゆさぶられるような思いでした。マスターだけではない、超能力をもった人が念じたら、知らないうちに心臓がとまるかもしれない。そういう不可解な力が飛び交う世界は、底が抜けたようで恐ろしいと思いました。一方で、もし超能力が本当なら、応用範囲はものすごいと思いました。だからオウムの弟子の気持ちがわかります。ただ冷静になってみると、そんなすごい能力が本当なら、なにを悲しくて喫茶店のケーキの付録にするんだろうとか、当たり前の疑問もうかんできました。それに、マスターの両親の言葉やきまりの悪いような表情がどうもひっかかりました。」
河端「やっと気がついたか。」
道端「マスターの実演の解説がないか探してみました。そしたら、ミスター・マリックの超魔術や手品の本にほとんど仕掛けが書いてありました。分かってみると単純なものばかりでした。」
河端「道端君の透視はどんな仕掛けだったんだい。」
道端「たぶん紙の台にカーボンか何かあって、台に書いたことがうつしとられたと思います。串にさして燃やしてたり、紙に注意を誘導していましたから。鍵に紙縒りで紙をしこみ、箱を開けるときに紙が箱に落ちるようにするなど、似たような手品は他にもあります。この場合も箱に注意を誘導します。鍵はノーマークで、そこに助手がしこみます。」
河端「そんなところかな。」
道端「そんなこんなで一時期、手品に凝りました。コインを2つに割って周りをゴムでとめた道具なども買いました。小さな口の瓶のなかにコインを入れるマジックのネタです。家族の前でやったら、ちょっとそれ見せろで、すぐにネタばれでした。そこで、知り合いの米国人と一緒に喫茶店にいって、実はこの人は物理学者(これは本当)で私の超能力を調べにきた、物質は分子の間は実際はすかすかで、こうやってその間をうまく合わすとなどと、アンデルセンのマスターのトークを真似してやってみました。大成功でした。その喫茶店の美しい女主人は、まじまじと驚嘆の眼で私を見つめていました。すっかり信じてしまったみたいです。」
河端「道端君も隅に置けないな。」
道端「いえ。その場でちゃんと種明かしをしました。」
河端「そうか。今日、話しを聴いてみて、超能力のトリックは、科学者なんかが案外だまされて、マジシャンの方が見抜くという理由がわかったよ。うっかりふつうに考えると脇の抜け道には気づかないからな。」
道端「はい。その意味でいわゆる超能力者とか、マジシャンは、すぐれた心理技術者だと思います。そういうのを除いて、ぎりぎり本当の超能力があるか、ないかですが、確かヒュームは奇跡論で、奇跡とされる事象の存在を認定するか否かの基準として、奇跡とされる事象が存在するという報告が誤りである確率Aと、その奇跡とされる事象が既存の知識体系に照らして存在しうる確率Bを比較して、確率Aが確率Bより小さい場合にのみ、存在を認定しようといっていたと記憶します。」
河端「奇跡の確率論は難しいな。確率Bの見積もりは人によって違うだろう。」
道端「はい。単純に言えば、科学的な常識外の事象には、事象の報告が誤りでないという検証がより厳しく求められることになります。この点で、いわゆる超能力の報告は再現性がなく失格だと思います。もし再現性があったら、応用も可能でしょうし、日の目をみないことはないでしょう。それを、こそこそ、いいわけがましく、あったように示すのは、結局のところ、ないからだと判断した方が妥当でしょう。とにかく、ありそうで、なさそうでと、思わせぶりなのは気に入りません。あるなら、あるで、きっちり出してほしいです。」
河端「その辺がオカルトなんだろうな。」
道端「江戸時代の哲学者、三浦梅園は「枯木に花咲くより、生木に花咲くに驚け」と言っています。至言だと思います。花が咲いて、それを見てといった、日々繰りかえされる出来事こそ、驚嘆すべき宇宙の不思議だと思います。それをそう思わないのは、たんに慣れっこになっただけです。」
河端「それをそう思うには、それなりの認識の前提も必要なんだろうな。今日は、道端君の体験談なかなか面白かったよ。確率論だの、ややこしい話はまたにしよう。」
道端「はい。わかりました」