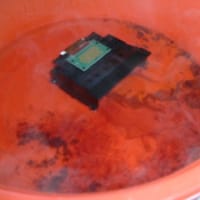とは言うもの結婚していないから、夫婦の機微など理解できるわけもなく
家に帰ると、FF12をダラダラとやるという生活を続けていて、すっかり小説から遠ざかっておりました。
自堕落だなぁ…………(小説を読んでダラダラすることも、自堕落と言えば自堕落だが)。
短編集でも読むか。
と言うことで、選んだのが三浦哲郎「短編集モダイクⅠ みちづれ」。
どこかにありそうな場面に、どこかにありそうな言葉。
壮大な設定も、奇天烈な人物も、ロマンあふれる時代背景も、大仰な登場人物のセリフもなく、日常の一場面を、ちょっと切り取ったようなものばかり。
が、それでいながら、なにか人生のちょっとした(本当にちょっとした)真理を、垣間見たような気分にさせる短編(掌編に近いかもしれません)ばかり。
そんなわけで、たいていの作品には、人生と同じように「救い」も「癒し」もありません。
強いてあるものは「慰め」でしょうか?
作者の特殊な境遇を知っていないと、ちょっと理解し難い作品も無きにしも非ずです。
それに、人生の機微を知らずしては共感できないような場面、設定なので、十代から二十代前半の人が読むと、ちょっとつらいかも。
そこはかとなく、人生に疲れている人(つまりは中年以降)あたりが、ちょうどよい読み頃だと思います。
三浦哲郎の他の作品の感想。
三浦哲郎「ユタとふしぎな仲間たち」ちっちゃいころは、なんか見えるもんだな
家に帰ると、FF12をダラダラとやるという生活を続けていて、すっかり小説から遠ざかっておりました。
自堕落だなぁ…………(小説を読んでダラダラすることも、自堕落と言えば自堕落だが)。
短編集でも読むか。
と言うことで、選んだのが三浦哲郎「短編集モダイクⅠ みちづれ」。
| あ、と妻はちいさな悲鳴を洩らして身を起こした。鳥籠ががたんと鳴った。同時に彼もロを開けたが、声にはならなかった。彼は急いで階下へ降りた。 妻は、まだ驚きから醒めない顔で、両手の拳を顎の下に並べていた。 「ごめんなさい、逃がしちやった。」 「見ていたよ、二階の窓から。どうも危ない恰好だと思ってたんだ。」 逃げたのは雄鳥で、隣の雌鳥は動顛してばたばたと籠のなかを飛び回っている。 「やっと馴れてきたのに……まさか逃げられるとは思わなかったわ。」 「馴れてきたころが危ないんだよ。野鳥は油断がならないんだ。」 二人は、縁先から、塀際に並んでいる背の低い数本の植木の枝々を丹念に見たが、うそ鳥の姿は見当らなかった。あたりに耳を澄ましてみたが、啼き声もきこえなかった。 「だけど、なんで籠のなかに手を入れたりしたの?」 「水の容器を取り出すつもりだったの。あんまり汚れてたから、替えてやろうと思って。」 「だったら、籠を回して、口をこっちへ向ければよかったのに。庭の方へ向けたまんまじゃ、不自然だし、不用心だよ。姿勢が無理だから、どうしたって手のまわりに隙間ができる。」 妻は、訝しそうに彼を見た。 「手のまわりって?] 「はっきりいえば、甲の下のところにね。ほら、こんなふうに。」 彼は、さっき妻がそうしたように、空の鳥籠の上へ覆いかぶさるように身を屈めて、伸ばした右腕の先を籠の口から差し入れて見せた。案の定、上を向いた手のひらには、ただ押し上げるだけの格子戸がひとりでに落ちて隙間を塞ぐが、反対側の甲の下には、確かに思いのほかの空間が生じる。 「ね?鳥はここから飛び出したんだよ。」 すると、意外にも、妻は鳥顔でかぶりを振った。 「違うわ。そこから逃げたんじゃないのよ。」 彼は微笑した。 「いや……君はびっくりしてよく憶えてないんだろうけど、僕は上から見てたんだ。鳥は確かに君の手の甲の下から逃げたまに。」 「違うわ。それはあなたの見間違いよ。」 思わず彼も真顔になって、妻を見詰めた。 「じゃ、どこから逃げたんだ?」 「籠の下の方からよ」と妻はいった。「ちょっと手首が引っ掛かって、上の方だけが持ち上ったんだわ。」 (中略) 彼は、やはり自分の目を疑うことができなかった。鳥は間違いなく、妻の手の甲すれすれに飛び出したのである。それをこの目ではっきり見たのだ。籠は決して斜めに待ち上ったりなどしなかった。 「ねえ、君」と、彼は押し黙っている妻にいった。 「僕は君をとがめてるんじゃないんだよ。僕は怒ってなんかいやしない。だから、正直にいえよ。」 「正直にいってるわ。鳥は籠の下から逃げたのよ。」 妻は平然とそういったが、嘘をついているのは明らかであった。彼には妻という人間が急にわからなくなった。二年前から親しんできて、ようやく結婚まで漕ぎつけた相手が、全く未知の、虚偽に満ちた女に見えてきて、彼は暗澹とした。 三浦哲郎「短編集モダイクⅠ みちづれ」67~69頁 新潮文庫 |
どこかにありそうな場面に、どこかにありそうな言葉。
壮大な設定も、奇天烈な人物も、ロマンあふれる時代背景も、大仰な登場人物のセリフもなく、日常の一場面を、ちょっと切り取ったようなものばかり。
が、それでいながら、なにか人生のちょっとした(本当にちょっとした)真理を、垣間見たような気分にさせる短編(掌編に近いかもしれません)ばかり。
そんなわけで、たいていの作品には、人生と同じように「救い」も「癒し」もありません。
強いてあるものは「慰め」でしょうか?
作者の特殊な境遇を知っていないと、ちょっと理解し難い作品も無きにしも非ずです。
それに、人生の機微を知らずしては共感できないような場面、設定なので、十代から二十代前半の人が読むと、ちょっとつらいかも。
そこはかとなく、人生に疲れている人(つまりは中年以降)あたりが、ちょうどよい読み頃だと思います。
三浦哲郎の他の作品の感想。
三浦哲郎「ユタとふしぎな仲間たち」ちっちゃいころは、なんか見えるもんだな
 | みちづれ―短篇集モザイク〈1〉新潮社このアイテムの詳細を見る |