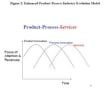「
サービス・マネジメント―統合的アプローチ〈上〉」の第3章(pp.57-74)では,「製造業のサービス事業戦略:製造業にもサービス・マネジメントが求められる理由」に関して書かれている.
この章では,製造業のサービス事業戦略が求められる理由として下記の2点を挙げている.
(1)顧客のニーズに応えるため
モノがある程度いきわたっている現代社会において,顧客が求めているのはモノ自体ではなく,モノを使って価値を生み出すプロセスまで踏み込んだサービスである.
(2)差別化を図るため
競合他社よりも優れたサービスを提供することによって,より魅力的な製品を顧客に提供できる.サービスによって競合他社との差別化を図ることができる.
また,注意点として,(1)に関しては製造業がモノに付加して提供するサービスが必ずしも顧客の求めるものになっていないケースがある(製造業視点の余計なお世話サービス),(2)に関してはサービスを重視するあまりモノを軽視するのは間違いであり,競争に勝つためにはまずはモノで予選を通過するのが前提で,サービスで決勝戦に挑むというのが正しい,と指摘している.
さらに,この章では具体的な製造業のサービス事業戦略として以下の4つを提示している.
(1)顧客情報システムの構築
顧客が困って電話をかけてくる前に予防保全サービスを提供するための情報システムの整備.
(2)サービス提供システムの管理
顧客と一緒に価値を協創するための組織体制(サービスオペレーションスキーム)の整備.
(3)適切なスキルの必要性
顧客との接点となる人材のスキルアップ.顧客との接点が顧客満足度に大きな影響力を持っている.
(4)仮想工場
サービスに必要なすべての活動を所有する必要はなく,外部から調達して管理すれば良い.顧客視点で考え,最も顧客満足にとって重要な部分にリソースを集中すべきで,それ以外の部分はアウトソーシングしても良い.アップルのiPod/iTunesは,まさにこの発想の戦略の成功例であろう.
以上の4つの項目を通じて,製造業がサービスによって顧客の満足と競争優位を獲得するためには,人間・組織・プロセス系の取組みと情報処理・知識処理システム系の取組みの組合せがポイントであることがわかる.サービスサイエンスが,社会科学と情報科学の学際的研究を標榜するのもここに理由がある.
ここで,人間自体は昔と変わっていないわけで,人間・組織・プロセス系は単体ではイノベーションを起しえない.情報処理・知識処理システム系の変化点(Web2.0など)を起点とし,人間・組織・プロセス系との合わせ技でサービスイノベーションを起こすのだと思う.