新選組の歴史的役割については異見百出なのでここでは触れない。
副長の土方の辞世の句といえるという見解が出されたのでここに記録しておきたい。


新撰組副長・土方歳三(1835~69)と最後まで行動を共にした隊士・島田魁(かい)(1828~1900)がまとめたとされる和歌集の巻頭歌が、土方の辞世と考えられるとの説を、幕末研究で知られる霊山(りょうぜん)歴史館(京都市)の木村幸比古・学芸課長が打ち出した。
「従来、辞世とされてきた歌は詠んだ日時の推定が難しいが、巻頭歌は間近に迫る死を覚悟した内容で、亡くなる前日に詠んだ可能性が高い」としている。
歌は「鉾(ほこ)とりて月見るごとにおもふ哉(かな)あすはかばねの上に照(てる)かと(鉾を手に取って月を見るたびに思う。あすはしかばねの上に照るのかと)」。島田家に伝わる和歌集の冒頭に土方の名で記され、和歌集は26年前に同館に寄贈されていた。
木村課長が今年、修復にあわせて、ほかに名のある30人を調査、大半が新撰組隊士や幕府側の藩士らで、戊辰(ぼしん)戦争(1868~69)で降伏し、長く生きたことがわかった。自然のはかなさを詠んだ歌が多く、維新後に隊士らが作り、島田がまとめたと判断した。
土方は、旧幕府軍の指揮官として戊辰戦争に加わり、新政府軍の総攻撃を受け、銃弾に倒れた。生き残った藩士らの証言などによると、その前夜、旧幕府軍幹部らが惜別の宴(うたげ)を開いていた。木村課長は「歌には悲壮な決意が示されており、土方が明日の死を予期しながらこの席で詠み、島田が大切に記録していたのでは」と話す。

















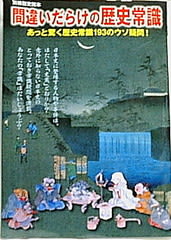




















 後
後












