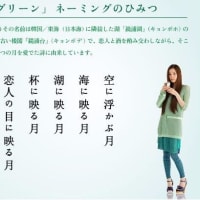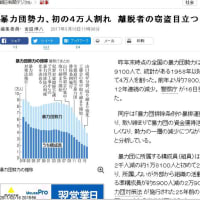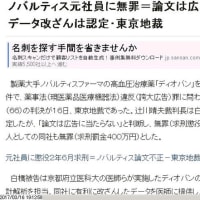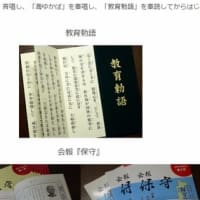必ずオリックスとコンビで登場する人物である。
曰くありの、元JALスチュワーデスである。しかもVIP専門であるから、この奥谷禮子の経歴はファーストクラスから始まったのであろう。
武見太郎が岩波文化人との交流で運を掴んだようなものである。
奥谷禮子のwikiの記事に纏められているが、いつ変更されるとも限らないので、ここに保存することにする。
奥谷禮子wiki
奥谷禮子
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 奥谷 禮子
(おくたに れいこ)
2009年6月19日、東京都にて
生誕 1950年4月3日(59歳)
兵庫県神戸市
出身校 甲南大学法学部卒業
職業 ザ・アール社長
甲南大学客員教授
表・話・編・歴
奥谷 禮子(おくたに れいこ、1950年4月3日[1] - )は、日本の実業家。本名は米澤 禮子(よねざわ れいこ)。名前に使われている漢字「禮」は旧字体であり、著書などでは奥谷 礼子とも記される。なお「奥谷」は旧姓。株式会社ザ・アール代表取締役社長[2]。目次 [非表示]
1 経歴
1.1 略歴
1.2 ザ・アール
1.3 役職
1.4 経済同友会との関連
2 派遣切りとの関連
3 人物
3.1 要職の歴任
3.2 思考・発言
4 日本アムウェイとの関係
5 週刊東洋経済インタビュー騒動
6 著書
7 参考文献
8 関連項目
9 外部リンク
経歴 [編集]
2007年11月16日、新潟県にて
略歴 [編集]
兵庫県神戸市出身。1974年甲南大学法学部卒業。日本航空に就職(国際線客室乗務員、のちVIPラウンジ)、7年間勤務。退職後の1982年、同僚6人と人材派遣会社ザ・アールを設立。1986年には、経済同友会初の女性会員の一人に選ばれた。また同年から6年間、当時の堤清二セゾングループ代表との縁で、セゾングループが設立した人材派遣会社ウイル(現株式会社ミレニアムキャスティング)の社長を兼務した。2002年5月には株式会社ローソンの社外取締役に就任する[3]。2006年1月には日本郵政の社外取締役に就任した[4]。
ザ・アール [編集] この節は中立的な観点に基づく疑問が提出されています。詳しくはノートを参照してください。このタグは2009年3月に貼り付けられました。
株式非公開企業であってIRなどでの株主構成、財務諸表、売上、経常利益、決算短信、決算内容などを公開しておらず詳細不明である。沿革に示されている第三者割当の増資者もザ・アールからは公開されていない。村上ファンドへの投資信託[5][6]に対する弁明も一切公表されていない。
なお、2006年05月時点での株主は、過半を所有する筆頭大株主が奥谷で、第二位株主はオリックス、堤清二、カルチュア・コンビニエンス・クラブの3者が同比率である。過去に、オリックスの宮内義彦会長が座長を務める総合規制改革会議(「規制改革・民間開放推進会議」を経て現・規制改革会議)の委員として奥谷が選ばれていた事実[7]に疑問を呈した民主党の城島正光衆議院議員(当時)による衆議院厚生労働委員会での発言[8]に外部から削除や訂正を求めるという前代未聞の通告を行った[9]。また、平成16年11月の第三者割当は日本エンタープライズによるものである。
役職 [編集]
2009年6月19日、東京都にてカルチュア・コンビニエンス・クラブ社長増田宗昭(左)、角川グループホールディングス会長角川歴彦(中)と
現職
ローソン・楽天野球団各社の経営諮問委員会委員[10]、経済同友会幹事、独立行政法人国立新美術館運営協議会評議委員、神戸市市長諮問委員会委員、神戸市神戸経済特区研究会委員、WOWOW放送番組審議会委員[11]、エンジン01文化戦略会議幹事[12]。
過去の公職
厚生労働省労働政策審議会臨時委員(労働条件分科会会員)[13]、郵政省郵政審議会委員[14]、内閣府未来生活懇談会委員[15]、国土交通省交通政策審議会委員[16]、通商産業省産業構造審議会委員、通商産業省航空機宇宙産業審議会委員、内閣府規制改革会議委員、公正取引委員会「21世紀にふさわしい競争政策を考える懇談会」会員[17]。
2002年、小泉内閣に、製造業での派遣解禁などを提言した『規制改革の推進に関する第2次答申 ―経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革― 』を提出した諮問機関『総合規制改革会議』(宮内義彦議長)の委員。
経済同友会との関連 [編集]
1986年に経済同友会に初めて女性会員が誕生した際、奥谷はその一人であった。以後、経済団体の役員、政府や自治体などの審議会委員などの職に就き、活発に同友会人脈を形成した。
元経済同友会の代表幹事である牛尾治朗・ウシオ電機代表取締役会長とは、現在も親しくしている。
派遣切りとの関連 [編集]
奥谷が宮内とともに推し進めた市場原理主義の結果として、今日の非正規雇用者が抱える「派遣切り」などの社会問題を生んだとの指摘がある。前民主党衆議院議員にして当時の民主党次の内閣・雇用担当大臣だった神奈川10区の城島光力と激しく対立。
宮内義彦が城島に送った手紙についてサンデー毎日は、「民主党議員を激怒させた高圧的文言」という題名にて報道した。宮内から城島への抗議文については、城島が質問主意書を提出。衆議院の厚生労働委員会は宮内の抗議文と奥谷禮子の一連の行動について、「議会制民主主義の基本的なルールを踏みにじるかつてない暴論である」との見解を正式に決定した。ちなみに当時の厚生労働大臣は公明党の坂口力。
人物 [編集]
要職の歴任 [編集]
政府関係の公職を多数務めている理由として、小泉純一郎、規制改革関連の審議会長を多数務めた宮内義彦とも懇意の仲[18]であることも大きく影響している。林真理子の「不機嫌の会」(林の小説「不機嫌な果実」に由来する)という晩餐会に小泉、野田聖子、宮内などと共にしばしば出席している[19][20][21]。なお小泉は「不機嫌の会」の創設時からの会員である。また、郵政民営化に反対していた野田と郵政社外取締役であった奥谷は親しい関係にある[22]が、この二人を取り持つ関係として野田が米国アムウェイ本社社長の表敬訪問を受けるほどのアムウェイ擁護派であることが挙げられる[23]。
思考・発言 [編集]
「格差論は甘えです」[24]と、格差社会論そのものに否定的な人物の一人である。2006年10月24日に開催された第66回労働政策審議会労働条件分科会に使用者側の委員として参加し、過労死の問題について、「自己管理の問題。他人の責任にするのは問題(=自己責任論)」「労働組合が労働者を甘やかしている」[25][26]と発言し、さらに週刊東洋経済のインタビューで「労働基準監督署も不要」「祝日もいっさいなくすべき」と発言し論議を呼んだ[27]。また、派遣切りについて「貯蓄をせずに自己防衛がなってない」「企業や社会が悪いなどというのは本末転倒である」などと批判した[28]。
インタビューで「人と接する上で気を付けてらっしゃることありますか」と問われた奥谷は「嫌いな人と付き合わないということですね。ぱっと見て嫌だなと思ったら付き合わない」と答えている[29]。
派遣社員の実態を描いたテレビドラマ「ハケンの品格」等で知られる人気脚本家の中園ミホとは、共演した番組内で意見が対立。隣り合った席に座っていたので、「この(座席)間に大きな川が流れている(=埋め難い見解の相違がある)ように思える」と、斬り捨てられた(中園は、脚本執筆のため派遣社員に対して取材を行っており、奥谷とは逆に派遣社員の待遇の悪さに同情的である)。
日本アムウェイとの関係 [編集]
日本アムウェイに関して、一般的に「マルチ商法」と呼ばれることも多い連鎖販売取引の手法が問題視されたが、その後同社に請われてこの問題の是正のため2001年から諮問委員に就任[30]。同諮問委員会はのちに廃止された。
就任当時には日本アムウェイによるインタビュー[31]で「“ものづくりの哲学”をきちんともって、情熱を傾けている会社」「いい製品を作り、消費者に届けたいという熱意や姿勢を持っている」「ディストリビューターは作り手の情熱と一緒に使い手に届ける使命があると発言するとともに、「アムウェイに携わるディストリビューターのモラル向上や教育に投資するべきではないか」「社会が成熟してきたところで、アムウェイの人々がきちんとした倫理観をもって進めて行けば、将来大きな躍進が期待できる」とモラル面の改善も申し入れていた。
週刊東洋経済インタビュー騒動 [編集]
週刊東洋経済2007年1月13日号で、「格差社会と言いますけれど、格差なんて当然出てきます。仕方がないでしょう、能力には差があるのだから」と発言し、インターネット上などで波紋が広がっている[32][33]。
記事では、「下流社会だの何だの、言葉遊びですよ。そう言って甘やかすのはいかがなものか」と持論を展開。過労死については「だいたい経営者は、過労死するまで働けなんて言いませんからね。過労死を含めて、これは自己管理だと私は思います。ボクシングの選手と一緒」とした上で、「自分でつらいなら、休みたいと自己主張すればいいのに、そんなことは言えない、とヘンな自己規制をしてしまって、周囲に促されないと休みも取れない。揚げ句、会社が悪い、上司が悪いと他人のせい。ハッキリ言って、何でもお上に決めてもらわないとできないという、今までの風土がおかしい」と経営者側よりも労働者側の意識が問題との認識を示した。
しかしこの発言に対しては、労働者側への現状認識が欠けているとの指摘、日本国憲法第27条とこれを受けて制定された労働基準法、および日本国憲法第28条で定められている労働基本権を失念した発言であるとの指摘がある。また、改正教育基本法に見られる“個人より国家・公共を優先し重んじる”政策からすれば、労働者の判断で休みを取るべきとの奥谷意見は相容れない。なお、最高裁判所は2000年3月に大手広告代理店社員の過労自殺訴訟において企業が社員に払うべき義務について「疲労が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことのないように注意する義務」という判断を示している[34]。言い換えると「社員の自己管理」ではなく「経営側に職場の環境を整備する義務がある」ということである。さらに、取締役であっても過労死の責任は会社にあるという判断を大阪高等裁判所は示している[35](これらの指摘については後述の国会審議録での川内博史議員による柳澤厚生労働大臣への詰問およびその参考文献を参照)。
また、今回の騒動を受けて奥谷が公表した文章[36][37]では過激な表現が控えられているものの、上で示した日本国憲法の意義や最高裁判所判例の趣旨と異なる発言を行っている。さらに「職種によっては、どこまでが仕事で、どこまでがプライベートか分からないものがある。研究者などは最たるもので、あるテーマに没頭しはじめれば、公私などありはしない」と発言している。
2007年2月7日の衆議院予算委員会で、川内博史議員(民主党)が「あまりの暴論なので提示させてもらった。柳澤伯夫厚生労働大臣の諮問委員に日本国憲法を無視している人がいて、ホワイトカラーエグゼンプションを推進しようとしている」と詰問し、この発言について同議員が読み上げた[38]。この質問に対し、柳澤厚生労働大臣は「まったく、私どもの考え方ではない」と答弁している。
この後、奥谷はマスコミの取材[39]に対し「発言の一部分だけをとらえた質問は遺憾」と反論したが、2007年2月19日の衆議院予算委員会で、枝野幸男議員(民主党)が「十分釈明を聞きたい」と述べ、参考人招致を要求した[40][41]。結局、与党側が3月2日に委員長職権で審議を打ち切り予算案が衆議院を通過したので野党側が要求していた奥谷の参考人招致は実現しなかったが『週刊ポスト』『女性セブン』(以上、小学館)や『サンデー毎日』(毎日新聞社)でも奥谷発言が取り上げられた。
この発言に関して奥谷は2007年4月2日付の朝日新聞におけるインタビューで、「真意が伝わっていない。工業化社会から知的創造の時代に移り、長く働けば生産性が上がる時代では無い。自分で労働時間を管理し、生産性が上がるよう働けばいいという意味だった」とコメントしている。しかし、このコメントに関しては対談相手の森永卓郎からは「規制がなくなれば地獄の底まで働かせるのは、産業革命で立証済み。最低限の権利を守る仕組みが必要だ」と反論されている。
2007年5月22日の参議院厚生労働委員会で櫻井充議員は奥谷について「この方が労働政策審議会のメンバーですね、ホワイトカラーエグゼンプションをどんどん進めていって、やられている方ですね。この方は、規制改革会議のメンバーでしたね。過労死は自己責任と言った人ですよ。こういう人が本当に有識者ですか」「何回も、いつもこの委員会で問題になっていますけれども、過労死は自己責任だとか、そういうことをおっしゃっている方が(労働政策審議会の委員として)適切なのかということです」と批判している[42]。
著書 [編集]
正しい仕事のやり方・すすめ方(日本能率協会マネジメントセンター、2006年、ISBN 978-4-8207-1685-3)
サービスの作法(郵研社、2006年、ISBN 978-4-946429-79-8)
成功する人は「気配り」上手(日本文芸社、2005年、ISBN 978-4-537-25295-8)
如是我聞(亜紀書房、2003年、ISBN 978-4-7505-0302-8)
日航スチュワーデス 魅力の礼儀作法(新潮社、2003年、ISBN 978-4-10-103121-7)
ポジティブになれる人ほど幸福に近づける(亜紀書房、2000年、ISBN 978-4-7505-0018-8)
ポジティブに生きる(ザ・アール21、1997年、ISBN 978-4-916134-02-8)
女が会社をつくる時(大和出版、1991年、ISBN 978-4-8047-0117-2)
男たちよ、そろそろお休みなさい(大和出版、1990年、ISBN 978-4-8047-1166-9)
こんな女性がオフィスで魅力的(三笠書房、1990年、ISBN 978-4-8379-0385-7)
もっと女性力が引き出せる本(大和出版、1989年、ISBN 978-4-8047-1156-0)
ワーキングウーマンのマナー術(永岡書店、1989年、ISBN 978-4-522-01206-2)
できる女は器量が光る(サンマーク出版、1987年、ISBN 978-4-7631-8936-3)
女でキラキラ生きてます(大和出版、1987年、ISBN 978-4-8047-0081-6)
女を読む・動かす・拓く(大和出版、1986年、ISBN 978-4-8047-1087-7)
参考文献 [編集][ヘルプ]
^ 生年月日(誕生日)データベース
^ ザ・アール トピックス
^ 株式会社ローソン 2003年アニュアルレポート
^ 総務省 竹中総務大臣閣議後記者会見の概要 平成18年1月17日(火)
^ SankeiWebBusiness i.ZAKZAKSANSPO.COM (リンク消失)
^ コラコラコラム 日銀の福井総裁は、自ら、人の倫を考え、潔く辞職せよ! (SankeiWebBusiness の記事引用あり)
^ 総合規制改革会議委員名簿
^ 第156回国会 厚生労働委員会 第14号(平成15年5月14日(水曜日))
^ 前衆議院議員-城島まさみつ-公式ウェブサイト
^ 楽天市場会社情報 日本プロフェッショナル野球組織への加盟申請について 2004年9月24日
^ WOWOW放送番組審議会
^ エンジン01文化戦略会議
^ 厚生労働省:労働政策審議会労働条件分科会委員名簿(平成18年5月24日現在)
^ 旧郵政省郵政審議会議事要旨(平成7年11月7日公表)
^ 内閣府未来生活懇談会 第14回議事概要
^ 国土交通省交通政策審議会 第1回総会
^ 公正取引委員会「21世紀にふさわしい競争政策を考える懇談会」提言書について 平成13年11月14日
^ 宮内義彦「経営論」出版記念の夕べ
^ AERA 2007年1月15日号
^ Yahoo!みんなの政治 - 政治記事読みくらべ - AERA - 小泉コワモテ側近の「野望」
^ 宮内義彦,「多士菜々―24人のランチタイム交友録」, PHP研究所 (2004) ISBN 978-4569634630
^ 奥谷禮子の私的通信:Reiko's style トピックス 婦人画報に登場いたしました
^ 衆議院会議録情報 第136回国会 商工委員会 第8号
^ 週刊日経ビジネス 2006年7月10日号
^ 厚生労働省 06/10/24 労働政策審議会労働条件分科会 第66回議事録
^ 2006年10月26日(木)「しんぶん赤旗」
^ 週刊東洋経済 第6059号 (2007年01月13日号)
^ 派遣切り・「社会が悪い」は本末転倒(上)(Voice) - goo ニュース
^ リクエールが提供する時代を担う経営者達のインタビュー企画 ベンチャーインタビュー
^ 2001年9月21日 日本アムウェイ株式会社 経営諮問委員会設置のお知らせ
^ amway.co.jp | もっと知りたいMLM | 奥谷禮子さん (Internet Archive)
^ 「財界のマドンナ」炎上!? (ゲンダイネット)(ウェブ魚拓)
^ 痛いニュース(ノ∀`):【労働者へ果たし状】人材派遣ザ・アールの奥谷禮子社長、「過労死は自己管理の問題」と労働者批判 労基署は不要とも
^ 平成10(オ)217 損害賠償請求事件(通称 電通損害賠償) 平成12年03月24日 最高裁判所第二小法廷
^ 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 取締役過労死で会社に責任 大阪高裁、遺族が逆転勝訴
^ コラム その人に合った働き方へ
^ コラム その人に合った働き方へ (ウェブ魚拓)
^ 第166回国会 予算委員会 第4号(平成19年2月7日(水曜日))
^ 「過労死は自己管理の問題」奥谷氏発言が波紋 (asahi.com)
^ 第166回国会 予算委員会 第11号(平成19年2月19日(月曜日))
^ 「過労死は自己管理の問題」発言で参考人招致要求 民主 (asahi.com)
^ 第166回国会 厚生労働委員会 第23号 平成十九年五月二十九日(火曜日)
関連項目 [編集]
ホワイトカラー・エグゼンプション
労働基準監督署
都道府県労働局
労働基準法
新自由主義
富の再分配
リバタリアニズム
格差社会
ローソン
日本郵政
連鎖販売取引
城島光力
中園ミホ
外部リンク [編集]
奥谷禮子の私的通信:Reiko's style
総合規制改革会議
サンデー毎日記事(城島公式サイト)
子供が生まれてくる。赤ん坊が生まれてくる。
その赤ん坊はすでに何をやるかどういう人生をたどるかは、はたして決まっているのであろうか?