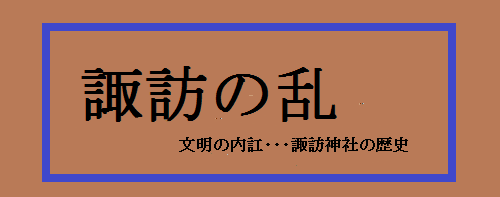 ・・第四章 室町時代
・・第四章 室町時代
内訌時代へ 諏訪家の内訌と小笠原家の内訌
・・・・・内訌 一族間の棟梁・覇権を争う内乱、領地分割相続から長子相続に変化した室町中期におこる
小笠原家の内訌・・・信濃国は守護小笠原氏による権力が確立されたが、嘉吉二年(1442)守護小笠原政康が死去したことをきっかけとして「嘉吉の内訌」が起った。小笠原氏は伊那と府中に分かれて相続争いを繰り返し、さらに伊那では鈴岡と松尾に分かれて、小笠原氏は三つ巴の骨肉相食む内乱となった。その結果、守護権力は弱体化し、国人層も複雑な動きをみせるようになり、信濃一国は内乱状態に陥ったのである。
諏訪氏の二重構造化・・・
ところで、諏訪氏は古代以来、祭政一致の統治形態をとり、神を祀る大祝家は政治権力の掌握者でもあり、その身は現人神(神霊の肉体的表現)ともみなされ聖なる身として神域である諏訪から外に出ることをタブーとされてきた。諏訪上社祭祀体系の頂点に立つ大祝は、諏訪氏一門が惣領家の幼男もしくは一門の子弟を奉じて実現するもので、いいかえれば幼児というべき年頃であった。そのため、諏訪氏が武士団として戦乱の打ち続く中世を生き抜くためには、幼い大祝に替わって惣領が戦陣の指揮をとり、諏訪地方の領主として領地の経営にあたったのである。
そして、神事運営に際しては大祝を頂点として、神長官・祢宜大夫・権祝・擬祝・副祝が実務官僚的祠官として存在し、大祝は惣領とともに前宮の神殿にいたのである。このようにして、諏訪氏は聖なる世界の権威である大祝と、諏訪一門の棟梁である惣領という二重構造を強めるのである。
とはいえ、大祝が幼児の間は権力を行使することもなく、惣領の支配体制を脅かすことはなかった。しかし、大祝の地位に長くとどまって成人になると、祭政一致の体現者という意識がややもすれば強くなり、権力への志向をみせるようになった。そして、ついには惣領と大祝の間に対立が生じるようになるのである。
諏訪氏は中先代の乱後、大祝頼継は朝敵ということで大祝職を失ったが、南北朝の内乱期は南朝方として足利尊氏に抵抗しながらも、大祝職は惣領家の系統である信嗣・信貞・信有・有継と伝えられてきた。しかし、有継以後の大祝は惣領家から出ず、ほとんど傍系から輩出するようになった、その結果、惣領家と大祝家の系統が分離し、在位期間も長引くようになった(平均十一年)ことで大祝の力が高まり、ともすれば惣領家と対立するようになった。
その背景には、南北朝期の内乱からその後の中世争乱のなかで惣領制的な分割相続から嫡子(惣領)による単独相続へという変化があった。惣領への権力集中がいちじるしくなると、惣領への就任志向が高まり、一族・被官を巻き込んだ相続争いが各地で頻発するようになった。その一事象が信濃守護小笠原氏の内訌であり、諏訪氏もそのような時代相と無関係ではなかったのである。
諏訪社の内部対立・・・
諏訪社の内部対立は、まず上社・下社の間に起こった。・・・宝治2年は、・・諏訪大社造営の年度に当たる、その年に上下社間に本宮争いが生じた。下社大祝の金刺盛基が、その解状で訴えた。しかし上社の諏訪氏は、鎌倉幕府の得宗家御内人であり、且つ重臣である。幕府の裁可は当然、「去年御造営に下宮の祝盛基は、新儀の濫訴を致すによって」として裁下し、「上下両社の諸事、上社の例に任せ諸事取り仕切る」とした。・・ しかし、(翌宝治3年(1249))・下社大祝盛基は、この幕府の下知に納得せず、上宮は本宮ではないと再度申し立てた。大祝信重解状は、それに対する長文の反論で、「進上御奉行所」として幕府に訴えた。
その内容は7ヵ条で 一、守屋山麓御垂跡の事、一、当社五月会御射山濫觴の事、一、大祝を以て御体と為す事、一、御神宝物の事、一、大奉幣勤行の事、一、春秋二季御祭の事、一、上下宮御宝殿其外造営の事
鎌倉中期以前の諏訪大社の鎮座伝承、神宝、祭祀、神使御頭(おこうおとう)、大明神天下る際の神宝所持、御造営等、詳細に上社が本宮である由来を記述して、先例通りの恩裁を請願している。・・・
この時の下社大祝は金刺盛基、対する上社大祝は諏訪信重、鎌倉幕府に訴状合戦をしている。・諏訪大社造営のこととは、神事運営の事か?。時は北条得宗家の時代に移り、上社諏訪家は得宗家と御身内の関係の親密さを増している時、裁定は上社有利に下される。
・・・「大祝信重解状」・諏訪家側の訴状のこと、神長守矢家に永らく秘蔵されていた。・・・
この対立は、下社の経済的衰退が根にあり、下社は対策するようになる。下社の領域とするところは、下諏訪、岡谷、辰野の一部、洗馬(塩尻)であるが、洗馬は府中小笠原家と木曽家から、辰野は木曽家と同族の上社から脅かされる状態だった。その為に、幕府に庇護の質を、上社より有利か同等にするように訴状を提出する。この対立は、上・下社の訴状合戦で終わり、下社の敗北に終わったようだ。そして武力衝突には到っていない。南北朝終盤の頃の桔梗ヶ原の合戦の時に変化は起こった。それまで南朝側に付いていた下社は、参戦を保留し、守護小笠原側が有利になるように動いた。結果は守護側の勝利で、以後信濃に於ける南朝勢力は急速に衰退する。この戦いは、途中で仁科氏を始めとする神党が戦線を離脱している。この戦いの以後、下社と府中小笠原家は同盟し、諏訪一族の対立と小笠原一族の対立が入り組んで絡み合い、様相を複雑にしていく。
次ぎに起こったのが、諏訪氏の内訌の予備選・・・
康正二年(1456)大祝伊予守諏訪頼満とその兄で惣領安芸守諏訪信満が争ったことが、「此年七月五日夜、芸州・予州大乱」と『諏訪御符礼之古書』に見えている。争いの原因は不明だが、頼満とその子頼長とは永享(1429~40)以来、大祝の位にあって勢力を拡大し、惣領である兄信満に対抗するようになったのであろう。乱そのものはそれほど大きなものではなかったようだが、この争いを機に惣領信満は上原に移住し、大祝頼満は前宮に残って、大祝家と惣領家とは分裂状態となった。
こうして、諏訪上社内でも 、大祝と惣領家の間で対立が起こった。これは内訌と呼べるほどの規模でないにしても、同族内の勢力争いで、戦国時代突入の前触れであった。
文明の内訌・・・前触れ・・
文明十一年(1479)、伊那の伊賀良庄に府中小笠原氏が侵攻し、諏訪氏は伊賀良庄の小笠原政秀(政貞)を支援するため、大祝継満は高遠信濃守継宗とともに出陣した。下社の金刺氏が府中の小笠原家と同盟したため、対抗上松尾小笠原家の番頭を任じる坂西孫六を通じて、上社大祝は松尾小笠原と手を組んでいた。坂西孫六は、上社の敬虔な信者であった。府中小笠原氏は下社および下社系の武士団と結んでおり、諏訪氏は対抗上伊賀良庄の伊那小笠原氏と結んでいたのである。翌十二年になると、伊那の小笠原政秀と叔父光康が争い、光康は府中の小笠原長朝を味方に付けたため、諏訪氏は政秀に援兵を送っている。この年、小笠原長朝は仁科氏を破り、さらに諏訪氏の保護下にあった山家氏を攻撃した。これに対して翌十三年四月、諏訪惣領政満は仁科氏・香坂氏らと協力して小笠原長朝を討つため府中に攻め入っている。以後、諏訪氏の惣領政満は、甲斐にも出陣するなどして伊那・筑摩郡にまでその勢力を及ぼした。しかし、台頭いちじるしい大祝継満との関係から微妙な立場におかれていた。継満は大祝の位にあること二十年におよび、伊那小笠原氏を支援して出陣もしていた。年齢も三十歳を越えており、惣領政満の指図にも従おうとはしなくなった。
文明の内訌・・・本格化
文明十四年(1482)、諏訪氏一族の高遠継宗と代官の保科貞親とが対立し、大祝が調停に入ったが不調に終わった。その結果、保科氏には千野氏・藤沢氏らが同心して、笠原氏らの支援を受けた継宗と笠原で戦い高遠方が敗れた。その後、保科氏は高遠氏と和解したが、高遠氏と藤沢氏とが対立し、惣領政満は藤沢氏を支援した。さらに府中小笠原長朝も藤沢氏を支援する立場をとり、小笠原・藤沢連合軍は高遠継宗配下の山田備前守が守る山田城を攻めたが失敗するという結果になった。ここにいたって、諏訪上社の対立構造は鮮明になった。上社の大祝と惣領家の関係は修復不可能になった。大祝と同盟を組んでいた高遠家は大祝の妻の兄であった。さらに諏訪上社の棟梁たる自負を持っていた。・・・・かって、諏訪頼重が、鎌倉に出陣後、大祝を継いだのは、時継の子・頼継であった。このため朝敵となった頼継は神野(諏訪神領の山岳か)に隠れる。尊氏は大祝の継承を、大祝庶流の藤沢政頼に就かせると、頼継の探索を厳しく命じた。頼継は、わずか5,6人の従者を連れて、神野の地をさ迷うが、諏訪の人々による陰ながらの援助で逃れる事ができた。そして隠棲して、後に出来たのが高遠家である・・・
文明の内訌・・・大祝継満は高遠継宗および小笠原政秀との連係を強め、一方の惣領政満は藤沢氏とともに府中小笠原長朝と通じるようになった。ここに、諏訪氏の分裂と小笠原氏の分裂とがからみ合うという、複雑な政治状況となってきた。そして、翌十五年(1483)一月、大祝継満は惣領政満父子を居館に招いて殺害し、惣領家の所領を奪って千沢城に立て籠るという一挙に出た。一気に上社の支配権を掌握しようとしたのである。これに対し、矢崎・千野・小坂・福島・神長官らの各氏は、大祝のとった行動を支持せず大祝の籠る千沢城を襲撃した。大祝継満は父頼満をはじめ一族に多数の犠牲者を出し、高遠継宗を頼って伊那郡に逃れ去った。
・・諏訪氏の戦国大名化・・・諏訪上社の内乱に対して、諏訪下社の金刺氏は継満に味方して挙兵した。下社は永年にわたって上社と紛争を起こして衰退の一途にあったが、上社の内訌を好機として頽勢挽回を図ろうとしたのである。金刺氏は継満の一派とともに高島城を攻略し、上桑原・武津を焼いた。対する諏訪勢は矢崎肥前守らを中心として出撃し、下社勢を討ち取り、下社に打ち入ると社殿を焼き払い一面の荒野と化したのである。金刺興春は討ち取られ、金刺氏は没落し、下社は一時衰退してしまった。
翌年五月、小笠原政秀の援助を受けた大祝継満は、高遠継宗・知久・笠原ら伊那勢を率いて諏訪郡に侵入し、上社近くの片山城に籠城したが小笠原長朝に攻められて退去した。十二月、さきに継満に殺害された政満の二男頼満が上社大祝職に就き、以後、祭政を一つにした諏訪惣領家が諏訪郡を支配するようになった。しかし、継満は滅亡したわけではなく、十八年には大熊に新城を築き、十九年には継宗が諏訪に攻め入るというように、諏訪氏と継満一派との戦いは繰り返されたのである。
この一連の抗争は「文明の擾乱」(=文明の内訌)と称され、大祝と惣領家の激突によって諏訪氏内部における二重構造が解消されるという結果になった。こうして、文明十五年より天文八年(1539)に至るまでの約五十六年間、頼満が惣領として君臨し、その間、下社の金刺氏を攻め滅ぼし、諏訪地方に大名領国制を展開するようになった。
こうして頼満は諏訪氏中興の主とよばれ、戦国大名としての諏訪氏は、頼満の代に始まった。しかし、その実態は諏訪の在地領主・小領主連合を従属下におく盟主的存在から離脱するまでには至らなかった。頼満の治世に関しては、史料も少なく実態は不詳。
この間の様子を、戦記物語風に、以下に記述する・
・・・・・諏訪の乱・・
国衙が後庁(現長野市南長野町・後町)にあった時代に、中御所守護館は、現在の長野市中御所2丁目に置かれていた。南北朝期から室町期の信濃国の守護所である。その漆田原(長野市中御所の長野駅付近)在地領主漆田氏の館跡が漆田城とも言われ、守護館の北西から西北西の方向に東西約254m、南北118mに漆田城を構えた。源頼朝が建久年(1197)8に善光寺に参詣した際にこの辺りの有力者である漆田氏の館に泊まったとある。
中御所守護館は文安3年(1446)漆田原の合戦のあと廃止になった。小笠原宗康が父の小笠原政康から相続したが、宗康の叔父の子持長(府中)といとこ同志で守護職と惣領をを争うようになった。宗康(松尾)は、持長との争いに敗れて討ち死にしたら光康(鈴岡)に跡目を渡す約束で、合力(援軍)を依頼した。宗康は漆田原で持長軍と戦い傷死したが、持長は戦勝しながら、家督を承継出来ず、その対立が後代にも及んだ。文明11年(1479)9月、伊那郡で松尾の小笠原政秀(政貞とも;宗康の子)と鈴岡の小笠原家長(光康の子)が争い始めた。ここに、小笠原家は3家に分裂し混乱した。諏訪上社大祝諏訪継満は政秀を助勢するため伊那郡島田(飯田市松尾)に出兵した。
文明11年(1479)7月、佐久郡内の小笠原一族、大井・伴野両氏は諏訪上社御射山祭の左頭・右頭として頭役を勤めていた。佐久岩村田の大井氏の当主は政光の後嗣、若い政朝であった。ところが、その1か月後の8月24日の合戦で、大井氏は前山城の伴野氏との戦いに大敗し、政朝が生け捕りとなり、大井氏の執事相木越後入道常栄を初め有力譜代の家臣が討死した。この戦いには、伴野氏方に、大井氏に度々侵攻され劣勢にあった甲斐の武田信昌が、報復として加担したといわれている。生け捕りとなった政朝は佐久郡から連れ出されたが、和議が成立して政朝は岩村田に帰ることができた。以後、政朝は勢力を回復できぬまま、文明15年(1483)若くして死去した。・・・佐久地方を拠点としていた小笠原家の別家筋の衰退である。翌年、村上氏の軍勢が佐久郡に乱入し、2月27日、岩村田は火を放たれ、かつて「民家六千軒その賑わいは国府に勝る」と評された町並みは総て灰燼に帰した。大井城主は降伏し、大井宗家は村上氏の軍門に下った。
翌文明12年2月、下社大祝金刺興春が、上社方を攻め安国寺周辺の大町に火を放った。3月には西大町に火を放つ。興春には諏訪一郡の領主権と諏訪大社上下社大祝の地位獲得の野望があった。同年7月、伊那郡高遠継宗が鈴岡の小笠原家長に合力し伊那郡伊賀良へ出陣し、松尾の小笠原政秀と戦い、8月には上社大祝継満が小笠原政秀と共に伊賀良の鈴岡小笠原家長を攻めている。
一方、高遠継宗は同じ8月、伊那郡高遠の山田有盛と戦っている。文明13年の『諏訪御符礼之古書』に記される明年御射山御頭足事条には「一、加頭、伊那,山田備前守有盛、御符礼一貫 八百、代始、使四郎殿、頭役六貫文」とあり、山田有盛が頭役を勤仕している。山田氏は山田地内の山上に居城を構えていた。翌14年6月、高遠継宗は藤沢荘の高遠氏代官として仕えていた保科貞親と、その荘園経営をめぐって対立し、大祝継満・千野入道某らが調停に乗り出したが、継宗は頑として応ぜず不調に終わった。継宗は笠原、三枝両氏らの援軍を得て、千野氏・藤沢氏らが与力する保科氏と戦ったが、諏訪惣領政満が保科貞親の助勢に加わると、晦日、高遠継宗の軍は笠原で敗れた。以後も保科氏との対立は続き、さらに事態は混沌として複雑になる。同年8月7日、保科氏が高遠氏に突然寝返り、連携していた藤沢氏が拠る4日市場(高遠町)近くの栗木城を攻めた。この時、上社惣領家諏訪政満は藤沢氏を助け、その援軍も共に籠城している。15日には、府中小笠原長朝の兵が藤沢氏を支援するため出陣をして来た。17日、府中小笠原氏と藤沢氏は退勢を挽回して、その連合軍は高遠継宗方の山田有盛の居城山田城(高遠町山田)を攻撃したが、勝敗は決しなかった。守矢文書によると、「府中のしかるべき勢11騎討死せられ候、藤沢殿3男死し惣じて6騎討死す」とある。
諏訪氏も小笠原氏同様、一族間の内訌が絶えなかった。諏訪惣領家・諏訪大社上社大祝家・高遠諏訪家、そこに下社大祝金刺家が加わる争乱となる。この戦国時代初期、諏訪氏は多くの苦難を乗り越える事で、戦国武将として成長しつつあった。諏訪氏は、下社金刺氏を圧倒し郡内を掌握する勢いであり、杖突峠を越えて藤沢氏を支援し、一族高遠継宗の領域を脅かしつつあった。大祝継満も大祝に就任して20年近い、年齢も32才に達している。諏訪家宗主としての誇りと、度々の郡外への出兵で、軍事力を養ってきた。そして、諏訪大社御神体・守屋山の後方高遠に義兄弟の継宗がいる。彼らは、自ずと連携し、そこに衰勢著しい金刺氏を誘い、「諏訪上社を崇敬すると自筆の誓紙」を差し出した伊賀良の小笠原政貞とも同盟した。
文明15年(1483)正月8日、
・・・大祝諏訪継満が惣領諏訪政満とその子宮若丸らを神殿で饗応し、酔いつぶれたところを謀殺した。・・・
しかし継満の行為は諏訪大社の社家衆の反発を招き、2月19日、神長官守矢満実・矢崎政継・千野・福島・小坂・有賀ら有力者は継満を干沢城に追い詰め、更に伊那郡高遠へ追いやった。・・・これが文明の内訌である。
下社大祝金刺興春は、上社大祝諏訪継満に同心していて、諏訪家の総領の不在を好機として3月10日、高島城を落城させ、さらに桑原武津まで焼き払い、上原に攻め込もうとした。神長官守矢満実らは、敵の攻撃に備えて高島屋城に総領家一族と共に立て篭もっていた。守矢満実の子継実・政美は、矢崎、千野、有賀、小坂、福島などの一族と共に逆襲に転じ、逆に金刺興春の軍を破り、勝ちに乗じて下社に達し、その社殿を焼き払い、興春の首を討ちとった。その首は諏訪市湖南にあった大熊城に2昼夜さらされた。興春亡き後、諏訪下社大祝は子盛昌、孫の昌春と代を重ね、上下社間の争闘は続くが、このころから下社方の勢力は衰微する。・・・この時府中深志の小笠原長朝は、神長官守矢満実・矢崎政継らに味方し、下社領筑摩郡塩尻・小野などを押領した。・・・高遠に逃げた継満は、義兄の高遠継宗と伊賀良小笠原政貞、知久、笠原氏の援軍をえて翌年の文明16年(1484)5月3日、兵300余人率い、杖突峠を下り磯並・前山に陣取り、6日には諏訪大社上社の裏山西方の丘陵上にあった片山の古城に拠った。その古城址北側下の諏訪湖盆を見晴らす平坦な段丘には、古墳時代初期の周溝墓がある。極めて要害で、西側沢沿いには、水量豊富な権現沢川が流れ地の利もよい。惣領家方は干沢城に布陣したが、伊那の敵勢には軍勢の来援が続き増加していく。 ところが小笠原長朝が安筑両郡の大軍を率いて、片山の古城を東側の干沢城と東西に挟み込むように、その西側に向城を築くと形勢は逆転した。その向城こそが権現沢川左岸の荒城(大熊新城)であった。伊那勢は両翼を扼され撤退をせざるを得なくなった。 継満も、自らの妄動が家族に残酷な結果をもたらし、却って諏訪惣領家を中心とした一族の結束を強め、下社金刺氏をも無力にし、ここに始めて諏訪平を領有する一族を誕生させたことを知った。以後の継満には諸説があり、各々信憑性を欠くが、いずれにしても継満一家は歴史上の本舞台からは消えていく。 惣領家は生き残った政満の次男頼満に相続され、同時に大祝に即位した。このとき5歳であった。
諏訪上社大祝諏訪頼満と下社大祝金刺昌春の戦が繰り返され、昌春の拠る萩倉要害が自落して、大永5年(1525)、金刺昌春は甲斐国の武田信虎を頼って落ち延びた。
これより先、文明10年12月、深志の小笠原清宗が、享年52で没した。子の長朝が後継となったが若年と侮られ、長朝が不在中に鈴岡の小笠原政秀が深志に侵攻してきた。小笠原長朝は諏訪氏と金刺氏同族間の戦いに介入にし、それに乗じようとする伊賀良の小笠原と戦い、その一方、筑摩と安曇地方で勢力を広げようとしたため周辺の豪族と争乱を繰り広げていた。長朝は、安曇地方の北部の雄族仁科氏とも争うことになる。長朝は、戦線が拡大し手薄になった府中を、諏訪惣領家政満による攻撃を受け形成が次第に不利になっていた。鈴岡の小笠原政秀が諸所に転戦する長朝の不在をついてきた。家臣団は防ぎきれず、長朝の母と妻子らを守護し、相伝文書を携え更級郡牧城の香坂氏を頼って逃れた。やがて長朝も寄寓してきた。府中の小笠原家存亡の危機に至った。小笠原政秀は長朝の本拠地林館(松本市)を奪い、深志にとどまり安筑(あんちく)2郡を合わせて領有し、名実共に小笠原惣領家たらんとした。しかし安筑2郡の国衆は反発し治政不能の争乱状態となった。やむなく長朝と和睦し、家伝の文書を譲り受け、代わりに、長朝を養子とし府中に返した。香坂氏は長朝と同盟関係となり、延徳元年(1489)8月、府中へ出兵し長朝に助勢している。
数年後、松尾の小笠原定基(光康の孫)が鈴岡の小笠原政秀父子を誘殺し伊賀良を掌握した。定基は勢いのまま、伊那地方制覇に奔走する一方、しばしば伊勢宗瑞(北条早雲)から要請され三河国に出兵し、更に遠江の大河原貞綱にも頼られ出陣している。その度重なる動員で、主力兵力の伊那地方の農民社会が崩壊し貧窮化する。そこへ府中の小笠原長棟(長朝の子)が3年間に亘って執拗に介入し、天文3年(1534)小笠原定基はついに降伏した。こうして信濃の小笠原氏は府中の小笠原家に統一され、長棟は次男の信定を松尾城に配して、府中から伊賀良までの完全支配を達成した。
この数年後、小笠原長棟の跡を継いだ小笠原長時が、甲斐国から侵攻してきた武田晴信と戦うことになる。



















