(前回)
『彼を知り己を知れば百戦殆(あやう)からず』(知彼知己、百戦不殆)は、言わずと知れた孫子の有名な言葉だ。戦いにおいて、敵方の情報は勝敗を左右するほどの重要性を持つ。言い換えれば「情報は戦局を制す」ということだ。敵の情報を知らなかったために、思わぬ不覚をとってしまったケースは多い。有名なところでは、平家が富士川に野営している時に渡り鳥の巣立ちの音に「すわ、源氏の襲来か?!」驚いて逃げたため、多くの死傷者を出したことが思い出される。
今回の話は、逆に敵方情報を正確に得ていなかったために、みすみす勝利を取り逃がしてしまったケースだ。
***************************
馮夢龍『智嚢』【巻24 / 872 / 太子晃】(私訳・原文)
北魏の帝が軽騎を使って柔然を攻撃させた。兵を4グループに分けて別々の道を取らせた。魏帝が鹿渾谷に到達した時敕連可汗の軍に出会った。太子の拓跋晃が言うには「敵は思いもかけない時に大軍が現われたので慌てているはずです。時を失わず、すぐにでも進撃しましょう。」その意見に対して尚書の劉潔は「敵の陣営は埃が高く舞い上がっています。きっと人数が多いのでしょう。味方の軍勢が来るのを待ってから攻めても遅くありません。」と反対した。拓跋晃は「埃が高く舞い上がっているのは敵の兵士が慌てている証拠です。慌てていないのなら、どうして軍営の上に埃が舞い上がることなどありましょうか?」魏帝は敵の人数の方がこちらより多いのではないかと疑い、攻撃命令を下さなかった。その間に柔然は遥か遠くに遁走して、追いつこうにも追いつくことができなくなってしまった。たまたま、敵の偵察の騎兵を捕まえることができた。問いただしてみると、言うには「柔然の主は魏軍の来るのを全く予想していませんでした。それで、慌てて北へ逃げました。逃走して6,7日経ってようやく追手がこないことを知るや、始めてゆっくりと進むようになりました。」北魏の帝はこれを聞いて悔やんだ。
魏主以軽騎襲柔然、分兵為四道。魏主至鹿渾谷、遇敕連可汗。太子晃曰:「賊不意大軍猝至、宜掩其不備、速進撃之。」尚書劉潔曰:「賊営塵盛、其衆必多、不如須大軍至撃之。」晃曰:「塵盛者、軍士驚擾也、何得営上而有塵乎?」魏主疑之、不急撃。柔然遁、追之不及。獲其候騎、曰:「柔然不覚魏軍至、惶駭北走、経六七日、知無追者、始乃徐行。」魏主深悔之。
***************************
草原の遊牧民は、幼いころから馬に乗り慣れているので、馬上でも寝ることができるともいわれる。桑原隲藏の『元時代の蒙古人』には遊牧民のモンゴル人は戦争ともなれば兵士一人が馬18頭を連れていくという。乗っている馬が疲れれば、替わりの馬に乗り、草原を疾駆する。それで、モンゴル兵の襲撃は噂より早く来るので、どの城も準備が間に合わなかったほどだといわれる。概算、一日に少なく見積もっても300Kmを走破するはずだ。
モンゴルの話が柔然にも適用されるとすると、敕連可汗は魏の大軍に不意に出会ったために狼狽して草原を疾駆し6、7日してから始めて安心したということは、2000Kmも走ったことになる。日本でいうと、青森から鹿児島まで駆け抜けてようやく、敵から逃れきったと安心ができた、という訳だ。なんとも、日本人の地理感覚ではぶっとんでいる距離だ!

ところで、日本では、築城するとなると、石と漆喰が必須と考える。それ以外の材料としては、木材ぐらいしか思い当たらない。しかし、中国の黄河流域から北の領域の冬は日本人の想像を絶するような極寒なので、冬の城壁には便利なものが手近にある。
***************************
馮夢龍『智嚢』【巻24 / 873 / 司馬楚之】(私訳・原文)
司馬楚之が軍隊の食糧を管理していた時、遊牧民の柔然が食糧を奪おうと計画していた。ある日突然、ロバの耳が切られたとの報告を受けた司馬楚之は「これは必ず、賊が軍営に入ろうとして偵察しに来て、その証拠に切ったに違いない。賊の襲来は間近い、急いで準備せよ」と命令した。そして柳を伐り、城壁とし、その上に水をかけた。城が出来上がって柔然が襲ってきたが、氷が堅くて滑るので攻めることができずに退散した。
司馬楚之別将督軍糧、柔然欲撃之。俄軍中有告失驢耳者、楚之曰:「此必賊遣奸人入営覘伺、割以為信耳、賊至不久、宜急為備。」乃伐柳為城、以水灌之、城立而柔然至、氷堅滑不可攻、乃散走。
***************************
昔、アメリカのビッツバーグに留学したことがあったが、冬には、マイナス20度になることも珍しくなかった。真冬のある朝、シャワーを浴びてから大学に行こうとして、たまたま頭の髪の毛がまだ乾ききっていなかった。寮の玄関を出た途端に髪の毛がパリパリと凍ってしまった。それほどの寒さでは、水も凍れば鉄よりも堅くなる道理だ。
さて、この事件は、5世紀の中国の話だが、高麗でも城壁に柳の枝を組んで、そこに水をかけてかちんこちんの氷の防壁を作ったと、高麗史および高麗史節要に記載がある(1361年 高麗史 巻113、高麗史節要 巻27)。石の城壁であれば、敵ははしごを掛けてよじ登ってこれるが、氷の城壁では滑ってしまうので、攻略できず、敵は諦めて引き返した。
(続く。。。)
『彼を知り己を知れば百戦殆(あやう)からず』(知彼知己、百戦不殆)は、言わずと知れた孫子の有名な言葉だ。戦いにおいて、敵方の情報は勝敗を左右するほどの重要性を持つ。言い換えれば「情報は戦局を制す」ということだ。敵の情報を知らなかったために、思わぬ不覚をとってしまったケースは多い。有名なところでは、平家が富士川に野営している時に渡り鳥の巣立ちの音に「すわ、源氏の襲来か?!」驚いて逃げたため、多くの死傷者を出したことが思い出される。
今回の話は、逆に敵方情報を正確に得ていなかったために、みすみす勝利を取り逃がしてしまったケースだ。
***************************
馮夢龍『智嚢』【巻24 / 872 / 太子晃】(私訳・原文)
北魏の帝が軽騎を使って柔然を攻撃させた。兵を4グループに分けて別々の道を取らせた。魏帝が鹿渾谷に到達した時敕連可汗の軍に出会った。太子の拓跋晃が言うには「敵は思いもかけない時に大軍が現われたので慌てているはずです。時を失わず、すぐにでも進撃しましょう。」その意見に対して尚書の劉潔は「敵の陣営は埃が高く舞い上がっています。きっと人数が多いのでしょう。味方の軍勢が来るのを待ってから攻めても遅くありません。」と反対した。拓跋晃は「埃が高く舞い上がっているのは敵の兵士が慌てている証拠です。慌てていないのなら、どうして軍営の上に埃が舞い上がることなどありましょうか?」魏帝は敵の人数の方がこちらより多いのではないかと疑い、攻撃命令を下さなかった。その間に柔然は遥か遠くに遁走して、追いつこうにも追いつくことができなくなってしまった。たまたま、敵の偵察の騎兵を捕まえることができた。問いただしてみると、言うには「柔然の主は魏軍の来るのを全く予想していませんでした。それで、慌てて北へ逃げました。逃走して6,7日経ってようやく追手がこないことを知るや、始めてゆっくりと進むようになりました。」北魏の帝はこれを聞いて悔やんだ。
魏主以軽騎襲柔然、分兵為四道。魏主至鹿渾谷、遇敕連可汗。太子晃曰:「賊不意大軍猝至、宜掩其不備、速進撃之。」尚書劉潔曰:「賊営塵盛、其衆必多、不如須大軍至撃之。」晃曰:「塵盛者、軍士驚擾也、何得営上而有塵乎?」魏主疑之、不急撃。柔然遁、追之不及。獲其候騎、曰:「柔然不覚魏軍至、惶駭北走、経六七日、知無追者、始乃徐行。」魏主深悔之。
***************************
草原の遊牧民は、幼いころから馬に乗り慣れているので、馬上でも寝ることができるともいわれる。桑原隲藏の『元時代の蒙古人』には遊牧民のモンゴル人は戦争ともなれば兵士一人が馬18頭を連れていくという。乗っている馬が疲れれば、替わりの馬に乗り、草原を疾駆する。それで、モンゴル兵の襲撃は噂より早く来るので、どの城も準備が間に合わなかったほどだといわれる。概算、一日に少なく見積もっても300Kmを走破するはずだ。
モンゴルの話が柔然にも適用されるとすると、敕連可汗は魏の大軍に不意に出会ったために狼狽して草原を疾駆し6、7日してから始めて安心したということは、2000Kmも走ったことになる。日本でいうと、青森から鹿児島まで駆け抜けてようやく、敵から逃れきったと安心ができた、という訳だ。なんとも、日本人の地理感覚ではぶっとんでいる距離だ!

ところで、日本では、築城するとなると、石と漆喰が必須と考える。それ以外の材料としては、木材ぐらいしか思い当たらない。しかし、中国の黄河流域から北の領域の冬は日本人の想像を絶するような極寒なので、冬の城壁には便利なものが手近にある。
***************************
馮夢龍『智嚢』【巻24 / 873 / 司馬楚之】(私訳・原文)
司馬楚之が軍隊の食糧を管理していた時、遊牧民の柔然が食糧を奪おうと計画していた。ある日突然、ロバの耳が切られたとの報告を受けた司馬楚之は「これは必ず、賊が軍営に入ろうとして偵察しに来て、その証拠に切ったに違いない。賊の襲来は間近い、急いで準備せよ」と命令した。そして柳を伐り、城壁とし、その上に水をかけた。城が出来上がって柔然が襲ってきたが、氷が堅くて滑るので攻めることができずに退散した。
司馬楚之別将督軍糧、柔然欲撃之。俄軍中有告失驢耳者、楚之曰:「此必賊遣奸人入営覘伺、割以為信耳、賊至不久、宜急為備。」乃伐柳為城、以水灌之、城立而柔然至、氷堅滑不可攻、乃散走。
***************************
昔、アメリカのビッツバーグに留学したことがあったが、冬には、マイナス20度になることも珍しくなかった。真冬のある朝、シャワーを浴びてから大学に行こうとして、たまたま頭の髪の毛がまだ乾ききっていなかった。寮の玄関を出た途端に髪の毛がパリパリと凍ってしまった。それほどの寒さでは、水も凍れば鉄よりも堅くなる道理だ。
さて、この事件は、5世紀の中国の話だが、高麗でも城壁に柳の枝を組んで、そこに水をかけてかちんこちんの氷の防壁を作ったと、高麗史および高麗史節要に記載がある(1361年 高麗史 巻113、高麗史節要 巻27)。石の城壁であれば、敵ははしごを掛けてよじ登ってこれるが、氷の城壁では滑ってしまうので、攻略できず、敵は諦めて引き返した。
(続く。。。)
















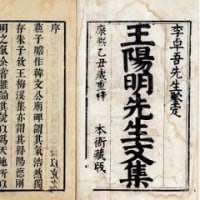


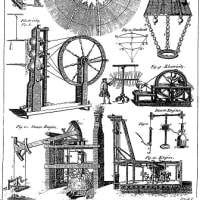







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます