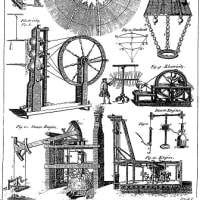(前回から続く。。。)
2.私の哲学遍歴
『私の哲学遍歴』という大げさなタイトルを掲げたが、素人の哲学愛好家として、私が感銘と恩恵を受けた哲学者と哲学書を振り返ってみたい。
以前のブログ
百論簇出:(第100回目)『哲学者と哲学屋』
にも書いたように、20歳の時にそれまで自分がそれまで何も真剣に考えていなかった事に気づいた私は工学部の勉強よりも人生について考えるために時間をついやした。そして次第に、哲学に惹かれていったが、それはドイツ観念論のような正統なものよりショーペンハウアーやモンテーニュのような世間的には通俗的と、あるいは素人的と見下されている流派であった。
そのような時に、同じ下宿にいた哲学科・博士課程の渡部さんとの話で、次第に自分が求めている哲学は大学では学ぶことができないということを理解して、がっかりした。
しかし、ドイツ留学をきっかけとしてモンテーニュやショーペンハウアーを媒介としてプラトン、キケロ、セネカなど、主としてギリシャ・ローマ時代の哲学、すなわちヨーロッパ精神がキリスト教に染められる前のヨーロッパ哲学の本流の書物を知ることができた。
これらの人々の本から受けた影響は、あれから30数年たった今なお強烈に残っている。もともと私は子供のころから他人の意見に振り回されることになじめなかったので、日本にいるときは何かというと、押さえつけれるような心理的圧迫感を感じていた。しかし、ショーペンハウアーの本で Selbstdenken つまり、独自の考えを持つべしとの強い主張に出会って、鎖から解き放たれように感じた。実際にドイツで暮らした一年の間、ドイツ人が子供から大人まで、男女問わず、自分の意見をはっきりともち、とことん自己主張する姿勢に一方では辟易しながらも、他方ではそれまでの自分を振り返り徹底さに欠けていたことを認識した。この意味で、私にとっては、ショーペンハウアーは哲学の本道の入り口まで導いてくれた恩師である。
尚、Selbstdenken は、斎藤忍随氏の名訳で岩波文庫『読書について 他二篇』に『思索』として出ている。僅か十数ぺージの小編であるが、読む人に大きなインパクトをもたらすに違いないと思っている。
ショーペンハウアーに次いで、私のギリシャ・ローマ趣味を不動のものにしたのがモンテーニュの『エセー』であった。この本で私は初めてヨーロッパ人が考える本物の哲学に出会ったと感じた。もっとも世間的には、モンテーニュは哲学者ではなく、単なるモラリストだと低く評価されているようだが、私にとってはそういうことは問題ではなかった。モンテーニュが愛惜を込めて描きだしたギリシャ・ローマの哲人たちはいずれも強烈な自由精神の持ち主であることが私には強く印象に残った。モンテーニュが一番好んだギリシャ人はプルタークであった。モンテーニュはギリシャ語は読めなかったが、ちょうど直前にアミヨ(Jacques Amyot)がフランス語に翻訳したプルタークの列伝とモラリアを愛読した。とりわけモラリアは彼のエッセーの元になったと言われているほどプルタークの文体や中庸を重んじる思想に心酔したようだ。
私もプルタークのこれらの書を読んだが、モラリアはどうも各編の主題がとらえどころがない感じがした。それに反し、列伝はアレキサンダーやカエサル、キケロという歴史上の人物を間近にみるような描写が大いに気に入った。初めは河野与一氏の訳した岩波文庫の『プルターク英雄伝』で読んだ。この本は、活字が旧字体である上に注が小さなフォントの割注の形で入れられているため、一般的に言って極めて読みにくいであろう。文体も多少時代がかっていて古めかしい。しかし、後日、Loebのギリシャ語で読むときに参照したが、翻訳は非常に正確であった。ただ、河野与一氏の翻訳の原本はギリシャ語ではなく、チィグラー(Konrat Ziegler)のドイツ語訳からの重訳との噂もある。

【出典】Socrates, 500 Drachmas (1955)
閑話休題
ギリシャの哲学者、プラトンからは初期の対話編でソクラテスが若者を相手にした対話を通じて物事を根本から考える思考方法 - これを通常、弁証法(dialektike)と呼ぶ - を学んだ。それまで私は物事を論理的に話す仕方が全く分からず、言ってみれば、口から出まかせにしゃべっていたので、言いたいことが言えずに我れながらいつももどかしく思っていた。しかし、ソクラテスの話し方を、一行ずつ丁寧にノートに取ってみて分析すると、あたかも幾何学の証明問題を解く時のような透明な論理のつながりを感じることができた。私はその時初めて、『言葉によって、物事を論理的に表現することができるのだ』と理解したのであった。この意識改革によって、私はようやく大学生活の終盤になって日本語をまともに話せるようになった。
一方、ローマ哲人、セネカからは迫力ある見事なレトリックを駆使した文章に、最初からぐいぐいと惹き込まれた。彼の説くストア派の教説(ドグマ)には、倫理的な観点、たとえば『無知は悪』や『不動心を養え』には賛同するものの、自然界の理解、たとえば『動物には理性が無い』や『宇宙は意志をもった創造主が統治している』などには疑問を感じた。しかし、総体的にストア派が理想とした人格については躍動に満ちた活き活きとしたものを感じた。当時は、そして今なお、私は秘かに不肖・ストア派を自認している。(本流のストア派からみれば、夾雑物が多いといわれそうだが。。。)
【参照ブログ】
想溢筆翔:(第46回目)『私の読書遍歴 -- 哲学から歴史へ』
沂風詠録:(第84回目)『私の語学学習(その18)』
さて、ドイツ観念論哲学の巨匠、カントに関しては、
沂風詠録:(第87回目)『私の語学学習(その21)』
で述べたが、私が読んだ唯一の本格的な哲学書であった。22歳当時、私はドイツ留学から帰国したばかりであったので、ヨーロッパの基底文化であるキリスト教の本体を知りたいという欲求を強く抱いていた。一言で言うと、『神は実在するか?実在するならその正体は何か?』というものであった。宗教と言う面では、世間一般の日本人と全く変わらない程度の浅い信仰心しか持ち合わせていない私であったので、キリスト教にしろ、仏教・神道にしろ信仰心とか帰依するという概念を全く持っていなかった。それで、神とは何か、という問題を取り組むのに、宗教から攻めるべきか、哲学から攻めるべきか、全く分からなかった。そういったなか、たまたま名前だけを知っていたカントの『純粋理性批判』(Kritik der reinen Vernunft)にとりかかり、次いで、『判断力批判』(Kritik der Urteilskraft)を読了した。これらの本によって、図らずも私にとって長年の課題であった神の存在についての納得できる解答を得た。つまり『神の存在は論理的には否定せざると得ない』というのが哲学者カントの結論だった。
カントのこの結論は私を十分納得させた。それは、カントが人間が物を認識するというのは、どういうステップを踏まないといけないか、という課題をあたかも幾何学の証明問題の解く時のように、まず公理系を構築してから論理的に証明していったからだ。確かに、現時点から見れば、カントが自明とした幾つかの前提条件、たとえば『ニュートン的時空の概念』や『物そのもの(Ding an sich)』『先験的認識(das a priori, transzendentale Schema)』などその妥当性を認めがたいものがあるのも事実だ。実際、その不備を補うべくカント以降のヨーロッパの近代哲学は発展してきたのであるが、それは認識論という極めて形式論的な形而上学になった。つまり、哲学という母屋が形而上学という店子に乗っ取られてしまったのだ。具体的には、フッサールやハイデッガーの現象学(Phänomenologie)や存在論(Ontologie)の系統である。彼らの本をちらっとは見たものの、私の粗雑な頭では到底ついていけないものを感じて、きっぱりと近代哲学(つまり形而上学)から離れることにした。
そういう経緯もあって、その後私の興味は次第に『...であるべき』論が主体の哲学(Sollen哲学)から、『...であった』論が主体の歴史に変わった。それは、私の当初の疑問であった『人間はいかに生くべきか』という問いに対してこれら哲学者が述べていることに対して私自身で判断するには経験不足であったと、気がついたからだった。この点に気づいてからは、私の読書は次第に歴史、それも特に人物論主体の記述が多い歴史に興味が移っていったのであった。
(続く。。。)
2.私の哲学遍歴
『私の哲学遍歴』という大げさなタイトルを掲げたが、素人の哲学愛好家として、私が感銘と恩恵を受けた哲学者と哲学書を振り返ってみたい。
以前のブログ
百論簇出:(第100回目)『哲学者と哲学屋』
にも書いたように、20歳の時にそれまで自分がそれまで何も真剣に考えていなかった事に気づいた私は工学部の勉強よりも人生について考えるために時間をついやした。そして次第に、哲学に惹かれていったが、それはドイツ観念論のような正統なものよりショーペンハウアーやモンテーニュのような世間的には通俗的と、あるいは素人的と見下されている流派であった。
そのような時に、同じ下宿にいた哲学科・博士課程の渡部さんとの話で、次第に自分が求めている哲学は大学では学ぶことができないということを理解して、がっかりした。
しかし、ドイツ留学をきっかけとしてモンテーニュやショーペンハウアーを媒介としてプラトン、キケロ、セネカなど、主としてギリシャ・ローマ時代の哲学、すなわちヨーロッパ精神がキリスト教に染められる前のヨーロッパ哲学の本流の書物を知ることができた。
これらの人々の本から受けた影響は、あれから30数年たった今なお強烈に残っている。もともと私は子供のころから他人の意見に振り回されることになじめなかったので、日本にいるときは何かというと、押さえつけれるような心理的圧迫感を感じていた。しかし、ショーペンハウアーの本で Selbstdenken つまり、独自の考えを持つべしとの強い主張に出会って、鎖から解き放たれように感じた。実際にドイツで暮らした一年の間、ドイツ人が子供から大人まで、男女問わず、自分の意見をはっきりともち、とことん自己主張する姿勢に一方では辟易しながらも、他方ではそれまでの自分を振り返り徹底さに欠けていたことを認識した。この意味で、私にとっては、ショーペンハウアーは哲学の本道の入り口まで導いてくれた恩師である。
尚、Selbstdenken は、斎藤忍随氏の名訳で岩波文庫『読書について 他二篇』に『思索』として出ている。僅か十数ぺージの小編であるが、読む人に大きなインパクトをもたらすに違いないと思っている。
ショーペンハウアーに次いで、私のギリシャ・ローマ趣味を不動のものにしたのがモンテーニュの『エセー』であった。この本で私は初めてヨーロッパ人が考える本物の哲学に出会ったと感じた。もっとも世間的には、モンテーニュは哲学者ではなく、単なるモラリストだと低く評価されているようだが、私にとってはそういうことは問題ではなかった。モンテーニュが愛惜を込めて描きだしたギリシャ・ローマの哲人たちはいずれも強烈な自由精神の持ち主であることが私には強く印象に残った。モンテーニュが一番好んだギリシャ人はプルタークであった。モンテーニュはギリシャ語は読めなかったが、ちょうど直前にアミヨ(Jacques Amyot)がフランス語に翻訳したプルタークの列伝とモラリアを愛読した。とりわけモラリアは彼のエッセーの元になったと言われているほどプルタークの文体や中庸を重んじる思想に心酔したようだ。
私もプルタークのこれらの書を読んだが、モラリアはどうも各編の主題がとらえどころがない感じがした。それに反し、列伝はアレキサンダーやカエサル、キケロという歴史上の人物を間近にみるような描写が大いに気に入った。初めは河野与一氏の訳した岩波文庫の『プルターク英雄伝』で読んだ。この本は、活字が旧字体である上に注が小さなフォントの割注の形で入れられているため、一般的に言って極めて読みにくいであろう。文体も多少時代がかっていて古めかしい。しかし、後日、Loebのギリシャ語で読むときに参照したが、翻訳は非常に正確であった。ただ、河野与一氏の翻訳の原本はギリシャ語ではなく、チィグラー(Konrat Ziegler)のドイツ語訳からの重訳との噂もある。

【出典】Socrates, 500 Drachmas (1955)
閑話休題
ギリシャの哲学者、プラトンからは初期の対話編でソクラテスが若者を相手にした対話を通じて物事を根本から考える思考方法 - これを通常、弁証法(dialektike)と呼ぶ - を学んだ。それまで私は物事を論理的に話す仕方が全く分からず、言ってみれば、口から出まかせにしゃべっていたので、言いたいことが言えずに我れながらいつももどかしく思っていた。しかし、ソクラテスの話し方を、一行ずつ丁寧にノートに取ってみて分析すると、あたかも幾何学の証明問題を解く時のような透明な論理のつながりを感じることができた。私はその時初めて、『言葉によって、物事を論理的に表現することができるのだ』と理解したのであった。この意識改革によって、私はようやく大学生活の終盤になって日本語をまともに話せるようになった。
一方、ローマ哲人、セネカからは迫力ある見事なレトリックを駆使した文章に、最初からぐいぐいと惹き込まれた。彼の説くストア派の教説(ドグマ)には、倫理的な観点、たとえば『無知は悪』や『不動心を養え』には賛同するものの、自然界の理解、たとえば『動物には理性が無い』や『宇宙は意志をもった創造主が統治している』などには疑問を感じた。しかし、総体的にストア派が理想とした人格については躍動に満ちた活き活きとしたものを感じた。当時は、そして今なお、私は秘かに不肖・ストア派を自認している。(本流のストア派からみれば、夾雑物が多いといわれそうだが。。。)
【参照ブログ】
想溢筆翔:(第46回目)『私の読書遍歴 -- 哲学から歴史へ』
沂風詠録:(第84回目)『私の語学学習(その18)』
さて、ドイツ観念論哲学の巨匠、カントに関しては、
沂風詠録:(第87回目)『私の語学学習(その21)』
で述べたが、私が読んだ唯一の本格的な哲学書であった。22歳当時、私はドイツ留学から帰国したばかりであったので、ヨーロッパの基底文化であるキリスト教の本体を知りたいという欲求を強く抱いていた。一言で言うと、『神は実在するか?実在するならその正体は何か?』というものであった。宗教と言う面では、世間一般の日本人と全く変わらない程度の浅い信仰心しか持ち合わせていない私であったので、キリスト教にしろ、仏教・神道にしろ信仰心とか帰依するという概念を全く持っていなかった。それで、神とは何か、という問題を取り組むのに、宗教から攻めるべきか、哲学から攻めるべきか、全く分からなかった。そういったなか、たまたま名前だけを知っていたカントの『純粋理性批判』(Kritik der reinen Vernunft)にとりかかり、次いで、『判断力批判』(Kritik der Urteilskraft)を読了した。これらの本によって、図らずも私にとって長年の課題であった神の存在についての納得できる解答を得た。つまり『神の存在は論理的には否定せざると得ない』というのが哲学者カントの結論だった。
カントのこの結論は私を十分納得させた。それは、カントが人間が物を認識するというのは、どういうステップを踏まないといけないか、という課題をあたかも幾何学の証明問題の解く時のように、まず公理系を構築してから論理的に証明していったからだ。確かに、現時点から見れば、カントが自明とした幾つかの前提条件、たとえば『ニュートン的時空の概念』や『物そのもの(Ding an sich)』『先験的認識(das a priori, transzendentale Schema)』などその妥当性を認めがたいものがあるのも事実だ。実際、その不備を補うべくカント以降のヨーロッパの近代哲学は発展してきたのであるが、それは認識論という極めて形式論的な形而上学になった。つまり、哲学という母屋が形而上学という店子に乗っ取られてしまったのだ。具体的には、フッサールやハイデッガーの現象学(Phänomenologie)や存在論(Ontologie)の系統である。彼らの本をちらっとは見たものの、私の粗雑な頭では到底ついていけないものを感じて、きっぱりと近代哲学(つまり形而上学)から離れることにした。
そういう経緯もあって、その後私の興味は次第に『...であるべき』論が主体の哲学(Sollen哲学)から、『...であった』論が主体の歴史に変わった。それは、私の当初の疑問であった『人間はいかに生くべきか』という問いに対してこれら哲学者が述べていることに対して私自身で判断するには経験不足であったと、気がついたからだった。この点に気づいてからは、私の読書は次第に歴史、それも特に人物論主体の記述が多い歴史に興味が移っていったのであった。
(続く。。。)