

(註)3月15日に開かれた「本多延嘉追悼50年の集い」の記事のつづき。向井拓治さんの開会のあいさつを転載します。
最後の探究派として――開会のあいさつ
向井拓治
本日はかくも多数の皆さんのご参加をうけて、本当に感無量です。私は5年前の45周年のときに追悼の会を開きましたけれど、その時の参加者はこれの半分以下、45人でした(2020年10月25日、全水道会館)。それから考えて、本当に今日はありがとうございました。
いろいろ前もって書いてきたんですけども、本当にもうこれだけで私のあいさつの終わりにしたいと思います。
いくつか情報だけお伝えします。
私は1956年に東京工業大学に入りました。当時東工大は5 、6人の活動家しか全学連の行動には参加しないというような状態でしたけれども、その1年後には300人近い学生を全学連の統一行動に参加させるという大学にしました。当時の学生数は1500人ですから、300人というと、もう5分の1の学生を参加させるというふうにしました。
いろいろ前もって書いてきたんですけども、本当にもうこれだけで私のあいさつの終わりにしたいと思います。
いくつか情報だけお伝えします。
私は1956年に東京工業大学に入りました。当時東工大は5 、6人の活動家しか全学連の行動には参加しないというような状態でしたけれども、その1年後には300人近い学生を全学連の統一行動に参加させるという大学にしました。当時の学生数は1500人ですから、300人というと、もう5分の1の学生を参加させるというふうにしました。
私が革共同に参加したのはそれからさらに時間がありまして、1959年の1月に革共同に加盟いたしました。しかし、59年8月、あの革共同の第二次分裂にあたっては、いわゆる大川スパイ問題があり、私は大川治郎(註:本名は小泉恒彦)だけでなくて、あの黒田寛一もクロなんだ、という信念を持っていましたので、全国委員会派に参加しなかった。
私が革共同に復帰したのは1961年の6月です。その時に本多さんに「お前はなぜ第二次分裂にあたってこちらに来なかったんだ」というふうに詰問されました。私は信念を持って「黒田はクロである。大川だけでなくて黒田もクロだ」というふうにいいましたところ、じゃあそれを復帰の意見書として書け、というふうにいわれました。当時の黒田の権威に対して私がそこまで書くことはできない、ということをいって、結局何も書かずに復帰を認められました。
今、「本多延嘉年譜 1934-1975」をいただきまして、中を見ると、政治局内では黒田はもうコテンコテンに批判されているんですね。そういう状態だったということを全然知らない私は、とてもじゃないが私は黒田批判を書くことはできない、ということで何も書かずに復帰を認められました。
当時の探究派はもう全員亡くなりました。(註:探究派とは、1958年7月の革共同第1次分裂以来、黒田、本多を中心に反帝国主義・反スターリン主義を掲げてきたグループ。第2次分裂で革共同全国委員会を創設。他に木下尊晤(野島三郎)、白井朗(山村克)、飯島善太郎(広田広)、小野田猛史(北川登)など。)
最後に、ここに参加する皆さんもぜひ長生きして欲しいと思うんです。これからがたたかいになるんじゃないか、というふうに思います。私はこの2月でクリニックをやめましたけれども、1985年に革共同を離れ、その間に医者になりました。その医者の立場からも皆さんに長生きしてほしい。これからがたたかいだということを申し上げて、開会の挨拶にかえたいと思います。
(医師、元革共同東京西部地区委員長)
当時の探究派はもう全員亡くなりました。(註:探究派とは、1958年7月の革共同第1次分裂以来、黒田、本多を中心に反帝国主義・反スターリン主義を掲げてきたグループ。第2次分裂で革共同全国委員会を創設。他に木下尊晤(野島三郎)、白井朗(山村克)、飯島善太郎(広田広)、小野田猛史(北川登)など。)
最後に、ここに参加する皆さんもぜひ長生きして欲しいと思うんです。これからがたたかいになるんじゃないか、というふうに思います。私はこの2月でクリニックをやめましたけれども、1985年に革共同を離れ、その間に医者になりました。その医者の立場からも皆さんに長生きしてほしい。これからがたたかいだということを申し上げて、開会の挨拶にかえたいと思います。
(医師、元革共同東京西部地区委員長)










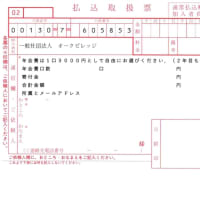




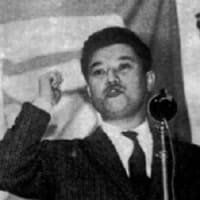









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます