
(註)3月15日「本多延嘉追悼50年の集い」の後の懇親会での発言のうち、渡部義就さんのもの(一部加筆)を転載します。
本多さんの革命党建設論と人間観をめぐって
渡部義就
本多さんの革命党建設論と人間観をめぐって
渡部義就
本多延嘉さんから教えてもらったこと、人物像など、尽きないほど思い出されます。
今日は二つのエピソードだけお話しします。
一つは、確か1972年のことだったと思います。田川和夫氏(政治局員)が革共同を離れるときに、本多さんが田川氏と党務の引き継ぎ、田川氏のその後のことなどについて話し合われました。本多さんは田川氏を壊滅的に批判していましたが、彼を石もて追うようなことはせず、除名処分にもしませんでした。
その数日後、「今日はタクシーで来い」と言われ、居酒屋に案内されて話を聞く機会がありました。多分、今後の新たな任務で私が使いものになるかどうかの品定めだったと思います。
まず本多さんは「俺は酒の席では、政治の話と金の話、女の話はしないことにしている。下司根性と付き合うのはいやだからな」と言って、雑談も含めていろいろな話をされました。
その中で「日本でも文化革命は必要になるだろう。だけど毛沢東のように、訳も分からない連中をけしかけて騒ぎ立てるようなことでは駄目だ。将来、党が本当に労働者階級の党になっていくためには政治、文化、歴史などの人間生活について包括的にとらえ、考え、理解でき、問題を解決できるようになっていかなければならないと考えている。」「党に結集してくる人たちは様々な生活体験、教育、政治体験など一様ではないのだし、一枚岩の党なんて初めからあり得ないんだよ。」「革命をやったって、その日から腹いっぱい飯を喰えるようになるわけじゃないし、民衆の生活がすぐに良くなるわけじゃない。いろんな問題に対する労働者階級の主体的な取り組み方が変わっていくということでしかない。」「だから思想上も理論上も色々なものが入り込んでくる。そうした時に『分派』を認める、ということではないけど、色んなグループが生じるのは当然だし、認めなくてはならないだろう。相互に議論し批判しあいながら統一していく道筋を見出していくしかないんだ。そうしないと労働者階級がプロレタリア革命を通して解決するべき課題を見つけ出して、歴史的に具体的に解決することなんてできないと考えている。」
そんな意味のことを言われました。
2006年か2007年頃、木下尊晤(野島三郎、本多さんの盟友)さんにこの話をしたところ、「本多とは何度も話しに出た。1966年に『中国革命論』を書いたときに、彼はそのことを書いている」と言っていました。
『本多延嘉著作選」(前進社刊)を読み返すと、その第一巻のⅣ「中国文化大革命批判」、三「紅衛兵運動のさらけ出したもの」の「危機を必然化させた「新民主主義」政策」に次のように書かれています(322ページ)。
まず本多さんは「俺は酒の席では、政治の話と金の話、女の話はしないことにしている。下司根性と付き合うのはいやだからな」と言って、雑談も含めていろいろな話をされました。
その中で「日本でも文化革命は必要になるだろう。だけど毛沢東のように、訳も分からない連中をけしかけて騒ぎ立てるようなことでは駄目だ。将来、党が本当に労働者階級の党になっていくためには政治、文化、歴史などの人間生活について包括的にとらえ、考え、理解でき、問題を解決できるようになっていかなければならないと考えている。」「党に結集してくる人たちは様々な生活体験、教育、政治体験など一様ではないのだし、一枚岩の党なんて初めからあり得ないんだよ。」「革命をやったって、その日から腹いっぱい飯を喰えるようになるわけじゃないし、民衆の生活がすぐに良くなるわけじゃない。いろんな問題に対する労働者階級の主体的な取り組み方が変わっていくということでしかない。」「だから思想上も理論上も色々なものが入り込んでくる。そうした時に『分派』を認める、ということではないけど、色んなグループが生じるのは当然だし、認めなくてはならないだろう。相互に議論し批判しあいながら統一していく道筋を見出していくしかないんだ。そうしないと労働者階級がプロレタリア革命を通して解決するべき課題を見つけ出して、歴史的に具体的に解決することなんてできないと考えている。」
そんな意味のことを言われました。
2006年か2007年頃、木下尊晤(野島三郎、本多さんの盟友)さんにこの話をしたところ、「本多とは何度も話しに出た。1966年に『中国革命論』を書いたときに、彼はそのことを書いている」と言っていました。
『本多延嘉著作選」(前進社刊)を読み返すと、その第一巻のⅣ「中国文化大革命批判」、三「紅衛兵運動のさらけ出したもの」の「危機を必然化させた「新民主主義」政策」に次のように書かれています(322ページ)。
「第二に指摘せねばならないことは、こんにちの中国には(他のスターリン主義諸国とまったく同様に)政府・党の政策を批判する政治的階級基盤がどこにも存在していないということである。……毛沢東とは逆にレーニンは、『左翼小児病(ママ)』のなかで「ソ連では寡頭支配がおこなわれている」と公然といいきったが、だがそのときソ連では共産党内で「グループ」を形成する権利が保障されていたし、工場地帯にはいぜんとして労働者評議会が存在していた。ところがわが「革命中国」には労働者階級が自己の主張を提起する制度的保障すら与えられていないのである。」
本多さんがレーニン主義の党建設論を確固として貫く立場であったことが示されていると思います。
二つ目は「人を尊敬する」ということ。
これも本多さんに誘われて居酒屋での話。「本多さんはどんな人を尊敬していますか」と問うたところ「俺は人を尊敬するなんてしないよ。その人が人類のために、プロレタリア革命のためにどんな役割を果たしたかを評価するだけだ」と言われたことがあります。
その数日後だったか数週間後だったか、清水丈夫氏が前進社のある人を話題にして「最近の活動家は人を尊敬することをしないんだよな。なべさんどう思う」と話しかけられました。つい先日、本多さんの「尊敬」の話があった後なので、うやむやな返事をしたと思います。
清水さんの「尊敬する・しない」という言い方には、「指導部に従う・従わない」という狭い支配的なニュアンスが感じられました。ぎゃくに本多さんの組織観、人間観が非常に巨視的なものだと思ったのでした。
この50年の間に多くの同志が鬼籍に入りました。私は宗像啓介さんが一緒に参加していれば、という思いがこの日一日ずっとありました。
1975年当時、彼は出版部の責任者で本多さんの飲み相手でしたが、「本多さんが居なくなってNC(革共同全国委員会のこと)は終わった」と言ってしばらく家に籠ってしまいました。その後、関西で部落解放全国連の運動に関わり、部落解放闘争の歴史的総括に亡くなるまで取り組んでいましたが、彼の目標は「本多さんの遺志を継ぐってことは、彼を乗り越える仕事をすることだ。お前も手伝え」ということで資料集め、読み込み、整理の手伝いをすることで勉強する機会を与えられました。
その宗像さんが居たら、涙ながらに本多さんを語ったことでしょう。
2025年3月15日、久々に顔を合わせた元同志たちのこの50年を「思い出話」に終わらせるのではなく、それぞれの苦闘や経験から「色んなグループが生じるのは当然だし、認め、相互に議論し批判しあいながら統一していく道筋を見出していく」たたかいの新たな一歩にしたいものです。
(東北大出身、10・8羽田闘争参加者)
2025年3月15日、久々に顔を合わせた元同志たちのこの50年を「思い出話」に終わらせるのではなく、それぞれの苦闘や経験から「色んなグループが生じるのは当然だし、認め、相互に議論し批判しあいながら統一していく道筋を見出していく」たたかいの新たな一歩にしたいものです。
(東北大出身、10・8羽田闘争参加者)
(3・15記事つづく)










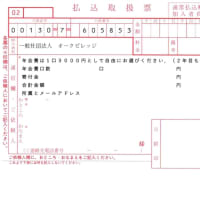




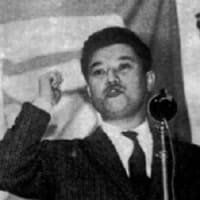









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます