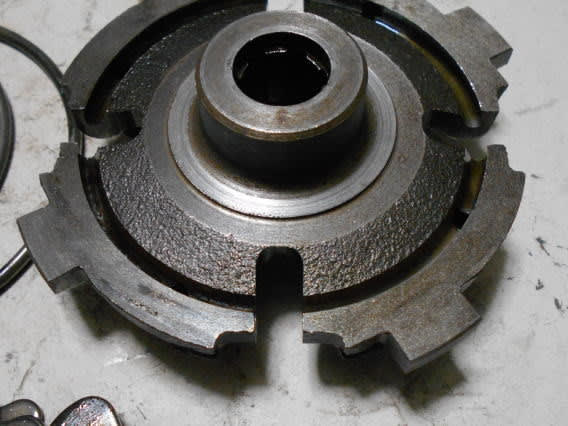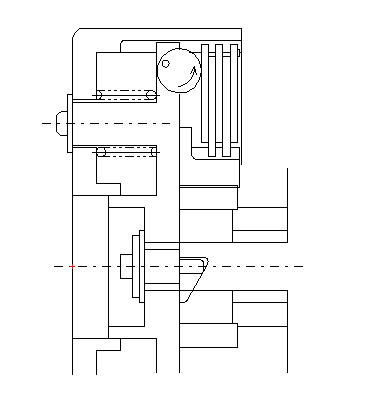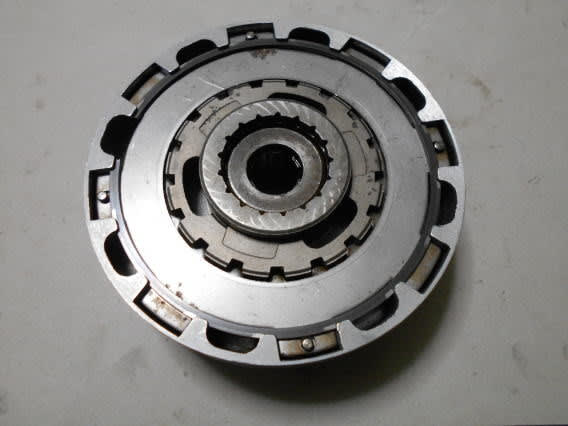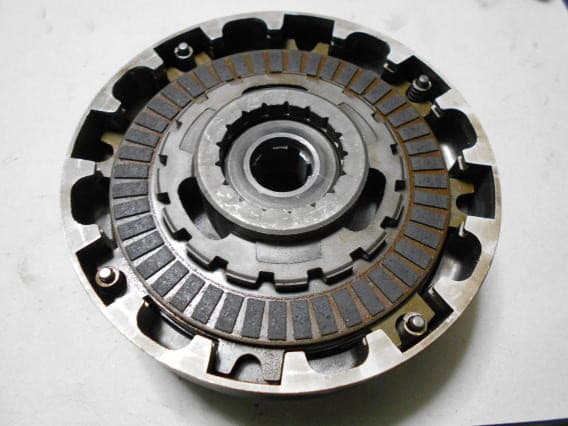カブ70のエンジン特性に合わせた 私オリジナルの6枚ウェイトクラッチ
女房のカブ70に組んで、近所を軽く試乗してフィーリングを確かめた時
なかなか良い感じだったので、
忘れ物を取りに行くついでに会社まで行ってみます。
とは言ってもまずは昼ごはん

夕べの鴨鍋の汁が残っていたので「鴨だしうどん」を作ってみました
昨日の鴨鍋の具は 鴨肉と九条葱だけ
これに、うどんを1玉と油揚げ、玉子を入れて煮込んだら出来上がり。
会社までは片道20キロ 調子を見るにはちょうど良い距離です。

会社では、いつもの屋根付き駐輪場に停めて、忘れ物を取ってきて
明日以降の勤務を確認して帰ります。
70&90ccノーマルの7枚ウェイトのクラッチと私オリジナルの6枚ウェイトのクラッチ
どう変わったかと言うと クラッチミートするエンジン回転数が上がった感じです
ウエイトの数から計算すると、15%くらいは回転数が上がっていることになるわけで
遠心クラッチ機能が実際にクラッチミートする回転数が
7枚ウェイト⇒1300rpmから 私オリジナル⇒1500rpmってところでしょうか?
具体的には、明らかに停止状態からのゼロ発進加速が良くなり
緩い上り坂での1速⇒2速⇒3速のミッションの繋がり感もアップ
さらに、平坦地での2速発進が そんなにストレス無く出来るようになりました。
日本人って、やたら上級志向なので 無駄な機能ばかり追求して
「強化型」と聞くと 全て良いものと勘違いしてしまいますが
本当は自分のバイクの排気量にあった「デ・チューン」のほうが良かったりします。
これからも既製の概念にとらわれず、私なりにカブ70を乗り易くしていきます。
多分、今持っているカブが終のバイクになると思うのでね。
女房のカブ70に組んで、近所を軽く試乗してフィーリングを確かめた時
なかなか良い感じだったので、
忘れ物を取りに行くついでに会社まで行ってみます。
とは言ってもまずは昼ごはん

夕べの鴨鍋の汁が残っていたので「鴨だしうどん」を作ってみました
昨日の鴨鍋の具は 鴨肉と九条葱だけ
これに、うどんを1玉と油揚げ、玉子を入れて煮込んだら出来上がり。
会社までは片道20キロ 調子を見るにはちょうど良い距離です。

会社では、いつもの屋根付き駐輪場に停めて、忘れ物を取ってきて
明日以降の勤務を確認して帰ります。
70&90ccノーマルの7枚ウェイトのクラッチと私オリジナルの6枚ウェイトのクラッチ
どう変わったかと言うと クラッチミートするエンジン回転数が上がった感じです
ウエイトの数から計算すると、15%くらいは回転数が上がっていることになるわけで
遠心クラッチ機能が実際にクラッチミートする回転数が
7枚ウェイト⇒1300rpmから 私オリジナル⇒1500rpmってところでしょうか?
具体的には、明らかに停止状態からのゼロ発進加速が良くなり
緩い上り坂での1速⇒2速⇒3速のミッションの繋がり感もアップ
さらに、平坦地での2速発進が そんなにストレス無く出来るようになりました。
日本人って、やたら上級志向なので 無駄な機能ばかり追求して
「強化型」と聞くと 全て良いものと勘違いしてしまいますが
本当は自分のバイクの排気量にあった「デ・チューン」のほうが良かったりします。
これからも既製の概念にとらわれず、私なりにカブ70を乗り易くしていきます。
多分、今持っているカブが終のバイクになると思うのでね。