 | 風の歌を聴け (講談社文庫) |
| 村上 春樹 | |
| 講談社 |
皆さんこんにちは、ナカダです。すでに5月も半ばを過ぎてしまいましたが、G.W.はいかがお過ごしでしたでしょうか?私は2年ぶりに神戸の実家に帰省しておりました。一口に神戸といっても結構広いのですが、私の地元は神戸と明石の市境付近でして、実家から車で10分ぐらいのところに明石海峡大橋があります。明石海峡大橋は世界最長の吊り橋で、近くで見ると、とてつもなく巨大な建造物です。
とはいえ、明石海峡大橋が完成したのは私が実家を出た後であり、巨大な吊り橋が眼前を横切る現在の風景は、自分の思い出にはないものです。私にとっての地元の風景は、あくまで明石海峡に面した小さな丘の町なのであり、橋が完成して10年以上が経過した今でも、たまに帰省するたびに、どこか違う町に帰ってきたような違和感を持っています。
などと、2年ぶりに帰省してみると、3日間しかいなかったわりに、いろいろと考えるところがありました。そこで今回取り上げるのは、「帰省小説」(というジャンルがあるのかどうか分かりませんが)の傑作、『風の歌を聴け』です。
本作は、『1Q84』の村上春樹のデビュー作として広く知られていることから、改めてあらすじの紹介は必要ないかもしれません。というよりも、この作品は、短い断片的なシーンの積み重ねで構成されており、そもそもストーリーらしいストーリーがありません。あえていえば、故郷の街に帰省した「僕」が、友人の「鼠」とビールを飲んで過ごした一夏のエピソード、というのが小説の大枠になります。つまりこの小説は、主人公である「僕」が、故郷である海沿いの「街」に帰省するところから動き始めます。
しかし、主人公の「僕」は帰省中でありながら、地元の旧友と再会するわけでなく、家族とどこかに出かけるわけでもありません。地元を出た後で知り合った友人の「鼠」と、ジェイズ・バーでひたすらビールを飲むだけです。つまり「僕」は、生まれ育った「街」に19日間(1970年の8月8日から26日まで)も滞在しながら、その滞在中の行動を、「街」での思い出や人間関係から意図的に切り離しているのです。
「街にはいろんな人間が住んでいる。僕は18年間、そこで実に多くを学んだ。街は僕の心にしっかりと根を下ろし、想い出の殆どはそこに結びついている。しかし大学に入った春にこの街を離れた時、僕は心の底からホッとした。夏休みと春休みに僕は街に帰ってくるが、大抵はビールを飲んで過ごす。」(文庫版 p.106)
この「街を離れた時にホっとする」心情は、実は私も深く共感してしまいます。それは決して故郷に良い思い出がない、からではありません(もちろん良い思い出ばかりでもありません)。良いものであれ、悪いものであれ、思い出が詰まった場所に留まる限り、そこで得た経験や培った感性から、いつまでも自分が自由になれないと感じてしまうからです。
ただし、それでもやはり「街は僕の心にしっかりと根を下ろし」ており、どれだけ遠く離れたところで、そこから完全に自由になることは出来ません。そのことに軽い諦念を覚えつつ、一方では、自分の心がどこかに確実に結びついていることに、ささやかな安心感を覚えてもいます。
おそらく主人公の「僕」が、春休みと夏休みの年に2回も律儀に帰省するのも、「街」からは完全には自由になれない自分を自覚しているからではないでしょうか。このように『風の歌を聴け』は、自分が帰省するときにつきまとうアンビバレントな感情が喚起されることから、数多ある村上作品の中でも、最も個人的に馴染みの深い一冊となっています。
あともう一つ、『風の歌を聴け』が強く喚起する感情、というか欲求があります。そうです、「ビールが飲みたい!」というものです。「僕」と「鼠」は、一夏かけて25メートル・プール一杯分ばかりのビールを飲み干したようですが、この小説は登場人物だけでなく読者にもビールを飲むことを求めます。これから気温が上がるにつれ、ビールも美味しくなりますので『1Q84』Book3を読み終えた方は、『風の歌を聴け』もビール片手にどうぞご一読ください。(文責 ナカダ)
















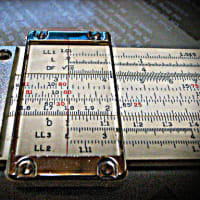

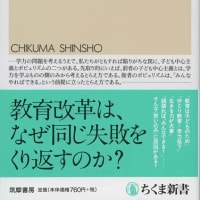

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます