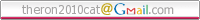前回のつづきです。
もう一度、厚生労働省の論点を見ていきます。
○ 支給開始年齢の65歳以上への引上げは、世代間格差を拡大するのではないかとの指摘について、どう考えるか。
・ 厚生年金の支給開始年齢の引上げを行うことで、総計としての年金給付費が減少し、年金積立金に余裕が生じることにより、マクロ経済スライドによる給付抑制の調整期間が短くなることから、「スライド調整終了後」の年金給付水準の低下が緩和されることとなる。このため、世代間格差の縮小に寄与する面がある。(このことは、スケジュールの前倒しにおいても同様。)
・ 一方で、支給開始年齢の引上げが行われる以降の世代については、年金給付費の減少が生じることとなる。つまり、支給開始年齢の引上げは、将来世代に影響が強く出ることについて、どう考えるか。
・ 特に、20ページの③のようなスケジュール(2年に1歳ずつの引上げ)の下では、受給者数が多く、年金財政上影響の大きい、いわゆる団塊の世代(1947~1949年生まれの者)には影響が無く、それ以降の世代の者(1950年代以降生まれの者)に影響を与えることによって、世代間格差を広げる要因ともなりうることについて、どう考えるか。
以上、抜粋終わり。
(下線は原文ママ)
出典:第4回社会保障審議会年金部会資料 資料1 支給開始年齢について (厚生労働省HP) 24ページより
1番目の論点は、マクロ経済スライドの発動は「おおむね100年間の財政均衡期間にわたり年金財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合」が前提ですので、年金財政に余裕が出来れば
マクロ経済スライドは発動されず、年金給付水準の低下が緩和され、世代間格差も縮小するかも!というものでした。
ただこのマクロ経済スライド、一度も発動されたことがありません。
マクロ経済スライドが発動されない理由については、こちら(リンク)が詳しいのでご参照下さい。
(リンク先:「マクロ経済スライド」発動の遅れ ニッセイ年金ストラテジー 2010年04月号 vol. 166)
結局、マクロ経済スライドという制度を作ったはいいものの、使われずに世代間格差が拡大し続けていることになります。
1番目での論点では世代間格差の縮小にはマクロ経済スライドの実施が必要なのですが...。
そして、このマクロ経済スライドには特例措置があり、物価や賃金が下がったとしても発動されない仕組みになっています。
詳細は こちら(リンク)をご参照ください。
(リンク先):基礎から理解する年金改革 ― (2)マクロ経済スライドと例外措置 ニッセイ年金ストラテジー 2004年05月号vol. 095)
激変緩和のためでしょうが...もはや既得権化してるのではないでしょうか?
今回の年金の支給年齢引き上げ。
年金受給額を考えると、若年層にとってはどう考えても「損」です。
でも、この年金制度が破綻してしまうと、全体がさらなる「大損」を被ることになります。
ですから、「損」の大きさを考えれば、今回の支給年齢引き上げはしかたないものと理解できます。
(論点2・3は支給年齢引き上げに伴い自然発生する問題であり、制度存続のためには引き受けるしかありません)
しかしです。
制度存続のための「損」は受け入れるべきですが、必要以上の「損」を引き受けるべきではありません。
『正常な』マクロ経済スライド(=現状のような例外措置が無い)を通じて、現在の受給者も「損」を受け入れてもらわないと、
しわ寄せがすべて若年層や後の世代へ流れていきます。
支給年齢引き上げは年金制度存続のためというのは分かりますが、物価や賃金が下がったとしても発動されない『現状の』マクロ経済スライド制度を存続するなら年齢引き上げは「反対」。
これが現時点での私の意見です。
※今回は「世代間格差」に絞って記述しました。
ほかにも論じる点はあるかと思いますが、大切なのは「自分で調べ、考え、意見を言う」ということだと思います。
「やっぱりもらえないのか」「どうせ破綻するんじゃないの?」と言うのは簡単ですが、それだけでは何も変わらないのです。
どんな意見でも「自分の意見を発信してほしい」。
そう切に思います。
もう一度、厚生労働省の論点を見ていきます。
○ 支給開始年齢の65歳以上への引上げは、世代間格差を拡大するのではないかとの指摘について、どう考えるか。
・ 厚生年金の支給開始年齢の引上げを行うことで、総計としての年金給付費が減少し、年金積立金に余裕が生じることにより、マクロ経済スライドによる給付抑制の調整期間が短くなることから、「スライド調整終了後」の年金給付水準の低下が緩和されることとなる。このため、世代間格差の縮小に寄与する面がある。(このことは、スケジュールの前倒しにおいても同様。)
・ 一方で、支給開始年齢の引上げが行われる以降の世代については、年金給付費の減少が生じることとなる。つまり、支給開始年齢の引上げは、将来世代に影響が強く出ることについて、どう考えるか。
・ 特に、20ページの③のようなスケジュール(2年に1歳ずつの引上げ)の下では、受給者数が多く、年金財政上影響の大きい、いわゆる団塊の世代(1947~1949年生まれの者)には影響が無く、それ以降の世代の者(1950年代以降生まれの者)に影響を与えることによって、世代間格差を広げる要因ともなりうることについて、どう考えるか。
以上、抜粋終わり。
(下線は原文ママ)
出典:第4回社会保障審議会年金部会資料 資料1 支給開始年齢について (厚生労働省HP) 24ページより
1番目の論点は、マクロ経済スライドの発動は「おおむね100年間の財政均衡期間にわたり年金財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合」が前提ですので、年金財政に余裕が出来れば
マクロ経済スライドは発動されず、年金給付水準の低下が緩和され、世代間格差も縮小するかも!というものでした。
ただこのマクロ経済スライド、一度も発動されたことがありません。
マクロ経済スライドが発動されない理由については、こちら(リンク)が詳しいのでご参照下さい。
(リンク先:「マクロ経済スライド」発動の遅れ ニッセイ年金ストラテジー 2010年04月号 vol. 166)
結局、マクロ経済スライドという制度を作ったはいいものの、使われずに世代間格差が拡大し続けていることになります。
1番目での論点では世代間格差の縮小にはマクロ経済スライドの実施が必要なのですが...。
そして、このマクロ経済スライドには特例措置があり、物価や賃金が下がったとしても発動されない仕組みになっています。
詳細は こちら(リンク)をご参照ください。
(リンク先):基礎から理解する年金改革 ― (2)マクロ経済スライドと例外措置 ニッセイ年金ストラテジー 2004年05月号vol. 095)
激変緩和のためでしょうが...もはや既得権化してるのではないでしょうか?
今回の年金の支給年齢引き上げ。
年金受給額を考えると、若年層にとってはどう考えても「損」です。
でも、この年金制度が破綻してしまうと、全体がさらなる「大損」を被ることになります。
ですから、「損」の大きさを考えれば、今回の支給年齢引き上げはしかたないものと理解できます。
(論点2・3は支給年齢引き上げに伴い自然発生する問題であり、制度存続のためには引き受けるしかありません)
しかしです。
制度存続のための「損」は受け入れるべきですが、必要以上の「損」を引き受けるべきではありません。
『正常な』マクロ経済スライド(=現状のような例外措置が無い)を通じて、現在の受給者も「損」を受け入れてもらわないと、
しわ寄せがすべて若年層や後の世代へ流れていきます。
支給年齢引き上げは年金制度存続のためというのは分かりますが、物価や賃金が下がったとしても発動されない『現状の』マクロ経済スライド制度を存続するなら年齢引き上げは「反対」。
これが現時点での私の意見です。
※今回は「世代間格差」に絞って記述しました。
ほかにも論じる点はあるかと思いますが、大切なのは「自分で調べ、考え、意見を言う」ということだと思います。
「やっぱりもらえないのか」「どうせ破綻するんじゃないの?」と言うのは簡単ですが、それだけでは何も変わらないのです。
どんな意見でも「自分の意見を発信してほしい」。
そう切に思います。