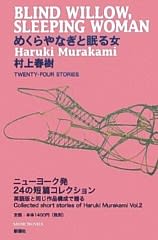不思議なほど父を嫌っていた母は、死の床で「おとうさん」とかすれかかる声で云った──。精神を病み、海辺の病院に一年前から入院している母を、信太郎は父と見舞う。医者や看護人の対応にとまどいながら、息詰まる病室で九日間を過ごす。戦後の窮乏生活における思い出と母の死を、虚無的な心象風景に重ね合わせ、戦後最高の文学的達成といわれる表題作ほか全七編の小説集。
出版社:新潮社(新潮文庫)
『海辺の光景』は居心地の悪い小説である。
たぶんそれは、主人公の信太郎の心情がどこか醒めて見えるからだろう。
そしてその居心地の悪さゆえに何かが引っかかる作品でもあった。
信太郎は、父との関係が希薄である。
それは父が軍隊生活を送っていて長い間家を空けていたこと、そして母が父との結婚を後悔し、父を軽蔑していたことが(そしてそんな母と長い時間を過ごしたことが)大きい。
信太郎にとって親しいのはあくまで母なのだ。
しかしそんな母もボケが始まり、その面倒は甲斐性がない父が見ることとなる。
だからだろうか。ぼけた母がうなされていたとき、その名を呼ぶのは、そのとき手を握っていた息子の信太郎ではなく、嫌悪感を持って接してきたはずの父なのだ。
その状況をまとめるなら、子の父への反発、子の母への愛着、母の父への愛着、となる。
構図的だけを抜き出すなら、フロイトのエディプス・コンプレックスそのものだ。
しかしそんな仕打ちを受けて、彼が感じたのはどこか醒めた失望と安堵という程度のものでしかない。
彼の母への心情は、その関係性のわりには冷えて見える。
そして、その冷えた感情の根っこには、あらゆるわずらわしさから、逃避したいという彼の願望が反映されているのではないか、っていう気がする。
彼は母の中から正気が少しずつ失われていることもなかなか受け入れようとしなかったし、正気でなくなる母と会わずに長い時間を過ごしている。
そして介護からも逃げているし、母の死からも目を背けている。
彼はそういう意味、息子としての役割から逃げているのだろう。
そもそも母親のために償いをつけるという考えは馬鹿げたことではないか、息子はその息子を持ったことで償い、息子はその母親の子であることで償う。(略)外側のものからはとやかく云われることは何もないではないか?
っていう文章が最後の方に出てくるが、それこそ逃げ続ける自分に対しての彼の言い訳なのだろう、と僕は思う。
そしてそんな彼の視線やものの考え方は、一人の母の息子でもある僕に、居心地の悪い思いをさせる。
あらゆるわずらわしさから逃れたい気もちは僕にだって、まったくゼロではないからだ。
そしてそれがゆえに読み手である僕にやましい感情を抱かせることとなる。
ともあれ、人の心に明確な爪あとを残す作品ということは確かだろう。
認めたくない気もちはあるが、ポテンシャルの高さは感じられる作品だった。
そのほかの作品もおもしろかった。
『宿題』
劣等意識を抱えた少年の心情が良い。
少年は弘前から青山に移ってきて、その環境に馴染めず、適応だってできない。
しかしそこには学校に馴染みたいと思っている気もちもまたあるのではないか。最後の少年の言葉が特にその思いを強める。
ユーモラスなのに、どこか悲しい話だ。
『蛾』
たぶん「私」は、流行ってもいない医者に一方的に親近感を持っていたのだろう。
もちろんその理由は、医者が世間的に見れば風采が上がらないからにほかならない。しかし医者はそんな「私」の共感意識を砕くように、いとも簡単に耳の中の蛾を取り出す。
そこにある宙ぶらりんになった気もちがどこか切ない。
『雨』
主人公の男は、どこかに鬱屈をぶつけたがっているように思える。
そこには、疎外感もあるのだろう。その結果が、通り魔的な行動なのだ。
最後の、「これではかえれない」という言葉は、呪いの言葉であり、彼の自戒の言葉とも見える。
『ジングルベル』
多様な解釈が可能な作品と感じた。
ジングルベルの曲に歩調を合わせるところといい、ウナドンを意図していないのに頼むところといい、ミカンを必要以上に頼むところといい、意図していないところで雰囲気に呑まれ、断りたくとも引き返せないまま、一つの状況に追いやられている状況を描いているようにも感じる。
戦後の作品ということを考えると、戦争中の日本の空気の陰画のようにも見えた。
深読みかもしれないけれど、これはこわい作品なのかもしれない。
『愛玩』
本作中で、一番おもしろかった。何より滑稽なのが良い。
金儲けのためにウサギを手に入れたものの、そのウサギに振り回されて、家畜じみてくる家族の姿がおもしろい。ウサギのために息子の髪を刈ろうとするところなんかは笑った。
ここに描かれているのは、生活能力がない家族ゆえの喜劇だろう。
そしてその生活能力のなさゆえに、大層物悲しい作品でもある。
評価:★★★★(満点は★★★★★)