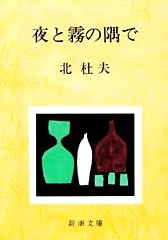海峡を目の前にする街に続く旧家・桜井家の梅代は、出戻ってきた娘美佐子と、幼稚園児の孫娘の三人で暮している。古びた屋敷の裏にある在日朝鮮人の教会に、梅代とその母はある憎悪を抱え、烈しく嫌ってきた――。注目の新鋭が圧倒的な筆致で描く芥川賞候補作。
出版社:新潮社
芥川賞の田中慎弥の受賞会見があまりにおもしろかったので、とりあえず一冊読んでみた。
外見からして、いかにも文士然とした感はあったのだけど、作品の内容もその風貌にたがわず、いかにも文学らしいたたずまいを見せている。
幾分古めかしくはあり、流行からはずれた作風だけど、その古風な味わいがまた良い。
表題作『切れた鎖』は、昭和の文学といった感じの作品である。
内容としては、没落しつつある旧家を舞台にした女系四代の話で、その負の連鎖を描いている。
その道具立ての時点で、いかにも古臭い。そしてそれゆえに、今読むと新鮮な気分になれる。
梅子、梅代、美佐子、美佐絵(もっと区別しやすくしてよ、と言いたくなるような名前だ)の四世代の女たちは、性的な鬱屈感と、他者(ここでは隣家の朝鮮系の信仰宗教団体)に対する憎しみを、負の連鎖のように伝えていっている。
たとえば、梅子は、となりの宗教団体の女(梅子は彼らの団体に根深い差別意識を持っている)に夫を寝取られた娘の梅代に対して、下品な言葉でののしっている。そしてそれがどうやら梅代にとって、トラウマになっていることが感じられる。
一方の梅代は、娘の美佐子に対して、隣の子(ひょっとしたら逃げて行った夫の子かもしれない)との接触を極端に制限するようになる。そしてそういった梅代の態度が、美佐子に隣家に対する差別意識と、性的にだらしない性格を形成する一要素になっていることが感じられる。
そして美佐子の娘の美佐絵は、いまだ無自覚ながら、性的に乱れた母に対し憎悪の芽のようなものを抱き始めている。そしてやはり先の世代と同様、隣家に対する謂れのない差別心を持ち始めている。
そんな四代の負のつながりを生み出したのは、旧家特有の抑圧なのだろう、と見えるのだ。
梅代も、美佐子も、母親からトラウマを植えつけられるような家庭に対して、居心地の悪さを感じていた。
だからか二人とも、その家から逃れたいようなことを口にする。そして二人は、本気でそれを願っていたのだ。
だけど結果的に、二人はその家から出て行けず、憎しみのような感情を、下の世代に伝えるだけで終わっている。その連関が、読んでいて痛ましい。
しかしラストは、ひょっとしたらその連鎖が終わるかもしれない、という淡い期待を抱かせるものになっている。
幼い美佐絵は、ラストで、自分の伯父かもしれない隣家の男に、差別的なふるまいをする。
それに対し、梅代は、「あんなこと、誰のためにもなりません」と言っている。
それをもって、これで負の連鎖が止まると考えるのは早計かもしれない。
だがそんな基本的な面を教えることから、物事に対する解放は始まるのかもしれない。そうも僕は感じられた。
併録作品では、『不意の償い』がおもしろかった。
恋人と初めてのセックスをしていた、まさにそのときに、親が焼死してしまった男を主人公にしているが、その心理描写がすばらしい。
男は、そんな重要なときにセックスしていた自分に罪悪感を覚えている。また結婚した後、欲望のまま妻とセックスして妊娠させたことに、いつまでもうじうじと悩んでいる。
そしてそんな男のうじうじが、やがて統合失調症気味の狂気に変わっていく過程がすさまじかった。
彼は男性的な要素にふり回される自分に対して、自己嫌悪を持っているのだろう。それが狂気に変貌していく様を無理なく読ませて、圧巻である。
だがそんなある種、男性的かつ理性的な感情も、子を産む、という女性的な行動によって、あっさり打ち砕かれてしまう。
その流れが、ちょっと爽やかでさえあり、深く心に届いた。
『蛹』もおもしろい作品だった。
みんなが地上に出て行く中、からを突き破れず、戦いの場に出られない。その理由を、言い訳がましい言葉を連ねている点がおもしろい。
言い換えれば、これは引きこもりのメタファーなのだろう。
だがそれにとどまらず、同時に父性的要素に対する違和感も、丁寧につづっている点を興味深く読んだ。
評価:★★★★(満点は★★★★★)