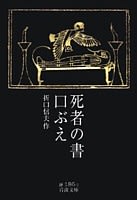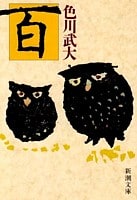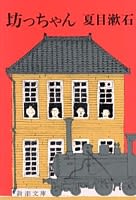良いニュースと悪いニュースがある。多崎つくるにとって駅をつくることは、心を世界につなぎとめておくための営みだった。あるポイントまでは…。
出版社:文藝春秋
マンネリズムに陥っているが、物語はおもしろい。
本作の感想をまとめるなら、そういうことになる。
そこはさすが、村上春樹で、読み終えた後には淡い感動すら覚えた。
引っかかる面もあるが、トータルではすてきな作品だった、と賞賛したい思いだ。
さてどうせ売れているので、遠慮せずにまずは気になった点から上げていこう。
本作の最大の欠点は、マンネリ化した物語と細部にある。
語り口はいつもの村上節で、それは心地よく、読みやすく、読み手を物語へと一気に引っ張っていく力にあふれていることはまちがいない。
ただ会話は例によって硬く、直訳っぽい口調もどこかもどかしい。
加えて登場するキャラクターにも、既視感を覚えるのだ。
主人公はいつもの村上春樹作品と似たような感じだし、クロは『ノルウェイの森』のミドリみたいで、灰田は『ダンス・ダンス・ダンス』の五反田くんと近いものを感じる。
エピソードも、シロの性夢は、『ねじまき鳥クロニクル』の加納クレタそのまんまだし、いつもの春樹のように、いくつかの謎(灰田のその後、緑川は何者か、シロの事件の真相)は解決されないまま終わる。
そういった点に不満がないと言えば、嘘になる。
しかしそれを補って余りある何かが、本作にはあるのだと感じたこともまた事実なのだ。
それは、主人公多崎つくるにもたされた、癒しの雰囲気によるところが大きい。
主人公の多崎つくるは、自己評価の低い男である。
彼は高校時代、仲のいい友人たちがいた。
そこには一体感のようなものがあった、と彼自身回想しているし、ほかの仲間も回想しているように、その五人のグループで過ごした時間は、幸福なものだったのだろう。
しかしそんな幸福なさ中にあって、つくるは「自分は本当の意味でみんなに必要とされているのだろうか?」などと考えている。
五人のグループの中で、彼だけ色がないことを含めて、自分は個性というものがない、と考えている。
そこにあるのは、つくるの自己評価の低さと、それに伴う自己卑下である。
個人的には似たような感情を、今でもときどき抱くので、共感を覚えずにはいられなかった。
そしてつくるは、大学二年のときに、その親しかった友人から突如拒絶されることとなる。
それは彼にとっては、トラウマレベルで、「自分が他人にとって取るに足らない、つまらない人間だと感じることが多くなったかもしれない」とすら言っているほどだ。
元々自己評価の低かっただけに、相当きつかっただろうことは疑いえない。
そしてそういった自己卑下や自己否定は、たとえば沙羅のような他者、なぐさめられたところで変わるわけではないのだ。
他人に優しく肯定されたからと言って、どうこうなるような問題でもない。
それはあくまで当人の心の問題だ。
そしてそういった自己卑下の強さが、他人を強く求めることに、ブレーキをかけることにもなっている。
恋人の沙羅は、何となくそんなつくるの心性に気づいている節がある。
だから彼に、きちんと過去と折り合いをつけることを忠告しているのだ。
つくるは基本的にはいい人だと思う。
だけど、人に向けて差し出せるものを持ち合わせていない、と考える人間は、自分自身をどこかで大切にできないのだろう、という気もしなくはない。
結婚も視野に入れている相手ならば、そんなパートナーと添い遂げるのは勇気が要ることだろう。そんな風に思う。
そうして多崎つくるはむかしの友人を訪ねる、「巡礼」を始まることとなる。
そのときの友人たちとの会話は、本当にすばらしかった。
彼らはかつて、つくるを切り捨てたことに傷ついていたし、今でもつくるのことを好きでいてくれている。
つくるは、自分を卑下しているけれど、彼が思うように、つまらない人間だとしたら、彼らはそこまで明確な好意を、つくるには示してくれないだろう。
それが伝わるだけに、読んでいると、胸が熱くなってならない。
たとえばアオの、「おまえは、他のみんなの心を落ち着けてくれていた」「でも正直なところ、家族に対してだって、あのときのような混じりけのない自然な気もちは、なかなか持てない」って言う言葉などは、彼なりのまっすぐな思いが伝わり、胸に迫る。
またアカの、古い友人の前で自分の弱さを語るところは、つくるに対して胸襟を開いていることがわかり、静かに胸をうつ。
つくるがアカのことを、おまえ、と呼びかけるところなんかも忘れがたい。
もちろんフィンランドでのクロとの会話もすてきであった。
クロことエリは、むかし、つくるのことが好きだったこともあり、つくるを肯定し、温かくはげましてくれる。それが非常に温かい。
特に最後の言葉には淡い感動を覚えた。
自分の評価を決めるのは、決して自分ではない。それを決めるのはあくまで他者なのだ。
そんな当たり前のことに気づかせてくれる。
最後はぼかしたままになっているが、そんなつくるへの肯定の雰囲気があるからこそ、ラストもまた明るい予感が待っているのだろう、と純粋に信じることができた。
そしてそう思わせる麗しさが、本作にはあったと思う。
そしてその麗しさが、僕の心をいつまでも静かにゆさぶり続けるのである。
本作は、村上春樹のベストではないかもしれない。
それでもすばらしい作品であると心から賞賛したいと思う。
PS
特に関係ないが、名古屋生まれの名古屋育ちとしては、名古屋が主要な舞台となっている点にも共感を持って読むことができた。
特に名古屋の、せまく閉鎖的でぬるい社会のことがちゃんと言及されていて、ああわかるわ、と元名古屋人としては何度か思った。
名古屋を知っている人には、一層楽しい作品でもあるのだろう。
評価:★★★★★(満点は★★★★★)
そのほかの村上春樹作品感想
『アフターダーク』
『1Q84 BOOK1,2』
『1Q84 BOOK3』
『海辺のカフカ』
『神の子どもたちはみな踊る』
『象の消滅』
『東京奇譚集』
『ねじまき鳥クロニクル』
『ノルウェイの森』
『遠い太鼓』
『走ることについて語るときに僕の語ること』
『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』
『若い読者のための短編小説案内』
『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』 (河合隼雄との共著)