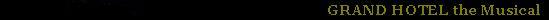
あゆあゆさんから、観に行けなかった方も想像をゆったりと膨らませていただける、
詳細な観劇レポートを頂きました。追体験組の私も嬉しいです♪
『グランドホテル』詳細レポ Ⅰ
The Grand Parade--- Some Have, Some Have Not--- As It Should Be
開演15分ぐらい前になると、羽をつけた帽子に、20年代の直線的シルエットのド
レス姿の女性、あるいはタキシード姿の男性、つまりオーケストラの方々が、チュー
ニングのために舞台上部のスペースに集まり始めます。当時のホテルで実際に演奏し
ていたバンドという趣です。そして、開演時間・・・。
階上のオーケストラ指揮者と一礼を交わし、ステッキを突きながら、階段を下りてく
るドクター・オッテルンシュラーグ。フロントのベルの音とともに、ホテルで働く従
業員たちの様々な声が飛び交います。青山さんの声は、「ルームサービス、朝食を二
人分お願い・・・」でした。冒頭のドラマティックなオケの音に合わせて、舞台左手
でドクターがカバンからモルヒネの注射を取り出し、その注射を腕に突き刺すことに
より、このストーリーは始まります。同時に、かすかなスモークが漂い、青系と黄色
系の照明がオケの音楽に合わせて劇的に変わるという幻想的なムードのなか、ジゴロ
と伯爵夫人が現れ、踊ります。再びドクターは、階段を上り、踊り場で宙を見つめ、
恍惚の表情を浮かべながら、豪華ホテルの光景を歌います。「クリスタル、ビロー
ド、香水の芳香、シャンデリアのきらめき・・・(歌詞はこんな感じでした)」いよ
いよ観客は「古きベルリン、グランドホテル」の世界へといざなわれてゆくのです。
そしてジゴロと伯爵夫人も、何かに引き離されるかのように、舞台両端へとそれぞれ
が消えてゆきます。
ドクターが歌う「人は来て、人は去る(People come, people go)・・・」のところ
で、ステージのあちらこちらからベルボーイなど、ホテルの従業員たちが登場してき
ます。青山さん演ずるベルボーイは回転扉の右横の扉からの御登場です。このときの
アンサンブルの動きは、普通の日常生活の動きからは何段階かスピードを落としたよ
うなスローなマイムです。しかし「マイム」とは言っても、その動きは、「パントマ
イム」という言葉からイメージするようなオーバーアクションな、ぎこちなさとつぎ
はぎ感のあるものではありません。青山さん演ずるベルボーイは、回転扉のそばで、
実際のゲストもいないし、カバンもないのだけれど、マイムの動きでベルボーイとし
ての仕事をこなしてゆきます。笑顔を浮かべながら、そこにいるはずのないゲストに
一礼し、あるはずのないカバンを持ち、ロビーを歩く・・・。どれも日常生活であり
ふれた動きのはずですが、ひとつの動作からもうひとつの動作に移るときの「継ぎ目
のなさ」、そしてそのような動きが流れるようにスローなスピードで展開されること
によって、非常に現実感のない、幻想的な空気感が漂うのです。「ドクターが打つモ
ルヒネ」と「アンサンブルのマイムな動き」は、この作品では連動しているようで、
ウォルフォードさんがパンフレットで述べている、「イリュージョン」な空気感が舞
台を包み込みます。(後半I Waltz Aloneでも「モルヒネ」と「マイムな動き」が連
動しています。)ドクターのどこか「死にかけている」存在感とともに、マイムな動
きによって醸し出される、アンサンブルたちの眼の前に生きている人間でないような
透明感と浮揚感に満ちた非現実的な存在感が、現代からは遠く時間を隔てて存在する
「古きベルリン・グランドホテル」のセピアな色彩と薫りを醸し出すのです。
ちなみに、Grand Parade/Some Have, Some Have Not/As It Should Beが絡み合う
ようにして展開される、冒頭のこのシーンの途中では、グルーシンスカヤが回転扉を
通って、ロビーに登場してくるという場面が挿入されますが、この場面に移るときの
質感の変化はたとえて言うなら「セピア色の写真」から「カラーの動画」といった感
じです。シーン自体がパッと急に色づく感じで、登場人物に生気が入り、観客が場面
に対して抱く現実感もいきなり増します。舞台の幻想的な雰囲気に包まれ、記憶の彼
方にまどろむような感覚が消え、観客の中では、舞台での出来事に対する同時代感が
一気に高まるという感覚が湧き起こるのです。確かに照明も変わるのですが、青山さ
んたちアンサンブルの動きの質、あるいは存在感、舞台上でのあり方の変化というこ
とが、観客のなかに起こる変化の一番大きな要因だったような気がします。またグ
ルーシンスカヤと男爵がすれ違う、ドラマティックな二人の出逢いも、アンサンブル
の動きがフリーズすることによって、このシーンだけ切り取られたように観客のなか
に印象付けられ、これからこの二人に起こる出来事がほのめかされていました。
前述の「スローなマイム」の後まもなく、右手の階段中段に上った青山さん@ベル
ボーイは、「ようこそ、古きベルリン、ようこそ、グランドホテル」と歌いながら、
客席正面と左手客席に向かって、ゆっくりと一礼をしてゆきます。ここで客席に座る
観客のひとりひとりも、まるでこの豪華ホテルをゲストとして訪れているかのような
錯覚を抱くのです。青山さんは、濃赤色のベルボーイキャップに、所々が金モールで
縁取りされた同色の上着、白シャツに折り目正しくネクタイを締め、茶色のズボンと
いうお衣裳。ベルボーイとしての青山さんは、格式高いヨーロッパの高級ホテルの玄
関で、一番にお客様をお迎えするという役割にふさわしく、背筋がピンと伸び、歩き
方をはじめ、身のこなしも優雅でありながら、機敏で端正、その存在感に圧倒されま
す。回転扉の傍らでたたずむ、荷物を持つためにかがむ、そして歩く・・・、完成さ
れた何気ない動作のひとつひとつに、この作品を舞台の上に乗せることに向けて青山
さんのなかで醸成されていった時間というものを感じました。くるりと向きを変え、
階段を上ってゆく後姿などでは、上半身が微動だにせず、カバンを持つ腕、肩と背中
から脚にかけてのラインが、一筆で描かれた完璧な一本の描線を辿るようでした。青
山さんがベルボーイとして舞台の上にいるその仕方、存在感といえば、とにかくそれ
は完成された圧倒的なものでした。
「人生の華やかさを極めつつも、時間のない」ゲストたち、登場人物のひとりひとり
がドクターの言葉で紹介されながら、回転扉を通って登場してきます。このときベル
ボーイたちはひとりひとりのゲストたちに深々と最敬礼をするのですが、ミニスカー
トの裾を翻して脚を高く上げポーズをとるフレムシェン御登場のときだけは、右手階
段中段に位置する青山さんと高山さん@二人のベルボーイは、「この美しい女性は
誰?」とばかりに、横から覗き込むようなしぐさをします。このときも、なんとなく
普通よりはスローな動きですが、覗き込む動作に入るときの機敏さが、「思わず、不
覚にもベルボーイである立場を忘れてしまった」気持ちを表現しているようでした。
また、高山さんから青山さんという動きの流れのなかにある「間」のとり方が絶妙
で、そのユーモアが漂う動きが、フレムシェンの向こう見ずな若さの輝きに重なっ
て、とても印象的でした。貧しいアパート住まいに辟易し、何とか現状を変えたいと
思っている若きフレムシェンとホテルで働く従業員たちの立場には、近いものがある
のかもしれません。後に続くジミーズとフレムシェンのダンスナンバー、Maybe My Baby Loves Meでも、最高にカッコイイ青山さん@ジミーズのひとりは、フレムシェ
ンとの駆け引きを楽しんでいるように見えて、そんな細かいキャラクター設定も、フ
レムシェンの人物像の輪郭というものを描き出しているようでした。
「金のない貴族ほど役に立たない者はない」というドクターによる男爵への注釈がつ
くと同時に、客席の前方端から「洗い場の労働者たち」が舞台へと飛び出してきま
す。(この作品では、「金」ということに話題が及ぶと、この「洗い場の労働者た
ち」が登場してくるようでした。例えば、プライジングの商談や男爵の駆け引きなど
の場面の周辺で。)労働者たちは、迫力のある歌声と、金物を入れた金属製の籠をゆ
すりながらの激しい動きによって、いくら働いても恵まれないという生活に押し潰さ
れそうな、フラストレーション爆発寸前の心情を、ホテルのゲストたちの豪勢な暮ら
しぶりと対比しながら吐露してゆきます。「籠のゆすり方、取り扱い方」という細か
いことを取ってみても、労働者たちひとりひとりの個性が感じられて、彼らが自分の
人生で抱えているものが見えるようでした。
そんな彼らとは対照的に、同じ労働者階級でも、ベルボーイたちは抑制した動きでそ
の心情を表現してゆきます。笑顔と誠意でゲストをお迎えすることが仕事である彼ら
の、もう一つの側面です。冒頭のこの場面では、男爵が歌うAs It Should Beと絡ま
りあいながら、このSome Have, Some Have Notは何度か歌われますが、青山さん演ず
るベルボーイの抑えの効いた動きには、観ているこちらが客席の背もたれに押し付け
られてしまうような「凄み」のようなものがありました。自分の気持ちのやり場のな
さを、階段中段のひとつの段で、右に左に数歩ずつ行ったり戻ったりする、またはそ
の場で動かず、「1日100万マルク使える」ゲストたちに対する不公平感を、上半
身、腕や掌の動きだけで歌いながら表現する・・・。あるいは舞台前方に出て、その
場で身体と顔の向きの角度を曲のフレーズとともに微妙に変化させる・・・。ただそ
れだけの、「ダンス」とは言えない、非常に動きの少ない振りなのですが、青山さん
の動きを観ているだけで、その心の内に渦巻く張り詰めた緊迫感のようなものが押し
寄せてくるかのようでしたし、抑えた動きを行う端正な身体/外面と、抑圧された不
満が渦巻く激しい内面とのコントラストが逆に、恐ろしいぐらいに印象的でした。同
時にステージの全体像として、それぞれのキャラクターが豊かな個性をぶつからせ
て、心情を吐露してゆくこの場面は、あの時代のドイツにあった空気を伝えるものと
してリアリティーがあったし、非常に迫力がありました。
Grand Paradeの後半、フレムシェン、ラファエラ、プライジング、オットー、男爵が
舞台のあちらこちらで電話で話す場面があります。その内容から観客は登場人物の置
かれた状況を察することができるのですが、ハーモニーを奏でながら、重層的に重
なっていく彼らの声が印象的な場面でした。これに続いて全てのキャストが勢ぞろい
して、Grand Paradeのラストを歌い上げるこの作品の「見せ場」とも言うべき場面
は、作品冒頭から観客が大きな感動に包まれる圧巻の素晴らしいものでした。『グラ
ンドホテル』冒頭のこのシーンを、ベルボーイは右手を胸の前に置き、礼をするとい
うポーズでしめくくります。
ベルボーイが着ていたのは、制服、ユニフォーム(uniform)でしたが、この言葉は
元来「一つのかたち」という意味です。彼らの存在意義ともいえる共通の目的、すな
わち「高級ホテルを訪れるゲストのおもてなしをする」、この目的の下に、彼らは
「お揃いの一つの」衣裳を身につける・・・。そんな彼らは、舞台上で場面転換する
ことなくそこにあり続けた、あの古きベルリンの高級ホテルのたたずまいさながら
に、「来たりては、去る」人々の織り成すドラマを見続けます。しかし、そのユニ
フォームが、単なる「お揃いの一つのかたち」から、研ぎ澄まされた末に完成された
スタイルを持つ「一つのかたち」となるとき、そしてさらにそこに豊かな表情と重層
的な意味が生起するとき、観客は演出家の意図した「イリュージョン」というものが
読み取れる気がしました。
あの「制服/ユニフォーム」を着て、ベルボーイとして舞台にいる限りは最初から最
後まで、身体の隅から隅までに全神経がはりめぐらされたような、一部の隙もない存
在感と集中力。「じっと立つ」という「動かない」動き(矛盾しているようだけれ
ど)というものから、「歩く」「かがむ」「階段を上る」というありふれた日常動作
に至るまでのひとつひとつの表現が、一貫して「ベルボーイ」としての身体秩序に
則って行われているかのようでした。青山さんの身体の表面を覆っていたあの服だけ
ではなく、あの青山さんの動き自体が「制服/ユニフォーム」だったと言っても過言
ではなかったのかもしれません。そんな確かな存在感の表と裏で、場面ごとに動きの
モードが変化することによって加えられる豊かな表情と、それにより観客のなかに連
鎖してゆくイメージ、与えられる意味の数々・・・、それらの間隙を彷徨っている
と、観客は固定されたセットのなかで展開されるストーリーでありながら、時折押し
寄せる「イリュージョン/幻」の波にたゆたうことができるような気がしたのです。
ユニフォームに生じるイリュージョンの力、それは間違いなく青山さんの卓越した秘
法といってもよい「マイムの錬金術」によって牽引されていたように思います。













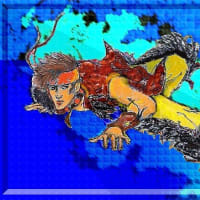






このシーンの冒頭、ユダヤ人会計士、オットー・クリンゲラインは回転扉を通り、ホテルのロビーへと、駆け込むように登場してきます。働き詰めの人生であったにもかかわらず、不治の病を患っていることを知ったオットー。何かを探し、見つけるために、このグランドホテルにやってきた、そんな彼に対し、ドクターはこのシーンの中盤で、「人生は路面電車に飛び乗るようにはいかない」という言葉をかけます。「気づかないうちにたくさんのものを失くしてしまった」という彼の人生とは裏腹に、彼が両手に持つ革製カバンには何かがぎっしりと詰まっているように見えます。こげ茶色の山高帽子に蝶ネクタイ、ジャケット・ベスト・ズボンのそれぞれが模様の違う生地で仕立てられている、素朴な感じのする装い、その上にはヘリンボーン地のコートを着込んでいます。「予約を入れてある」と主張するオットーですが、その身なりで、とっさにホテルの支配人、ベルボーイたちは、このホテルにはふさわしくない客であることを判断し、あいにく満室であることを告げて、お引取り頂くように、慌てて取り計らいます。青山さん演ずるベルボーイも、即座にこの客の頭のてっぺんから足の先までを眺め、「困惑と嘲笑の眼差し」を投げかけ、慌てて彼の革製カバンを、オットー本人の意志に反して、「カバンをお運びいたします」とばかりに、無理やり回転扉の外へ運び出そうとしていました。
そんな押し問答をしていると、オットーは突然、持病の発作を起こし、胸を押さえてよろけてしまいます。このホテルにはふさわしくない客として、オットーに対して横柄な態度をそれまで取っていたベルボーイたちは、驚いた様子で、オットーを気遣い、椅子を差し出します。そこに座ったオットーは、自分が「ユダヤ人」であるから、このホテルに泊まることが出来ないということを指摘します。そんなことは決してない、と支配人たちは弁明しますが、「お金持ちになったら、ユダヤ人ではなくなるのですね。」とオットーは、精一杯に反論します。
そのようなオットーを傍らから見つめるベルボーイたちですが、小堺さん演ずるオットーのすぐ横で、刻々と繊細に変化するオットーの表情と言動に呼応するかのように、肌理の細かいベルボーイとしての演技をする青山さんがとても印象的でした。小堺さんのオットーと、すぐ横に立つ青山さんのベルボーイを組み合わせてひとつの視界のなかで観ていると、オットーの置かれている状況というものがどのようなものであるのか、そのようなひとつの文脈のようなものが読み取れるような気がしました。複雑な状況を抱えて、何かを決意し、このグランドホテルにやってきたオットーを、一人のベルボーイのまなざしと合わせて観ることで、観ている者としては、彼に付随する様々なことを想像することができたのです。格式高いホテルのベルボーイとして、貧しい身なりを即座に読み取るその視線、お引取りいただくよう計らう態度。表向きは丁重な応対をしつつも、横柄さが滲み出るような態度で追い払おうとしたときに、その相手が急に倒れてしまうという驚きと、一人の人間としての気遣い。そして実は持病を持っていて、長い命ではないということを感じ取ったときの衝撃と同情の表情。ロビーのど真ん中で、「ユダヤ人」であることの不公平感を精一杯主張するオットーに対する困惑の混ざった、一部同感しているような表情。小堺さん演ずるオットーの感情の起伏の線が、青山さん演ずるベルボーイが反射鏡のように反応を返すことによって、さらにくっきりと見えるような気がしました。
ここグランドホテルに宿泊することこそが、彼にとっての「人生」である、と期待と希望に満ちた決意を込めて、Table with a Viewを歌うオットー。ホテルで繰り広げられる光景を歌いながら、これこそが自分にとっての「人生」である!と4ヶ国語で”das Leben, la vita, la vie, the life!”と歌い上げます。危うくホテルから追い払われそうになったオットーでしたが、男爵の計らいにより、幸運にもこのグランドホテルに宿泊することができるようになります。自分が計画したとおりに宿泊できることになった幸運を喜ぶオットーは、男爵、ドクター、エリックと共に、チェックインする部屋に向かって、階段の床を一歩一歩大事そうに踏みしめ、その感触を確かめるかのように上ってゆきます。「死ぬことが待ちきれない」というドクターの存在と、「死ぬのがわかっていても、なお生きようとする」オットーの存在は、対照的に映りますが、そんなドクターは、自分とは対照的なオットーの存在感に、心の奥底では惹かれている様子です。「貝殻を突き破り 飛び出せる気がする この瞬間を生きよう ここグランドホテル」というAt the Grand Hotelの歌詞とともに、オットーが、やっと手にしたホテルの部屋の「鍵」を宙に投げ上げて、再び大事そうに両掌で握り締める、というこの場面のラストが、小堺さんの表情とともにとても印象的でした。そして、そんなオットーを照らし出していたスポットライトが消え、舞台が暗転するとまもなく、フレムシェンとジミーズのダンスナンバー、Maybe My Baby Loves Meが、階下で繰り広げられます。
幸運にもグランドホテルの宿泊客になることができ、階段の踊り場で、やっと手に入れた部屋の鍵を宙に投げ上げ、両掌で大事そうに受け止め、「もう逃すまい」という様子で握り締めるオットー。「貝殻の中から 飛び出せる気がする この瞬間を生きよう ここグランドホテル」、この曲のラストフレーズが耳の奥に届くと、オットーを照らし出していたスポットライトが消え、舞台が暗転します。そしてフレムシェンとジミーズのダンスナンバー、Maybe My Baby Loves Meが始まるのです。上手の電話台で客席に背を向けて、音楽に合わせてコケティッシュにリズムを刻むフレムシェン。若さに輝くフレムシェンのイメージと、オットーがやっと手にした「鍵」のイメージとが重なります。「気づかぬうちにたくさんのものを失ってしまった」というオットーがこれから見つけることになる「何か」がほのめかされているような場面転換の仕方により、観客のイマジネーションも広がります。
一方、ジミーズもあちらこちらから「アメリカン・バー」に登場、サクソフォンなどの楽器を演奏するバンドメンバー数人も右手階段を下りてきて、賑やかなホテルのショーの雰囲気を盛り上げます(場面としては、「ショーのお稽古」という設定です)。ジミーズのひとりである青山さんは、上手から御登場。電話台の魅力的なフレムシェンが気になっているご様子です。紫吹さん@フレムシェンは、ピンクのベロア地のミニ丈のワンピース。青山さんをはじめ、アンサンブルの皆さん@ジミーズは、紫色の燕尾服。へーまさんも書かれていましたが、青山さんのダンスに合わせて、この燕尾服が生み出す表情がとても印象的です。ターンのたびに燕尾服のテールが空気を孕んで身体の動きを追いかけるように描く線、そしてチャールストンのステップに合わせて、まるで小刻みに踊っているかのように揺れるテールのシルエット。またこの燕尾服の脚のシルエットは、若干ゆったりとした感じでしたが、青山さんにおいては、チャールストンを踊っているときも、そんな条件を少しも感じさせませんでした。衣裳の細部に美感を生み、ご自身のダンスの魅力に取り込んで魅せてしまう青山さん、本当に素敵でした。そして同じ紫色の燕尾服でも、他の場面で音楽とともにダンスも変わると、青山さんはその扱い方を微妙に変化させていたように見えました。
「それが、ホットなジャズっていうやつ?」「今のお稽古だったの?」フレムシェンは、歌い踊るジミーズに、言葉をかけます。この場面は、フレムシェンとジミーズにより、ダンスと台詞、歌が巧みに織り交ぜられ展開していく、眼にも耳にも楽しい、こちらも思わず踊りだしたくなるようなものとなっています。当時大流行して人々が夢中になっていたという、アメリカからやってきたジャズ。そのジャズに合わせて、「お稽古」とは思えないぐらいにダンスを楽しんでいるジミーズ。そして「お客様」と「従業員」との間にあるはずの垣根を、いつの間にか飛び越え、ダンスを踊りながら、つかの間の駆け引きを楽しむかのように、一時を共に過ごすフレムシェンとジミーズ。この作品では、ホテルでダンスに興じる人々が様々な形で登場しますが、新しい音楽であるジャズに合わせて、当時一世を風靡していたというチャールストンのダンスというものを、最初に、しかも鮮烈な印象で楽しめるのがこの場面です。この場面の後半部分で、非常に短いものではありますが、紫吹さん@フレムシェンと、青山さん@ジミーが、向かい合ってチャールストンを踊るシーンがあるのです。『グランドホテル』におけるダンスの「見せ場」のひとつと言ってもよい場面だと思います。
この曲の冒頭、スキャット、「シュビドゥバンドゥンデ(こんな音に聞こえました)」の音の響きがスパイスとして効いた、テンポの速い小粋なリズムを、青山さん、高山さんのお二人が舞台前方で、しなやかな動きと勢いのあるターンを散りばめながら魅せてくれます。低音を奏でるベースの弦が周囲の空気を振動させるかのようなビート感、ピアノの鍵盤の上をピアニストの指先が即興で走るかのような軽やかさ、管楽器が勢いよく空間を切り裂くように刻むリズム・・・。ジャズを奏でる楽器さながらに、身体の真ん中にスッと通った軸を中心として、腕と脚に導かれるように左右にしなやかに展開する悩ましげで曲線的な動き、フロアとおしゃべりをしているかのように軽やかに刻まれるステップ、そして音楽に一歩先んじるように、そこに急に加えられるスリリングな動きやターン。ジミーズのひとりである青山さんの身体から伝わってくるもの、この「スリリングな感覚」と「音楽と戯れている感じ」は、テンポというものに自由自在に追いつくように、また時に追いかけられるように関わりあう、その仕方によるものではなかったかと思うのです。青山さんがこの曲の「音楽そのもの」であることは明らかですが、「メトロノームのように正確なリズムを刻む青山さん」(へーまさんの05年2月「春が来るたびに」をご参照ください)の進化したヴァリエーションのひとつとも言うべき、「ジャズを踊る青山さんの魅力」にある、この「スリリングな感覚」と「音楽と戯れている感じ」に、完全に魅了されてしまいます。洒落た台詞のやりとりの間に挿まれる、短くも非常に凝縮されたダンスに詰め込まれたエネルギーと、溢れんばかりの豊かな表情に、思わず吸い付けられ、引き込まれてしまいます。青山さんのダンスは、非常に濃密なフレーズの魅せ方を究めたものでした。
(長くなりましたので、この続きは、「その2」として、続けて投稿させていただきます。)
曲の後半、盛り上がりの部分では、そんな青山さん@ジミーと、紫吹さん@フレムシェンのお二人が、舞台前方に出て向かい合ってチャールストンを踊りあいます。それぞれが左右の腕を交互に出したり引いたりしながら、速くなってゆくテンポに合わせて、ひとつひとつの脚の関節を頂点にして、ジグザグに空気をかき混ぜるようなチャールストンのステップを刻みます。ダンスとしては非常に短いものですが、膝を中心にして内側に蹴られる爪先が、足首のバネによって力強く戻る・・・、そんな青山さんのバネの力強さと軽やかさが同居しているような、しなやかでありながら鋭角さを印象付ける脚全体の動線が、とても鮮烈に心に刻み込まれます。フレムシェンの「子鹿のような」足捌きと合わせて観ていると、このダンスの魅力、つまり鼓動が速くなるようなスリル感、そして、ハートが熱くなるような当時の人々の熱狂ぶりというものに対する臨場感が、身体のなかに湧き起こるのを感じます。青山さんと紫吹さんが向かい合って踊るチャールストンは、生命の躍動感に溢れ、まさに「踊ること=この瞬間を生きること」、そんなことを観客に直感させるものだったのではないでしょうか。
曲の中盤、フレムシェンとジミーズが会話をするシーン、横一列に重なるように並んだジミーズ。端から順番に、「僕の名前はジミー」、「僕の名前もジミー」、最後にジミーズ全員で「そして僕の名前もジミー、君は?」と声を揃えて、そう尋ねられたフレムシェンは、魅力たっぷりに「フレムシェン」と応えます。「オーラーラー(仏語っぽく)、フレムシェン~」と肩を揺り動かしながら、すかさず反応を返すジミーズ。高級ホテルのお客様と従業員の関係という枠を外れて、ダンスによって心を通わせてゆく様子が、とても楽しいシーンです。またあるときは、あんなにダンスを楽しんでいたはずのジミーズが、急に整列して姿勢を正し、うやうやしくお辞儀をしながら、「我々一同は、ここグランドホテルでお客様の皆様にショーも披露しております・・・」とフレムシェンに説明したりもします。個性豊かなジミーズのメリハリのある演技によって、洒落た台詞のやりとりに、軽妙さと媚態に溢れたユーモアの表情が付加されます。そんな台詞のやりとり、そして短いながらも非常に濃密なフレーズが詰め込まれたダンス、この二つの要素が交互に、コントラストも鮮やかに展開されることにより、いつの間にか、当時の華やいだざわめきに満ちた空気に巻き込まれ、酔うことができるような気がしました。
この場面は、確かにショーとしての魅力に溢れた「ダンスシーンの見せ場」です。しかし同時に、20年代・ベルリンという背景提示の役割をも負っているようにも思われました。「ショーのお稽古」あるいは「仕事」としてのダンス、そのことは脇において、理屈抜きにつかの間のダンスという享楽に身を任せて、酔う、そしてそんな「ダンス」を通じて、男と女がひと時の駆け引きのようなものを楽しむ。青山さんの肌理の細かい演技が織り込まれたジミーズのダンスを観ていると、そのような当時の空気が眼前にとても魅力的な光景として繰り広げられる気がしました。「自ら踊るためのダンス=チャールストン」の流行は、二つの大戦に挟まれたあの時代につきまとう無意識的な不安感を背景に、つかの間の華やかさを求める当時の人々の、心の奥底に根ざしたものだったのかもしれない、しかし明るみの裏に暗闇を潜在的に秘めたそんな時代を生き続けた人々が確実にいた・・・。この場面での青山さんを観ていると、そんな人々の息づかいというものが聞こえてくるかのようです。この作品においては、「踊る」という言葉が主要登場人物の台詞に多用されていて、この言葉には、ウォルフォードさんがパンフレットで述べている「人生の波が溢れ出てくるような巨大なエネルギー」、そのようなものが託されているような気がします。この場面でジミーズの青山さんが魅せてくれたダンス、とりわけチャールストンには、あの時代の人々を突き動かしていた「何か」が宿っていたような気がします。
この曲の華麗なフィニッシュの直前、センターで踊る青山さん演ずるジミーにウインクを送られたフレムシェンは、この「アメリカン・バー」でつかの間のチャールストンを楽しんだ後、ベルリンのホテルでの一日をどのように過ごすことになったのでしょうか・・・。
「炎と氷」「22年間」「丘の上の別荘」
軽快なジャズに合わせたチャールストンのダンスが終わると、薄暗くなった照明のなか、ジミーズたちは静かに、何もなかったかのように舞台袖に消えてゆきます。それまでの明るく華やかな世界が嘘のように感じられます。舞台は一転、喧騒からは遠ざかった、どこか物憂いグルーシンスカヤの部屋へと場面を移します。階段の手すりに手を掛け、バレエのレッスンにいそしむグルーシンスカヤ・・・。
「どうしよう やめるべきなの? 踊るべきなの? この人生救うには・・・」迫りくる老いに怯え、衰える人気を憂い、バレリーナとしての自分に限界を感じる日々を、苛立ちと戸惑いを込めながら、切々と歌うグルーシンスカヤ。Fire and Iceの冒頭、グルーシンスカヤがバーレッスンをしながら刻むトォーシューズの音が、そんな彼女の気持ちを物語っているようで、とても印象的です。Fire and Ice、「消えそうな炎と解けそうな氷」、グルーシンスカヤにとって、これほど耐えられないものはないのかもしれません。「踊るには、若さが必要なの!」という彼女。しかし、劇場主のサンダーやお取り巻きは、「会場は満員」と彼女には嘘をつき、舞台に立たせようとします。グルーシンスカヤは、歌詞にもあるように、「天使のイリュージョン」のような「鳴りやまないアプローズ」という「消えはしない愛」がなくては生きてはいけないのかもしれません。プリマバレリーナとしての輝かしい過去が、彼女につきまといます。
「バレエはもう流行遅れ、これからはジャズだ、ヌードだ、ジョセフィン・ベイカーだ。」グルーシンスカヤのいないところで、仲間に本音をもらす劇場主。お取り巻きにさえも本当のことを告げられず、苦しみのなかで舞台に立ち続ける孤独なグルーシンスカヤですが、自分が舞台に立たなければ、自分を支える周囲の人々が路頭に迷ってしまう、そう思ってなんとか舞台に立とうとします。これまでバレエ一筋に生きてきたグルーシンスカヤに対して、「私はただトーシューズの紐を結びなおす手助けをして差し上げたいだけ・・・」とこちらも22年間グルーシンスカヤ一筋に生きてきた、付人のラファエラは、精一杯に気持ちを伝えようとしますが伝えきれません。「私はただバレエのお稽古がしたいだけ」とあっさりと返答するグルーシンスカヤは、ラファエラの「深い愛」にも似た感情に気づく余裕がありません。
薄暗い照明のなか下手の階段で、物憂げにうなだれるグルーシンスカヤ。その上方、下手よりの階段の上のバルコニーで、22年間付き添ったグルーシンスカヤへの秘めた想いをラファエラが歌い上げます。いつかバレリーナとしての時が終わり、誰もグルーシンスカヤに振り向く人がいなくなったとき、そんなときのためにひたすら準備をしてきたラファエラのこれまでの22年間。そして傷心のグルーシンスカヤを支えて、二人で過ごそうと願っている、ベルリンからは遠いポズィターノの丘の上の別荘でのこれからの生活を夢見るラファエラ。グルーシンスカヤに打ち明けることはできない想いを抱えて、叶うかどうかは定かでない夢を、彼方を見つめてバルコニーで歌うラファエラの声がとても印象的なシーンです。そして、ジャズでチャールストンを踊り、ハリウッドに行くという未来を夢見るフレムシェンと、「過去の遺物」となりつつあったバレエを踊り、情熱を失いつつあるグルーシンスカヤ、直接に交わることはない対照的な二人の登場人物の生のあり方が、観る者の心に刻み込まれていきます。
「君、可愛いね。」男爵は舞台上手のフレムシェンに近寄って声をかけます。そんな男爵に自分の魅力をアピールしようと、フレムシェンは、足元の台に片足を掛けて、ただでさえ短いスカートの裾を更に引き上げ、ガーターベルトのついたストッキングの端をちらつかせます。男爵に「魅力的だ」と言われた彼女は、「あなたも悪くないわ」と、大人の女性の雰囲気を漂わせて、19歳の女の子からはかなり背伸びをした様子で答えます。男爵は魅力的なフレムシェンを「黄色い館で、5時に」と誘い、約束をした後、その場を去ってしまいますが、その様子を傍らから眺めていたドクターは、この曲が始まると、音楽に合わせて指揮をするような手つきで、魅力的なフレムシェンに引き寄せられてしまうかのように、掌をひらひらとさせてリズムを取ります。重い存在感のある役どころにもかかわらず、何故かコミカルな動きをするドクター。ドクターでさえも思わず、リズムを取りながら美しいフレムシェンに引き寄せられてしまうのでしょうか。それともドクターは、若さにまかせて思いのままに進んでいこうとするフレムシェンの心の内をありのままに覗き込んでしまいたくなったのでしょうか。そんなドクターの指先の動きに導かれるかのように、観客は、フレムシェンの鏡の中の空想の世界へと誘われてゆきます。
素敵な男爵からのお誘いを受けてしまい、心弾むフレムシェン。上手の台に腰かけ、唇に指を添えて、嬉しさのなかにわずかなためらいを滲ませ、鏡のなかの自分を見つめながら、自分自身に問いかけているように見えます。「私のどこが気に入ったのかしら・・・」「鏡の中のあの子は誰なのかしら・・・」この曲は、フレムシェンのそんな胸のざわめきを表わしたような問いかけから静かに始まります。やがて、世の何百万もの男性を虜にして、カメラマンたちの眼を釘付けにする、「行きたいのよ、あなたと ハリウッド・・・」と素敵な男爵から誘いを受けたことをきっかけに、夢見るフレムシェンの想像は、果てしなく大きなものへと膨らんでいきます。ハリウッドに行って、映画に出て、大スターになって、豪勢な生活をして・・・、そんな夢のような生活を想像していくフレムシェン。「歌いたいのよブルーズ、つま先にはシューズ(履きたいのよナイスシューズ?)、唇にはルージュ(確かこんな訳詞でした)」と韻を踏んだ歌詞に合わせて、長く美しい脚を水平方向におおらかに伸ばしたり、腰を振ったりするコケティッシュな振りで紫吹さん@フレムシェンは、夢見る19歳のフレムシェンの輝きをのびやかに、そして鮮やかに魅せてくれます。
しかし、美しいフレムシェンが、どれほどハリウッドに行くという夢を見ても、現実の彼女の生活は、フリードリッヒ通りにある安アパートでの希望のかけらもない、うんざりするようなみすぼらしいもの。鏡の中の世界から再びこちら側に引き戻され、厳しい現実を突きつけられるフレムシェン。壊れたままの手鏡とポット、隣家の騒音、調子の悪い暖房・・・。毎日嫌というほど向き合わなければならない現実への失望感を、フレムシェンは舞台中央で歌います。そんなフレムシェンただひとりをスポットライトが照らし出し、彼女の周りは真っ暗で闇に包まれています。脱け出したいにも脱け出せない、そんな生活への不安と失望から、病気にでもなってしまいそうな彼女の状況が伝わってきます。(ちなみにこの曲の中盤、現実の生活への不満をフレムシェンが歌うこの部分のメロディーは、I Waltz Aloneの後、男爵が撃たれる直前、プライジングにフレムシェンが服を脱ぐよう強要されるあのシーンで、もう一度奏でられ、印象的でした。)
そんな現実の生活からは絶対に脱け出さなくてはならない、なんとしてでもハリウッドに行かなくてはならないフレムシェンが、今はただ夢に描いているだけの自分の未来を、何とかして現実のものにしなくてはと決意し、一歩踏み出してゆく・・・。そんなフレムシェンの心情を描いているのが、この曲の後半、青山さんたちアンサンブルがシルクハットを被って登場してくる場面なのです。Maybe My Baby Loves Meのときと同じ紫色の燕尾服を着ているので、ジミーズと書きましたが、この場面は、あくまでフレムシェンの想像の世界、鏡の中の世界での夢のような出来事という気がします。首から下は先ほどのジミーズの衣裳、つまり紫色の燕尾服ですが、シルクハット(トップハット)の存在によって、より一層エレガントな雰囲気へとイメージががらりと変わります。そして、上流階級へのあこがれを語り、非日常性とショーらしさを演出するというシルクハットの特性が、ハリウッドへ行きたいというフレムシェンの夢が語られる、このシーンの雰囲気にとても適したものであると思いました。そんなシルクハットに添えられる指先、燕尾服の襟に添える手の形を取り出してみても、青山さんはとても表情豊かで、「鏡の中のあの子」が踊るというこの場面の空気を創り出しているようでした。御登場は曲の終盤になってからで、ダンスをしている時間としては非常に短いものですが、洗練されたエレガンスとスリルが渾然一体となった表情が全身から溢れ出ているダンスに、フレムシェンのみならず「夢見心地」に舞い上がってしまいます。
つらく厳しい現実の生活、しかしフレムシェンのなかにどうしても湧き起こってくる、それとは正反対の夢の世界。そんな鏡の中だけで許されるような夢の世界を象徴するかのように、回転扉の両脇の扉からジミーズの四人が、二手に分かれて、シルクハットを被り、ステップを踏みながら、中央のフレムシェンを後方からそっと包み込むように登場してきます。このときシルクハットをうつむき加減に被り、顔の表情というのが見えにくいのですが、この「誰かわからない」という正体を隠している感じが、自分の可能性に賭けることへのためらいのようなものを抑えこんで、フレムシェンのなかにどうしても湧き起こってきてしまう夢の世界をイメージさせ、胸がじわじわと高鳴るような感覚を与えてくれます。片方の手をシルクハットのブリム(鍔)に添え、もう片方の手を燕尾服の襟に添え、かっちりとした折り目正しさ、洗練されたエレガンスを漂わせながらも、フレムシェンをふんわりと再び夢の世界に誘い込むようにステップを刻みます。そんな衣裳に添えられる青山さんの指先、そしてそこを起点にして始まる腕から足先までの身体の描線は、まるで線描画のそれのように、とても緊張感に溢れた繊細なもの。それにもかかわらず、その動き全体から受けるイメージは、ふんわりとした優美さで充満しています。このようにして言葉だけで説明してしまうと、「緊張」と「ふんわり」などという、相反する言葉を用いることになってしまうので、矛盾しているような印象を与えてしまうと思いますが、そんな「矛盾」が青山さんのダンスのなかでは、当然のことのように美しく同居してしまうから不思議です。この場面での青山さんのダンスを、試みにたとえてみると、「非常に繊細なガラス細工、でもそのガラス細工の作品の中には、その薄い表面が割れてしまうのではないかというぐらいにエネルギーがギュッと詰まっている感じ」のダンスとでも言えるでしょうか。青山さんのダンスのそんな雰囲気が、Maybe My Baby Loves Meのときとは異なる「スリル」を醸しだしている気がしました。フレムシェンが夢見る、華やかなハリウッドの世界と大スターだけに許されるゴージャスな生活。そんな夢のような生活へと突き進んでゆくフレムシェンの若さと勢い。そして、フレムシェンが鏡のあちら側とこちら側、空想と現実の間を行き来するなかで立ち現れる、鏡の中の世界のはかなさ、危うさ・・・、そんなものを、青山さんのダンスは観客の中に刻み込んでいるように思えました。
この場面では、中央で歌うフレムシェンを中心に、左右両サイドのジミーズが両腕を上方に広げながら、交差してポジションが入れ替わるところがありますが、このときも青山さんが描く腕から指先に掛けての弧線は、とても柔らかい優美なもの。一方腰から大腿部、足先にかけての交差する動きには、緩急自在なスピード感があります。フレムシェンの周囲で交差してゆくジミーズたちの動きを見ていると、フレムシェンのなかに残っていたわずかなためらいのようなものも消えてゆき、再び夢の世界へと誘われていってしまう感じが伝わってきます。
やがてフレムシェンのなかで、ハリウッドに対する想いが、「行きたい(I want to go)」という単なる願望から、「行かなきゃ(I have to go)」という必然に変わっていきます。そのヴォルテージの上昇してゆく様子が、スピード感を増してゆくダンスからも伝わってきます。左右交互に力強く伸ばされる大腿部から足先にかけての完璧なライン、力強いのだけれど、エネルギーをありのままに思いっきり外に押し出すという感じではなく、あくまでエレガントな繊細さを感じさせるようなもの。身体が描くその線がこれ以外のものはありえないと確信してしまうような完璧さなのです。さらにそのような動きのなかで、一瞬ドキッとするような表情が、シルクハットに宿ります。シルクハットとお顔、首、肩そして帽子のブリムの添えられた指先が生み出すエッジの効いたフォルム、青山さんの生み出すそんな瞬間には、視線が合うわけではないのに、こちらがハッとしてしまうほどのスリルがあるのです。登場のシーンでは、シルクハットが彼らの正体を隠して、フレムシェンのなかにあるためらいをほのめかしていたような感じでしたが、ここにきてこの帽子は、フレムシェンのなかに定まった強い意志を感じさせて、とても印象的です。そんなシルクハットの扱いとともに、真ん中にスッと通った揺らがない軸を中心にして展開する上半身の端整な動き。完璧な全身のフォルムが、テンポが速くなっていく音楽のなかで、少しの狂いもなく眼の前で連続してゆきます。
この後に続く部分では、フレムシェンを青山さんたちジミーズが代わる代わる軽くリフトします。このときも、正面を向いて、身体を斜めに傾斜させ、傾いた身体の右半分のラインに、紫吹さん@フレムシェンを寄りかからせるように乗せるのですが、スッと傾いていく感じがとても優雅で、お二人の創り出す傾斜時のフォルムと動きの流れがとても綺麗です。そして間奏部分に続く、BW版の”I swear that girl in the mirror, that girl in the mirror is going to go to Hollywood !”のところでは、「この子は絶対にハリウッドに行くわ!」というフレムシェンの決意にある勢いが最高潮に達する場面。ダンスの勢いも、そんなフレムシェンの感情の高まりを反映するかのごとく、ラストまで一気に高まっていきます。ここでは最初、音楽を追いかける感じで、ゆらゆらと揺れるように少しルーズな感じで、左右の腰の前あたりに両手をあてて全身でリズムを取っているのですが、やがて青山さんの動きを音楽が追いかけているのではないかと錯覚してしまうほど、緊張感とスピード感が高まっていきます。上半身の端整さと優雅さはそのままに、片膝を引き上げるような振りを織り交ぜながら力強く刻まれるステップ、やがて再び登場シーンと同様に、両腕を上方に広げていくようにしながら、フレムシェンを取り囲む形で交差するジミーズ。そしてラストに中央で彼らにリフトされるフレムシェンは、眼の前の現実から脱け出して、夢の高みまで一気に上り詰めてゆこうとするエネルギーに溢れています。
「ハリウッドに行きたい」という夢を抱く19歳のフレムシェン。そんな彼女が、幼い頃から「カラス」の寓話に囚われているプライジングに間もなく出逢うことになります。
「歪んだ道」「あるべき人生」(リプライズ)
フレムシェンをタイピストとして雇ったプライジング。舞台下手側の片隅、プライジングのそばでフレムシェンはタイプライターを打ちます。プライジングはフレムシェンに、自分と共に秘書のような身分でアメリカについてくるよう提案。ハリウッド行きを夢見るフレムシェンは、そんなプライジングに「ボストンとハリウッドは、汽車で行けるほど近いのか」というような質問をします。フレムシェンの期待を裏切らないように、プライジングはとりあえず誤魔化しながら答えます。一方プライジングは、自分が社長を務めるサクソニア・ミルズ社の経営悪化から、今夜中にボストンの会社との合併を決めなければ、自社が倒産するという窮地に立たされています。電報を受け取った彼は、合併の話が白紙になったと知って、激しく動揺します。この危機的状況をどうにかして切り抜けるには、事実を隠蔽してでも株主たちに「合併成立」と伝えるしかない、という選択を弁護士に持ちかけられます。経営者としての選択を迫られ、人生の岐路に立たされたプライジングが、幼い頃から聞かされた「カラス」の寓話を引きながら、どちらの道を行くべきかを歌うのが、The Crooked Path、「歪んだ道」です。
この作品の冒頭、「グランドパレード」で、プライジングをはじめとする登場人物たちが、重層的なハーモニーを奏でながら、舞台のあちらこちらで電話をするというシーンがありました。このとき既にプライジングは、自分も幼い時から聞かされてきた、分かれ道でカー、カーと鳴く「カラス」の寓話を、電話の向こうで父親に昔話をしてほしいとせがむ自分の子供に向かって、話して聞かせているのです。プライジングには冒頭から、傲慢さの陰で、初めから破滅に向かって歩みだしている予感がつきまとっています。しかしながら、そのようなプライジングも父親であり、愛する妻と子供がいるわけで、プライジングの身に起こる以後の出来事が、彼らに及ぼす影響を想像してみても、切ない想いになります。作品終盤、フロント係のエリックには待ちわびた新しい生命が誕生し、父親になった喜びを噛み締めることになるのですが、その一方でプライジングは、一人の経営者としてだけではなく、一人の父親としても破綻を迎えることになり、とても対照的に思われました。
歌詞にもある、分かれ道の中央に立つ一本の木にとまっている、年老いた一羽のカラス。「どちらの道を行くべきか」と尋ねる少年に対して、このカラスは、「このヤバそうな道を行け」、「真っ直ぐな道は流行らない(訳詞はちょっと違ったかも)」、と「歪んだ道(真っ直ぐではない道)」を行くようにそそのかすのです。岐路に立たされ苦悩しながらも、「このヤバそうな道」を行くという選択肢しか、自分には残されていないということを、プライジングは半ば悟っているかのようです。そんなプライジングを「歪んだ道」へと誘い込むかのように、そして彼の弱さを嘲笑するかのように、不吉な「カラスたち」が集まってくるのです。ホテルの従業員たちが、四方八方から静かに登場してきますが、このときのアンサンブルの皆さんには、お客様をお迎えするというような、ホテルの従業員としての血の通った「人間らしさ」というものがなく、従業員としての役柄を感じさせない、「抜け殻」のような無機的な存在感を漂わせています。しかしプライジングの歌声と同時に「カアカア」と鳴きながら、「カラス」の身振りをし始める彼らには、悪魔の手下のような不気味なカラスの魂がスッと宿るようにも見えます。
青山さんも、舞台上方の上手側から、階段踊り場付近へと登場してきて(この位置はとても目立つポジションでした)、プライジングを破滅の道へと転落させていく「カラス」を、身振りで表現します。「鳥類」の動きを表現する青山さんは、「おどろんぱ!」でも、既に見ていましたが、悪魔的な匂いのする冷酷さが重なる「鳥」は今回が初めてでした。狙った獲物を包み込むかのように広げられた緊張感のある指先から、腕、そして肩にかけての波打つような力強い動きには、鞭打つような瞬発力に溢れています。それでいてその動作の始まりと終わりには、息を殺したような静けさのようなものが感じられて、一言で「カラスの羽ばたき」と言ってみても、一連の動きには見事な緩急を感じることができ、これがより一層不気味さを醸しだします。獲物の居所を物色するかのように、音楽に合わせてあちらこちらの方向へと胴からするりと伸びる首、あるいは逆に胴のなかへと入り込む首。そのような動きをする首と肩との角度には、どこまでも追いかけてくるようなカラスの執念のようなものが感じられました。カラスの冷たく湿ったような、重たい羽先、餌食となるはずの標的を見つけた瞬間の鋭い視線による焦点の合わせ方、一瞬にして空を黒く覆いつくすかのように面積の大きい翼、そして標的をあっという間に掴みさらって行くような冷酷で力強い動きが、この後のプライジングを待ち受けている運命を暗示しているようでした。カラスの鳴き声に引きずられ、悩まされるプライジングの叫びにも似た「カーカーカー」という最後の鳴き声とともに、舞台から消えてゆく「カラス」からは、プライジングをあざ笑うかのような不吉な羽音が聞こえ、地面に重たく舞い落ちる、黒光りした重たい羽が見えるようでした。
このシーンに引き続き、再び洗い場の労働者たちによる、Some Have, Some Have Not、「持つ者と持たざる者」が歌われます。経営者であり、ここグランドホテルの宿泊客として当然の身分を保証されているはずの、「持つ者」であるプライジング。しかしそんな「持つ者」としての彼の身分でさえも、一つの嘘で辛うじて保たれているようなものであり、「持たざる者」へと一夜にして変わり果てる可能性があるのです。その一方で、「持つ者」としてのお客様のためにどれほど働いたとしても、決して「持つ者」としての身分が変わることはないホテルの下働きの人々。一晩で1000マルク使える「彼ら(持つ者)」のために、自分たち(持たざる者)が朝から晩まで働いたとしても、何も変わりはしません。この曲がフェイドアウトしていくなか、「なぜ~」という叫びにも似た歌声(中村元紀さん)が舞台奥へと消えてゆきますが、そんな労働者たちの声は「持つ者」には聞こえるはずがないのかもしれません。さらに、見かけは「持つ者」である男爵の人生も、いつ「持たざる者」としてのそれに転落したとしてもおかしくはない状況に置かれています。運転手に、明日の夕方までに金を用意するように要求され、もう後はないような窮地に立たされているのです。男爵は、何かを決意したかのように、ここで再びAs It Should Be、「あるべき人生」を歌い上げます。洗い場の労働者たちによって歌われる「持つ者と持たざる者」、それを挟んで対置される、プライジングと男爵がそれぞれ歌う、「歪んだ道」と「あるべき人生」の2曲。これらの一連のシーンを通して、「持つ者」と「持たざる者」の身分の差などはまさに紙一重、「持つ者」としての彼らの人生は「危険な賭け」によって辛うじて成立する世界であるようなイメージを観客は受けます。そして同時に男爵とプライジングが「危険な賭け」という名の同じ鎖で背中合わせに囚われの身となり、終盤に起こる悲劇へと向かって、共に静かに助走をし始めているようでもあります。
男爵によってドラマティックに歌い上げられる「あるべき人生」ですが、「綱渡りの人生」を渡ってゆくような張り詰めた緊張感に満ちた曲調が、サビの部分から間奏部分にかけて、とろけるような甘いムードが溢れる曲調に変わってゆきます。次のシーン、Who Couldn’t Dance with You?、「あなたとなら誰でも踊れる」へと場面転換してゆくのです。タキシードやドレスで正装したホテルのゲストたちがあちらこちらから舞台中央へと登場してきて、彼らが行き交う「黄色い館」でのダンスシーンへとあっという間に転換してゆきます。青山さん演ずるタキシード姿のホテルのゲストも、上手より歩きながら登場、下手寄りの階段手前あたりで、ビーズの煌き(スパンコールだった気もします)がとても美しいドレスに身を包んだ女性に一礼し、彼女の手を取ってダンスを踊り始めます。男爵、フレムシェン、オットー、そしてプライジングの人生が、「黄色い館」で交錯してゆくことになります。
「あなたとなら誰でも踊れる」「合併問題」「炎と氷」(リプライズ)「アンコールはなし」
As It Should Be、「あるべき人生」の曲がいつしかロマンティックなダンスのための曲に変化するにつれて、正装したホテルのゲストたちが四方から集まってきて、カップルになって優雅にダンスをし始めます。舞台はあっという間にフレムシェンと男爵が「5時に」と会う約束をした「黄色い館」へと、場面転換していきます。黒いタキシードに身を包んだ青山さんも、上手より登場、舞台中央下手よりの階段下まで歩みより、シャンデリアの光を反射してキラキラ光るビーズ(スパンコール?)が印象的なドレス姿の美しい女性に一礼し、ペアになってダンスを踊り始めます。音楽に合わせて上手から中央へと歩み寄ってくる何気ない動作にも、青山さんの場合には「音楽」が感じられます。この場面転換のしかたが、音楽の変化とともに、流れるようにスムーズで、緊張感溢れるシーンがいつの間にか、ダンスを楽しむ華やかで優雅な雰囲気へと変わってゆくのです。中央で楽しげに踊るフレムシェンと男爵、その周りで正装した男女のペア数組が音楽に合わせてダンスを楽しんでいます。ダンスを楽しむそれぞれの男女が思い思いにホールに描くふんわりとした動線が、ロマンティックで印象的です。ベルリンの高級ホテルのダンスホールでダンスに興じる、当時の人々の華奢な雰囲気が伝わってきます。ダンスをしながら男女が甘い恋をささやくような甘美な雰囲気も漂います。ちなみにこの場面の曲ですが、Grand Hotelのスコアブックでは、The Grand Fox-Trot(Trottin’ the Fox/Who Couldn’t Dance with You?)というタイトルがつけられています。
さてこの場面でのタキシード姿の青山さん、とにかく透明感と洗練を漂わせるエレガントさが印象的でした。ピタッと撫で付けられたヘアースタイル(照明によっては金髪に見えるようなかなりブラウン系の強いカラーでした)に、ニヒルな微笑、タイトな黒タキシードの優雅な着こなし、葉巻の持ち方、そしてお相手の女性に対する堂々としたリードの仕方・・・。ダンスのほとんどは、女性と手を組み、靴幅ほどのスペースを前に後ろにと、踵を浮かせながら弾むようにステップを刻むものなのですが、音楽のテンポからは故意に半歩遅れたような青山さんペアのダンスが、フレムシェン・男爵ペアのテンポを先取りするような急ぎ足のダンス(フレムシェン的には、「男爵婦人」の座を射程に入れて、張り切って浮かれてしまうのは当然なのです)と対照的で、それらをひとつの視野のなかでダンスルームの「風景」として観ていると、場面に遠近感が出て、奥行きが感じられました。
またこの曲の後半では、病気を患って余命幾ばくもないオットーのダンスの相手になるよう男爵から提案されたフレムシェンが、オットーとペアを組んで踊るシーンもあります。「踊りたい、ウィズ・ユー(Who couldn’t dance with you?)」という歌詞に、曲の前半では、フレムシェンの男爵に対する思いが重ねられ、後半ではオットーのフレムシェンに対する思いが重ねられます。元々このシーンの冒頭で、オットーは自分が宿泊しているグランドホテルの素晴らしさにすっかり浮かれて、このダンスルームに登場してくるのですが、そんなオットーの幸福感は、フレムシェンにダンスに誘われることにより最高潮に達します。上手側のカウンターで一人お酒を楽しんでいたオットーは、フレムシェンの言葉を受けて、あまりの嬉しさに子供のように、誤ってズボンを足元にまで下ろしてしまいます。バーテンダーに手伝ってもらいながら、慌ててズボンをウエストまで上げてもらい、ベルトのようなものを調節してもらうオットー。ズボンのウエスト部分をバーテンダーに引っ張られ、ウエストから下は後ろ方向に置き去りになったまま、上半身はフレムシェンの腕の中、という絵が、何とも微笑ましくて笑いを誘います。この一部始終を傍から眺めていたゲストを演じる青山さんも、困ったような、驚いたような表情を浮かべ、お相手の女性に大変なものを見せてしまったという気持ちが読み取れました。これまでほとんどダンスなどしたことのなかったオットーが、喜劇役者のようにコミカルな動きを織り交ぜながら、フレムシェンとの夢見心地のダンスを楽しみます。最初は緊張した面持ちで、子供のようにぎこちなく踊っていたオットーが、フレムシェンにリードされながら、ダンスの手ほどきを受けるうちに、自信とよろこびを取り戻して、「羽のように軽い」ステップを刻むようになるのです。そんなオットーが、病気を患っていることなど信じられないほどに、華麗にターンをするところがあるのですが、まさにそのすぐそばを、青山さんたちのペアがダンスをしながらすれ違います。そこで青山さんは、お相手の女性に同意を得るように、そんなオットーに対する驚きとよろこびの混ざったような、あるいは祝福しているかのような表情を浮かべるのです。あのシーンは、ほんの一瞬なのですが、「踊れない」はずのオットーが「踊れる」ようになるような、つまり失っていたはずの自信やよろこびという「生の輝き」のようなものを取り戻し始めるシーンのような気がします。そんなオットーのよろこびを、その場に居合わせた人々が、身分の差を超えて、わずかながらも分かち合い、祝福する、そしてあのダンスルームもパッと一瞬色づく、そんな瞬間を、印象づけていたような気がするのです。ドクターは、「黄色い館」で踊る彼らの様子を傍から眺めていましたが、ついにこんな言葉を観客に投げかけます。「御覧なさい、踊っている。彼の身体は音楽になり、その生命は永遠に続くかのようだ。しかし、我々はどうしてこんなことにこだわるのか・・・」
(この続きは、「詳細レポ Ⅶ その2」として、続けて投稿します。今回投稿した分は、「Ⅶ」の「その1」ということです。)
「あなたとなら誰でも踊れる」「合併問題」「炎と氷」(リプライズ)「アンコールはなし」
ところでこのダンスホールでのシーンでは、フレムシェンの雇い主であるプライジングも登場してきて、仕事をするようにフレムシェンを呼びとめます。彼女と踊るオットーは、そのプライジングが、自分が会計係として勤めていた会社の社長であることに気づき、挨拶を交わそうとしますが、当のプライジング社長は、オットーのことなど覚えているはずもなく、冷たくあしらいます。会社に儲けさせてやったにもかかわらず、ひどい待遇を受けこれまで生活してきたオットー。しかもこうして再会したとしても、自分を虫けらのようにしか扱わないプライジング社長に対して、オットーは逆上して、大声で怒鳴り散らします。ふと我に返って、彼に雇われる側としてのお互いの立場を思いやるオットーとフレムシェン。ダンスルームで踊る正装した人々(タキシード姿の青山さんも)は袖に引かずに、背景としてその場にとどまっていますが、華やかで夢見るようなダンスルームの幸せな雰囲気は、ここから少しずつ暗雲が立ち込めるものに変容していきます。
ここで、この作品での「タキシード」の持つ意味合いを明確にするために、このMerger Is On、「合併成立」のシーンの直後(だったと思う)のシーンでの、男爵とオットーのやり取りをご紹介しておきます。ダンスルームでの出来事が自分にとっては「おとぎ話」のようだ、と話すオットーに対して、男爵は、タキシードを着て踊っている彼らも皆、株に投資をして成功した結果、あのように楽しんでいるのだ、と説明します。だからオットーも株に投資してみてはどうか、と提案するのです(これが後でオットーに幸運をもたらすことになるのです)。オットーは、タキシードなんて、自分は棺桶に入るときぐらいしか着ない、と言うのですが、タキシードというものが、この作品では、あの時代の富と成功と華やぎの象徴のように受け取られていることがうかがえます。そんなタキシードを着て正装している青山さんたちアンサンブルの存在感(表情)も、この一連のシーンの流れのなかで、残酷とも言えるほどに変容するのです。
プライジングは、株主たちが合併問題をめぐって集結している中2階の階段の踊り場へと行き、追い込まれた状況のなかで、「ボストンとの合併は成立」と、嘘の発表をしてしまうのです。彼を取り囲む株主たちは一斉に歓喜し、階下のダンスルームにとどまる正装した人々も、それとともに「やったぞ、ボストン!やったぞ、合併!」と音楽に合わせて一斉に歌い始めます。ついに「歪んだ道」へと歩き始めてしまったプライジング。そのプライジングが苦しみに満ちた台詞を語りますが、それと同時に、さきほどオットーの幸福感を祝福していたはずのタキシードを着ていた彼らが、急に掌を返すように、プライジングを「歪んだ道」へと誘い込む悪魔の手下のような存在に変わってしまうのです。モノトーンの陰影が強調されるような照明のなかで、不気味に黒光りするタキシードを着た青山さんにさきほどの「カラス」のイメージが重なります。また、照明によって強調されるお顔の陰影、さらに恐ろしいほどに増した透明感は、人の人生を狂わせてしまうような冷酷さを感じさせます。ダンスルームのシーンでは、高貴さをイメージさせるような透明感溢れる表情を浮かべ、生を謳歌するような幸福感に溢れていたタキシード姿の青山さんでしたが、このシーンでは正反対とも言えるほどに、その表情をガラリと一変させるのです。
プライジングは、自分の行く道が定まってしまった、という後戻りができないことへの絶望感と、不透明なこれからへの不安感を露にしながら、「歪んだ道」のフレーズ(?)をつぶやきます。プライジングがあきらめを滲ませながら、「やはりこうなった」とでも言うように口ずさむ「カア~、カア~」の二鳴き。それとともに、階下のダンスルームの正装した人々も、プライジングをあざ笑うかのように、「カア~、カア~」の声は出さずに、この言葉を口真似だけで(顔の表情だけで)「カア~、カア~」と鳴いてみせるのです。このときの青山さんですが、客席には背中を向け、お顔だけを横顔のラインが見えるようにこちらに傾けています(下手側の座席でないと、見えづらかったかもしれません)。照明もモノトーンを意識させるような冷たい感じのものに変わり、お顔全体にさす影と、冷たい陶磁器のような質感が、とても印象的でした。そのような質感のなかで、首から下は微動だにせず、口元だけで音(声)は出さずに、「カア~、カア~」と口真似だけをするのです。「カア~、カア~」とカラスの鳴き声を出しているのは、プライジングだけなのですが、鳴き声を出さずに口真似だけをしている青山さんたちアンサンブルが、逆に声は出さずとも、プライジングを完全に操っているようで、異様なぐらいの恐ろしさと冷酷さが押し寄せてくるようでした。黒光りするタキシードに、「歪んだ道」のシーンで観客の心に焼き付けられた、不吉な「カラス」のイメージが、重層的に重なったシーンでもありました。
昔からとらわれていた「カラスの寓話」が現実のものとなりつつあるプライジング。その一方でグルーシンスカヤが過去からずっとこだわり続けてきたがゆえに、今になって苦しめられることになってしまったもの、それは「炎と氷」です。自分を奮い立たせて、精一杯にぎりぎりのところで舞台に立った彼女でしたが、観客からのアンコールの拍手はありません。つまり「アンコールはなし」なのです。その代わりに彼女を襲ったのは、嘲笑とブーイングだったのです。今となっては、彼女の踊りにおいては、炎も消え、氷も解けてしまったのでしょうか。「合併問題」が片付いたことを受けて、中2階の階段踊り場で音楽に合わせて肩を組みながら、「カラス」の振りを踊る株主や弁護士たち。その彼らが袖に消えてゆくと、その背後から背を向けて「白鳥」のように踊るグルーシンスカヤが現れます。このグルーシンスカヤも、「カラス」たちに苦しめられているように見えます。観客の冷たい反応に耳をふさぎ、怯え、倒れるようになりながら、やっとのことで階下へと下りてくるグルーシンスカヤ。「炎と氷」を歌うアンサンブルの歌声が聞こえます。そして他でもない、先ほど正装をしてダンスを踊っていた人々が、グルーシンスカヤの踊りを冷たく嘲笑する観客に変容します。薄暗い照明に照らされた階下の舞台中央で、冷たく甲高い笑い声が響き、グルーシンスカヤをその笑い声が取り囲むのです。青山さんも身体はほとんど動かさずに、高らかな笑い声を浴びせます。絶望したグルーシンスカヤは、これ以上舞台には立てない、と舞台の途中で劇場から逃げ出すように、ホテルへと向かいます。
この一連のシーンにおいて「タキシード」を着て正装して登場した青山さんでしたが、まず「黄色い館」でダンスを楽しむ裕福な当時の青年、次にプライジングを「歪んだ道」へと誘いこむことに成功した「カラス」、そして「アンコールなし」のグルーシンスカヤを冷たくあざ笑う観客、とその役柄は、大きく変化していました。しかし「役柄が変わっていた」、青山さんを観ていた観客としての私が言いたいのは、ただそれだけのことではありません。青山さんにおいては、「役柄が変わること=質感が変わること」だったということを強調したいのです。このことが私の拙文でどれほど伝わるのか、本当に恐ろしいのですが、そのような青山さんを観ていると、同じ「タキシード」でも、前半と後半とでは、全く別の意味を、観客はイマジネーションを働かせながら、読み取ることが出来るような気がしました。この一連のシーンの流れのなかで、ダンスという「動き」が目立った前半部分とは打って変わって、後半部分ではそれとは正反対にアンサンブルの方々はそれぞれのポジションでほとんど身動きせずに(わずかな動きで)立ち尽くしたまま演技し続けました。タキシードに身を包んだ青山さんも、下手よりの中央前方という目立つ位置で、その立ち位置をほとんど動くことがなかったと思います。「タキシードのアンビバレンス(両義性)」を観客に効果的に印象付けることにより、場面を動かし、情景を観客の心に印象付ける・・・、勿論これは演出の手腕によるものだったのでしょう。しかし、「一ヵ所に集まる多数の登場人物の思いと行動が交錯しながら物語が進む」というこの作品を可能にし、へーまさんも、「記憶のソファ」の記事で書かれていた、「プロットの有機的な連続」というものを見事に実現させていたもの・・・、これは一体何だったのでしょう。それは「動かないセット」のなかで「空気」のようなものを変容させ、転換させていた、アンサンブルの力量によるところが大きかったのではないか、と、このシーンの青山さんを観ながら、私は確信していました。
男爵は運転手にこれまでも再三借金の催促をされてきましたが、ついに拳銃を突きつけられて、公演で留守のはずのグルーシンスカヤの部屋に侵入し、首飾りを盗んでくるよう言い渡されてしまいます・・・。男爵とグルーシンスカヤの運命的な出逢いは、もうすぐそこです。