
2015年10月5日(月)、一関市萩荘霜後地区にある霜後の滝を見に行ってきました。滝は前日の大雨の名残で水量豊富で見応えがありました。妻は60年ほども前に来たことがあるあると言っていましたが、周辺は幾らか整備されているものの、景色は余り変わっていないようでした。

(上と下)入口の「水と花とふれあい(霜後の滝)公園」の案内板。


(上と下)久保川に架かるもみじ橋。


(上と下2つ)もみじ橋から久保川の下流を見た風景。ここにも段差の低い滝がある。



(下3つ)もみじ橋の上流にも段差の低い滝があった。





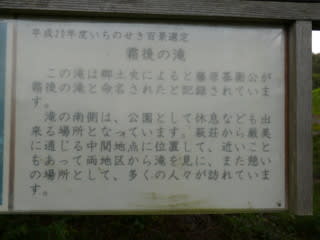






(下4つ)ここにも段差の低い滝(ひめ小滝)があった。









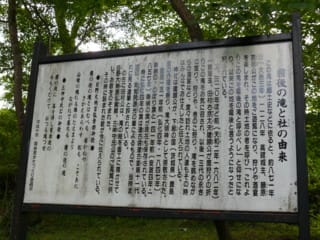
(上)霜後の滝と社の由来説明板:この滝は郷土史などによると、約871年前(大治3年)1128年 高舘城主、藤原基衡公がこの地をご遊覧になり、狩りや酒宴を楽しまれ、その時土地の者を呼び「これよりこの滝を霜後の滝と呼ぶべし」と仰せになり、以来この地を霜後と言うようになったと記されている。又、320年ほど前(天和2年1682年)一関藩主、田村右京太夫建顕公が鷹狩りの折りこの滝をお気に召され、以後13代の永きに亘り、狩りや、きのこ狩り、滝を眺めながらの酒宴など、度々訪れた土地の人達もその時はみんなでお仕えしたと伝えられている。
神社は建顕公が、下総の国(茨城県)鹿島宮の分霊を祭り、滝大明神として崇敬された。現在151年前(弘化4年、1847年)奉納の、のぼり旗と141年前(安政4年、1857年)奉納の旗が現在も保存されている。特に弘化4年の旗は達古袋達古家第11代法印、常覚読源光の筆によるもので、当時まれに見る達筆と評されている。のちに田村公は、滝の絵を画工に描かせて日野大納言弘資卿、三神守氏公のご高覧に供し、お歌をのぞまれた。その詩に詠まれた歌が今に伝えられている。
●日野大納言弘資卿御歌●
霜の後の滝とはむべも 岩かねや さかえあらわす 松も こそあれ
山?の?れる錦のたえまより ながれて落ちる 霜の後の滝
●三神守氏公の御歌●
霜の後に 名を得し昔白波の 今もくだけて おつる滝つぼ
平成10年 霜後里まちづくり委員会

(上と下2つ)「霜後の滝ご覧場」から眺めた霜後の滝:迫力がありません。



(上)少し奥に滝壺に降りる道が作られていました。手摺がついていたので降りてみました。やはり迫力がありました。折角行ったのであれば、滝壺まで下りてみることをお勧めします。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます