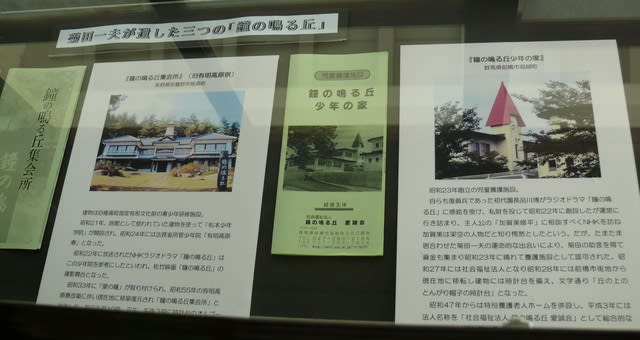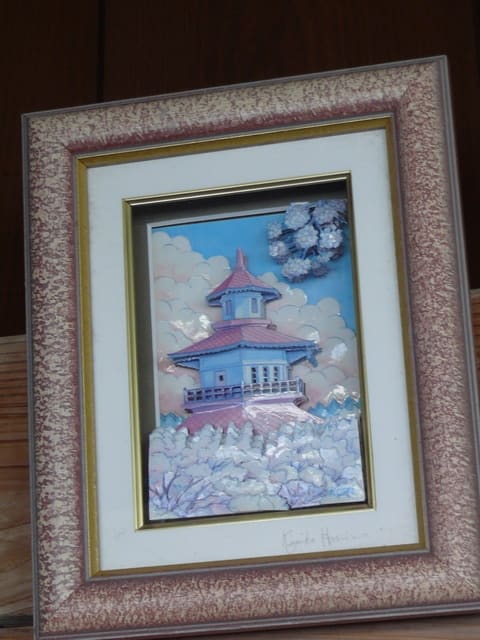2019年10月18日(金)、妻が、一関市東山町長坂字南山谷にある掻引城(駆引城)跡を写真に撮りたいと言うので、マイカーを運転して行って来ました。この城跡は、東山町が毎年実施している「唐梅館城まつり」の唐梅館城の出城と思われる施設で、創建者は唐梅館と同じ千葉左衛門尉頼胤とされています。

(上と下)東山町長坂字町の三菱マテリアル(株)岩手工場や松川石灰工場の石灰石鉱山が見えます。


この道は、旧県道19号線(旧今泉街道)から分岐している道で、特養老人ホーム・やすらぎ荘の所で県道237号線(一関市役所東山支所前を通り、東山町田河津字高金方面へ続いています)に合流しています。城跡の場所がはっきりわからないので、やすらぎ荘の入口の所にあるゴミ小屋の前に車を駐めて、城跡を探しました。



(上)県道237号線に合流している東山町長坂字南山谷地区。


(上)県道237号線から分岐している市道を100mほど入って行くと城跡がありました。

(上と下)一関市営住宅が30軒ほど建っていました。


(上)正面の遠くに見えるのが、東山中学校。

(上)市営住宅の間にある細道から城跡と思われるものが見つかりました。

(上)東南側の腰部(2段)

(上)南側に設けられている階段を登ったら”ここは「山谷(やまや)ふれあい緑地公園」ですの表示板が建っていました。
ここにも「掻引城(駆引城)」の案内板が欲しいと思いました。


(上と下)頂上に登ると平地になっており、ベンチが置かれ、古碑が建っていました。


(上)主郭南側には空堀が配されず、自然の谷を生かした切岸となっていました。現在は宅地となっていました。

(上)城跡の北側部分。現在は道路となっていました。近くには市営住宅、遠くには東山中学校も見えます。

(上)北西側には民家が沢山建っていました。(下)西側にも民家が見えました。

(下)南側に見えるのは、少し高台にある特養老人ホーム・やすらぎ荘。右の道は「長平」地区に通じている。

(下)主郭は、標高78mの丘陵に位置する。東西37m、南北45mの方形状の主郭をもつ単郭の城館で、主郭の北西から西側にかけて空堀が配されており、そのまま南側の谷へと続いている。東側遠くに見えるのは、松川石灰鉱業所。


(下)遠くに見えるのは、県道49号線(今泉街道)。真下に見えるのは西本町地区。


(上と下)東山野球場も見えました。遠く鉄塔が見える所が唐梅館方面。

(下)真下に見えるのは、立派なトイレでしたが、鍵が掛かっていました。


(上)城跡の北側にある登り坂。「掻引城(駆引城)」の標柱が建っていました。中世・城館跡、南北34間、東西36間、御城主葛西御家臣千葉刑部小輔様の由申伝候 [安永4年(1775)長坂村風土記]



(上)主郭北側の空掘跡。(下)主郭北側は現在道路になっています。(この先は北山谷集落に通じている)


(上)唐梅館城主郭からの郭引城(駆引城)跡遠望。(直ぐ下が市営住宅。右側下は東山中学校、上は特養老人ホーム・やすらぎ荘)
http://joukan.sakura.ne.jp/joukan/iwate/kakehiki/kakehiki.html [掻引城]