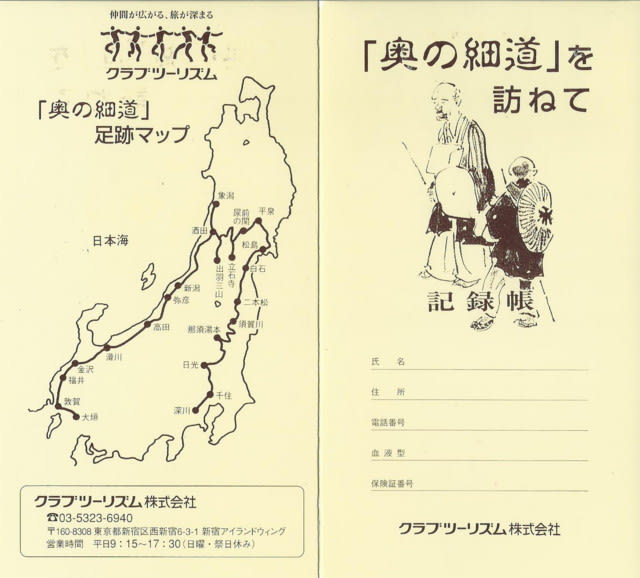
クラブツーリズム主催の「奥の細道を訪ねて・第14回~加賀百万石の城下町 金沢より福井まで」のバスツアーに妻と一緒に参加しました。第1日目 東京羽田空港・第1ターミナルから小松空港に向かって飛行機で出発です。
小松空港には予定通り8:55時に到着。地元・小松市の「京福バス」で最初の目的地である「妙立寺(みょうりゅうじ)」(金沢市野町1-2-12)に向かいます。バスの中で、講師の大橋洋子先生から、これから見学する妙立寺などについて詳しい説明を聞きました。

バスは金沢西ICから北陸自動車道に入り、一路「妙立寺」を目指して走ります。いつの間にか高速道路を出て、極楽寺の有料駐車場には9:40時頃到着しました。ここから最初の見学地の妙立寺(金沢市野町1-2-12)に徒歩で移動です(9:45時頃到着)。
この寺は、金沢城の出城の役割があった加賀藩ゆかりの寺で、芭蕉や「奥の細道」とは関係が無いようでした。攻め入れられた時を想定した仕掛けがなど沢山あって、「忍者寺」とも呼ばれて人気を集めているので特に組み込まれたようです。

(上)この日、3番目に訪れたのは、「春もやゝけしき調ふ月と梅」という芭蕉の句碑があるという本長寺(ほんちょうじ)。
妙立寺(みょうりゅうじ)の裏門を出て、すぐ隣にある願念寺(がんねんじ:金沢市野町一丁目)を見学した後、妙立寺の表門の方に回って、さらに徒歩で移動です。

(下)願念寺の表門から約300mほどでしょうか、長遠山・本長寺(金沢市野町一丁目2-8)に着きました。









http://kimassi.net/teramatijiin/hontyouji.html [本長寺(金沢の寺町寺院群):金沢観光情報<きまっし金沢>]

(上と下)本長寺の境内にあった朱紅色に熟したカラスウリ(烏瓜)の実。一関市内では「キカラスウリ(黄烏瓜)」は良く見かけますが、カラスウリは見たことがありません。

カラスウリ(烏瓜)ウリ科 カラスウリ属 Trichosanthes cucumeroides
林の縁や人家近くの藪などによく見られるつる性の多年草。茎は細く、巻きひげでいろいろなものに絡み付きながら伸びる。葉は長さも幅も6~10㎝で、縁は3~5つに浅く切れ込む。表面には白くて粗い毛があり、触るとザラザラする。花期は8~9月。白いレースでつくったベールを広げたような花が咲く。花は日が沈んでから開き、夜明け前には萎んでしまう。雌雄別株。雌花は細長い筒状の萼の下に丸い子房の膨らみがある。果実は長さ5~7㎝の球状または楕円形で、葉が枯れる頃に赤く熟す。分布:本州~九州。[山と渓谷社発行「山渓ポケット図鑑3・秋の花」より]

(上と下2つ)本長寺から次に見学する成学寺に向かって歩いていたら、「落雁」の看板や金箔などを販売している「民芸品・のむらや」、「竹筆の里・生きる」などがありました。



(上と下)道路の向かい側にも「宝勝寺」や「真長寺」などがありました。





















































































































