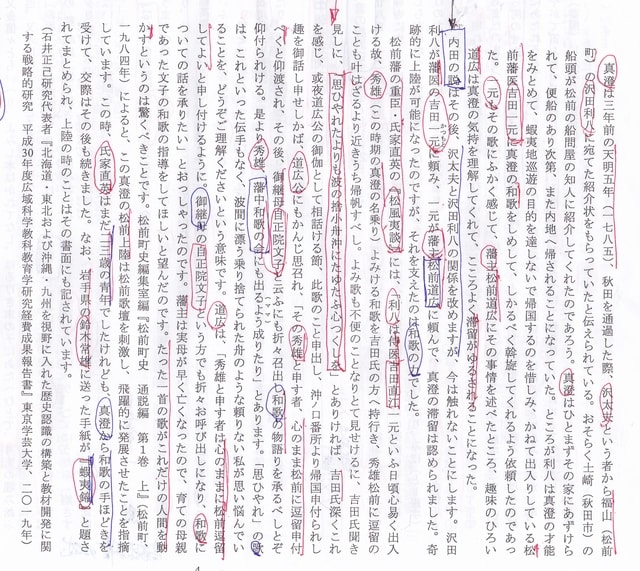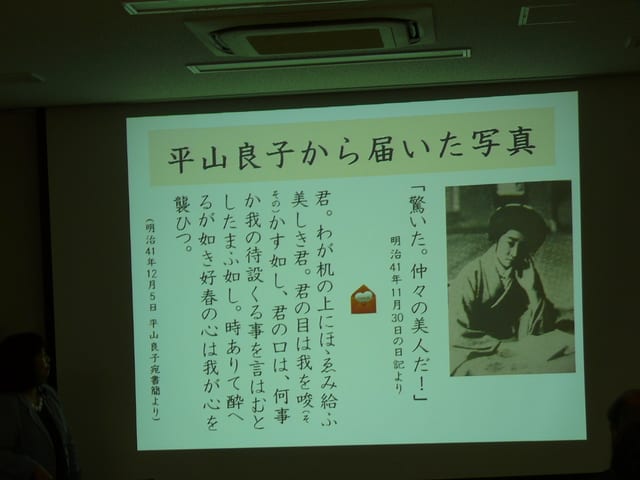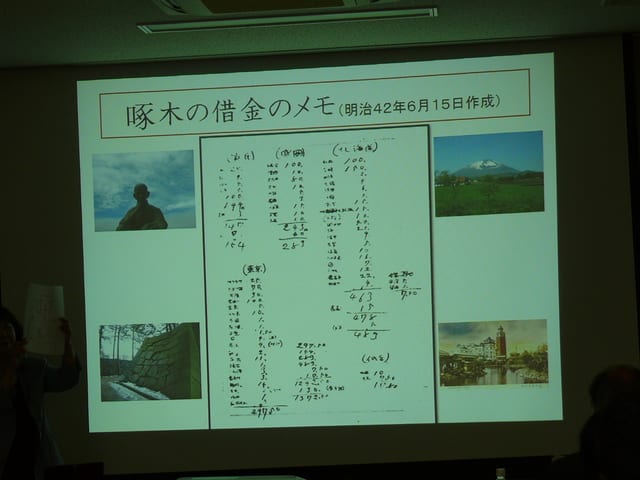https://ja.wikipedia.org/wiki/熊谷達也



2019年3月17日(日)[13:30~15:00時]、大東コミュニティーセンター(室蓬ホール、一関市大東町摺沢)で、株式会社・潮出版社主催の講演会が行われたので聴きに行ってきました。講師は宮城県仙台市在住の直木賞作家・熊谷達也さんで、演題は「無刑の人~芦東山が生きた時代」。
一関市大東町渋民出身の儒学者で、刑法思想の先駆者とされる芦東山(あし・とうざん、1696~1776年)を題材とした小説「芦東山」が、月刊誌「潮」の2019年1月号から連載が開始されたことに関連した講演会。
熊谷さんは、東京電機大学理工学部数理学科卒で、その後も埼玉県と宮城県気仙沼の公立中学校で数学教諭を8年間務めたが、もともとが理系ということもあって2016年に潮出版社から出筆依頼を受けたとき、芦東山のことはほとんど知らなかったと告白した後、聴衆に向かって「芦東山を知っている人は手を挙げて」呼びかけ、5分の一ほどの聴衆が挙手したのを見て、さすがは一関だと感心していました。
講演内容は省略しますが、難聴で補聴器がないと会話もままならない私にも、講演が良く聞き取れて良かったです。写真撮影は禁止でした。