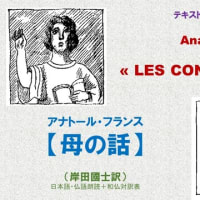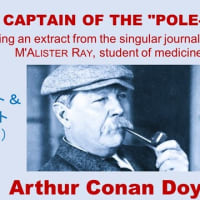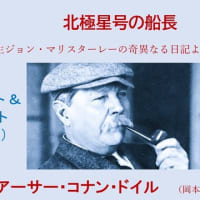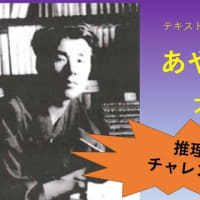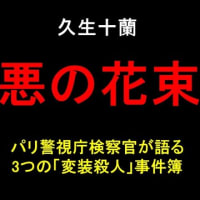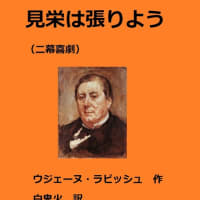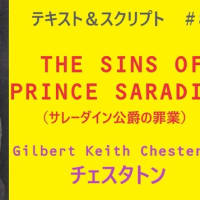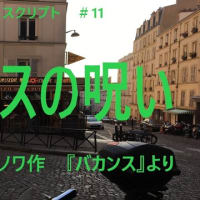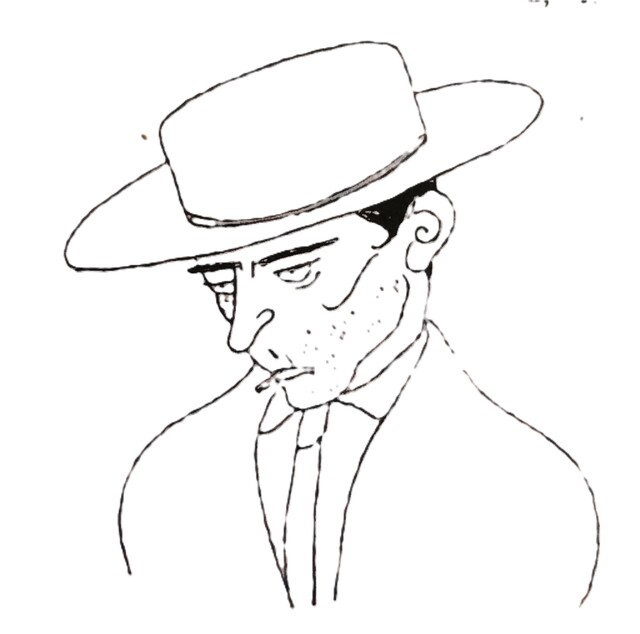若い頃、恩師から聞いた話だ。
恩師の学生時代、名物教授がいた。その先生は哲学の講義を担当していたのだが、その内容たるや難解至極、生徒の誰も理解できない。いつもよれよれの背広にボサボサ髪で、考え事をしながら教室に入り、教壇の机に大きな鞄をボンと置くやいなや、出欠もとらず、前置きもなく、カントやヘーゲルの考え方について延々と話し続ける。見ているのは黒板と床と天井だけ。学生の方へはほとんど目を向けない。ときどき、話を中断しては黒板を見つめて考え事をしたり、急に鞄の中の原書をひっぱりだして口でぶつぶつ言いながら何かを納得したりしている。
学生だった恩師は、ある日、その教授を呼び止めて尋ねたことがあるそうだ。
「先生、哲学を勉強して何かいいことがあるんですか?」
「ああ、あるとも」その教授は胸を張った。「だいいち、オレみたいに頭がぼーっとしてくる」
先日、人里離れた温泉宿で湯につかっている時、そんなことを思い出した。そして、妙に納得して、「そうだよな、悪くないよな」とつぶやいていた。
誰でもそうだろうが、還暦という大してありがたくもない記念日を過ぎてしまうと、世の中の大方のことは見尽くし、聞き尽くし、味わい尽くした気分になるものだ。だから、目の前で何が起きようと、何を言われようと、いちいち反応するのが面倒になる。だから「ああ」とか「ふむ」とか「ほう」だけで済ます。
若い頃なら、同じようなヘマを何度も繰り返す自分に腹を立てたり悔しがったりしたものだが、今では「オレはそういう人間なんだ」と居直って終わり。ましてや他人事になると、いちいち応接するのは本当に面倒くさい。そうやって鈍い反応しか返さなくなると、周囲から「あの人、ちょっと呆けてきたんじゃないか」と言われることが多くなり、しまいには完全に呆け老人扱いにされる。
そう思われても別に不都合はないから、こっちも呆けたフリをして喜ばせてやる。ただし、時には釘を刺すことも忘れていない。 どうせ聞いちゃいないだろうと高をくくって、私の横で家族や親類の悪口なんか言おうものなら、後日本人たちの前で、「お前、このあいだ、こんなことを言っていたよなあ」と暴露し恥をかかせるのも重要である。