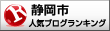今日は、第33回全日本高校女子サッカー選手権のお話を書きますが、男子の方も始まっています。1回戦で静岡学園は2-0で勝利。エスパルスに内定している嶋本悠大選手が所属している大津高校も4-0で勝利しました。こちらも楽しみですね。
いよいよ今日から、
第33回全日本高校女子サッカー選手権大会が始まりました。
このブログでも触れていますが、
出場チームが画期的に増えています。
今までの9地域代表制から、
初めて全都道府県から代表校が出場することとなりました。
この変更だけではなく、第33・34回大会のみの特例で、
47都道府県協会から選出された47チームに加え、
配慮5枠(宮城県、東京都、静岡県、大阪府、兵庫県)から、
プラスで1チームが出場するので、
昨年までの32チームから、
一気に52チームと出場チーム数は大幅アップする事となりました。
日本の女子サッカーは世界ランクでは8位。
トップクラスと言って良い位置にいますが、
実態は男子に比べれば、すそ野が広がっているとは言い切れず、
まだまだ、地域格差も大きいです。
つまり、高校サッカーだけを見れば、
恐らくトップのチームとそうでないチームの差は大きく、
「点差がかなり開く対戦も多いのだろうな?」と、
個人的には思っていました。
さて、実際の初日の結果を見て見ましょう。
全部で20試合が行われましたが、
10点以上の点差が開いた試合が3試合。
5点差以上開いたのが4試合ありました。
学校名を上げるのは止めたので、
具体的な結果を知りたい方はこちらをどうぞ。
初出場校は
八戸学院光星高校(青森)、山形明正高校(山形)、昌平高校(埼玉)、日本航空高校石川(石川)、豊川高校(愛知)、帝京大学可児高校(岐阜)、近江兄弟社高校(滋賀)、高取国際高校(奈良)、和歌山北高校(和歌山)、神埼高校(佐賀)、宮崎学園高校(宮崎)
全ての県を調べた訳ではありませんが、
岐阜県、高知県、山口県、佐賀県からは初めての全国大会出場。
秋田県からは2015年以来2度目の出場。
石川県からは2013年以来2度目の出場。
滋賀県からは2008年以来2度目の出場。
和歌山県からは2002年以来2度目の出場。
鳥取県からは2020年以来2度目の出場。
奈良県からは1992年、2000年以来3度目の出場。
宮崎県からは2013年、2014年以来3度目の出場。
沖縄県からは1997年、2011年以来3度目の出場。
特に今年の沖縄県代表は、
八重山高校、浦添高校、浦添商業高校、陽明高校、興南高校、久米島高校による合同チーム。
全国大会をあまり経験していない県は、苦戦が予想されました。
R中女子ソフトテニス部関連のブログでもいつも書いていますが、
強い相手と対戦すれば負けて、
弱いところと当たれば勝つのはある意味当たり前です。
大切な事は、勝敗だけではなく、
試合で持てる実力を全て出せたのか?
もちろん緊張で思うように動けなかったとしても、
途中で投げ出さずに最後まで頑張れたのか?
そういうことが大切なのです。
今回は負けてしまったとしても、
それを糧にこれからも頑張り続けられるのか?
後輩は、その先輩の姿を見てもっともっと頑張って行けるのか?
それが大事であり、スポーツの醍醐味です。
「負け」は失敗ではありません。
次に繋がる礎になれば成功です。
負けたチームの今後にエールを送りたいです。
さて、静岡県代表の藤枝順心高校は1回戦を突破しました
常葉橘高校は2回戦方の出場です。
この大会の常連校である過去3回の優勝を誇る日ノ本学園は、
PK戦の末1回戦で敗退となりました。
全体的レベルが少しずつ向上している証です。
初出場の県、4県の代表チームは、
山口県代表が2回戦からの登場ですが、残り3県は1回戦敗退でした。
2回目の出場県、5県の代表チームは、
鳥取県の代表チームのみ勝利し、
残りの4県は1回戦敗退でした。
やはり全国大会で勝ち進むのはハードルが高いですね。
これからの頑張りを期待します。
みんなガンバレ!
そして藤枝順心高校、そして常葉橘高校がガンバレです!
さて、今年の目標である年間読書150冊。
122冊目です(今年359日目)
「表御番医師診療禄6 往診」 上田秀人
勝手に評価10点満点中6点
さて、今年の目標である年間読書150冊。
123冊目です(今年361日目)
「表御番医師診療禄7 研鑽」 上田秀人
勝手に評価10点満点中6点