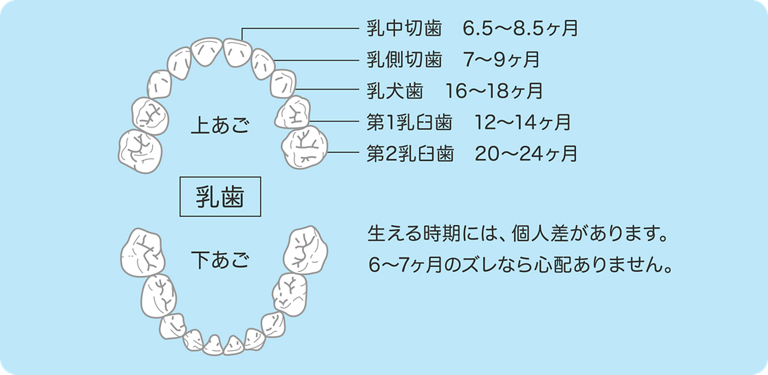インフルエンザについて
インフルエンザは例年12月から3月にかけて流行します。しかし、昨年から今年にかけては、散発的にインフルエンザが発生しており、現在、「流行注意報基準」を急速に増加しています。今後もさらに流行が拡大する可能性があるため、十分な注意が必要です。
インフルエンザとは
インフルエンザウイルスによって発症します。通常の風邪に比べて感染力が強く、全身症状が強く出やすいのが特徴です。
症状
おおむね1~3日の潜伏期間の後に、以下の症状を呈します。
①40℃前後の高熱が出ることが多い。
②頭痛や喉の痛み、咳、鼻水、悪寒や倦怠感がある。
③関節痛や筋肉痛が起こる。
④嘔吐や下痢が伴うこともある。
多くの人は1週間程度で回復しますが、高齢者や心疾患など基礎疾患のある方は、肺炎を伴うなど、重症化することがあります。また、乳幼児がかかると、肺炎やインフルエンザ脳症を引き起こすこともあります。
予防
①こまめに手洗い・うがいをしましょう。
インフルエンザだけに限らず、感染症予防として手洗い・うがいを行い、体内にウイルスや菌を入れないことが大切です。親子で楽しく取り組んでいきましょう。
②規則正しい生活を送って十分な休養をとり、バランスのとれた食事と適切な水分の補給に努めましょう。
③普段から一人ひとりが咳エチケットを心がけましょう。
せき・くしゃみの症状がある場合は、マスクをしましょう。また、せき・くしゃみをする時は、周りの人から顔をそらし、ティッシュなどで口と鼻を覆いましょう。
④こまめな換気を心掛けましょう。
冷暖房により室内の空気が汚れたり、ウイルスが増えやすくなります。また、閉め切った部屋にいると感染のリスクは高まります。定期的に窓を開けて新鮮な空気を取り入れましょう。
⑤乾燥に気をつけましょう。
ウイルスは湿度に弱いです。室内の湿度を60%ほどに維持できるのが理想ですが、戸外の湿度が30%を切るようなときは、維持するのもなかなか難しいものです。40~60%を目安に加湿していきましょう。濡れたタオルを干すのも効果的です。60%以上になるとカビ・ダニが発生しやすいので気を付けましょう。
⑥人混みへの外出を極力控えましょう。
登園の目安
発症後5日間、解熱後2日を経過してからの登園が基本となります。病院で医師の診断をしっかり聞いて、登園可能日を確認しましょう。また、医師の登園許可証が必要となります。
インフルエンザの予防接種について
インフルエンザの予防接種が医療機関で開始しています。世田谷区では、こどもにはインフルエンザの予防接種の助成金制度があります。先週、園からもお便りを配布しました。
予防接種を受けておくと、万が一かかっても軽い症状となるため、安心です。
インフルエンザの予防接種は、こどもの場合、1シーズン2回接種が標準です。
ワクチンの抗体がつくまでに2週間以上かかります。接種する場合は、計画立てて接種することがよいでしょう。
Q:去年インフルエンザの予防接種を受けたので、今年は受けなくてよいか?
A:原因になるウイルスは、主にA型、B型、C型の3つがあり、年によって流行する型が違います。A型B型がよく流行しますが、毎年予防接種を受けることで、効果が期待できます。
Q:受けるとインフルエンザにかからないの?
A:必ず発病を防げるというものではありませんが、かかっても重症化したり、合併症を起こしたりするリスクを減らすことができます。
Q:予防接種の効果が続く期間は?
A:接種後、効果が現れるまでに約2週間ほどかかり、その後半年くらいは持続します。
Q:接種の方法は?
A:生後6ヶ月から受けられます。大人は1回接種、13歳以下の子どもは2回接種が必要です。1回目の接種の後、2~4週間あけて2回目を接種します。ただし卵アレルギーのある子は、医師と相談しましょう。
朝晩は涼しくなり、日中との温度差が激しいですので、身体に気を付けて元気に過ごしましょう。