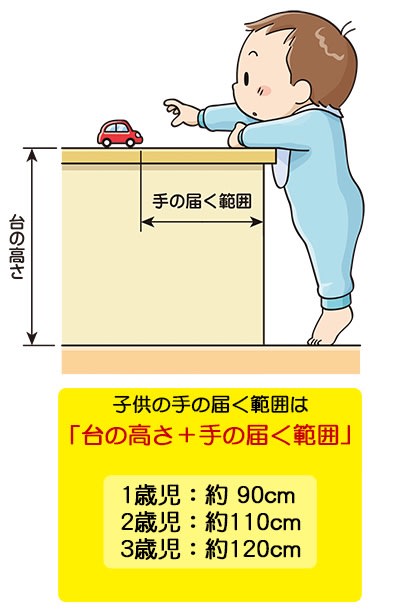良い姿勢を身に付けましょう
悪い姿勢になっていませんか?
・ポケットに手を入れて、背中を丸めている。
・椅子にもたれかかって、スマホやタブレット、テレビを見たりしている。
・寝転んで絵本を見たり、絵を描いたりしている。
乳幼児期は「背骨」や「背骨を支える筋肉」が成長発達していく大切な時期です。良い姿勢を身に付けましょう。
姿勢が悪いことによるこどもの体への悪影響とは
①骨格がゆがむ
姿勢が悪い状態が続くと肩や背中の筋肉に負担がかかり、体が疲れるだけではなく、骨格がゆがみ、慢性的な肩こりなどにつながります。
②呼吸が浅くなったり、消化不良を起こしたりする
猫背のままでいると、肺がしっかりと膨らまず肩で息するような状態になり呼吸が浅くなります。内臓も押される状態になるので、消化不良を起こす場合もあります。
③近視になる可能性がある
姿勢が悪くなる要因としてスマホやタブレットの使用機会の増加が挙げられますが、適切な距離感で使用しないと近視が進んでしまう可能性があります。
ほかにも、姿勢が悪いまま運動するとケガのリスクが高まる場合もあります。
姿勢が悪くなる原因は
①こどもの筋力低下
スポーツ庁のこどもの運動機能に関する調査によると、令和元年度以降、こどもの体力が急激に低下しています。コロナ禍の影響でおうち時間が増えた上に運動時間が減少し、身体を支える筋力が低下したことが理由と考えられます。
②スマホやタブレットの使用
小さなうちからスマホやタブレットに触れる機会が多くなると、運動不足だけではなく使用する際に猫背になるなど悪い姿勢が癖づいてしまいます。
③生活リズムの乱れ
生活リズムの乱れにより、朝早くに起きられずに朝食を抜くこどもが増えています。朝食を抜くと、脳のエネルギーが不足して集中力が保てなくなります。集中力低下によって頬杖をつく等をすることで、姿勢が悪くなります。
④保護者の姿勢の悪さが影響している場合もある
こどもは保護者を見て育つため、保護者の姿勢が悪いとこどもも姿勢が悪くなる可能性が高くなります。まずは、保護者が姿勢の重要性や姿勢の悪さによる体への悪影響について再認識し、正しい姿勢でいられるようにしましょう。
良い姿勢をするメリット
①運動能力を発揮することができる
姿勢が良いと、なんらかの動作を行う際に、無駄な動きや体重移動が減り、効率の良い動きが出来るようになります。
逆に姿勢が悪いと体のバランスが取れず、無駄な動きや体重移動が増えてしまいます。それが体のゆがみや動きの癖などに繋がってしまうこともあります。
②呼吸を整え、心の良い状態を保つことができる
正しい姿勢でいることで、呼吸が入りやすくなり、自律神経を整えることができます。背骨をまっすぐに保ち、深く呼吸をすることで自律神経が整い、心を落ち着かせることができます。
逆に姿勢が悪く、浅い呼吸をすることを続けていると、なんとなく落ち着きがなくなったり、イライラの原因になります。
③集中力を持続させることができる
姿勢が悪いと、呼吸が深く入らないのと同じく、血流も悪くなってしまいます。それによって脳の活動も低下し、集中力の低下にもつながってしまう場合があります。
良い姿勢を目指そう!
乳児期
・ハイハイを十分にさせましょう。
・前に進んだり、後ろへ下がったり、グルグル回ったりすることで、骨や筋肉が発達します。
幼児期
・背筋を伸ばして、土の上、砂利道、坂道、雪の上など、色々な場所を歩く経験をたくさん出来るようにしましょう。
・飛んだり、跳ねたり、走ったりすることが骨や筋肉を鍛えて、良い姿勢を作ります。
立つとき:耳たぶ、肩の中心、くるぶしが一直線になるような状態。
座る時:背中は座面に垂直に、太ももは床に水平になるように足全体を床に付ける。
こどもの姿勢を正すためにできること
①姿勢を正す重要性やメリットをまず保護者がしっかりと把握しましょう。
こどもに分かりやすく伝えることで、こどもも納得しやすくなります。
重要性やメリット
・運動能力が向上する
・疲れにくくなる
・ケガの予防になる
・体の不調が減る
②保護者が手本を見せましょう。
こどもに正しい姿勢を教えるために、まずは保護者が手本を見せましょう。その上でこどもの姿勢をチェックしてあげましょう。こどもたちに「背中がまっすぐだとカッコいいよ」と声を掛けてください。
姿勢が良いと、気持ちもシャキッと前向きになります。小さい時からの習慣づけが大切です。