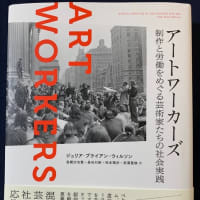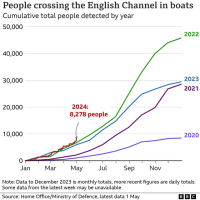Caithness の作品例 Photo Y.Kuwahara
「クリスタルグラス・ペーパーウエイト」というのものをご存知だろうか。要するに、クリスタル・ガラスで作った文鎮である。ただ、ガラスの文鎮といっても実は色々な種類があって、ガラスの中に美しい模様、花、虫などのデザインを埋め込んだり、ガラス自体を加工して、動物や微妙な文様などの形に成形したものなどきわめて多様なものがある。
世の中に出回っている作品のほとんどは、大量生産の製品で価格も安い。しかし、数は少ないが絶妙な技能を持った職人の手仕事による、目を見張るような美しい作品がある。こうした作品はコレクターズ・アイテムとして、サザビーなどでオークションの対象にもなり、当然、価格も驚くほど高い。プロのコレクターの世界が出来上がっている。
バカラの拠点
ナンシーからリュネヴィルへ行く道の少し先に、世界的なガラス装飾品メーカー・バカラ Baccarat の工場とガラス作品の博物館があることを偶然知った。めったにない機会なので、立ち寄ることにした。バカラのブランドは世界中に知られているが、工場、博物館がここにあったことは知らなかった。同社の製品は、装身具や照明、美術品などが多く、ペーパーウエイトは今はわずかしか作られていない。
いつ頃からこうしたペーパーウエイトが作られるようになったかは、定かではない。1845年頃、フランスではナポレオン戦争の後、低迷していたガラス工房が、お土産用、装飾品などに作ったところ、当時の人々に受け入れられたといわれている。その後、フランス、イギリス、ボヘミア、イタリア、そして後にはアメリカなどでも制作されるようになった。確かに、当時の職人がどのようにして作ったのだろうかと思わせるきわめて美しい作品もある。日本ではなぜかあまり精緻なものは作られていない。
こうした作品は、初期には大変な人気を博したらしいが、まもなく1860年代には衰退してしまう。それでも、一部の工房が細々と制作していたらしい。
新たなブーム
その後、時代が変わって1950年代に、フランスのバカラとサン・ルイの工房(今はいずれもエルメスの傘下)が、エリザベス2世の戴冠式とアイゼンハウアー大統領の就任式記念品として作ったのが、再びブームを巻き起こすきっかけになったらしい。アンティーク、現代の作品を含めて投機対象となり、作品によっては、一部のコレクター以外にはとても手が出ない高値がつくようになった。
ペーパーウエイト(PW)に関心を持つようになったのは、ちょっとしたきっかけであった。1980年代初めの頃、ガラスや銀細工、木工家具など、伝統職人の熟練とその伝承のあり方の調査をした時に、たまたま出会った作品が目に留まり、その製作工程に興味を抱いた。
その後、縁あってガラス製品の世界的な企業、コーニング社のガラス博物館(PWの大きなコレクションを所蔵している)を見学し、工法についてもかなり詳細な説明を受けることができた。海外に滞在した折などに、いくつかのガラス工房を訪れて、インタビューをし、製作過程を見学させてもらった。Caithness (UK)、Whitefriers (UK、今はCaithness傘下)、 Kosta Boda(Sweden)、Corning Glass (USA) などが記憶に残っている。
多くの作品は大変高価で、作品を所有することは初めからあきらめていたが、製造工程には大変興味を惹かれた。溶けた高熱のガラスを扱いながら、どうしてあれほど精緻なものが作れるのだろうか。いくつかの工房を見学することで、実は製作技術にもいくつかの方法があることが分かったのだが、いずれにしてもきわめて高度な熟練職人の技が生み出したものである。
高度な技能の維持・伝承
コレクターの追い求める美しい製品は、加工技術も難しく、単品ないしは限定数の製造になっている。多くはアンティークの部類に入る。そして、サン・ルイやバカラの工房などでは、今日も職人のサインと日付入りの限定版として製造されている。サインや日付はしばしばガラスの製品の中に隠されたように記されているので、贋作は出る可能性は少ない。また、それほど高価でないものでは、作品数とその作品が何番目にあたるかを記した証明書がついているものもある。
従来、作品の製作工程は、高熱で溶解したガラスの加工のため、職人が作業場の近くに絶えずいること、高度な熟練・技術の保持と外部への流出阻止などの理由で、工房に隣接して住居が設置されていた。しばしば、辺鄙な場所に工房が置かれていた。たとえば、サン・ルイの工房は、ボージュ山脈の山中に置かれている。また、バカラの工房もパリなどの都市に近い便利な場所に位置しているのではない。リュネヴィルの南東30キロほどの丘陵地帯である。併設の博物館は公開しているが、工房は見学できない。写真を撮らないことを条件に少しだけ覗かせてもらった。原料の選別、溶解、保持など、設備は大変近代化していたが、作品の制作は昔ながらの手仕事である。
Baccarat のアンティーク作品の例
10年ほど前に、イギリス北部、キングス・リンの近くのケイスネス Caithness の工房を見に行ったこともあったが、設備は昔ながらであり、町工場のような印象であった。花瓶や水差しなど一般のガラス器製品の製造工程は公開していたが、クリスタル・ペーパーウエイトは、時々しか製作しないという理由で見せてもらえなかった。
今回のロレーヌ、とりわけナンシーへの旅は、再び眠っていた記憶細胞を少し活性化してくれた。これまであまり関心のなかったエミール・ガレ、ナンシー派のおびただしい数の作品に出会って、ガラス工芸の絶妙、華麗な次元に魅了された。それらに込められた熟練の奥深さ、伝承のあり方などについて改めて考えさせらた。これについては改めて記す機会があるかもしれない。
ガラス工芸品の製作は、原料を調合し、溶解炉の中に設置された大型の耐火粘土製の坩堝に入れて溶解する。坩堝には高温な材料が真っ赤に溶かされている。あの陶磁器窯やパン竈に燃えている焔の世界がそこにもあった。