表現世界(作品)に対する読者(観客)の位置
―読者の作品内外における様々な行動
※(「人、作者、物語世界(語り手、登場人物)、についての再考察」の補遺)
例えば、わたしは観ていないけど一時期韓流ドラマが人気になったことがあり、そのドラマの登場人物を演じた役者を追っかけたり、あるいはドラマのロケ地を訪ねたりという記事やニュースを目にしたことがあります。わたしの場合は、流行にずいぶん遅れて近年になって偶然のきっかけでわが国の時代劇に当たる韓国のドラマを6、7作観たことがあります。どの作品もとても長い続き物でした。わが国の時代劇とは違ったおもしろさがありました。そして、あの登場人物はおもしろいなとか、当然ながら殺陣や映像がエンターテインメント的だななどと作品の印象をつぶやくことはあります。けれど、俳優やロケ地などを追っかける気持はわたしには全くありません。作品は作り物の虚構の世界であり、登場する人物を演じる俳優たちはその虚構の世界だけを生きていると思うからです。
しかし、そのような追っかける気持はなんとなくわかるような気もします。おそらく、気に入った歌手や俳優やスポーツ選手や芸術家などの個人的なことも含めて興味を持ち追っかける心理と同一なのでしょう。さらに、それは遙か太古から続く根深い精神の遺伝子のようなものだと思われます。
まず、現在的に見て、人は誰でも、この人間界では個人、家族の一員、職業人、など多重の関係網の中を、私的~公的に渡って日々行き来しながらわりとシームレスに行動しています。様々な役柄を演じているように見えても、それはひとりの人だという受け止め方は、自然であろうと思われます。特に西欧社会と違って我が列島では、一人の人の中の私的な面と公的な面をはっきりと区別することがなく、あいまいな同一性と見なしがちです。つまり、誰でも実感としては違いを感じることはあっても、ひとりの人間の中に私的~公的に渡って現れるいろんな層が未分離だということです。
テレビの草創期の笑い話として本で読んだことがあります。ある役者があるドラマの中で一回死んだのにまた別のドラマに出ていて、テレビを観ていたおばあちゃんが役者が死んだのに生き返っているととてもビックリしたという話です。今では、そういう風に思うことはなくなっていると思いますが、もしそのようなあいまいな同一性でひとりの人を見るならば、そういう驚きは成り立ち得ます。また、有名人を追っかける意識もそのあいまいな同一性に基づいているように思います。これをまとめると次のようになります。西欧の実情は知らないから、西欧的な言葉や論理や書物から得た西欧人の考え方に基づいた大雑把なイメージ把握になります。テレビなどで西欧人を観ていると、スポーツや芸能人に対して、パパラッチもいて、ということは普通の人々のそんな興味や関心の需要の存在もうかがえて、わが国の人々と似たような面もありそうに思います。したがって、わが列島と西欧との意識の大まかな主流の区別として取り出してみます。
あいまいな同一性(わが列島の場合)
「ひとりの人」≒「表現者」≒「表現の舞台」≒「表現」
それぞれの差異性(西欧の場合)
「ひとりの人」≠「表現者」≠「表現の舞台」≠「表現」
註. (≒ : 大体等しい) (≠ : 等しくない)
歌手や俳優やスポーツ選手や芸術家などが、〈表現者〉に変身して〈表現の舞台〉に上り〈表現〉し終わったなら、また元の〈個人〉に戻ります。しかし、〈表現者〉が〈表現の舞台〉を降りても、社会も人々もそのように〈個人〉と見なすのではなく、〈表現者〉という色の付いたフィルター越しに見ます。有名人として見ると言い換えることができます。傾向性としては、わが列島と西欧とにおいて、上記の区別のようなものがあるとしても、この「有名人」に対する眼差しや意識の有り様は、度合いの差を含みつつの人類普遍と言えるかもしれません。また、わが国で見ても、今から半世紀前と現在とでは、有名人に対するまなざしや意識はずいぶん変貌してきているように感じられます。つまり、有名人もわたしたちと同じ普通の人々ではないかと捉える部分が増大してきて、そのマレビト性が薄らいできています。つまり、「有名人」に対する眼差しや意識の有り様の度合いが薄まっています。
では、次にそのような人類普遍とも言えるような「有名人」に対する眼差しや意識の有り様はどこから来ているのでしょう。たぶん、簡単に言えば、遙か太古の巫女やシャーマンの登場(発生)の仕方や彼らへの普通の住民たちの眼差しや処遇から来ている根深い精神の遺伝子だと思います。わが列島は、近代以降大きな西欧化の波を二度もかぶり、その影響も少しずつ浸透し、徐々にひとりの人間の中に私的~公的に渡って現れるいろんな層の区別が付けられる方向に向かうと思います。しかし、政治を含めてその「有名人」へのまなざしや意識が、マレビト性として当人たちも周りの人々も負性として依然として根強く現在に生き残っています。
ところで、読者(観客)は、スポーツや芸術のどんな表現(作品)でもそれを観(読み)終われば、ちょうど上映が終わって映画館を出て行く時のように現実の世界に帰還して行きます。もちろんどんな作品でも観(読み)終わっても余韻を引きずったり、さらにもっと後まで印象に残るということはあります。「有名人」や「聖地」への追っかけの人々を別にけなすつもりはさらさらないけれど、それでいいのだとわたしは思っています。表現された作品こそが全てだという方向に向かえばいいなと思っています。
註.「あいまいな同一性」について
柳田国男がこの列島に数多く残っていた小町伝説について取り上げたことに以前触れたことがあります。諸国を巡り歩いた語りの女性たちが、村々で一人称で小野小町になりきって語ったから、その語りを聞いた村々の人々は語り手と小野小町を同一化して小野小町伝説を生み出したり小町塚などを築いたりした、と捉えています。これも「あいまいな同一性」に当たります。
(因みに一人称の語りについては、『アイヌ神謡集』・知里幸惠にも、「梟の神の自ら歌った謡」など一人称の語りの作品が収められています。)
最新の画像[もっと見る]
-
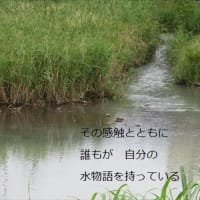 水詩(みずし) #3
3日前
水詩(みずし) #3
3日前
-
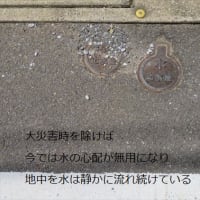 水詩(みずし) #2
1ヶ月前
水詩(みずし) #2
1ヶ月前
-
 画像・詩シリーズ #12 お茶を摘む
1ヶ月前
画像・詩シリーズ #12 お茶を摘む
1ヶ月前
-
 画像・詩シリーズ #12 お茶を摘む
1ヶ月前
画像・詩シリーズ #12 お茶を摘む
1ヶ月前
-
 最近のツイートや覚書など2024年3月
2ヶ月前
最近のツイートや覚書など2024年3月
2ヶ月前
-
 最近のツイートや覚書など2024年3月
2ヶ月前
最近のツイートや覚書など2024年3月
2ヶ月前
-
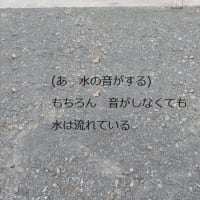 水詩(みずし) #1
2ヶ月前
水詩(みずし) #1
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
3ヶ月前
農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
3ヶ月前
-
 農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
3ヶ月前
農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
3ヶ月前
-
 農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
3ヶ月前
農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)
3ヶ月前









