先のブログ 「アリウム(ネギ属)野菜専科の外房菜園」の中で紹介した玉ネギの収穫シーズンが、今年も間もなく始まる季節になります。
その外房菜園の北に位置する九十九里浜に面した千葉県長生郡白子町一帯は、昔から関東の玉ネギの産地であり、其の栽培の歴史は大変古く、大正時代に始まったとあります。
それが特に盛んになったのは、昭和30年代後半頃から行われるようになったマルチ栽培に依る早出し玉ネギの出荷であり、その結果の栽培面積が急拡大して、玉ネギの国の指定産地になったと言います。
それが近年になって、生産農家の高齢化、労力不足に価額の低迷が重なって、生産量は年々減少し、今では最盛期の4割にも減ってしまっていると言うのです。
其の一方では、生産者の努力によって当地域の特色を生かした新しい玉ネギ品種が導入され、辛味が少なく、生でも食べられる程甘くて美味しい玉ネギが作られるようになり、其の早出し玉ネギが今では、他産地に先駆けて5月上旬には出荷されるようになっているのです。

―広大な南九十九里浜の海岸風景―千葉観光スポットより
その早出し玉ネギの美味しさが高い評価を受け、今や知る人ぞ知る早生玉ネギの一大産地となっているのです。
その早出し玉ネギ、今では栽培圃場に直接訪れて掘り取る玉ネギ狩りが大評判となって、ここ数年で訪問者が大変増え、玉ネギ祭りと呼ぶ毎年の恒例行事となり、今年も連休明けの5月13日には開催される事になって居ります。
其の美味しい玉ネギの秘密はといえば、冬でも温暖な九十九里浜からのミネラル分豊富な海風と、水はけの良い砂質土壌にあり、何処にも負けない玉ネギとっての適地適作の恩恵を、フルに受けているからです。

―南九十九里の初夏の味覚の白子たまねぎー千葉の恵みより
その玉ネギの味を守るために、現地の生産者組合では、栽培土壌管理が何よりも大切と、毎年堆肥を多く施用して、化学肥料と農薬の使用量を如何にして減らすか腐心していると言うのです。
そこで決まられたのが化学合成農薬の総使用回数を削減して5回とし、豚糞ともみ殻堆肥は10a当り5tと決め、硫安及びNKグリーン各23.1㎏/10a、野菜美人35.6kg/10aの施肥量としたとあります。
玉ネギは定植後、気温も低いので病虫害の発生は殆ど無く、使われる農薬はと言えば、種苗の育成で発生する苗立ち枯れの防止薬、種ハエの殺虫剤、圃場の除草剤、べと病、灰色カビ病防止殺菌剤ぐらいであります。
その点では、当地で作られる玉ネギは、今どきには驚く程のエコな農産物であり、生でも安心して食べられるサラダ食材向きと申しても、先ずは依存ありません。

―年々大盛況になる白子玉ネギ狩りー千葉県公式物産サイトより
尤も、拙宅の外房菜園で作っている玉ネギは全くの無農薬の有機肥料中心の栽培であり、其れが実現できるのは、育苗には新プランター栽培に使われている無菌に近い珪藻土焼成粒材に播種しての養液栽培であるからです。
その苗を移植する本圃の作土管理では、蛎殻石灰に、たっぷりの牛糞堆肥と発酵鶏糞の乾燥粒材を基肥にし、追肥には有機配合化成肥料をマルチシートの上から少量ばらまく程度に徹しています。
そして、この春収穫できる玉ネギ品種はと言えば、例年通りの早出しできる早生玉ネギの「ソニック」、続いては、今年から始めた長期保存が可能な晩生玉ネギ 「ネオアース」、同じく「スイートグローブ」、赤玉葱の「チャイナクィーン」の4種です。
その中で早出しできる「ソニック」以外は、どれも長期に保存が可能と言う晩生種玉ネギであり、今年がそれら栽培の初挑戦です。
実は、毎年自家用玉ネギを作っていても、早出し品種だけでは長くは保存できない為に、拙宅では秋口からは、素性の不明な市販品玉ネギを毎年買って食べる羽目になっていたからです。
其の自家製の無農薬玉ネギに拘る主な理由はと言えば、農薬に少しでも汚染された野菜類は、大なり小なり真の健康維持にはマイナス要因になっているからであり、先のブログ「有害物質から身を守る!」 を見ればご理解出来るかと思います。
扨て、此処で話が一寸変わりますが、某種苗会社が行った昨年の野菜消費動向調査の結果が紹介されている記事をネット上で見つけました。
其の調査方法、310人の男女を対象に作物別消費量や価格、購入方法などの項目に別けてインターネット調査を行い、総合的に集計・分析した結果を、「2017年の野菜の総括」として発表したと言うのです。
その調査結果で分かった事は、昨年中で最も多く食べられた野菜が玉ネギであったと言うのです。その日本の玉ネギの総生産量、最近の統計によれば年間で126.5万トンであり、それでも総需要に供給量が追い付けないのか、昨年の輸入玉ネギ量が26万トンもあり、中国・台湾・韓国・アメリカ・トルコ・オーストラリア・ニュージランドなど、多くの輸入玉ネギが日本に入ってきていると言うのです。其の理由は一体どこにあるのでしょうか。一寸不思議に思われます。

―玉ネギの国内収穫量は80%を超えるー玉ネギ画像より
近年、食料品店の減少や大型商業施設の郊外化などに伴い、過疎地域はもとより、都市部でも高齢者を中心に食料品の購入に困難を感じる消費者が増加、いわゆる「食料品アクセス問題」が顕在化してきていると言います。
実は、そうした危機意識を背景に行われた、全国1741市町村(東京都特別区を含む)にアンケート用紙を配布しての調査で、1175市町村から回答が寄せられ、その回答率は67.5%であったとあります。
それによると、964(82.0%)の市町村が「何らかの対策が必要」と回答し、その背景として、(1)住民の高齢化、(2)地元小売業の廃業、(3)中心市街地の衰退を挙げる市町村の割合が高い傾向にあったとあります。
対策を必要とする市町村のうち、594の市町村で「何らかの対策を実施」しており、その実施率は61.6%と前年より0.6ポイント上昇したと言うのです。
その理由は、需要と供給のバランスの問題であり、地域の過疎化や購買層の減少で、需要が衰退すれば供給は必然的に細るのであり、起こって当然の市場経済の原則です。
それを玉ネギに限って見て考えられるのは、生産・流通コストの低減化、端境期対策としての栽培法の改善、極早生の早期化、貯蔵技術の向上、極早生品種・高貯蔵性品種の開発、品質面の対策など、多々に云々されているのですが、そうした生産面側からの議論よりも、一般消費者側の玉ネギ認識、その捉え方の意識構造に問題の根源があるのではと思われるのです。
簡単に言えば、玉ネギの本当の価値を知らない、ただ単に野菜の一種としての一物一価の相対的な金銭的な価値でしか、玉ネギが理解されて居ないのではないでしょうか。
言うなれば、輸入品も、国産品も、玉ネギは玉ネギであり、基本的には玉ネギは皆同じと言う、単純な野菜認識であります。
其の裏にあるのは、口にさえ入れば皆同じと言う理屈です。強いてその価値を問うならば、金銭的な価格での違いでしかなく、ものとしての違いの正しい価値判断が出来ていない、玉ネギの生産地の真の違い、その味や栄養面などの理解が不足しているのです。

―玉ネギの主要な輸入国と輸入量の推移―Web画像より
一方玉ネギの生産供給者側からすれば、そうした消費者の単純な価値判断に応えるには、一にも二にも、コストの低減化しか無く、当該市場で提示できる単価でその全てが決まるしか無い事になります。
もし、その提示できる限度額が極限に達して対応不可となれば、もはや生産供給者は退散するしか手立てが無くなる理屈です。
その好例が、前述の過疎地域はもとより、都市部でも高齢者を中心に食料品の購入にも困難を感じる消費者の増加であり、いわゆる「食料品アクセス問題」が顕在化する程の消費市場構造の変容であり、其処に同様の問題が有るからです。一部の少数の消費者が見捨てられる食品流通構造が、今や生まれる社会現象が少子高齢化の日本に起こっているのです。
其れが国産玉ネギが市場に並ばないからと、輸入玉ネギが代わりに並ぶのであり、これも亦然りの日本の社会現象と理解されます。
先のブログで触れた話の食べて美味しい妥当な価額の野菜等、これからは更に望むべくも無い時代の到来となり、消費過疎化地域に住む皆さんは、其れを覚悟しなくてはならないかもしれません。
でも、そうなっても心配はありません。対策は昔に戻って小さな菜園を作って、美味しい野菜を自ら作る事であり、手間暇を惜しまずに自分が食べる野菜は自分で育てる事に喜びを見いだして下さい。それは自らの健康維持に大きな成果をもたらし、当に一挙両得にもなりますよ!そんな勇気が在ればの話ですが‥‥。
![]()



















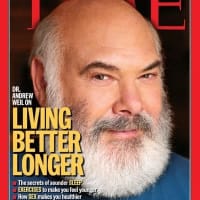


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます